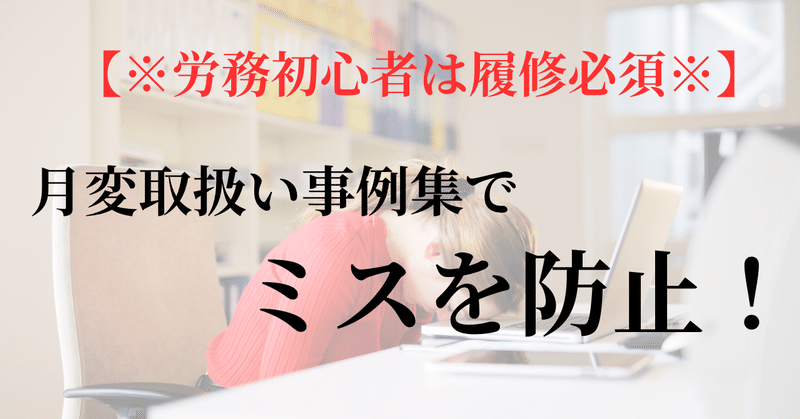
【※労務初心者は履修必須※】月変取扱い事例集でミスを防止!
こんにちは、名古屋で社労士事務所を開業準備中のもちづきです🌸
またまたドラゴンボールの話になってしまうのですが、
「映画ドラゴンボールZ復活のF」を観ました。
また作中悟空とベジータが修行で長いこと留守にしていたので、「あれ?この前のスーパーヒーローの映画でも修行してていなくなかった?」と家族に聞いたら、「悟空とベジータは大体修行してて地球にいない。」と教えてもらいました。
私なら2回もフリーザ倒したらもう自分が一番強いからいいかな~と思ってしまいそうなのですが、貪欲に「オラ、強くなりてえから!」で修行を続ける悟空とベジータって勉強熱心ですごいなあ・・・と思いました。
大人になってから見ると「強い」というよりも、「強くなりたい気持ちを薄めることなく修行を続ける」ことができることが凄い、と感じました。
大人になってから子供の時に見ていたアニメを見ると、また違うことに気づけて良いですね😊
前置きが長くなりました💦
今日は
【※労務初心者は履修必須※】月変取扱い事例集でミスを防止!
について投稿します。
労務の仕事の中で必ず発生するのが、「月額変更の手続き」です。
正式には随時改定といいますが、「月変(げっぺん)」というのが労務業界の共通言語ですよね。
この月変の手続きは、
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である
の3点が全てそろった時に手続きが発生します。
特に、労務ワーカー初心者の方に注意いただきたいのが、
「この3点に該当するしないという判断だけでは月変の確認は不十分で、高確率でミスが発生する」
ということです。
例えば、
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
の「変動」ってなんでしょうか?
「昇給または降給等」という文字から、
「基本給や手当が増えたり減ったりしたときが変動」
と思う方が多いと思います。
ですが、この変動には「新しく手当が作られた」という変化も含まれます。
8月支給の給与計算をしていた時、社長から「8月に○○手当を新しく作った。8月支給から全員に○○手当を1万円支給して欲しい。」と連絡が入ったとします。
この場合、「○○手当が新しく作られて初めて支給開始となった8月」を起算として、8月支払い、9月支払い、10月支払いで月変に該当するか見ていく必要があります。
このように、「変動があった」の中に様々な事例が含まれますし、いつを起算月にするかも様々なパターンがあります。
この様々なパターンが多すぎるので、社労士試験のテキストでは全て事細かに書かれていないことがほとんどです。
なので、社労士試験のテキストや、ネットのコラム記事の内容では対応できないのが月額変更です。
そこに書いてあることだけでは、全ての事例をさらえません。
「じゃあその事例が詳しくまとまっている何かは無いのか?」と思いますよね。
その詳しくまとまっているのが、
「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
です。
▼事例集PDF
この事例集は「日本年金機構 随時改定」で検索して出てきたページの「6.参考資料」です。
▼このページです!

定時決定のことも書いてあるので、算定基礎届提出の時期にも大活躍です。
見ていただくと、
・休業した場合
・手当の新設について
・月の途中で昇給降給
などなど、一見「そんなことあります?」みたいな例が書いてありますが、実際まあまああります。
毎月毎月必ず起こるわけでは無いのですが、何か月に1回とかでは発生するので、その度に「あれ?この場合どうやって判断するんだっけかな?」と悩み、事例集を確認していました。
怖いのが、この事例集を読んでいないと、完全にスルーしてしまうことです。
そして、労務の先輩は「知ってて当然でしょ?」という感じがある方もいるので、入社した時に「月変はこの事例集を必ず読んでね。」と教えてくれる先輩や事務所は少ないと思います。
なので、知らず知らずのうちに知らないままスルーして、後で「これ月変の対象で手続き必要だったんじゃ・・・」ということになりかねません。
この事例集は「読んでおくといいよ~」というレベルではありません。
「読まないと必ずミスするから絶対に読め!」というレベルです。
読んでから、自分でチェックリストに起こすとさらにミスが防げます。
「変動はこういうこと」というようにチェックリストを作っておいて、一つずつ「該当していない」チェックを入れておけば安心です。
また、この事例集を読んでも判断が難しい時もあります。
そんな時は日本年金機構へ電話して聞くこともOKです。
その際、ただ「わからないので教えてください。」と言うより、
「今回こういった事例があって、事例集の○○に当てはまると思いますが、判断が合っているか念のため確認させていただけませんか?」
と聞くと、スムーズに答えてくれます。
役所の方も忙しいので、自分でも悩んで調べて当たりを付けておくと話もしやすいですし、役所の方もやりやすいと感じてくれているのか、快く対応してくださる方がほとんどです。
この事例集、必ず確認して自分でミス防止策を作っておきましょう。
今回は強めに書いてしまいましたが、私が労務の仕事をしていてとても大切だと感じていた点なので熱く書いてしまいました。
私も月変手続きでミスしたことがあるので、読んでくださった方のミス防止に少しでも参考になれば幸いです。
ありがとうございました😌😌
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
