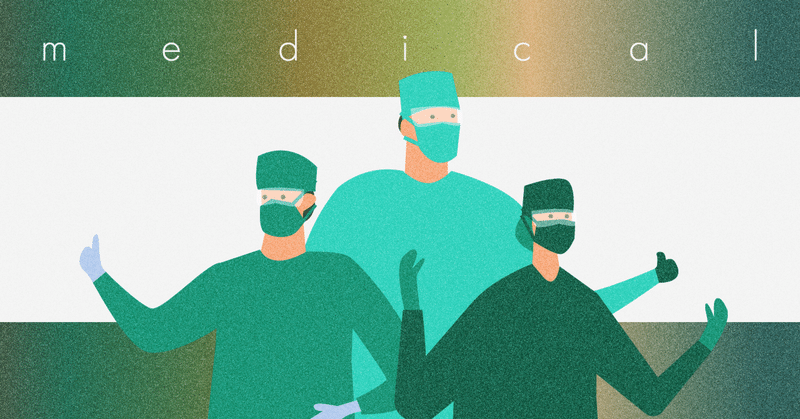
潰瘍性大腸炎の記録 #3:病名告知と最初の寛解
病名告知と最初の寛解
検査が終われば、次は外科教授の診察である。父親の友人の名誉教授に紹介されたこの先生は、温和な雰囲気の老教授だった。ただ、非常に無口な方で、こちらから質問しないとほとんどしゃべってくれないというのにはやや閉口したが、基本的には信頼できる雰囲気の人物だった。検査では内視鏡は奥まで入らなかったが、結局病変部は直腸部分が中心だったらしく、ここで正式に「潰瘍性大腸炎」という病名を告知された。自分としては検査中にあの二日酔い野郎が発した「一生モノ」という言葉が引っかかっており、その事を質問すると教授は「まあ、やっかいな病気なんだよね」と一言言っただけで、あとはナースに指示して、この病気についてのもろもろの資料を渡されたのだった。このとき、もらった資料の中に、難病認定患者が受けられる補助の申請書類があった。「潰瘍性大腸炎」と教授に告知されたときは、初めて耳にする病名でもあり、まだあまり実感を伴っていなかったのだが、帰宅して資料に目を通してどういう病気かを理解したとき、「難病患者」という響きは実に重たいものだった。自分がまさかそんな病気になるなんて、まさに青天の霹靂であった。
さて、老教授からは当面投薬による治療を行うと言われ、この日から、ペンタサとリンデロン座薬(ステロイド座薬)を処方されたのだった。ペンタサは、当時1日6錠。リンデロン座薬のステロイド量はあまり記憶が定かでないのだが、まず2mgあたりからスタートしたのではないかと思う。
大学病院での検査から診察というのは、実に時間がかかる。当然その間も病状は進行しているわけで、その当時、だんだん状況は悪くなってきているようだった。最初の下血のときは、食後に急に下痢がきたわけなのだが、その後、だんだん腹痛を起こす回数が増えていく。そのたびに下血を伴う下痢に襲われるという按配である。さすがにこうなると酒どころではない。それこそ人生において高校時代以来になろうかという全面禁酒に踏み切って、処方された薬をまじめに飲みながら、2週間に一度の大学病院通いをはじめることになったのだった。
余談だが、この老教授、さすがに大腸系の病気の専門家だけあって、診察もなかなかだった。というのも、ほぼ毎回、診察のたびに大腸を診察するのである。その診察の仕方がなかなかすごい。下着を脱いで四つんばいにされ、後ろからぶすりとやられるのである。最初は指なのだが、次に何か金属の拡張具のようなものを突っ込まれ、その後懐中電灯で直接目視確認のような診察である。ポーズ的にははっきり言ってかなり恥ずかしい。女性の患者にもこれをやっていたかどうかはわからないのだが、さすが年季の入った老教授、これがあまり痛くない。痛くないどころか、ケツに入れられたブツを抜くときなど、ちょっと背筋にゾクっとくるくらいうまくやってくれるというオマケ(?)つきで、さすがに年季の入った教授は違うなあ、という感じだったのである。
しばらくすると、明らかに病状が良くなってきた。下痢の回数が減ってきて、下血もだんだん少なくなり、ついに下血が目では確認できないようになった。最初の寛解である。ここまで来るのに、最初に薬をもらってから、およそ3ヶ月かかったと記憶している。ただ酒を断って、飲み薬と座薬だけで、まあ簡単に良くなったのである。下痢と下血さえなければ、健常者とは全く変わらない。難病患者としての医療費補助申請をしたにもかかわらず、自分がそういう持病もちであるという意識はまだまだ薄く、あっさり寛解したこともあって、結局病気を甘く見てしまったのだった。つまり、また酒を飲み始めてしまったのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
