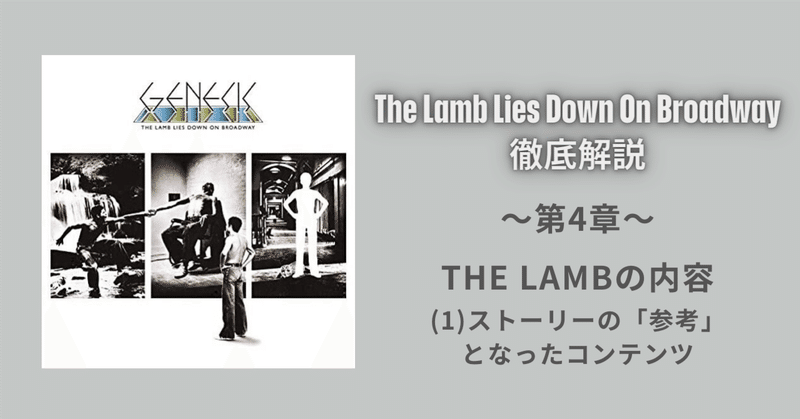
〜第4章〜 The Lambの内容 (1)ストーリーの「参考」となったコンテンツ
どのような芸術作品にも、そのベースというか、創作者がインスパイアされたネタというものがあるものです。ピーター・ガブリエルも、The Lambのストーリーを作るに当たって、様々なコンテンツを下敷き、参考にしています。これらは、これまでピーター・ガブリエルが直接言及したものだけでなく、研究者などに指摘されてきた資料も含んでいます。The Lambのストーリーを解釈するための「補助線」として、たいへん重要なものだと思います。
●ウエスト・サイド物語
1961年公開のアメリカのミュージカル映画。アカデミー賞11部門にノミネートされ、うち10部門を獲得したという大ヒット映画。ラブストーリーではあるが、プエルトリコ系アメリカンと、ポーランド系アメリカンのギャング団がニューヨークを舞台に繰り広げる抗争がストーリーのベースになっている。
【類似点】
恐らくこの作品は、The Lamb の主人公レエルが、ニューヨークの少年院帰りのギャングであり、その出自がプエルトリコであるということの元ネタです。また、ウエスト・サイド物語は、シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」的なラブストーリーを取り入れることによって物語の厚みを出しているわけです。The Lamb は、同じような主人公を設定して、「天路歴程」(後述)を取り入れているわけで、この物語構造はウェスト・サイド物語にインスパイアされているのだろうと指摘されています。ちなみに、The Lamb のストーリーではレエルは生粋のプエルトリコ人ではなく、プエルトリコ人のハーフだと表現されています。実際何人とのハーフかは明かされてされていませんが、この「ハーフ」という設定は完全にピーターの創作だろうと思います。
●天路歴程(The Pilgrim's Progress)
イギリスの作家ジョン・バニヤンが1684年に発表した宗教小説。「破滅の街」に住んでいたあるクリスチャンの男が様々な困難を通りぬけて理想的なクリスチャンとして成長し「天の都」にたどり着くまでの旅の記録という体裁の物語。
【類似点】
これもピーター・ガブリエルが真っ先に参考としてあげた書物です。彼はたびたび「天路歴程の現代パンク版のようなものを作ろうとした」と発言しています。これはThe Lamb の個々のエピソードの元ネタというよりは、物語全体の体裁を表現したものでしょう。主人公が荒廃した世界の住人で、そこから旅の途中での様々な苦難、困難を乗り越えて、主人公が成長し、最終的に救われるというストーリーは、The Lamb もほとんど同じであるからです。ただ、古来からの神話的なストーリーというものは、たいていがこのパターンであり、スターウォーズが数々の「神話」を下敷きにしているのと同じように、The Lamb も、他の多くの神話をインスピレーションの源としている可能性が高いと思います。結局 The Lambは、いわゆる Hero's Journey といわれるRPGでおなじみの物語スタイル(その起源はメソポタミアの「ギルガメッシュ叙事詩」まで遡れる)なのです。
●エル・トポ
1970年のアレハンドロ・ホドロフスキー監督、主演の映画。公開当時、アンディ・ウォーホルやジョン・レノンが熱狂的に支持し、ジョン・レノンに至っては、この作品と、ホドロフスキー監督の次回作の配給権を買い取ったというエピソードが残されている。ストーリーは、「創世記」「預言者たち」「詩篇」「黙示録」と旧約聖書に則った4部構成になっているが、一般的には「意味不明」と言われる極めてシュールなもの。自らを神と称するさすらいのガンマン、エル・トポをホドロフスキー自らが演じている。
【類似点】
この作品も、かなり早い段階でピーターが参考にしたとコメントしたものです。この作品は、「天路歴程」と違って、個々のエピソードの元ネタがいくつか含まれていると指摘されているようです。4人のマスターガンマンを殺せと愛人に依頼されたエル・トポが、突如現れた女性に導かれて2人目のガンマンの元にたどりつくシーン、また「洞窟内で暮らすフリークス(異形の人間たち)」、またこのフリークスを案内する女性が登場したり、主人公を池に誘い込む若い美女など、The Lamb のストーリーとのいくつかの類似点があると指摘されています。アイデア元でもあると同時に、ピーター・ガブリエルとしては、この作品を例に出すことで、いわゆるシュールレアリスム的な手法を取り入れているということも公表しておきたかったのではないかとも思います。
●フロイトとユング
ジークムント・フロイト(1856−1939)は、オーストリア精神科医・心理学者。カール・グスタフ・ユング(1875−1961)はスイスの精神科医・心理学者。「精神分析」という学術分野を確立したのはフロイトで、ユングはその弟子であったが、あるとき決別する。いずれも「夢」についての分析が特徴だが、二人のスタンスはかなり異なる。フロイトは、「夢は願望を充足させるもの」と考えたのに対し、ユングは「あるがままの姿で心の状況を描くもの」とし、「自我・意識に対する補償」と考えていた。
【類似点】
The Lambの制作当時、ガブリエルは自身の精神的な問題もあって、かなり熱心にフロイトやユングの著作を読んでいたことが知られています。直接どの著作が、The Lambのどのストーリーと結びつくというような話ではないのですが、やはり「夢」と「現実」の関係についてかなりいろいろと興味を持って調べていたことは事実でしょう。どちらかというと、フロイトよりユングの著作に傾倒した傾向があったようです。
さて、ここまでは、ピーター自身がアルバムリリース後にインタビューなどで自ら言及していた「参照コンテンツ」なのです。これだけでも、案外具体的なイメージはつかめるとは思います。つまりピーターが言う「天路歴程の現代パンク版のようなもの」というのが、やはり本質的な The Lamb のストーリーの骨子であるわけです。主人公は、ニューヨークで、誰にも顧みられないような最下層の若者(=悪人)であり、彼が精神的な旅を経て最後に救われる物語というわけです。そしてその「旅の過程」には、非常にシュールなエピソードが用意され、その背景には、フロイトやユングの夢分析のような心理的なものが隠されている。こういう理解で良いのだと思います。
実際ピーター・ガブリエルは、こんなことも言ってます。
In October 1974, for example, he revealed to Armando Gallo that he had been sleeping badly for months and was tormented by nightmares.
例えば、1974年10月、彼はアルマンド・ギャロに、何カ月も睡眠が浅く、悪夢に苦しめられていたと明かしている。
74年10月といえば、ちょうどアイランドスタジオでのマラソンミックス作業が佳境に入っていた頃ですが、「何ヶ月も」というのは、まさにHeadly Grange当たりからのことではないかと思われます。最終段階でも相変わらずかなり勝手なことをやっているわけですが、でもやっぱり精神的にはそうとう参っていたということなのです。そして、その間ユングの本などを読んでいたということでしょう。そして、そういう精神状態がやはりストーリーや歌詞に何らかの影響を与えたのだと思います。
During the "Lamb" tour, Gabriel explicitly named dreams, which are so important for Jung and Freud, as mediators between the unconscious and the conscious, as one of the central sources of inspiration for his story.
The Lamb のツアー中、ガブリエルは、ユングとフロイトにとって無意識と意識の仲介役として非常に重要な存在である夢を、物語の中心的なインスピレーションの源のひとつとして明確に挙げている
結局ピーターとしては、The Lamb の「空想」「夢」のような世界でのストーリーも、単に「夢そのもの」だけではなく、いずれも「現実との繋がりがあるもの」という意識だったのだと思います。
ところが、ピーターが参照したのはこれだけではありません。以下はピーターが自ら明らかにしたものではなく、他の人が指摘しているコンテンツです。これはあまりピーターとしては知られたくなかったものなのかもしれないのですが、こちらも非常に重要な「参考コンテンツ」だと思われます。
●チベット死者の書
肉体が機能を停止した後49日間、死者は意識だけの状態となり、その後新しい生命として再生するという輪廻思想に基づき、意識だけの49日間を切り抜けるための教えが書かれた書。もともとは、死者の枕元で49日間唱えられる経である。この49日にわたって「意識」が体験する光やビジョンはすべて死者自身の意識が作り出したもので一切が幻想であるとされる。60年代にハーバード大学教授が、LSD体験と死者の書の記述が類似していると指摘したことで、ヒッピーたちのバイブルともてはやされた。死者の書は、以下の3部で構成される
第1部 チカイ・バルド:肉体の死の瞬間の心霊現象に関する記述
第2部 チョーニッド・バルド:死直後の魂の旅を扱い、「カルマの幻想 」を伴う一連のエピソードの記述
第3部 シッドパ・バルド:魂が再生に向かって引き寄せられ、再生の準備のための記述
【類似点】
構成に類似の部分があるので、細かい指摘をする研究者がいます。The Lambのストーリーについては、冒頭からBroadway Melody of 1974までがチカイ・バルド、Cuckoo CocoonからLilywhite Lilithまでがチョーニッド・バルド、The Waiting RoomもしくはThe Lamiaからエンディングまでがシッドパ・バルドであるとの指摘です。言われて見れば何となくそんな感じも受けますね。ある意味「天路歴程」よりも、こちらの方が近いような印象すらあります。ただ、死者の書は、あくまで「死者」の魂がさまよった後、別の生命として生まれ変わるという前提ですが、ここはそっくりThe Lambには採り入れられてないようにも思います。
●ホーリー・マウンテン
エル・トポ同様、アレハンドロ・ホドロフスキー監督・主演の映画(1973年公開)ホドロフスキーが扮する錬金術師が9人の仲間とともにホーリー・マウンテン(聖なる山)を目指すストーリーだが、前作と同じくシュールなもの。この映画の最大のトピックは、映画の最後に役者が「これは映画だ」とネタばらしする部分。ホーリーマウンテンにたどりついた役者が、「ズームバック、カメラ!」と言うと、カメラが引いて、それまで画面外だったセットや照明、スタッフが見えて、最後に役者が「さようなら聖なる山、実生活が私たちを待っている」と言ってエンディングとなる。
【類似点】
映画には性器が容器に入れられる去勢のシーンがあり、これがレエルが去勢手術を受け、自分の性器をチューブに入れたストーリーの元になった可能性が指摘されています。また、映画のエンディングのネタばらし的なオチは、「今見た(聴いた)ばかりのストーリーを脱神話化する」作用であり、The Lambのエンディング曲 it の役割と同じであると指摘する人もいます。
●チャンピオンたちの朝食(Breakfast of Champions)
アメリカの作家カート・ヴォネガット・ジュニアによる1973年の長編小説。ヴォネガット作品複数に登場する、SF作家キルゴア・トラウトを主人公としているが、作品終盤に作者ヴォネガット本人が「わたし」として登場する。この作品についてもピーターは言及していないが、トニー・バンクスは2013年のインタビューで次のように述べている。"I think some of the lyrics are great. But I don’t enjoy the story as a whole. It owes quite a bit to Kurt Vonnegut’s The Breakfast Of Champions."(歌詞の一部は素晴らしいが、ストーリー全体は僕には楽しめない。カート・ヴォネガットの「チャンピオンたちの朝食」にかなり負っているからね)。
【類似点】
この作品には、「まえがき」が存在します。この前書きは、いかにもカート・ヴォネガット本人が書いているような感じで進むのですが、最後のところに、まったく別名の謎の人物の署名がされているのです。文章を注意深く読めば、これが作者の変名である可能性が高く、やはりこれは作者本人の前書きである可能性が高いわけですが、かなり凝ったというか、人を食ったような仕掛けがされています。また本編にも「作者」が登場するという、いわゆるメタフィクションと言われる作風の小説です。ヴォネガットの前作「スローターハウス5」でも、同様のスタイルがとられています。トニー・バンクスが言うように、この当時ピーターがカート・ヴォネガット作品をよく読んでいたようで、ストーリー全体のトーンや文体なども、この作家に影響を受けてる可能性があると思います。特にこの作品の「まえがき」部分は、"Keep your fingers out of my eye. "で始まる、あのインナースリーブの物語の冒頭部分(物語に対する前書き部分)のアイデア元である可能性は高いと思います。(この件は後に詳述します)
ちなみに、The Lambの日本版初版LPのライナーで立川直樹氏が、「スローターハウス5」に言及しています。あのライナー執筆時点の情報量のなかで、この作品に目を付けるとは、大変な慧眼だと思います。
●意識(サイクロン)の中心―内的空間の自叙伝(Center of the Cyclone)
アメリカの医師・哲学者・発明家であるジョン・C・リリー(John Cunningham Lilly)の著作。リリーは50年代に人間を一切の外的刺激から隔離するアイソレーション・タンクを開発し、様々な実験を行った。また、自らLSDを体験し、意識と心の内面世界の問題を研究した。60年代のカウンターカルチャー、サイケデリックムーブメントにおいて第一人者として注目された研究者。
【類似点】
洞窟の中にひとり取り残されるシーンを着想した背景に、彼の開発したアイソレーション・タンクによる実験があったのではないかという指摘があります。ピーター・ガブリエルはこのアイソレーション・タンクを後に個人で購入するなど、かなり興味を持っていたそうです。また、洞窟内でレエルを案内するLily White Lilithに登場する女性 Lilith は、本来ギリシャ神話からの由来であるとされているのですが、この本の著者Lilyとの類似を指摘する人もいます。
もちろん、これが全てではなく、聖書はもとより、古典的な詩、ギリシャ神話、民間伝承など、ピーター・ガブリエルがそれまでの人生で接してきたさまざまなものが物語のヒントになっていたりするはずです。音楽の世界では、以前にヒットしたThe Whoのコンセプトアルバム Tommy(映画はThe Lambの後の作品なので純粋にアルバムのみ)や、Jethro TullのA Passon Play(キリスト受難劇が下敷きとなっている)なども頭の片隅にあったはずだと思います。
そしてそういうあらゆるものがごちゃ混ぜになってアウトプットされたのが、The Lambではないかと思うのです。
その中で感じるのは、「チベット死者の書」とか、「意識(サイクロン)の中心」などは、いずれも60年代のヒッピー文化の流れで流行った書籍だと思うのです。ピーター・ガブリエルは、このヒッピー文化の中心世代からはちょうど1世代くらい下ではあるのですが、やはりカウンターカルチャーの影響を相当受けているような気がします。
正直わたしも、映画もYouTubeでトレイラーしか見てません(ネタバレサイトなどはいくつか見ましたがw)、本も「チャンピオンたちの朝食」は入手しましたが、「まえがき」しか読んでいません(笑) それでも、こういう作品が「補助線」としてあると知ったことで、ちょっとだけピーター・ガブリエルの頭の中に迫ったような感じがして、The Lamb の諸々がなんか「腑に落ちる」感が増したと思います。それでいいのです(笑)
もし、英語が苦にならない人でしたら、カート・ヴォネガット・ジュニアの作品を原語で読むと更なる新しい発見があるかもしれません(^^)
次の記事
前の記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
