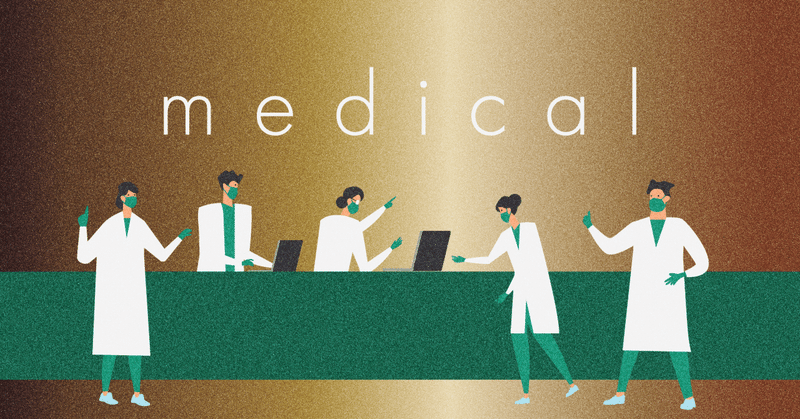
潰瘍性大腸炎の記録 #6:神経内科と貧血、そして転院
神経内科と貧血、そして転院
頭痛と大腸の病気はまったく関係ないと言われ、大腸炎の投薬は、結局このときも変わらなかった。判で押したように以前と同じ量がきっちり処方された。カミさんの実家近くの開業医が言いにくそうに「大腸炎の治療がうまく行ってないと思う」という意見をのべてくれたのだが、教授には全く伝わらなかった。血液検査のデータを見せても、結局「たいしたことないね」の一言で終わったのだった。
ただ、その時は、まず夜も眠れないほどの頭痛を何とかしないと、まともに仕事もできない。とにかく紹介された神経内科を受診することにした。ここでも最初は検査ではじまる。頭痛を訴えて神経内科に行くと、まずセオリーとしては髄膜炎あたりをうたがって、その検査を行うようなのだが、もろもろの検査はすべてパス。結局、重篤な病気の疑いはないので、ロキソニン飲んで安静にしててね、ということになった。
ここでは普通にロキソニンを処方してくれたので、それだけは救いだったが、やはり1日3錠は変わらなかった。そこで、これをいつ飲むのかというのがやはり毎日の大問題となった。まず寝る前の1錠は欠かせない。これによって3時間だけ頭痛から開放されて熟睡できるのだ。3時間後に薬が切れると、再び頭痛が襲ってきて、もうそれからはほとんど寝ることができないのだが、それはしょうがない。ここで次の1錠を消費してしまうわけにはいかないのだ。次は朝食後に会社に向かうが、昼間に残されたのはあと2錠だけだ。これをいつ飲むのかは、あまり決めずに仕事をして、とにかく耐えられるだけ耐えて、耐えられなくなったら飲むみたいなことをやっていた。何とか仕事に復帰したらしたで、仕事は相変わらず忙しく、残業どころか休日出勤することさえあった。ある日、自分の車で休日出勤した帰りに追突事故をもらったりして、もう踏んだり蹴ったりの日常だったのだが、それでも、数週間かけてゆっくりと頭痛が緩和されてきて、なんとか頭痛からは離脱することができた。ただ、そうなっても、大腸のほうは相変わらずだったのだが。
このことがあってから、大学病院では大きな変化がおきた。それは、教授の診察日に病院に行っても、当の教授は診察に一切出てこなくなったのである。診察に行く度に、講師とか助手とか、その下の若手医師とか、外科の教授以外のスタッフがとっかえひっかえ出てくるようになったのである。今思えば、このときこの大学病院を見切ればよかったのだと本当に思うのだが、やはりあの「大腸内視鏡検査」が強烈すぎて、その時は病院は変えずに、あのクソ教授以外の先生ならまだなんとかなるかもしれないと一縷の望みを持っていたのだった。
ところが外科の教授以外のスタッフは、これまた微妙な連中ばっかりだった。助教授は、教授よりはだいぶ年配に見えた。自分の頭の上にどこか他からスライドしてきた教授に頭が上がらないのだろう。陰気そのもので、それがそのまま顔に出ていて、まるで死神博士だった。一方、講師は妙に明るくて話好きのキャラクターだったが、「まあね、この病気は行くとこまで行くと、大腸全摘出って手術があるんですよ。全部とっちゃうとね、もう病気は体にないわけだからね、それで良くなるんですよ」などという、本当に闘病中の患者の気が滅入るようなことを平気で放言して、何にも感じてないような奴だった。本当に無神経というかなんというか。まあ外科の医者というのは、わりとこの手の人間が多いような気もするのだが...。そして、もう一人、一番若手のちょっと頼りなさげな医者がいた。こうして外来に出てくる医者はこの3人がとっかえひっかえという状況になったのだが、結局今までと同じ硬直的な投薬がずーーーと続くだけで、何か別の薬が処方されるとか、容量が変わるなどは一切なかったのだった。
そうこうしているうちに、会社の健診があった。このとき血液検査でひっかかった。「ひどい状態の貧血なので、すぐに治療を要する」という結果が返ってきたのだった。言われてみれば、そりゃそうだろう。だって、毎日何回も下血してるわけで、血は足りなくなるよなあと。ただ、これまで大学病院に2週間に1度必ず行っていたにもかかわらず、この大学病院でただの1度も血液検査をしなかったということにも同時に思い当たる。あの頭痛騒動の時も、外科では血液検査すらしてくれなかった。結局この大学病院の教授以下スタッフは、こういう患者に対して、一切貧血のケアもしないで、いつも同じ薬だけを延々と処方し続けたのだ。そういえば、新しい教授に変わって以降、前教授のようなぶすりとやられるような診察も一度もなかった。こいつら本当に治療する気があるのか・・。と、さすがに腹が立ってきたのだった。ただまあこちらもお人好しである。さすがにこういう結果が出れば、少しは違うこと考えるのではないかとも思い、早速その結果を持ってまた診察に行ったのだった。するとその日出てきたのは、一番下っ端の若造医者だった。そして、おもむろに「では血液検査してください」といわれ、この大学病院で初めての血液検査に望んだのだった。そして、その日にあがってきた血液検査データを見た彼は、こう言ったのだ。
「あの、入院してもらえますか」
これにはさすがに驚いた。全く想定してなかったリアクションである。
「はあ? そんなにひどい状態なんですか?」
「確かにかなり貧血が進行していますので、輸血したいと思います。通院でもできなくはないのですが、念の為に入院して治療したいと思います」
この話を聞いて、ついに堪忍袋の尾が切れた。その場で怒鳴ったりはしなかったが、これはもうだめだと思った。こんな病院にいたら、殺される。自分の命は自分で守らなければならない。どんなに検査がつらくても、この病院にいるよりはましだ。このとき、この大学病院に通ってすでに2年以上が経過していたがようやく、この大学病院に訣別する決心がついた瞬間だった。
「もう結構です。他の病院に転院したいので、紹介状を書いて、カルテを全部いただきたい」
すると、特に動じた感じでもなく、その医者は「わかりました。では処理しますのでおまちください」と淡々と言うのだった。
ということで、本当に拍子抜けするくらいあっさりと転院することになったのだった。これは推測ではあるが、あの頭痛事件以降、あそこの外科教室では、恐らく私はクレーマーみたいな厄介な患者として認識されていたのだろう。前教授は外科でありながら、たまたま潰瘍性大腸炎をよく見ていて内科的処置にも通じていた医者だったのだろうが、新しい教授は本来の意味の外科医であり、切った張ったしか興味がない人に違いなかった。私が診察に行ったときに、となりのブースに教授がいて、手術後の患者にたいして、「ほらー、よくなったでしょー」みたいな声をかけているのを何度か聞いたことがあるのだが、そういうことなのだ。他のスタッフも、投薬だけという患者なんか、できれば他行ってくれという意識だったに違いない。だから、このときの私の判断も、きっと渡りに船だったのだろう。
結局この大学病院は、目線が患者に据えられていないのだと思う。最初のひどい内視鏡検査の後、1時間近くもロビーの椅子に倒れていても、病院のスタッフが誰一人声もかけてくれるようなこともない。本当にひどい症状でわらにもすがる思いで来ている患者に対する医者やナースの態度、もろもろすべてがあまりにもひどい。いや、「この大学病院」と主語を大きくしてはいけないのだろう。でも、この外科教授の教室だけは、ナースを含むすべてのスタッフが、教授だけを見ていて、患者を見ていないと断言できる。父親の友人の名誉教授の紹介とはいえ、とんでもない病院に行ってしまった。この2年間はもう取り返せないが、とにかく自分を守るためには次に向かうしかないのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
