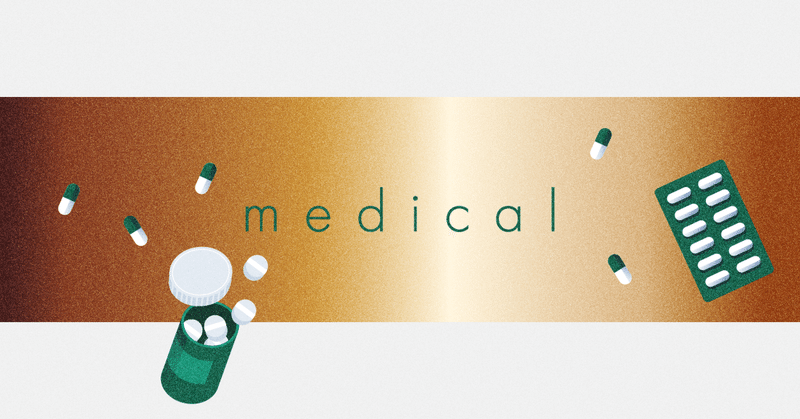
潰瘍性大腸炎の記録 #1:はじめに〜前兆
はじめに
私が潰瘍性大腸炎を発病したのは、1997年(38歳)のときのことだ。ちょうど、サラリーマンとしての仕事に脂がのりはじめ、私生活では結婚10年目にしてようやく長男に恵まれた直後というタイミング。まさに人生これからというところでの発症だった。そして、それからの約7年間にわたる闘病は、なかなか紆余曲折があり、大変な経験だった。
これを書いているのは2022年。発病から四半世紀近くが経過しているが、すでに15年以上の長期寛解を継続中であり、普通の人と何ら変わらない生活を送ることができるようになっている。安倍元総裁の持病としても有名になったこの病気は、今でも「難病」というカテゴリに分類されるため、誤解や偏見で見られることも多いのだが、医療技術や知見が蓄積された現在、かなりの方が克服可能な病気になってきているように思う。
ネットにはこの病気の闘病記を綴られている方も多くいらっしゃるが、現在進行形の闘病記というのは、とかく改善しない症状についてのリアルタイムな記述であることが多く、病名を告知された後、ネットを検索してこれらの闘病記を読んで、絶望的な気分になってしまう方がいるかもしれない。当時の私がまさにそれだった。
しかし、紆余曲折を経たが、2005年頃からはほとんど普通の人と変わらぬ生活を送れるようになっている。この状態がいつまで続くのかわからないし、また暗転する日が来るのかもしれないが、「こんな人もいるよ」ということが、何かの役に立つこともあるかもしれないと思い、今までの経過を記録しておくことにした。
このような病気との闘いというのは、私の人生初めての経験だった。またそのことで人生観が変わるような出来事にも遭遇することにもなった。還暦を過ぎた今ふり返ると、まさに自分の人生そのものにかなり大きな影響を与えた出来事だったのだと思う。
前兆
私が大学を卒業して企業に就職したのは1982年のこと。会社では最初の1年だけ営業を経験したのだが、2年目から企画系に異動となり、以後一貫して企画系の仕事をしていた。この会社の企画系の人たちの間では、打ち合わせと称して酒を飲むことが日常的に行われていた。ついでに言うと、その経費もかなり寛大に会社が処理してくれるという文化が当時はまだ残っていた。地元では、学生が酒を飲んで騒ぐことで有名な某地方大学出身の私は、大学在学中に酒の味を覚え、さらにそんな会社に就職したおかげで、入社以来酒量と体重が直線的に増えていくという生活を、その時すでに15年近く続けていた。
仕事はそれなりに忙しく、締め切りを抱えたりして結構なストレスもあり、仕事を口実に酒を飲んでも、結局最後は自分の憂さ晴らしになってしまっていたのだった。20代の頃は、それでもまだ有り余る体力のおかげで、相当無茶をしても仕事に穴を空けたりすることなどは皆無で、自分なりに人並み以上には働いていたつもりだった。しかし、さすがに35歳もすぎ、大酒を飲むと次の日がかなりつらいという状態になりはじめていた。それでも酒の魔力に抗えず、また昔からの惰性的生活習慣はちょっとやそっとでは変わらず、飲み始めると、もう1本とか、もう一軒となってしまい、翌日ちょろっと後悔するという状態は相変わらずだった。ただ、以前とちがって、後悔の度がだんだん上がってきて、「俺もそろそろ少しはセーブしないとな」なんて頭の片隅では思うのだが、やっぱり飲み始めると・・・という調子だった。
今にして思うと、最初の異変は皮膚病だった。もともと皮膚方面はあまり強くなかったのだが、あるとき妙に頭皮からかなりのフケが出るようになる。それも、大酒を飲むとてきめん大量のフケが出るのだ。そうこうしているうちに、足にかなりの面積のかぶれが出て、皮膚科を尋ねると、「尋常性乾癬」なる病名を告げられた。ただ、皮膚がちょっとかぶれる程度の病気ではなかなか生活習慣を変えるには至らず、適当に薬を塗りながらだましだまし、相変わらず酒を飲む生活を続けていた。皮膚科の医者も、「少し酒を控えろ」とは言ったが、「絶対に飲むな」とは言わなかった。結局こういうことを都合よく解釈して、「1杯のつもりが、いつのまにやらハシゴ酒」という長年の習慣はそうそう変わるものではなかった。
そして、次に異変が訪れたのは血尿だった。いや、正確に言えば、最初は「尿」ではなく「精液」だったのだが・・。本来白いはずのものが、真っ赤であるというのは、これはこれで相当なインパクトである。しかも、その後放尿のたびに真っ赤な尿が出るとあっては、さすがに仰天して、このときばかりは酒も控えてすぐに医者に駆け込んだのだった。このときはいろいろ検査しても明確な原因がわからずに、結局抗生物質の投与でそのうち直ったのではあったが、これはその後2度程再発した。再発のタイミングはいずれも二日酔いの日だったような覚えがある。結局、喉元すぎれば元の生活だったのである。ちょうどそんな折、36歳になって初めて子供に恵まれ、プライベートでも随分忙しくなっていた時期のこと、今度は会社の健康診断の検便で、引っかかったのだった。
検査の結果は「便潜血反応が+なので要再検査」というものだった。要するに、便に血液が混じっているので、再検査せよとのことだったのだ。仕方なく、会社指定のある病院に出向くことになった。そのとき再検査に行った病院は、東京都内の某私鉄駅至近の立地にも関わらず、その日、私以外にいたのは、私と同じ理由で訪れた同じ会社の社員たった一人だけなのであった。いくら平日の昼間でも、近所のご老人などが待合室にそれなりにいるのが普通の病院だと思うのだが、この病院は、どういうわけか、近所のご老人など一人もいないのだった。あらためて私の会社専用の診療日かと思ったが、どうもそのようでもなく、奇妙に薄ら寒い雰囲気の病院なのだった。
そこでいよいよ、院長先生の問診となるのだが、この先生健康診断の結果データを見るなり、「ちゃんと検査するには大腸内視鏡をやらないといけないんですよね。やります? やるならここの病院には設備がないんで、紹介状かきますけど。」という実におおらかな問いかけ。「大腸内視鏡」なんて、当時は聞いただけで震えてしまうほどのインパクトのある言葉であり、内心ビビリまくりながら、「いや、それはー・・。そういえば、痔があるので出血はそっちの方じゃないかと・・」と消え入るような声で答えたのだった。するとその先生は「じゃ、少し様子を見ましょうか。」と言って、カルテになにやら書き付けて、そのまま薬ももらわず、何事もなかったかのように無罪放免になったのだった。
もしこのとき、「これは大腸内視鏡をやるべきでしょう。はじめてですか? いやあれはそんなに恐れなくても大丈夫ですよ。胃カメラなんかよりずっと楽ですから。」なんて言ってくれたら、検査もしてみる気になったかもしれないし、そうすればもっと早期に潰瘍性大腸炎が発見できたのかもしれない。ただ、今となっては、いずれも「たら」「れば」の話であり、このとき早期発見できたからといって、即禁酒したわけも無かったと思うので、結局同じことだったのかもしれないのだが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
