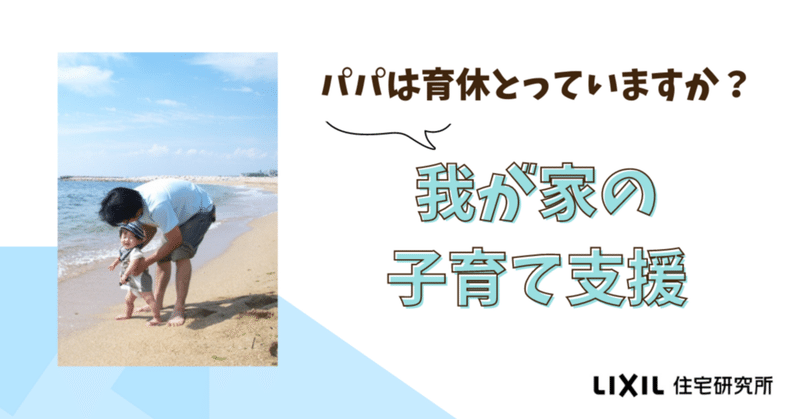
パパの育休取得状況は?育休中に助かったことは?-我が家の子育て支援 vol.2-
みなさん、こんにちは。LIXIL住宅研究所note編集部です。
アイフルホームの家づくりに参加している「ママアンバサダー」にご協力いただいたエピソード集の第三弾として「我が家の子育て支援」をテーマに5回連載でご紹介しています。
第二回目は、『パパの育休取得状況は?育休中に助かったことは?』編です。パパの育休取得は、とりやすい職場や職業、とりにくい職場や職業などさまざまだと思います。しかし、出産後のママのケアのためにも、パパの育休はとても重要です。パパとママががっちりスクラムを組んで、子育てするためにも、パパの育休取得はもっと当たり前になればと思っています。
今回のレポートでは、パパの育休の取得状況と育休中に助かったことについてご紹介します。
※これまでのnoteの子育てエピソード「我が家の子育て支援」第1回目はコチラ!
パパの育休取得率は30.2%
ママアンバサダー43名の内、育休をとったパパは13名=30.2%となりました。一方、育休をとらなかったパパが27名=62.8%、育休の代わりに有休をとったパパが3名=7.0%となりました。

育休をとらなかったパパが62.8%
・とっていない。職場がとれる雰囲気ではないらしい。悲しいです。
・育休はとれたことがないです( ;꒳; )
2021年の厚生労働省の調査によると、民間企業勤務のパパの育休の取得率は13.97%。2020年12.65%、2019年7.48%となっていて、徐々に増加していますが、まだまだ低いのが実情です。つまり約86%のパパが育休を取得していないことになります。
今回のアンケートでは62.8%のパパが育休を取得していない結果だったので、ママアンバサダーのご家族においては、厚生労働省の調査結果よりも多くのパパが育休をとっているということですね。
一方、2022年10月に「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」が施行されました。これをきっかけにさらに育休をとれるパパが多くなればと思っています!
育休の代わりに有休で対応=7.0%
・育休ではなく、産まれた日から5日間有休。市役所に届出をやって
もらえて助かりました。
・有休として1週間取得。自分の睡眠時間が確保できて助かりました。
また、買い物をはじめ、家事をしてもらえたこともありがたかったです。
・有休をしっかり2ヶ月まるまる消化。パパがいてくれるだけで助かり
ました。産褥期⁽¹⁾、私は本当にゆっくり寝て過ごしました。
(1) 産褥期(さんじょくき):出産後のカラダが元の状態に戻るまでのおよそ6~8週間の期間のこと
様々な状況から有休を取得して、ママをサポートした事例です。パパが出産後のママのケアをしっかりするためには、ある程度まとまった休みが必要ですね。
育休がとりにくいなら、せめて子育て期間中の在宅勤務を!
・育休無しでしたが、テレワーク体制で子どもの幼稚園送迎だけでも
助かりました。
・育休はとってないけど、在宅勤務にしてくれたおかげで幼稚園の
お迎えに行ったり、行事に参加できた。
コロナ禍で増加した在宅勤務やテレワークのおかげで、パパが子育てをサポートしてくれて助かったとのエピソードです。育休をとりにくい職場や職種などでは、子育て支援の観点からパパの在宅勤務を進めることも一案と思います。

育休を取得したパパ。育休の期間は?
今回のアンケートでは、育休の期間でもっとも多かったのが2週間で13名中4名、続いて2ヶ月が3名、1週間と1ヶ月が各2名。3ヶ月、6ヶ月(3ヶ月が2回)が各1名でした。

パパの育休で助かったことは?
パパが育休や有休をとったご家庭でママが「パパが育休をとってくれてよかった!」と感じたエピソードを3つ紹介します!
①ママの身体が回復しない間のサポート
・最初はやっぱりたいへんなので育休とってくれて助かりました。
・身体が回復しない間は基本的な家事は全てやってくれて、私は子どもの
世話だけに集中できました。
・産後動けなかったので、出生手続きなどをしてくれて助かりました。
産後のママは身体的にとてもたいへんです。この時期にパパが育休をとってサポートすることはママの早めの回復にも結びつくと思います。

②上の子の育児をサポート
・上の子の育児やご飯など炊事洗濯など全てしてくれとても助かりました。
・上の子の保育園の送り迎えをしてくれたのが助かりました。
・下の子の出産で私が入院する際に上の子と一緒に自宅で過ごしてくれた。
第二子の出産の時に一番の気がかりが上の子の世話です。パパが育休をとってくれて、しっかり上の子を見ることで、ママも安心して出産&産褥期をすごすことができます。

③パパの子育て意識の改革
・育休のおかげで仕事より子育てが大変だ、と身をもって実感したみたい。
・助かったエピソードはないです。育休取る前に、父親学級などで
しっかりお世話のことを理解して欲しかったです。
いつもは育児に協力しないパパが育休をとったことがきっかけで育児の大変さを知ったようです。さらに「助かったエピソードは無い」との厳しいコメントもありました。育児はパパとママが協力するのが当然です。パパも育休の時だけでなく、普段から育児に協力しましょう!
さいごに
職場環境、業種・職種、会社の制度などから、パパの育休の取得はまだまだ少ないようです。育休がとりにくい状況もあるとは思いますが、一番大事なママと子どもたちをサポートするのはパパの責任です。少なくとも、産後のママが身体的にたいへんな時期は、パパが育休をとって産後のママをしっかりケアする必要があると感じました。
さらに第二子以降は、もっとパパのサポートが必要となります。パパの育休取得が当たり前になり、パパとママが協力して育児を楽しめる社会が実現して欲しいと思います。
次回「我が家の子育て支援」の3回目は、「子育て中にパニック!その時欲しかったサポートとは?」を紹介する予定ですので、皆さんお楽しみに!

