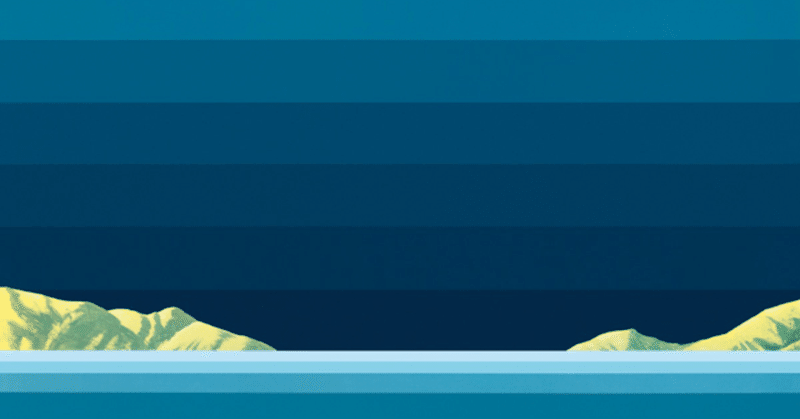
静寂の外れ値、異端のECM作品
初めまして、尾野と申す者です。
自宅にテレビがないので、はまじあき先生原作の『ぼっち・ざ・ろっく』アニメ第1期の盛り上がりを蚊帳の外から眺めていたのですが、遂に堪えきれなくなって漫画を全巻購入してしまいました。
そして読了した結果、音楽へのモチベーションが爆上がりしてこの記事を執筆するに至っています。偏屈者が偏屈な感性で選んだ偏屈なディスクレビューなので需要があるかは分かりませんが、参考にして頂ければ幸いです。
はじめに
1969年にミュンヘンでマンフレート・アイヒャーが設立したECM Recordsは、残響感のある透徹な音作りの面で、言わずと知れたジャズや古楽、現代音楽の有名レーベルです。コンセプトの”The Most Beautiful Sound Next To Silence”に象徴される、石庭の如き幽玄美と空白美に貫かれたアルバム群は人々の心を掴んで止まず、日本でもECM全作品に関する詳細なディスクガイド、そしてその改訂版が東京キララ社より出版されています。改訂版は940ページある大著です。
そのECM Recordsからリリースされた膨大な作品の中には、このコンセプトから多少なりとも逸脱したアルバムが含まれています。今回は、そんな「らしくない」アルバムを色々と紹介していきます。
有名な作品;ECM Records
本題に移る前に、ECMの主要作品についても紹介しておきます。人によって多少違いがあると思いますが、セールスや知名度を加味するとこの辺りに落ち着くのではないかと。
Chick Corea - Return to Forever (ECM 1022, 1972年発表)
Keith Jarrett - The Köln Concert (ECM 1064/1065 ST, 1975年発表)
Pat Metheny Group - Offramp (ECM 1216, 1982年発表)
『かもめ』の通称で今なお親しまれている『Return to Foever』や、400万枚というワールドレコード級のセールスを記録した『The Köln Concert』、いずれも名盤揃いです。とは言え、これらは今回の本題ではないので詳細な説明は省きます。何ならユニクロのTシャツの柄に選ばれるほどですから、音楽を全く聴かない人でもジャケットくらいは知っていると思います。なので今回は、ECM Recordsの定番からかなり遠いところにある作品を紹介していきます
Robin Kenyatta - Girl from Martinique (ECM 1008 ST, 1971年発表)
ジャズファンクやフリージャズの領域で活動した金管奏者のロビン・ケニヤッタが初期のECMに残した音源です。ベースのアリド・アンデルセンは現在までECM Recordsを代表する演奏家として活動していますが、リーダーのケニヤッタを含め、鍵盤のウォルフガング・ダウナーやドラムのフレッド・ブレースフルは一時的にECMに参加したのみです。余談ですが、ダウナーの『Output』もECMらしくないECM作品として語られることが多いので、そちらも聴いてみてはいかがでしょうか。
後代に確立されるレーベルカラーとは一味違う、スピリチュアルかつスペイシーな響きには、当時隆盛を見せつつあったアフロ・フーチャリズムと類似したものを感じます。ファンク畑のケニヤッタと当時アバンギャルド方面に傾倒していたダウナーの音楽性が融合した結果のの「再発明」なのか、あるいは意識されていたのか。残響感はそこまで無いので、ECMらしさを期待して聴くのは適さないでしょう。
John Abercrombie - Timeless (ECM 1047, 1975年発表)
電化マイルスに始まり、Mahavishnu Orchestraやレーベル移籍後のReturn to Forever、Weather Reportといったジャズロックやクロスオーバーを演奏するバンドが全盛期を迎えていた60年代末期から70年代。後にECMを代表するギタリストの1人となるジョン・アバークロンビーのECMに於ける初リーダー作の『Timeless』はそんな時代の真っ只中の1975年にリリースされています。
1曲目の『Lungs』は、前半では切迫した演奏で高速フレーズを連発し、後半部では一転して浮遊感漂う即興演奏が繰り広げられるという2部構成、4曲目の『Rea and Orange』は教会旋法を早回しで展開するハマーのプレイが印象的です。一方で2曲目の『Love Song』や表題曲の『Timeless』ではアコースティック・ギターや幻想的なシンセサイザーが登場したりなど、ジャズロック一辺倒ではありません。両脚をロックの領域に突っ込んでいますが、ジャズとしての体裁が保たれるラインは踏み越えていない、理想的なジャズロックです。
Arild Andersen - Molde Concert (ECM 1236, 1982年発表)
1981年のモールド国際ジャズフェスティバルでの録音。アリド・アンデルセン、ビル・フリゼール、ジョン・タイラー、アルフォンソ・ムザーンによるカルテット編成での演奏です。サブスクリプションで公開されている音源はCDで再発された際のもので、ボーナストラックが3曲追加され、曲順も変更されています。
ECMらしい静と暴発寸前のエネルギーを秘めた動が込められているというか、各々が離散しようとするのをアンデルセンのベースがジャズの形態に押し留めているというか、先に紹介した『Timeless』と同じくジャズ・ロックに分類されるようなアルバムですが趣きが異なります。快速に飛ばすフリーゼルのギターとタイラーのピアノ、それを煽る手数の多いムザーンのドラムス、それらを纏め上げてジャズとしての指向性を持たせるアンデルセンのベース。担っている役割の違いに注目しても楽しいアルバムです。
Shanker / Caroline - The Epidemics (ECM 1308, 1986年発表)
ドラムマシンが刻む電子音と歯切れのよいエレキギター、背景で微かに鳴るシンセサイザー、テクノポップ或いはニュー・ウェイブを見据えた方向性はECM Records随一の異色作です。
自身が考案したダブルネック・バイオリンを得物とするインド人バイオリニストのラクシュミラナヤーナ・シャンカーが、ボーカリスト兼鍵盤奏者としてキャロライン・モルガンを迎えて制作された本作、レーベルカラーとの乖離から評価に悩むアルバムです。Ulrich Laskの『Lask』然り、1980年代のECMはポストパンクに対しても意欲を示していたようですが、この場合はECMでテクノポップを演奏するという行為そのものが実験要素なんでしょうかね?
上記の通り、作品としては真面目にポップスしているので気を張らずに聴けます。6曲目の『No Cure』と7曲目の『Don’t I know you』ではシャンカーがオリエンタルなバイオリンを披露しており、常に存在感を示す線の荒いギターと合わせて東南アジアのヒットチャートにあって違和感ない内容です。
David Torn - Cloud About Mercury (ECM 1322, 1987年発表)
エフェクトやサンプリングを大胆に駆使した演奏に定評のあるギタリスト、デヴィッド・トーンがリーダーを務めた1987年のアルバム。King Crimsonのメンバーを勤めたトニー・レヴィンとビル・ブルーフォードが参加しており、プログレッシブ・ロック方面でも有名とのこと。金管楽器は映画音楽家として数多くのサントラを手がけるマーク・アイシャムです。
King Crimsonの2人が参加しているのもあって、Islands期のKing Crimson或いはHatfield & the Northのようなカンタベリー・ロックの音楽性に近いものを感じます。残響感に伴って透徹な雰囲気を漂わせながらも、リズム隊の2人がドラムシンセやチャップマン・スティックなどを用いた変態的な音使いでプログレへの接近を見せる、何とも表現の難しい音楽です。気怠げなアイシャムのトランペットは最晩年のマイルス・デイヴィスを思わせます。金切り声のように鋭いトーンのギターソロと織りなす対比も美しく、奇を衒った構成が見事に成功している意欲作。
終わりに
ECM Recordsに限らず、傑作として評価されるアルバムは一握りです。ヒットチャートや名盤番付を見ていると、あたかもそれ以外に聴くべき音楽は存在しないように感じられます。実際それは仕方ないことで、傑作ばかりの世界の外に足を踏み出すと、アルバムと趣味嗜好と合致しない空振りを経験することが増えます。とは言え、音楽の深淵を覗き込まんと欲すれば興味の有無な踏み越えていく気概が必要です。しかし、それは難しいことではありません。名盤を聴くなら、そのカタログ番号が隣り合っているアルバムまで聴いてみる、そういった心掛けで案外簡単に克服できるものです。
そしてぼざろを買いましょう。買え(豹変)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
