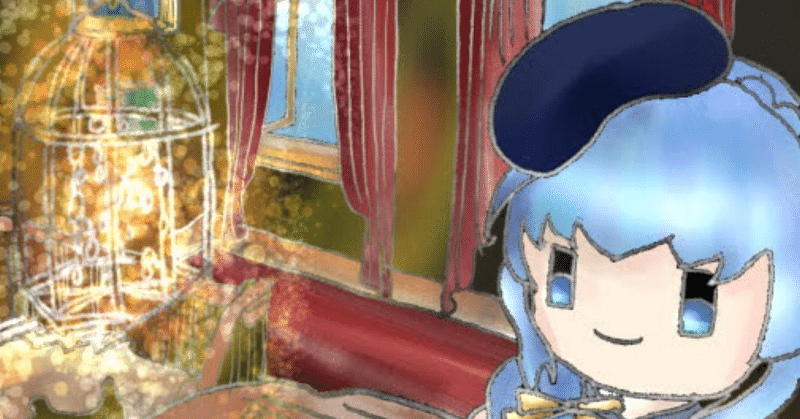
「自分の個性」を探して三千里
在りし日のあなたを思い出して
幼いあなたが好きだったものは何ですか。
その中で、今までずっとその熱い感情を持ち続けられたものはありますか。
大きくなるにつれて、「その歳になってまだそれが好きなの」「恥ずかしくないの」などと自分自身や他人から言われて諦めたもの・隠してきたものはありますか。
周りに合わせるため・なんとか話を合わせるために好きになろうとしたけど、今一つ気持ちが向かなかったものはありますか。
私は割と沢山あります。
しかし当時恥をかくまいと人前に出さず机の引き出しに押し込んできたそれらが、いかに自分の心奥底に眠る本心に深く結びついているか。より強い個性が求められる現代でどれだけ重宝されるのか。
数年前に読んだ本の記憶とついさっき結びつき、自分なりの答えの1つを見つけました。
良ければ私の過去を聴いていっていただけませんか。
幼少期:「魔法」に憧れて
私は物心がついてから「プリキュア」シリーズが好きでした。
幼稚園生の私からすれば大きな「お姉さん」だった彼女たち。鮮明に記憶に残っている中で最初に観たシリーズは「プリキュア5」、丁度昨年秋にEテレで公開されたアニメ通称「オトナプリキュア」(公式名:「キボウノチカラ~オトナプリキュア’23」)の元になっている作品です。自らの過去や弱さに向き合う勇気、幻想的な演出と共に繰り出される魔法、そして一緒に戦う仲間を武器に世の中の苦難や絶望を体現した敵を倒していく。そんな姿に憧れ、彼女たちのようにかっこよくて強いお姉さんになりたいと親にねだって変身グッズを買ってもらっていました。
しかし小学校2年生の時、その趣味を諦めました。
きっかけは母からの言葉に説得された、現実的な意味で大人になりたかった自分でした。親に言われたからやめたというわけではなく、あくまで周囲と比べて浮いてしまうのが怖かったからやめたのだと、今になって思います。「プリキュアは幼稚園生っぽい。小学生になったしもうちょっと別のものを好きになった方がいいのではないか。」と助言した母。
「もし自己紹介やクラスメイトとの会話でプリキュアが好きだと言ったら、お子ちゃまだと馬鹿にされるかもしれない。」とある種の恐怖を抱いた自分。当時の妥協案として、小学校低学年からは「ジュエルペット」に触れました。
中学生:「浮く」のが怖くて
小学校中学年の時、あることをきっかけに転校することになりました。
引っ越し・転校は今も昔も恐らく子どもにとって大きな試練の1つ。「学校ガチャ」を引き直さなければなりません。数年前から話題になっている言葉に「親ガチャ」がありますが、基本的な概念はこれと同じではないでしょうか。親も学校(特に小中学校)も子ども自身が選ぶのは難しく、本人の価値観や人生に少なからず影響を与えるからです。
環境が大きく変わり、期待と不安が同時に心を襲ってくる場面。
今の学校環境はどうかわかりませんが、私が小中学生の頃(約10~15年前)は明らかに「スクールカースト」が存在し、最初数日間どう振る舞うか・誰と関わるかがその後の人間関係を左右しました。
現在(ここ2~3年位)こそテレビアニメや漫画などの二次元文化が広く認知されビジネスチャンスとして利用される域ですが、当時はそのような物を好む人に対するイメージはどちらかと言えば悪く「陰キャ」「3軍」などといじめられたり馬鹿にされたり揶揄われたりする対象になり得ました。実際当時の私の中学校の休み時間は「1軍キラキラ女子」がげらげらと笑いながら中央で洋楽の有名どころを教室の真ん中や廊下で熱唱し、「2軍普通女子」は他のクラスへ遊びに行き、「3軍隅っこ女子」は教室の隅で漫画を交換したりアニメの考察を語ったりしていました。そして「1軍」が「3軍」を指さし「ネクラ」などと陰で蔑んでいました。時には冷やかしで声をかけ、好きなアニメを熱弁する姿を鼻で笑うこともあったものです。
そんな背景で私は転校初日や入学、クラス替え後クラスメイト達に趣味を訊かれても「私はジュエルペットが好きです」なんてとても恥ずかしい、かつ怖くて答えられませんでした。
クラスメイト達から浮かない無難な答えが欲しくて洋楽を聴いたりドラマや映画を観たりしました。小説はいくつか気に入りましたが、どうしても生身の人間が演じるものへの苦手意識が拭いきれず結局「1軍」への接触は必要最低限のみになりました。
今は彼女らと解り合えなかったことをほんの少し後悔しています。
大人になった私たちを度々悩ませる「同窓会」は大抵彼女たちが主導しますし、一度断ったら二度と招いてもらえず更に浮いてしまうリスクがあるから。
高校生:引き出しに隠して
進級して、大学受験が視野に入り始めた高校生の時。普段の勉強に飽きた私はクラスメイト達の視線がないことを確認してロシア語の単語帳を開いたり、オリジナルの物語を考えたりしていました。
*ロシア語と出会ったのもこの頃です。詳しくは↓こちらの記事で。
今は亡きオリガ・ヤコヴレヴァさんへ 届かないとわかっていても伝えたい想い|マルメロ (note.com)
オリジナルの物語の題材となったのは、中学生の頃父のパソコンを借りてせ
っせと履歴を消しながら見た「東方project」の音楽やキャラクターたちです。簡単に言うと人間や妖精、妖怪の女の子たちがそれぞれの特殊能力を使いこなし弾幕バトルをするシューティングゲームです。ゲーム音痴でシューティングは戦力外でしたが彼女たちの特徴的な魔法や服装、ストーリーが好きで、それらをモデルに私の好みを詰め込んだキャラクターたちをメモ帳や裏紙に書き殴っていました。
しかし先述した通り、他の同級生にばれて「中二病」と笑われるのが怖かった私はメモ帳を常に制服のポケットや鞄に隠しました。スマートフォンを持ち始め机の奥でただの雑貨と化した「ガラケー」に打ち込むこともありました。
後にこれを漁ることになるとは知る由もありませんでした。
大学生:見失った「私」を探して
自分はどのような人間なのか。
今までに何を成し遂げてきたのか。
「自分」について訊かれ自分自身でも問わねばならなくなった大学生の現在。私は人生を賭けて極めたいものは何なのか、就活目前の今でもこれっぽっちもわかりません。周りと同化して好かれようと心から欲するものを投げ捨ててきた私に、磨き上げたいと思うほど突出した個性もスキルも何もありません。ジョブ型雇用に移行しつつある日本社会で自分を売り込むのに必要な能力、いわば「自分の魔法」が見つからないのです。
興味を持ったことでも「こんなことが好きだと思ってしまう自分は恥ずかしい」「そもそも本当に好きなことなのか」迷いが先に来て、すぐに熱意が冷めてしまいます。
仮に少しブログサイトやInstagram、画像デザインや簡易的な動画編集ソフトに手を出してみても「わざわざ私がやらなくても、ネットの世界には自分より若くしてずっと上手な人たちが山ほどいる」と劣等感に押し潰され、時間と労力を費やしてきた自分を憎んでしまいます。言語だって、いつ翻訳に取って代わられてもおかしくありません。
そんなある日ふと引き出しを開けると、かつて書いたメモ帳やガラケーが姿を現します。
まだ純粋に「魔法」を信じていた頃の遺物であり、「私」の欠片でした。
メモ書きを手掛かりに、最近触り始めたデジタルイラストソフトで彼女たちの絵を描き始めました。学校で習った詩歌や偶然見聞きした神話の物語、アイルランドで知ったケルト文化や海外各地の旅行の思い出と掛け合わさり、過去の私が置いていった一次創作達に命が吹き込まれていきます。
(カバー画像は、アイルランド/ダブリン中心部にあるダブリン城でぬいぐるみと撮った写真を基に描いたものです。)
海外留学中の今、言語のハンディギャップがありながらクラスメイト達と接点を持つきっかけになってくれるのがぬいぐるみ達、一次創作の子達のイラストです。
あれは恐らく小学校高学年から中学生の頃。
とある2冊の本を町の牛乳屋さんの広告で見かけて、親に買ってもらい読みました。
「中学時代にしておく50のこと」
「高校時代にしておく50のこと」(いずれもPHP研究所、中谷彰宏氏著)
どちらに書いてあったのか、本文でどう書かれたのかば覚えていませんが、このような言葉を朧気ながら思い出しました。
「机の引き出しに隠しているものこそ未来の君をつくる」
読んだ数年後になってやっと何となく、1つの答えを見出した気がしました。正解かどうかは著者に訊いてみないと確かめようがありませんが、少なくとも今の私にとっては納得のいく答えです。
長々と語ってしまいましたが、最後まで聴いてくださりありがとうございました。
おやすみなさい、良い夢を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
