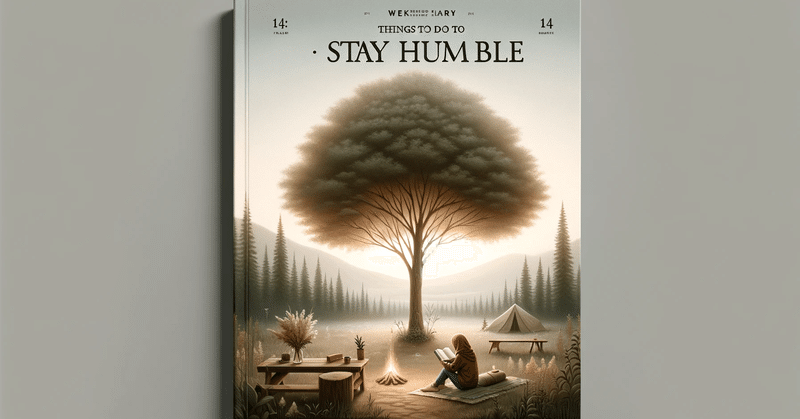
謙虚であり続けるためにするべきこと(週末日記#14)
謙虚であり続けることが大事だということは以前のnoteで幾度も書いてきた。謙虚であることによって、人に優しくすることができ、無駄な敵を作らずに済む。すなわち、人に応援されやすくなる。
しかし、謙虚であり続けることは非常に難しいと思う。一朝一夕でなれるようなものではない。今回の記事はそうなるためにはどんなマインドセットと行動が必要か、という問いに対する、現時点での自分なりの答えを書いておこうと思う。
自尊心の認識と自制
謙虚と自尊心というのは切っても切れない関係にあるのは言わずもがな理解いただけるだろう。まずはこれらの関係、特に自尊心とは何か、ということから書いていくことにする。
自尊心とは「自分は他人よりも優れている」だとか、「自分があの人より劣っているはずがない」だとか、いろんな表現ができるが、いわゆる自分は優れていると信じる感情だ。自我を持つ人間は誰しもが、多かれ少なかれ自尊心(プライド)を持っている。
特に、経験が全くない(年齢と比例することが多い)人、または大きな成功を収めたと自信で認識している人ほどこれが高い傾向にあると感じている。前者は、経験が少なく、自分が何をできて、何をできないのかということを認識していないがために、自身の過大評価や過信から過度な自尊心を生み出す。後者はいわゆる根拠のある自尊心だ、これは立派なファクトである。だが、ファクトがあるがために、それに関係しないこと、すなわち自分は全てにおいて優れていると勘違いしてしまう人が多いと感じる。これは生物学的にも実証されていることだ。老害という言葉があるように、人は年齢を重ねるにつれて、その人たちの経験からくる正解が出来上がり、それに沿って人生を歩んできたがために、考えが凝り固まり、新しいことへの吸収が難しくなってしまう。
これらから言えるのは、自尊心というのは、自分の経験の度合いに影響されるものであって、それによって自分を過大評価、すなわち「自分が絶対正しい、優れている」と勘違いしてしまうことだ。こうなってしまうと、吸収ができなくなり、成長は止まる。謙虚であり続け自分の成長を止めないためには、この自尊心の認識と自制が必要である。
自尊心を認識し自制するための行動
自尊心を認識し、それを自制するにはいくつかの方法があることがわかった。自分の経験と、古典を読み、先代の偉人の経験から汲み取ることができた方法を記しておく。
人と話しているときに自分の感情を観察する
これは、(何度も重複して申し訳ないが)陽明学を説いた王陽明も弟子たちに言っていたことである。人と話すということは、自分を修めることができる方法の一つである。話し相手の言葉、行動によって自分が何を感じ、どんな行動を起こしているのか、ということを客観的に観察することで、自分の感情をより深く理解し、自尊心をも認識することができる。
僕は、自身を客観視することが比較的得意であるため、難しいことだとは思わないが、難しい人のための練習を教示しておくと、瞑想だ。メディテーションと言った方が馴染みがあるかもしれないが、僕が意味しているのは座って無心になり、雑念が生まれたらそちらに意識を向け、消えたらまた戻ってくる、というものだ。座禅がこれに値する。これが派生して、現代のヨガや太極拳などの「集中して自分の感覚を研ぎ澄ます」ことを目的としたあらゆる形の精神統一法が存在するようになった。
日本人にとっては少し馴染みのなく、信じがたいことのように聞こえると思うが、騙されたと思って一度試して見て欲しい。
敬語を使う
敬語というのは東洋独特の言語形態である。ご存知だと思うが英語にはそのような概念はない。しかし、日本人であれば馴染みのある言葉だし、使う機会も多いだろう。
もし自分の自尊心を抑えることができないと感じている人がいればできる限り人と会話するときは敬語を使うことをお勧めする。これもまた主観的なことになってしまうが、自分は幼馴染や家族といった、ある程度自分のことを理解してくれている人の前で自尊心が高くなる傾向にある。幼い頃から理想が高く、何事もうまくこなそうと努力していたがために、自分がそう見られている、とどこかで感じているのかもしれない。その期待を裏切らないために、自尊心が高くなる。
もちろん、家族や親友に対して敬語を使うべきだと言っているわけではない。それは不自然すぎるし、うざがられる可能性もあるだろう(実際僕も家族LINEで兄に対して敬語を使っていたら叱られたことがある)。
しかし、初対面の年下の人や、何度か会っている同僚と久しぶりに話すときなど、に敬語を使うことで自尊心の自制は少なからず可能であると思う。特に、ファーストコンタクトは人の印象に強く残るため、自尊心が高いと感じる人にとっては良い武器になるだろう。
「辛いけど必要だと感じること」から逃げないこと
苦行から弱さを見つける
謙虚である続けるためにこの記事で特に強調しておきたいことがこれ(辛いけど必要だと感じることから逃げないこと)だ。
例えば、初めてのオンライン英会話はすごく緊張するし体力も使う。今日はやめておこっかな、なんて思ったりもするだろう。しかし、そこに自分の弱さがあり、成長のきっかけがあるのだと信じている。英会話をしながら、自分は人と会話するのが苦手なのか?どういう感情が生まれているんだろう?英語が下手なのが恥ずかしいのか?てことは英語ができない自分はカッコ悪いと思っているのか?など、自分の弱い部分、見たくない部分を観察し、認識するにはもってこいの状況であることが多い。
僕のマインドセットを説明しておくと、もし「うわ嫌だな」と感じたり、緊張して心拍が上がっているなと感じるときは、そこにお宝があると感じることにしている。成長というお宝だ。謙虚でありながらも成長を止めないためにはこの「成長への貪欲さ」を忘れずに、辛いことをする前の一瞬の我慢も必要である。
辛いスポーツの勧め
もし自分の弱さを見つめたいと思っている方がいれば、ぜひ長距離のランニングなどの比較的辛いスポーツを始めることをお勧めしたい。僕は最近、トライアスロンを初めて、ものすごく辛い練習を重ねている。がこれがものすごく良い。死ぬほど辛い練習の後に感じることができるあの感覚は、サウナの後や瞑想したときのような感覚と似ていると感じる。自分の弱さに柔軟になり、見つめることができる(こんな練習二度とするか、とは思うが)。
僕は休学をする1年4ヶ月の間に、アイアンマンレース(Run 42k, Swim 3.8k, Bike 180k)と100kトレイルラン(山の中を100キロ走るレース)を完走することを目標として掲げている。これらのような高い目標を目指し、日々辛い練習をすることによって謙虚であり続けることができるように感じるからだ。人は辛い経験をした分だけ他人に優しくできると思う。
これらはあくまでも仮説であるため、一年後、どう感じているかはまたそのときに書こうと思う。全く意味なかった、ということにならないことを願っている。
締め〜かわいい子には旅をさせよ〜
かわいい子には旅をさせよ、この言葉の意味を最近よく理解できるようになってきたと感じている。教育論的な話になってしまうが、やはり自分一人で辛いことを乗り越えるということは程度と方向は違うにせよ人を強くするのだと思う。
もし(はるか未来の話ではあるが)自分に子供ができたのなら旅をさせたいと思う。旅といってもバックパックなどの本当の旅(もちろん本人が望むのであればそうさせる)ではなく一人で辛い経験を味わうということだ。
僕が感じるに、親は(物心がついてからは)何事であれ子供に無理強いさせてはいけないと思う。なので、自分から〇〇がしたいと言える子に育てる必要がある、そのためにはいろんな経験をさせてあげて、失敗も味わいながらも、挑戦へのハードルを下げてあげることが親が唯一できることだろう。僕の親がそうしてくれているように。
では。また次回の記事で。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
