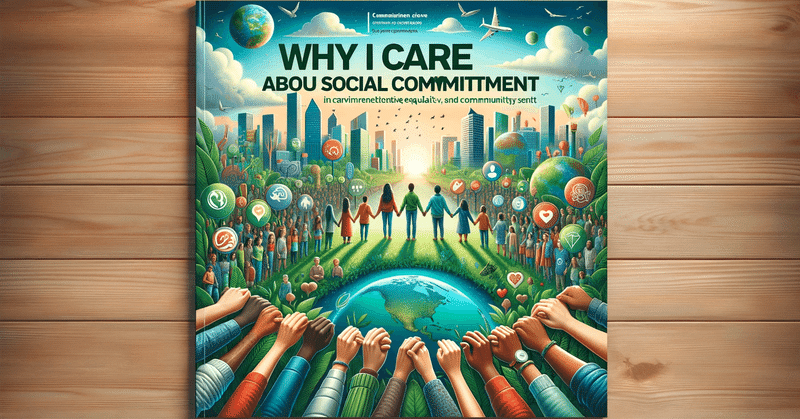
僕が社会貢献にこだわる理由(週末日記#13)
僕の日記を毎週見てくれている方ならお分かりだと思うが、僕は社会問題、特に貧困の解決に情熱を注ぎ、自分にできることを探すべく奮闘している。僕は、よくこのようなことを人に話すと「偉い」だとか「優しい」だとか言われるが、そういう言葉を聞くたびに、心のどこかで突っかかりを感じる。「自分は偉いと言われるためにやっているか?」、「褒められるのが嬉しいからやっているのか?」と。
先週の自己紹介の記事を書いたあと、そのようなことを深く考え、今感じている僕なりの落とし所が見えてきたのでこの記事に記しておこうと思う。僕に関わってくれている人は、「なぜこの人はそこまでして社会貢献にこだわるのだろうか」と疑問を抱いている人が多いと思う。そのような方々が納得できるような記事になることを願っている。
在日朝鮮人というマイノリティーとして生きてきたこと
記憶に残っている僕の感情以前に、自分の生い立ち、性格、考え方などを客観的に分析してみることから始めてみる。誰もが社会貢献に興味があっても情熱を注げるものではない。が、僕はそれなりに長い間この問題について考えを深め、将来的には(キャリアにおいて)人生を捧げることもできると感じている。その背景には必ず僕の性格や、それに影響を及ぼした環境が関わってくると思うからだ。
僕は在日朝鮮人として生まれてきて、朝鮮学校というところで教育を受けて育ってきた(詳しくはひとつ前の週末日記を参照していただきたい)。
そのような環境で育った僕は、日本ではいわゆる「少数派」であって、様々な不平等を感じてきた(ありがたいことに生活に不自由はなかったが)。物心がつく頃から「この世の中は平等ではない」という認識がついていた。
その中で代表的なことは、朝鮮学校に対する差別だ。僕が通った高校は正式な高校として認められていない。そのため学生たちは大学受験をするために高校卒業認定試験を合格しなければならない。それに有する勉強時間とお金は本来の高校生なら負担しなくていいものである。
文部科学省によると、「朝鮮学校の運営元である朝鮮総連が北朝鮮との関わりがあるから高校として認められない」、ということであろう(実際の裁判では理由を明確に表明していない)。幾度も裁判をしたが最高裁で敗訴した以来、結果が覆ることは無くなった。僕は法律に精通しているわけではないため、多少の間違いはあるだろうが、憲法上では、簡単にいうと、政治的な問題を子供の教育に反映させてはいけないという記載があるらしい。北朝鮮からの資金が反日教育などに使われるのはいかがなものか、という主張だと思うが、そう思うならぜひ学校を一度訪問して学生たちと話をしていただき、判断をしてもらいたい。
このような偏見や差別というのは何事も「無知であること」から始まる、ということをどこかの小説で目にしたことがある。「理解しようとする努力」なしで判断をすると差別が生まれるということを、物心がついた頃から感じていた僕は、マイノリティーとして生きている人、生まれながら不平等である人の感情を理解する能力に優れているのではないかと分析する。これが僕のバックグラウンドがどう現在の思考に影響を与えているのかである。
始まりは憧れから
このような感情を知らないうちに持っていたが、特に高校生までは「行動に移そう」だとか「キャリアとして社会貢献をしよう」とかは一切思わなかった。上記で示したのは、今になってみて自分の感情を分析してみただけである。実際はそのような強い関心や願望は皆無であった。
しかし、これもまた以前の日記と重なってしまうが、高校2年生の時の進路講習で出会った経営者の方に出会ってその気持ちは徐々に強くなっていくことになった。詳しい内容は以前の日記をみていただきたいが、彼は東南アジアでの貧困問題解決のためにマイクロファイナンスを行っている会社を営んでいた。簡単に説明すると、信用や担保がないために金融(主に融資や預金)サービスを使うことができない低所得者に向けた金融サービスを提供している会社である。
その当初はマイクロファイナンスに感銘を受けたというよりも、社会貢献を世界規模で行っていること、それをゼロから始め、今では様々な国で数千を超える従業員を持つ会社になっていることに憧れを感じた。素直にかっこいいなと感じたのだ。
これが僕が「社会貢献」に興味を持ち始めたきっかけである。
真似事の感情の変化
そのような憧れを抱いていたが、その当時はただの真似事であった。「将来的に世界をより良いところにできる人になれればいいなぁ」くらいの。子供が戦隊ヒーローを真似するくらいの。
そこから5年ほどが経った今はその真似事が、自分の本心になりつつあると感じている。その過程は自分でもよく分かっていないというのが本心であるが、貧困や環境問題、戦争などについての本を読んだり、人の話を聞いたり、実際に活動を行っているいひとを訪ねたり、とにかく「知ること」が大きな後押しになったと感じている。
しかし、その中でも多くの葛藤はあった。社会貢献活動というのは現在の世界では「慈善活動」という意味合いが強い。そのような慈善の心が自分にはあるのか?何か他の欲が自分の感情を作っているのではないか?などいろんなことを感じてきた。実際に、志した初期の頃は、慈善という感情よりも、かっこよさや憧れといった感情が強かっただろう。
今考えてみると、その頃は社会貢献は慈善の心がある人のみができることと認識していたが、それではいけないと感じる。慈善の心だけで行う活動なのであれば、生活が苦しい人や、自分のことで精一杯の人は社会に貢献できないということだ。さらに良い世界を作っていくには「社会貢献が自分の利益にもつながる」という価値観や何らかのシステムが生まれるべきだと思う。価値観を生み出すことは容易なことではない。そのために資本主義の構造をリデザインすることも必要だろう。
陽明学からのヒント
少し話が飛んでしまったが、真似事の感情から本心へと移った最後の一手になったのは陽明学であった。そこまで深く勉強したわけではないため、正確に伝えることができないかもしれないが、そこは大目に見ていただきたい。
こちらも詳しいことは以前の記事で書いた。
陽明学における「万物一体の仁」と「知行合一」という考え方が僕の感情と行動原理を明確にまとめてくれた。一つずつ説明してみる。
「万物一体の仁」とは人には皆、生まれながら良知(良い心)があり、人の痛みを感じることができる能力が備わっていて、苦しい状況に置かれている人を助けたいと感じることは人間として当たり前のことであるという考え方だ。例えば、他人でなくても、自分の身内が川で溺れているとしたら、誰もが迷わずに飛び込み助けるだろう。これは学校で教わったわけでもないし、親から言われることでもない、純粋な人間の行動原理なのである。このように、困っている人を助けたいと思う感情は本来備わっているものであるということである。しかし、この「良知」というのは私欲により徐々に失われていくため、それを保つためには、自分を修めることが重要であると王陽明は説いている。自分にそのような感情が、多少なりとも残っているのは、留学など、自分を修めることができたいろんな辛い経験があったからなのではないかと推測する(まだまだ未熟であるのは確かだが)。
次に「知行合一」だが、これは知ることと、行動することは同一でなければならないという考え方だ、すなわち、行動するということは知るということであり、知る(理解することや勉強すること)には行動することが必要であるという考え方である。さらにそれらの行動や感情は、論理的なものに基づくのではなく自分が正しいと感じることに基づき、選択することが大事だとも説われている。この考え方は僕の感情をまとめてくれたというよりも、これからの行動の原理原則の礎になってくれたと感じる。
僕はまだまだ未熟で、何も知らない上に、何もできない。だが、知るためには行動を起こさなければならないので、どんなにちっぽけなことであろうと今できることをすることに力を入れていこう、と思えるようになった。その行動が最大限の良い影響を与えることができるように、ただ行動をするだけでなく、思考も続けるべきだ。僕にとっての知ることとは「不平等な環境に置かれている人や地域」であり、そのような問題が解決され、世界が平等であることが正しいと感じる。このように「知行合一」という考え方は僕の「行動」の部分に大きな影響を与えてくれた考え方である。
締め
まとめると、僕の「社会貢献」に対する感情は真似事、憧れから始まった。が、今では本心になりつつあり、行動に移そうと準備するまでに至った。その過程は、僕のマイノリティーとして育ってきた環境や、「陽明学」から学んだ考え方が大きく影響していると感じる。自分の「困っている人を助けたい」という感情は人が本来備えている良知であり、それが正しいと思うならばそれ以上の判断材料は必要としない。知るためにただ行動に移すだけである。
行動を移しながら感情の変化があるかもしれない。特に僕は興味や趣向の変化が激しい。がいつでも「自分が正しいと思うことを行動に移す」ということは忘れずに生きていきたい。加えて、感情の変化や新たなことへの挑戦を好む自分だが、自分が定めたある程度のところまではやり抜く、ということも重要であると感じる。この二つを肝に銘じて、さらに成長しながら生きていきたい。
では、また次の記事で。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
