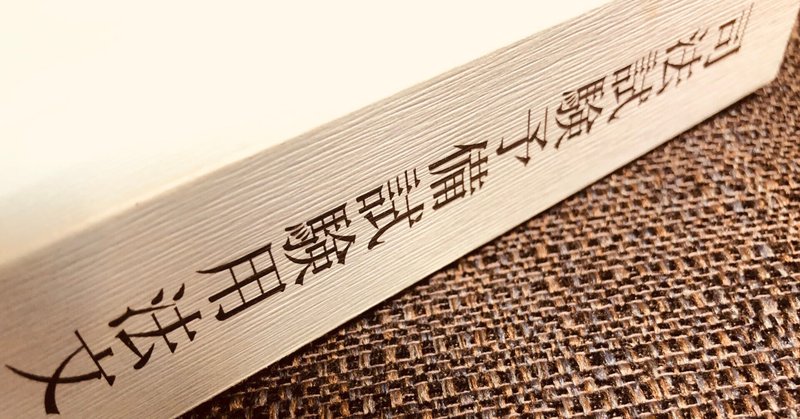
令和4年予備試験論文式試験[法律実務基礎科目(民事)]の振り返り②(設問3、4)
1 設問3
直接証拠の有無
まず、嫌なのが、「冒頭に、XとYが本件契約を締結した事実を直接証明する証拠の有無について言及」しないといけないことですよね。
ターゲットは、「XとYが本件契約を締結した事実」です。これが本問で主要事実とか要証事実と呼ばれるものです。
さて、「本件契約」とは「XがYとの間で、令和4年2月8日に締結した報酬を1000万円とする本件工事の請負契約」でしたね。なお、設問1の【Xの相談内容】から、「本件工事」とは「本件建物を飲食店に改修するための外壁・内装等のリフォーム工事」です。
そうすると、Xが本件工事を報酬1000万円で請け負い、Yがこれを注文したという意思表示の合致が示されている証拠があれば、これが直接証拠になります。
試験現場で、本件見積書①が直接証拠に当たるかもしれないと考えた人もいるかもしれません。でも、見積書は、Xが一方的に作成してYに交付できるものなので、上記の意思表示の合致を示すものではないんです。じゃあ、直接証拠はないのかな、と思うかもしれませんが、訴訟の当事者が当事者尋問でした供述も、主張とは区別された証拠となりますので、【Xの供述内容】を見ましょう。すると、「Yが同月8日、本件工事を報酬1000万円で発注すると言いましたので、私は、同日、本件工事を報酬1000万円で請け負いました」というセリフが見つかりますね。この供述部分が直接証拠になります。
え?Xが自分で自由に言っているだけじゃん、それで証拠になるの?って疑問があるかもしれません。そう、その疑問・違和感は誰もが抱きます。そのため、このXの供述は証拠ではあるものの、全然決定打にはなりません。結局、これを支える事実があるかどうかという角度からも詰めていく必要があります。ここで、方針・ルートとしては、形式上、二つあります。一つは、供述の信用性を支える補助事実を指摘してXの供述の通りだよね!とする方針。もう一つは、供述の信用性を支えようとするよりは、間接事実から主要事実が推認できるね、つまり、Xの供述の通りだね!とする方針。前者の補助事実と後者の間接事実は実際上重なることが多いけれど、発想が違うので区別することが大切です。前者は直接証拠型の認定、後者は間接事実型の認定と呼ばれます。仮にXが第三者である証人の場合は、前者で行くので問題ないのですが、実務では、本問のように当事者の場合は、そもそもその供述の信用性が低いということで、供述の信用性を支える事実を頑張って検討するんじゃなくて、後者で行くことが少なくないと言われています。
答案例では、後者でやっています。答案上では、証拠構造や認定方法について分かっているぞアピールをしたいのですが、問題の設定としては、弁護士Pが準備書面に記載する内容を書こうということなので、「Xは当事者にすぎずその供述は信用できないので、間接事実を検討する」と書くのは、弁護士倫理的にも問題ですから、真面目に論述する場合は少し言葉使いに神経使いますね。
事実認定
本問が面白いのは、XY間で、外壁工事を含む本件工事をYが依頼した、他方、これをXが請け負った、という点については、争いがないという点です。つまり、報酬額が、Xの主張する1000万円なのか、Yの主張する700万円なのか、そこだけが争点なんです。
そのため、本件工事の報酬額が1000万円であったことを具体的なターゲットにし、これを推認できる事実を挙げて、その推認過程を経験則(≒常識)や論理則を使用しつつ説明することになります。
まず、P・Xの側からは、本件工事の報酬額が1000万円であったことが推認されるような事実を挙げなければいけません。ここで気を付けたいのは、700万円と書いてある本件見積書②がでたらめなものであることを主張立証しても、それだけでは、本件工事の報酬額が1000万円であったことは推認されないということです。確かに、本件見積書②についてのYの供述も潰す必要がありますが、これを潰しても、報酬額が1000万円だったとは限らず、900万円だったかもしれません。そのため、Xとしては、本件見積書①に書かれた金額1000万円が正しい報酬額であることを、本件見積書②の金額は違うという消去法的理由からではなく、説明する必要があると思います。
ただ、本件見積書①も②も、共に契約締結前の同じ日にXからYに交付されたものなので、それぞれを見ていても、どちらの金額が真の報酬額かは決まりません。でも、XYの双方一致供述から、本件工事の内容には外壁工事が含まれていたこととXが外壁工事を実施したことが認められます。なお、双方一致供述とか不利益事実の自認の場合、その事実は動かし難い事実として認定できる事実になりますから、準備書面でエンジンになります。
本件見積書①にあって②にないのは、外壁工事の部分です。①は外壁工事ありの金額、②は外壁工事なしの金額が書いてありますね。で、実際に、上記のとおり、本件工事の内容には外壁工事が含まれていたこととXが外壁工事を実施したことが認められますよね。そうすると、XY間で外壁工事までやることになっていたのなら、それに対応する金額で契約しているのが普通だから、本件見積書①に書かれた1000万円が報酬額だったと考えるのが自然でしょう。このように、X側からは、先制攻撃をする必要があると思います。これで主要事実・要証事実は推認されます。
他方、Yは色々いちゃもんを付けてきますので、上記推認を妨げられないように、Xはこれらを潰す必要があります。
まず、Yは、本当は700万円なんだけど、本件見積書①は、運転資金として300万円を上乗せで借りたくて、銀行提出用に自分からXにお願いして作ってもらったものにすぎない、と言っています。この主張の意味、わかります?おそらくですが、銀行から融資を受ける際、正直に運転資金名目と伝えるより、リフォーム名目の方が金利が安くなる傾向にあるため、リフォームを口実に運転資金分まで含めて融資を受けようという発想があるのですが、そのために作成されたのが本件見積書①だという意味だと思われます。そのように理解すると、このYの供述は、ある程度あり得る話なのですが、なぜXが、何が悲しくて、そのような不正な方法でYが融資を受けることの手助けをしたんだと、普通するわけないじゃないかというように、反論したいですね。
次に、Yは、外壁工事分はサービスするといわれた、とも供述しています。つまり、本件見積書②の金額が正しいと。Yの上記の供述は、本件見積書①の金額は嘘であるといって煙に巻こうとするものですが、今度の供述は、積極的に、本件見積書②の金額700万円が正しいことをアピールするものです。でも、普通の業者が30%オフしたら、利益でないですから、そんな馬鹿なサービスをXがする理由はどこにもないですよね。ちなみに、リフォーム業の利益率は目安として30%前後と言われています。
あと、Yは、もともとXは700万円でできると言っていたと供述したのに、その後Xが700万円にサービスすると言ったとも供述していて、仮にもともと700万円なら、サービスの余地なくない?ということで供述が矛盾していることも信用性を下げる理由として、Xから主張できるといいと思います。ただ、Xが年末頃に700万円でできると言ったのは、そもそもサービス込みでの700万円という意味だったと善意解釈する余地もあるため、あまり噛みつく必要はないかもしれません。でも、代理人弁護士Pとしては、気付いたなら、主張すべきでしょうね。
それにしても、Yの言い分だけ聞いていると、YはどんだけXに愛されてるんですかね。
それはそうとして、むしろ、Xが語る本件見積書②の作成目的は、筋が通っています。本件建物の賃貸人の承諾を得やすくするためというものです。通常、賃貸人は自己の建物に大規模改修されるのを嫌がりますから、それに照らせば、なるほど、と思える作成目的ですので、そこに700万円と書いてあっても、その金額は報酬額ではない、となります。Yも自認していますが、Yは本件見積書②を賃貸人に見せていますよね。
最後に、Xは1000万円と書いた契約書作っておけばよかったと後悔してます。作ってないので、1000万円ではないのでは?1000万円なら普通作るでしょ、と一応言われることを想定して、十年来の仲だから大丈夫だと思うのは自然でしょう、とカバーしておくと良いです。こういうウィークポイントに対する手当も大事です。
なお、弁護士が準備書面を作成するときは、動かし難い事実・認定できる事実だけじゃなくて、たぶん認定されないだろうなという事実も当事者が言うのであれば書いたりします。一方当事者からの主張書面なので、動かし難い事実・認定できる事実を軸に主張を展開するにしても、それ以外の事実も書くことになると思います。動かし易い事実しかない場合だってありますから。予備試験でも、裁判所の立場からの事実認定プロセスを書くのではなく、一方当事者の立場からの主張書面を書くのであれば、同じになると思います。
2 設問4
この問題は、民事執行法35条の請求異議の訴えにすっと辿り着けるかどうかがまず試されていて、短答合格者ならけっこうな確率で可能かと思いますが、そうしたら、2項の「異議の事由」が(事実審の)口頭弁論終結時前からある事由はダメで、後から発生した事由はOKということが分かるかと思います。
それで、相殺を主張するのですが、相殺の主張は、口頭弁論終結時の後にするからOKというだけでは説明としては足りませんから注意してくださいね。詐欺取消しの主張だって口頭弁論終結時の後にする場合もあると思いますが、ダメですからね。ここについては、相殺権は訴訟物たる権利関係の発生原因に内在する瑕疵に基づく形成権でないとか、相殺は実質的敗訴だから、等と他の形成権とは事情が違うんだよと説明を加える必要があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
