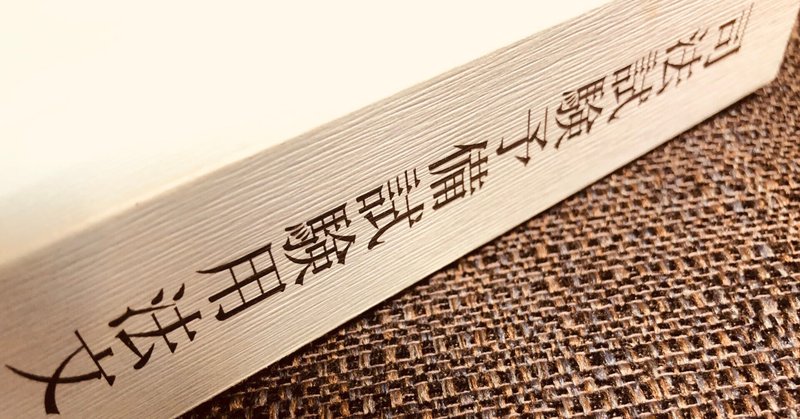
令和4年予備試験論文式試験[法律実務基礎科目(民事)]の振り返り①(設問1、2)
1 設問1
小問⑴
Xは、①報酬金だけじゃなくて②遅延損害金も請求したいと話しているので、②を落とさず、ちゃんと訴訟物書かないとですね。表現については、①は、「請負契約に基づく報酬請求権」というように「支払」がなくても良いです(たとえば、岡口基一『要件事実マニュアル2(第5版)』P113など)。②は、履行遅滞となっている債務が複数ある場合には、特定のために債務から書くこともありますが、単に「履行遅滞に基づく損害賠償請求権」でいいです。
訴訟物の個数や併合形態の記載は、司法修習の起案では設問で明示的に求められますが、予備試験では明示的には求められていないので、書かなくて良いと思います。書くならば、本問では、それぞれ1個で単純併合ですね。
小問⑵
この問題で気をつけないといけないのは、遅延損害金の発生日が5月28日ではなくて、「5月29日」ということです。履行期が28日ならば、その経過時、つまり、次の日である29日からYは遅滞に陥るからです。
なお、不法行為に基づく損害賠償債務については、不法行為のあったまさにその日から遅延損害金が発生する(最判昭37.9.4)ので、次の日からだ!ってならないようにして下さいね。
小問⑶及び小問⑷
報酬請求については、仕事の完成まで必要だよ、ということと、損害賠償請求については、同時履行の抗弁の効果を先回りして消すために、本件建物を引き渡したよ、ということを書く必要があります。
あと、なぜ、その事実を請求原因で書いたのか、という小問⑷のような質問は結構困りますよね。「それが請求原因だから」としか言いようがないと思いませんか。ほとんど禅問答ですよね。
ただ、これについては、いったん条文の要件に戻って、その要件に該当する事実だから書いた、という形で説明すると様になります。また、要件ではあるけれど、これ関する事実の主張は反対当事者がしないといけないので書かなかった、というように。なお、出題の趣旨にも「前記各訴訟物の法律要件及び要件事実の正確な理解が問われている。」と書いてあるし、だいぶ懐かしい問題になりますが、平成24年設問1小問⑴でも「…までの各事実について、抗弁事実としてそれらの事実を主張する必要があり、かつ、これで足りると考えられる理由を,実体法の定める要件や当該要件についての主張・立証責任の所在に留意しつつ説明しなさい。」とありますね。
2 設問2
小問⑴
これは、ど壺に嵌ったら、難問ですね。とんち的な難しさがあります。こういう問題で頭真っ白になっちゃった場合は、みんなもきっと頭真っ白になっているにちがいないと決めつけて、誰よりも早くリフレッシュすることが大切です。そのために別の問題に進むのもいいですし、トイレに行くのもいいです。一度立ち上がって歩くと、少し落ち着く場合があります(2、3分消費するのは痛いですが利益衡量してくださいね。)。事案を俯瞰して見ることにつながる可能性があります。
免除の要件事実は免除の意思表示だけだよね?他の要件事実あったっけ、もっとちゃんと暗記しておけばよかった…と免除の中だけで頭をぐるぐる回しても答えに辿り着けない怖い問題でした。
(a)におけるYの発言には「本件契約が締結されたというのであれば、…Xは、…300万円の支払を免除しました」とあります。そして、「本件契約」については、設問2の冒頭に、「以下、XがYとの間で、令和4年2月8日に締結した報酬を1000万円とする本件工事の請負契約を『本件契約』という。」とあるため、報酬代金が1000万円であることを前提に、検討することが求められていたといえます。
ところで、抗弁(事実)とは,請求原因と両立し,請求原因から発生する法律効果を障害・消滅・阻止する事実をいいます。では、本件訴訟の訴訟物が300万円であるとして、(イ)の事実が抗弁事実として機能するかどうか考えてみましょう。免除の額が300万円なので、消滅させられそうに思いますね。でも、相殺や過失相殺の論点で有名ですが、外側説っていうのがありますよね。判例ですね。訴訟物が債権全額のうちの一部についての請求権である場合でも、債権全額を捉えた上で、この一部を内側とすると、それ以外の部分、つまり、外側の部分から減額処理をして行きます。本問で、免除の事実をまず外側にぶつけていくと、外側は700万円なので、300万円しかない免除の効果はここで消えて、外側だけでもあと400万円残ってしまうことになります。当然、内側の訴訟物は無傷です。つまり、(イ)だけだと、内側の訴訟物を少しも消滅させることができず、全く機能できていないので主張自体失当になります。でも、Xも自認していますが、700万円の弁済があったという事実もぶつけることができればどうなるでしょうか。弁済700万円を外側の700万円にぶつければ、残りは内側である300万円の訴訟物となり、ここに免除300万円をぶつければ、訴訟物を消滅させれますよね!かなり古いですが、漫画のデスノートでもニアが言ってますね、「二人ならLに並べる、二人ならLを越せる」と。あれと似た感覚です。
なお、本問の理解については、大島眞一『新版 完全講義 民事裁判実務の基礎入門編〔第2版〕』P68から72までが非常に参考になります。
小問⑵
直観的に、相殺又は反訴、あるいはその両方が思い浮かんだ方が多いと思います。「訴訟手続を利用して選択できる訴訟行為」を挙げなさいというのがヒントですよね。
ところで、設問4を先にみると、Yは負けているんですよね。Xの300万円請求が認容されています。なので、出題者の頭の中では、免除の抗弁は認められないという前提があり、(b)損害賠償請求権は、その場合に備えたものという位置づけだった可能性があります。だから、相殺を検討するのはもちろんありなんですが、設問文には「350万円の回収方法として」とあることに着目したいです。
確かに、相殺については、ちゃんと判例(最判昭53.9.21、最判令2.9.11)もあるため、相殺による回収ということも考えられるんですが、相殺では差額の50万円については回収しきれません。また、免除の抗弁がうまくいった場合、相殺の抗弁は審理さえされず、この350万円は全く回収できません。そこで、本訴請求と関連性があることに簡単に触れつつ反訴に言及できると良かったと思います。
そして、反訴については、反訴係属後に、「反訴原告が」「本訴で」反訴債権を自働債権として相殺の抗弁を主張した場合、反訴は予備的反訴になるから大丈夫(民訴法142条に反しない)といった判例(最判平18.4.14)があります。さらに、判例(最判令2.9.11)は、①本訴、②反訴、③「本訴原告が」「反訴で」本訴債権を自働債権とする相殺の主張、という事案(本問事案とは異なる)で、相殺による清算的調整を図るべき要請が強いこと等を理由に相殺の主張を認めており、この理由が、最判平18年の事案にも妥当すするとして、評判の悪かった予備的反訴構成にとって代わられそうです(判タ1484号61頁参照)。もしかしたら、出題者は、これらの判例も多少念頭に置いていたかもしれません。が!こんなこと書くなら、刑実を一文字でも多く書くべきなので、不要と思います(答案例には、知識整理の役に立てばと思い書きましたが…)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
