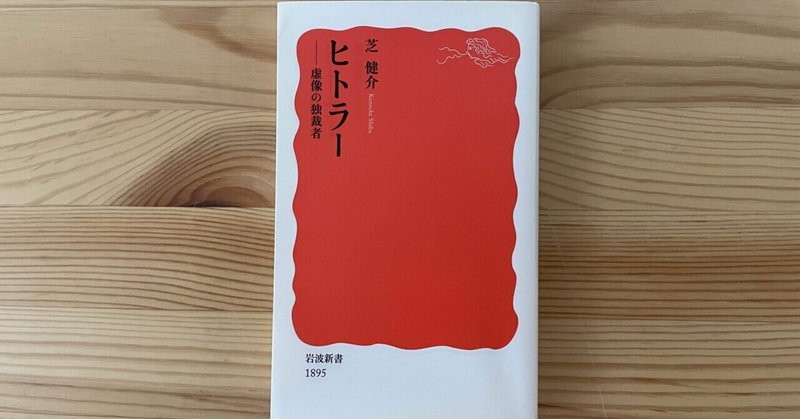
ドイツ人ではない画家志望だったヒトラーの実像に迫った本「ヒトラー」
本(ヒトラー)(長文失礼します)
ヒトラー(1889~1945)の生い立ちから死後のヒトラー現象までを時系列的に分析し、ヒトラーの人物像の全体を考察した本です。筆者の芝健介さんは、長年ナチス・ドイツを研究してきた歴史学者です。
この本を読もうと思ったのは、話題の本「ナチスは「良いこと」もしたのか?」を読んだ後、関連本を読みたくなり、本屋さんで見つけて参考資料として読み始めた次第です。
オーストリア人として生まれたヒトラーは、10代の頃は画家を目指しますが、美術学校に連続して不合格となり、次に建築家を目指しながらも、高等教育を受けていないのでこの道も閉ざされてしまいます。その後絵葉書描きを経て軍隊に入隊、第1次世界大戦を戦っています。
ナチ党に入党後、ヒトラーの才覚で特筆すべきはその卓越した演説力であり、聴衆を引き寄せるカリスマ性と説得力があったと評されています。
極右政党だったナチスが国民政党となりえたのは、第一次世界大戦後のドイツ国内の内乱があり、経済不況や失業率の増加などワイマール共和国内での国内不安がありました。ナチスが掲げるのは「民族共同体」をスローガンに、全体主義としての民主主義や議会政治の否定であり、強力なリーダーシップの指導者の元での国民の団結でした。
ナチスの反ユダヤ主義は一貫しており、資本主義社会での搾取者であるユダヤ人の追放は、全体主義を標榜する面との合致点を見い出すことができます。それは偽書「シオンの賢者の議定書」における反ユダヤの歴史修正主義でも端的に表れています。
1939年9月1日のポーランド侵攻により第二次世界大戦が勃発し、当初はドイツ軍の各国への侵攻が拡大してフランスのパリも陥落しますが、ソ連との独ソ戦でのスターリングラードの攻防と敗北が転機となり、劣勢に転じていきます。その後連合軍によるノルマンディー上陸作戦が、ドイツの敗北を決定的にしたともいえるものでした。
戦況が劣勢の中、ベルリンの地下室に避難していたヒトラーは、1945年4月30日に愛人のエヴァー・ブラウンと共に自殺します。ムッソリーニのように処刑後の遺体をさらされないように、自殺を選び死後は遺体を焼失させるように指示していました。
死後の分析で、顧問医師による薬の投与の薬物依存の実態が、克明に記述されています。
ナチスとは何だったのか?それは「私的な帝国、私的な軍隊、私的な情報機関の乱立」であったと総括することができるとの指摘もあります。それでも「ヒトラー神話」が今でも存在する事実や、死後にその言動を再評価する歴史修正主義に加えて、再生産される「ヒトラー現象」まで、全体主義が台頭し閉塞感が強まる全世界的な潮流の中で、その残像は今でも不気味に浮かび上がっていると認めざるを得ません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
