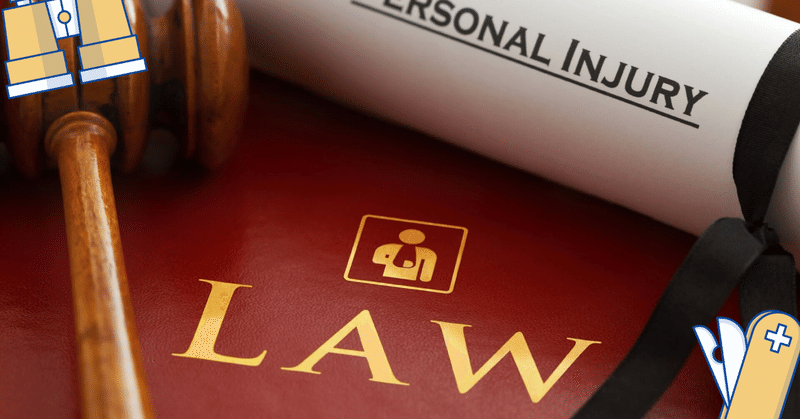
本人訴訟で未払い残業代を請求する(43)-証拠説明書の書き方9【給与支給明細書】
雇用契約書とタイムカードと給与支給明細書は最強の証拠3点セット。今回から給与支給明細書について解説していきます。
まず、給与(賃金)とは、第18回noteで解説したように、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」(労基法第11条)です。そして、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)」(労基法第24条1項)、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(以下略)」(同法第24条2項)として、賃金の支払いに関する原則が定められています(例外がありますが、機会があれば後のnoteで説明とさせてください)。
一方、「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」(労基法第108条)、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。」(同法第109条)と定められています。
整理すると、会社の従業員は、労働の対価として、①通貨で、②直接、③全額を、④少なくとも毎月一回、⑤決められた期日に、給与を受け取ることができるということ。つまり、給与の一部を自社の商品・サービスで支給したり、営業成績が悪いから罰金を控除したり、備品を壊したからその弁償分を控除したり、二ヶ月に一回の支給であったり、月末の出納の締め次第で支給日を変更したり、そのようなことはすべて違法ということです。ちなみに、ストックオプションは労基法が言う賃金にはあたりません。
そして、会社(雇主)は、その給与の計算に関する事項を賃金台帳として最低三年間保存しなければならないということ。給与を計算して支給するわけですから、当然、その基礎となる数字や計算プロセスは残っているでしょう。その3年間の保存が義務付けられています。
では、
Q:会社(雇主)は給与支給明細書を従業員に渡さなければならないのか?
答えは、
A:会社(雇主)には従業員に給与支給明細書を渡す法律上の義務がある!
労働基準法には給与支給明細書に関する規定はありませんが、所得税法第231条1項に「居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」と定められ、違反には罰則も適用されます。居住者とは日本国内の居住者のことで、非居住者であれば所得税の課税対象とはなりません。
つまり、会社(雇主)は給与支給明細書を従業員に必ず渡さなければならないということ。
なお、所得税法第231条2項には、「前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。(以下略)」とされ、電子メールなどによる給与支給明細書の交付も、従業員の承諾を条件に認められています。
本人訴訟で労働審判ないし民事訴訟を起こすに当たって、必ず給与支給明細書を準備して、書証として添付してください。証拠説明書では、給与支給月毎に「甲第○号証の1」「甲第○号証の2」「甲第○号証の3」~というような表記にするとよいでしょう(⇒第41回noteに添付したテンプレートを参照してください)。
会社によっては、わざと給与支給明細書を交付しないところもあるようです。給与支給明細書にはいろいろな情報が含まれています(含まれていなければなりません→内容は次回のnoteで解説します)。もし会社が不正を働こうという意思があるなら、ありのままの情報が記された給与支給明細書が従業員に渡ってしまっては、確かに不都合でしょう。しかし、上記のとおり、会社には賃金台帳が少なくとも3年間保存されているはずです。また、会社は給与支給明細書を従業員に交付する法的義務を負っています。これらを踏まえて、給与支給明細書が入手できない時には会社と交渉してみてください。
次回も給与支給明細書についてです。給与支給明細書の構造について解説をしようと思います。お楽しみに!
街中利公
本noteは、『実録 落ちこぼれビジネスマンのしろうと労働裁判 労働審判編: 訴訟は自分でできる』(街中利公 著、Kindle版、2018年10月)にそって執筆するものです。
免責事項: noteの内容は、私の実体験や実体験からの知識や個人的見解を読者の皆さまが本人訴訟を提起する際に役立つように提供させていただくものです。内容には誤りがないように注意を払っていますが、法律の専門家ではない私の実体験にもとづく限り、誤った情報は一切含まれていない、私の知識はすべて正しい、私の見解はすべて適切である、とまでは言い切ることができません。ゆえに、本noteで知り得た情報を使用した方がいかなる損害を被ったとしても、私には一切の責任はなく、その責任は使用者にあるものとさせていただきます。ご了承願います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
