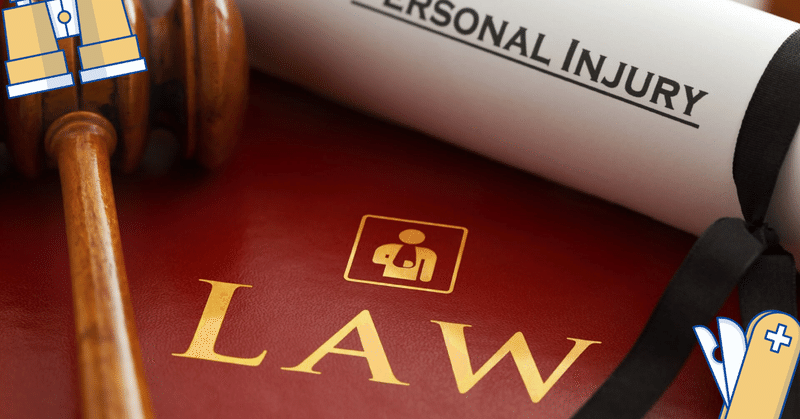
本人訴訟で未払い残業代を請求する(44)-証拠説明書の書き方10【給与支給明細書】
今回のnoteも前回に続き給与支給明細書についてです。
口座振込での給与支給に関する通達(平成10.9.10 基発第530号)によれば、給与支給明細書では①賃金の種類毎の支給額、②差し引かれる控除額、③控除された後の差引支給額の3つが明示されなければならないとされています。通達は法律ではありませんが、これら3項目が給与支給明細書に記載されることは当たり前でしょう。
一般的に、給与支給明細書は「勤怠」「支給」「控除」の3つのパートから構成されています。
「勤怠」パートには、
■ 出勤日数
■ 有給休暇日数
■ 欠勤日数
■ 所定労働時間数
■ 所定外労働時間数(普通残業時間数)
■ 所定外労働時間数(深夜残業時間数)
■ 法定休日勤務時間数
■ 法定外休日勤務時間数
などの数字が記載されます。
「支給」パートには、
■ 基本給
■ 各種手当
■ 普通残業代
■ 深夜残業代
の数字が記載されます。基本給と各種手当は雇用契約書に基づいた数字です。第20回noteで解説した通り、各種手当には「給与の基礎額」に算入される手当と算入されない手当があります。労働基準法第37条5項・労働基準法施行規則第21条に基づいて、家族手当・通勤手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金などは算入されず、管理者手当・係長手当・主任手当・リーダー手当などは算入されると考えられます。普通残業代・深夜残業代は、当然、「勤怠」パートの所定外労働時間(普通残業時間・深夜残業時間)、法定休日勤務時間、法定外休日勤務時間の数字と連動します。
「控除」パートには、
■健康保険料
■厚生年金保険料
■介護保険料
■雇用保険料
■労働災害(労災)保険料
■所得税
■住民税
の数字が記載されます。
余談ですが、健康保険と厚生年金保険と介護保険(40歳以上に加入義務あり)は社会保険、雇用保険と労災保険(労災保険料は雇用保険料に含まれる)は労働保険と呼ばれます(加入条件などは改めて後のnoteで説明します)。それぞれ健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法、雇用保険法・労働者災害補償保険法によって規定されています。
社会保険は、保険料額表(例:東京都の料額表)に規定された標準報酬等級・標準報酬月額に基づいて、月々の健康保険料・厚生年金保険料が決まってきます。標準報酬の対象となる報酬は、全国健康保険協会によれば、基本給のほか役職手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当など労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。年4回以上の支給される賞与も標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。通勤手当は含まれません。この社会保険料算定の根拠となる報酬は、当然、「支給」パートの基本給・各種手当の数字に連動しています。
給与支給明細書の最後のパートには、「支給額」から「控除額」を差し引いた差引支給額が記載されます。この金額がいわゆる手取り。給与を銀行振込としている方は、この金額が口座に振り込まれます。
以上、給与支給明細書の構成を説明してきました。本人訴訟で未払い残業代を請求するに当たっての重要なポイントは、
■ タイムカードと給与支給明細書の「勤怠」パートは整合しているか
■ 給与支給明細書の「勤怠」パートと「支給」パートは整合しているか
■ 雇用契約書の内容と基本給・各種手当の金額は整合しているか
■ 給与支給明細書の「支給」パートは労基法第37条に基づいているか
です。未払い残業代が発生しているということは、故意か過失かはともかく、これらの何処かに誤りが存在するということなのです。
ここまでお読みいただきありがとうございます。証拠説明書についての説明は、最強の証拠3点セット(雇用契約書・タイムカード・給与支給明細書)の説明と証拠説明書のテンプレート(第41回note)の提示をもって、いったんこれで完了にしたいと思います。noteシリーズ『本人訴訟で未払い残業代を請求する』、まだまだどんどん続きます。次回をお楽しみに。
街中利公
本noteは、『実録 落ちこぼれビジネスマンのしろうと労働裁判 労働審判編: 訴訟は自分でできる』(街中利公 著、Kindle版、2018年10月)にそって執筆するものです。
免責事項: noteの内容は、私の実体験や実体験からの知識や個人的見解を読者の皆さまが本人訴訟を提起する際に役立つように提供させていただくものです。内容には誤りがないように注意を払っていますが、法律の専門家ではない私の実体験にもとづく限り、誤った情報は一切含まれていない、私の知識はすべて正しい、私の見解はすべて適切である、とまでは言い切ることができません。ゆえに、本noteで知り得た情報を使用した方がいかなる損害を被ったとしても、私には一切の責任はなく、その責任は使用者にあるものとさせていただきます。ご了承願います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
