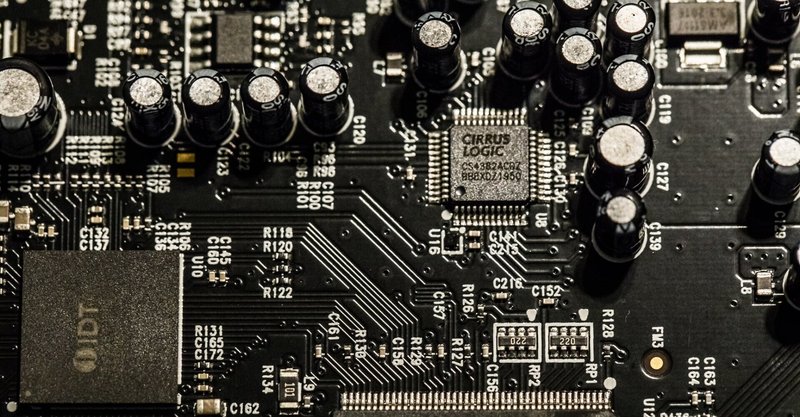
BTOと自作PCの違いとはなにか?
おはようございます。またはこんにちは。もしくはこんばんわ。マゲっちSCと申します。2021年もいよいよ12月に入りました。今年も大詰めですね。ですがこれから春までの時期は何かとイベント事が多い時期でもあり、また年末ということで多忙を極める時期でもあります。学生さんも社会人さんもご無理はなさらないようにお気をつけください。
さて前回のブログでは、改めてゲーム用途のPCはなぜ高性能である必要があるのか?ということをゲームを構成しているデータをご紹介しながらお話させていただきました。ビジネスで扱っているデータとゲームで扱っているデータの総量の差がご理解いただけたでしょうか?そしてゲーミングPCというものに関しての誤解も解けたのではないかと思っています。ゲーミングPCはゲーム機ではありません。ゲームもできるPCです。もちろんビジネス用途で使用することもできます。また、PCは何かを生産することができます。プログラムを組んでアプリを作り販売すればお金を儲けることもできます。私のようにブログを書いて文章力をあげてウェブライターとして活躍することもできます。今や動画の編集ができれば企業は外注していた案件を社内で処理することができるようになるため、就職活動で有利になります。趣味で描いた絵がSNSを通じてバズり、そこから画集を出すという可能性も否定はできません。音楽を作って公開すれば最近の若手アーティストのようにデビューすることもできます。ところがスマホやタブレットPCではそれが不可能です。厳密に言えばできなくはないのですが、フリック入力でワープロをするよりもキーボードを使ったほうが早くて楽です。また、スマホやタブレットPCで動作するプログラミングの開発ツールなどは非常に数が少ないですね。私は見たことがありません。
BTOパソコンとはなにか?
では本題に入る前にBTOパソコンについてもう一度軽く触れておきます。BTOパソコンとは大手PC専門店などが作っている自社ブランド的な組み立てPCです。皆さんもガレリアやレベルインフィニティなどの名前のPCを聞いたことがあるかと思います。さすがにご年配の方はご存じないかもしれませんが、PCに詳しくなくてもお若い世代の方なら名前程度なら聞いたことがあると思います。このガレリアやレベルインフィニティというのはいわゆるPCの商品名です。ビジネス向けPCにも商品名がありますがそれと同じですね。そしてBTOパソコンの大半はゲーム用途の高性能PCとなります。もちろん動画編集にも使えますし、ゲームプレイの生配信を行うこともできます。
自作PCとは何か?
では続いて比較対象となることが多い自作PCについて軽く触れておきましょう。自作PCとは読んで字のごとく自分で作るPCです。PCって自分で作れるの?と思われるかもしれませんが意外と簡単に作ることができます。私は指先が器用な方ではなくどちらかといえば不器用な方ですが、そんな私でもすでに3台作っています。自作PCには私個人でつけた段階があり、大きく分けて3段階に分けることができます。第1段階は構成部品の選定と購入です。第2段階は組み立てです。第3段階はUEFI設定とOSや各種ドライバ・応用ソフトのインストールとなります。
BTOパソコンと自作PCの共通点とはなにか?
ではBTOパソコンと自作PCの比較に入りましょう。最初の共通点は組み立て式であるという点です。BTOパソコンはPCショップが組み立てて販売しているゲーム用途向けのPCです。自作PCはショップではなく個人で部品を集めて組み立てたあとOSのインストールを行いますが、そういう手間をすべてPCショップ側で行った上で販売しています。ちなみにゲームソフトなどの応用ソフトや各種ドライバは購入後にユーザが自身でインストールします。そして購入時に入手可能なのはPC本体と保証書とPC用電源ケーブル程度であることを覚えておいてください。ビジネスや簡易的な娯楽用とのPCの場合はモニター・スピーカー・キーボード・マウスが付属していますがBTOパソコンや自作PCの場合はそれらは付属しません。また、BTOパソコンも自作PCも必要な用途によって部品をカスタマイズして自分だけの1台を作ることができます。BTOパソコンに関しては基本セットがあり、この基本セットを量産して売っています。ですが中には基本セットでは物足りないと思う方もいらっしゃるため、金額が多少上がりますが基本セットをベースにしつつもいくつか部品を差し替えることが可能です。自作PCに関しては基本セットがないため最初からBTOパソコンのカスタマイズを行っているのと同じ状況になります。ちなみに基本セットという言葉は私が勝手にそう呼んでいるだけです。
BTOパソコンと自作PCの違いとはなにか?
共通点を抑えた上で相違点の方に入っていきます。まずは保証に関してのお話になります。BTOパソコンの場合はPCショップ側が基本セットを作っているため、それをそのまま購入すればPC単位での保証が付きます。いわゆる家電量販店で売られているビジネス向けのPCと同じ状態ですね。ただし、先ほどお話したとおりPC本体のみの販売となるためモニターやスピーカー・キーボードやマウスに関しては保証対象外になります。またPCショップによっては基本セットをカスタマイズした場合に関しては保証が受けられないこともありますので必ず事前に確認を取るようにしてください。
続いて自作PCに関してですが、自作PCは本体に保証は付きません。なぜなら自分で部品を組み立てるからです。部品ごとの保証はありますが、どの部品が不具合を起こしてるかの判断は組み立てた個人が行い、初期不良だと断定できたら部品のメーカーに初期不良であるとの旨の連絡を入れ、メーカーからの連絡に沿って交換のために送り返すようになります。ただし初期不良だと思ってメーカーにお繰り返したものの、メーカー側のテストでメールなどで報告した現象が再現しなかった場合は初期不良にはならず、組み立てた本人が壊したという扱いになることがあります。保証が受けられるという保証はありませんのでお気をつけください。また、部品はすべて正常であるにも関わらずメーカーAとメーカーBの部品同士の相性が悪くて動作しないというパターンもあります。いわゆる相性問題です。最近はあまり聞かなくなりましたがPCの部品は国内外実に様々なメーカーが製造販売を行っています。稀に相性が悪くて動作しない場合があり、この場合は部品そのものは破損していないため保証を受けることができません。代替の部品があれば差し替えることで動く場合がありますが、代替部品を持っているのはある程度自作を経験した人が、たまたま手元に前使っていた部品が残っていたというパターンがほとんどです。自作PC初挑戦の場合は手元に余剰部品や代替部品は存在しないことが多いため、違うメーカーのものを改めて購入する必要があります。自作PCは基本的に自己責任で行うものであり、これらが許容できない方は自作PCに手を出してはいけません。
BTOパソコンと自作PCの価格差はどうなっているのか?
ではBTOパソコンと自作PCの価格差についてのお話をしていきます。PCの購入を考えているがどうしたらいいか?ということをPCをある程度知っている方に相談してみると
「どうせ買うならBTOよりも自作したほうが安く済むよ」
と言われることもあるかもしれません。では実際の価格差はどの程度のものでしょうか?数週間前に気になって自分で調べてみたのですが、BTOも自作もほぼ価格差はありませんでした。BTOの方が保証や組み立ての手数料などを入れると確かに高くなるのですが、せいぜい1~2万円程度です。高性能PCにおいて1~2万円という金額差は誤差です。昨今は半導体不足やビットコインのマイニングブームなどもあり。自作しても部品によっては高騰しているものがあるため、2021年12月現在では
若干BTOパソコンのほうが高い。
という結論です。
ゲーミングPCの選択について
BTOパソコンと自作PCの共通点と違い・価格差についてはだいたいご理解いただけたでしょうか?では次はゲーミングPCの選択についてのお話です。自作PCを考えていらっしゃる方に関しては構成部品の選択というふうに読み替えていただけると幸いです。
第1段階はゲーミングPCでやりたいことをすべて漏れなく紙に書き出してください。ゲームはもちろんですがゲーミングPCは高性能PCとしての側面もあるので、プログラミング学習や動画編集などもすべてやりたいことに入ります。具体的にはプレイしたいゲームタイトルや、動作させたいソフト名をネットなどで調べてすべて書き出します。
第2段階は書き出したソフトが動作する推奨環境をネットで検索してそれぞれ追記していきます。各ゲームやソフトの公式サイトにアクセスしてWindows版の推奨動作環境を確認します。その時必須環境ではなく必ず推奨環境の方をメモしておきます。必須環境というのはゲームを動かすために必要最低限の環境で、ゲーム設定の変更をして品質を引き下げる必要があるということになります。また、対戦するゲームの場合はPCやモニターの性能によって勝敗が普通に左右されます。つまり推奨環境以上のPCやモニターなどを用意しなければゲームの腕前に関係なく対戦で勝利することは難しくなります。推奨環境以上の性能のPCであればゲームの設定を変更する必要もなく快適に高画質でゲームをプレイすることができるようになります。ですので各ソフトの推奨環境をすべてメモします。
第3段階は購入したり組み立てたりしたPCに接続する周辺機器の選定です。周辺機器の定義ですが簡単に言うとゲーミングPC以外のものすべてです。モニターもそれ相応の反応速度やリフレッシュレートのものを選択したり、音声もステレオスピーカーでいいのか5.1ch対応のものがいいのかはゲームによって変わります。キーボードも普通のキーボードでいいのか、マクロ機能のあるゲーミングキーボードがいいのかを見極める必要があります。マウスもゲーム用途であればそれ相応の反応の良いものを選択する必要があります。また通常のPCとしても利用できるため、必要に応じてプリンタを接続してもいいと思います。ゲームによってはコントローラーやアーケードコントローラーの購入も見据える必要があるでしょう。
第4段階で実際に洗い出したメモをもとにPCショップを訪れたりネットで調べて実際に購入するゲーミングPCを選択決定します。自作の方は各部品の選択と購入ですね。しかし注意点があります。ここでネット検索していいのはあくまでもPC部品に関しての基礎知識がある方のみです。私の過去のブログを見ていただければ超初心者の方が1人でPCを選択・購入できるようになっていますが、その知識がない方は必ずPCショップに行くことをおすすめします。家電量販店でもゲーミングPCコーナーがある場合がありますが、家電量販店のPC担当者が全員PC知識があるかどうかと言われると、ないと思っていただいたほうがいいでしょう。私の過去の経験からしても家電量販店のPC担当者のほとんどがPCやネットワーク機器に関して知識がない方でした。ですがPC専門店であれば当然自社ブランドのBTOパソコンや自作部品も扱っているため店員の知識の量は家電量販店より信頼性も高く知識量も豊富にあります。そういう側面からもPC部品や性能などがわからない方は必ずPCショップへ行くようにしてください。
マゲっちSCはどのようにして今使用している自作PCを手に入れられたのか?
では上記の第4段階までを私の事例に当てはめて紹介させていただきます。ゲーミングPCの購入を考えておられる方はこれをお読みいただきマネをしていただくと失敗が少なくなるはずです。
私マゲっちSCは現在FINAL FANTASY XIV ONLINE(FF14)と鉄拳7をプレイしていることは前回のブログで少しお話させていただきました。私はPCは自作してPCのメンテナンスなどのスキルを上げたいと思っていたため、簡単にではありますが自作PCを組むという方向性を決めました。次に今現在使っているPCでインターネットにアクセスしてFF14が動作する推奨環境を洗い出しました。そしてそれ相応以上の部品を通販サイトで検索し購入手続きを行っていきました。ただこれは私にPCの基礎知識があったため可能だったわけです。PC部品の性能がまったくわからない方はゲームの推奨環境をメモして家電量販店ではなくPC専門店に行き、店員さんに必ず相談してください。
続いて私が行ったのは周辺機器の選択と購入です。これは先ほど行っていたPC構成部品の選択と同時に行いました。まずはモニターですが、私はすでに2台目の自作PCを持っていたため当然その当時使っていたモニターがありました。モニターそのものはそのまま流用できましたしリフレッシュレートで60Hz出ればFF14は問題なくプレイできるためモニターは当時使用していたものをそのまま使うことにしました。スピーカーも同様ですね。周辺機器は必要に応じて簡単に買い換えできるので当時使っていたステレオスピーカーをそのまま流用することにしました。キーボードとマウスもその当時使っていたものをそのまま流用です。ゲームコントローラーもそのまま流用しました。が、これでは新規で購入される方に関して何の参考になりませんので、初代自作PCを選んだときのことをお話したいと思います。
私が初めて自作PCを組んだときは当然モニターもスピーカーもキーボードもマウスも当然持っていませんでした。最初はモニター選びを行いました。当時接続用の最先端だったインターフェイスがDVIだったため、グラフィックボードにはDVI-D搭載のものを選びました。ですがモニター側には必ずしもDVI-Dポートが付いているとは限りません。当時はまだネット通販での買い物は一般的ではなかったのと、実物を見て大きさを確認したかったということもあって私はPC専門店へ行き実際の大きさとDVI-Dポートがあることを確かめました。スピーカーに関してはあまりこだわりがなかったのでPC用の普通のステレオスピーカーを選びました。キーボードとマウスに関しても、ゲームで使用するのはゲームパッドになるため通常のメンブレンのキーボードと一般用途向けのマウスを選びました。ただ、キーボードとマウス・ゲームパッドは直接手で触るものなので、PC専門店のいわゆる試遊台と呼ばれるもので実際の感覚を試して気に入ったものを購入しました。正直なお話をさせていただくとゲームパッドに関しては何度か買い替えをしました。ゲームデバイスに関してはあまり試遊台というものがなく、多分これでいいだろうという思い込みのもとで購入するしかなかったためです。入力機器に関しては実際に手で触って納得したものを購入するのをおすすめします。また、最近ではネット通販サイトのレビューで良し悪しを書かれていますが、それはその人にとってはよかったというものになります。必ずしも皆さん全員に当てはまるわけではないのでお気をつけください。
購入後の初期設定について
それではゲーミングPCの初期設定についてお話をさせていただきます。これはビジネス向けのPCにも当てはまります。初期設定というのはOSに対して行う設定で例えば時間をどこの標準時に合わせるのか?とか、言語はどこの国の言葉を表示させるのか?などです。家電量販店やPC専門店ではオプションとして初期設定が用意されていますが、本体代に追加して別途2~3万円程かかります。PC専門店ではあまり言われないと思いますが、家電量販店で店員が
「この客はPC知識のレベルが低い」
と判断するとこれらのオプションを強制的につけようとしてくる傾向があります。場合によっては不安を掻き立てるために
「PCの初期設定を誤ると取り返しがつきません」
などと言う方もいらっしゃるそうです。では実際はどうなのでしょう?まずOSの設定に関してですが何をもって初期設定の誤りとしているかが一切不明です。私も初期設定の失敗というものの定義を家電量販店の店員さんに聞いたことがないためなんとも言えません。ただそれ以前にPCの設定というものは使いながら不便だなと感じた場合その都度その都度変更するものです。例えば初期設定で言語設定を英語にしてしまったとしても、言語設定を日本語に後で変えることができます。
壁紙の設定も変更できますし、マウスポインタの移動速度も後で変更できます。言語も基本的には文字が読め理解できる言語であればそのとおりにマウスで設定項目を選択しクリックしていけば簡単に初期設定は終了します。むしろゲーミングPC購入時に初期設定を店舗任せにしてしまうと、その後のゲームソフトのインストールや、ゲーム起動時に必要なユーティリティソフトのインストール、設定も自身で行えなかったりゲーム設定の変更も行えない可能性が考えられるため、ゲーミングPCを購入したのであれば初期設定程度はプレイヤー自身で行えるようにするのが当然ですね。PCの設定や変更ができないのは、プロサッカー選手がボールを蹴られないのと同じです。またキーボードの入力もゲームによっては必要です。PCゲーマーでキーボードのタッチタイピングができない人はまずいません。必ずマスターしましょう。
ゲームそのものの動作保証について
最後に意外と軽視されがちなゲームそのものの動作保証についてお話します。まず家庭用ゲーム機とPCゲームの違いについてですが、家庭用ゲーム機は必ず動作することを前提に作られています。例えばPS4向けに作られたゲームソフトであればPS4の世代に関係なく必ず動作するようになっています。ですがPCソフトになると話は変わってきます。ビジネス系ソフトもそうなのですが、PCソフトの動作環境の本来の意味は、
「この性能のPCを用意してくれたら動作するかもね」
です。BTOパソコンでは例えばですが、「FF14動作確認済み」という文言が貼られているものがあります。この文言があればOSが正しく動作している場合にゲームが動作しなかった場合保証の対象になります。ただBTOパソコンはパーツの組み換えも可能になっているため、保証の範囲の詳細はBTOパソコン販売店と必ず相談して納得した上で購入するようにしてください。例えば基本セットの状態で購入し、OSが正常動作している状態でFF14が動作しなかった場合は保証対象ですが、部品の組み換えを行った場合は対象外になるという場合が考えられるためです。
自作PCの場合はゲームメーカー側も動作保証の対象外としていることが多いです。BTOパソコンの場合であればあるゲームとのコラボがあったり、動作保証モデルとして売り出されることがありますが、自作PCの場合は完全に自己責任になります。そして自己責任の範囲はPCそのものはもちろんですが動作するソフトに対しても自己責任です。確実に推奨環境以上の性能があるPCでも自作PCの場合はごく稀にソフトが起動しない、または動作しないことがあります。現在は動作しないということはほぼ見かけることはありませんが、自作PCは何が起きるかわかりません。企業でメーカー製PCは使用するけれども自作PCを使用しないのはそのような事態を避けるためでもあります。ゲームメーカー側もサービスの運営や今後のバージョンアップ作業、開発作業や保守作業など業務が多岐にわたるため、動作保証を行っている機種以外は責任は取れません。特に自作PCの場合はグレーゾーンであり、ゲームメーカーによっては動作保証対象外と記述されているゲームもあります。ゲームが動作する可能性が高い環境がほしい場合は必ずBTOによるゲーミングPCを購入することをおすすめします。
まとめ
結局のところ金額としては保証や組み立て手数料などでBTOパソコンのほうが少し割高になりますが、自作PCは完全に自己責任になるため何かあった際に助けを求めることが難しいです。価格的に安くてもトラブル解決に自信がない場合は確実にBTOパソコンの購入をおすすめします。特に1台目のPCに関しては確実に自作しないほうがいいと思います。しかし自作PCにもメリットはあります。それはハードウェアの取り付けやUEFI、OSインストールという普通にPCを購入した場合に体験できないことが体験できることです。自作経験者であれば動作が不安定な友人のPCを修理して喜ばれることも割とあります。私も過去に勤務していた会社の上司や先輩のPCの修理を行い食事をおごってもらうことも普通にありました。PCの修理やメンテナンスができるという技術を身につけることはこれからの情報社会でかならず役に立つでしょう。また、UEFI設定をいじることでゲームによる高負荷時でも安定したPCにしたり、CPUの自動オーバークロックを抑える設定を行えば電気の消費量を抑えることもできます。保証は何もありませんが経験を積むことは可能です。
また、プレイしたいゲームや使用したいソフトのOSは必ず確認を行ってください。2021年12月現在ではWindows11が発売されています。しかし、公式にゲームソフトがWindows11に対応しているかどうかの明言がないものに関してはゲームメーカー側の保証対象外になります。ゲームが動作しても仮に不具合が発生した場合に、Windows10で発生せずWindows11だけで発生する不具合であった場合は修正されません。またソフトの動作環境に関して現行のWindows10よりも前のWindows7やWindows8が記述されていることもありますが、マイクロソフト社側でサポートが終了しているOSに関してはゲームメーカー側も保証の対象外にしている場合があります。本来であれば対応OSの記述を変更するべきなのですが、現行OSよりも前のOSでの動作保証はないものと思ってください。それでは次回のブログですがPCの冷却についてのお話をしようかと思っています。あなたのPC、ちゃんと冷えてますか?ご興味がありましたらまたお立ち寄りください。それでは失礼いたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
