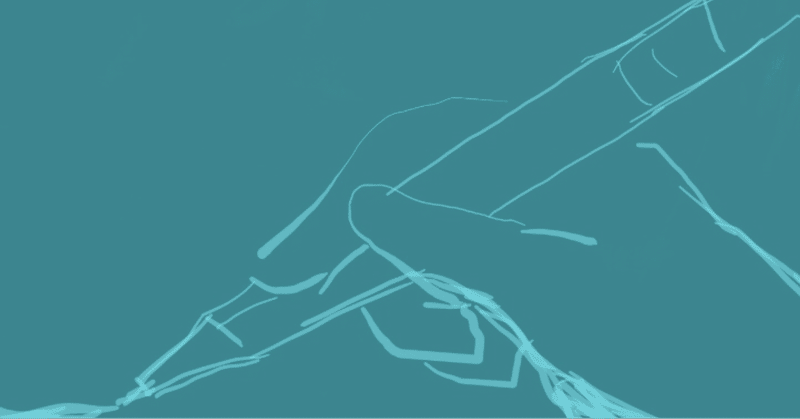
小説未満 新作小説創作途中中継だよ①
創作大賞の募集がスタートすると、新たに物語を書きたくなる。
毎年募集されるのであれば、もう少し計画的にちょっとずつ進めればいいものの、いつも、募集スタートしたよと告知されたタイミングでようやく書き始めようかとなる。
小説をちょこちょこ書いてきたことがあるものの、ファンタジーのジャンルで物語書いたことがないなーと思い、じゃあファンタジーを書いてみようかと思い立つ。
7月の〆切までにどこまでの物語が書けるだろうと悩みつつも、
ざっくりとした世界観と書きたいテーマを考えたあと、細かな詳細の構成などは置いといて、見切り発車で物語を書き進めていくことにした。
最終的に創作大賞の〆切に間に合うように、短くてもいいからひとつの物語として完結できるように書きたいなーと思っている。
書きながら物語を進めつつ、詳細の設定とキャラクターつくりをしていきたいな。最終的には募集要項にそうように体裁を整えて応募しようと思っているけれど、創作途中のメモというか書きなぐったものも、現状こんな感じっすと出していきながら書いていくのもよいのかなということでこれ書いている。
「小説未満 新作小説創作途中中継」という形で
どこまで創作進めたか書いていきたいなと思います。
とりあえず、今日まで考えた物語の断片。
最終的には書き直したり、構成をし直すする可能性大だけど
書きなぐりメモ残します。
noteだしね。実験的なこころみも載せてみるのもよいかなと思いつつ。
では。
創作途中のファンタジー小説の断片。
ーーーーーー書きなぐり途中の物語のシーンーーーー
<世界観の説明的な話>
ジャーニマー国ではピソを食べると力が湧くと信じられている。ピソを食べれば食べるほど、勇者にはより勇気が、魔法使いにはより強力な魔力がわきあがる不思議な食べ物だ。そのピソはギムという希少な植物の種子をすりつぶして粉にしたギム粉をもとに、水と少しの塩と酵母を練り合わせて発酵させて膨らんだ生地を高温の窯で焼く。焼きあがったばかりのピソは金色に輝き、粗熱が取れれば取れるほどくすんだ黄色に褪せていく。黄色くなったピソを食べても十分な力がわくが、焼きたての金色ピソを食べるとその力は黄色のものより2倍以上と言われている。ジャーニマー国はピソの原料となるギムの一大産地で、そこで得た富をもって諸外国に影響を与えていた。ジャーニマー国の政治家はもちろんのこと、貴族を含め、富を持つものは、それぞれお抱えのピソ職人がいて、広い屋敷内にピソ職人の工房をつくり、焼き立ての金色ピソを食べていた。優秀なピソ職人を抱えれば抱えるほどその国家は栄えると言われていた。そのピソをつくるピソ職人は人々から大変敬意を払われていて、権威職であった。ピソ職人になるには国家の認定試験に合格しなければ正式なピソ職人として認められなかった。その難易度はいかばかりか。試験に受からず、認定ピソ職人になれない者はそれでも、ピソ職人の勲章がほしく、自分は正真正銘のピソ職人だとうそぶいた。その者らは、のらピソ職人と呼ばれた。時代が進むにつれてのらピソ職人も増えていった。のらピソ職人と認定ピソ職人を目指す見習い職人が集まるギルドができていた。
<とあるシーン>
少女の人生の最初の記憶だ。ぼろ布を身に着けて、とにかく空腹で、粉塵が舞う集落を歩いていた。それ以前の記憶はない。また小さくて言葉もろくにしゃべれない。腹が減っていることも、ゆっくり寝る場所を探していることも、何もかも意思表示することができない。ただ困っていて、トボトボと歩くのみ。集落の人々は手を差し伸べることもなく、小汚い彼女の存在をないものとしてそばを通り過ぎた。あてもなく歩いて、どれくらい時間がたったのかもわからず、体力も限界で、視界が狭くなって、足も動かなくなり、力が抜けて、パタンと前に倒れこんだ。
「おや、きみは…」
倒れこんできた少女の肩に触れると、骨を触っているかのようだった。粉塵にまみれながら、何日も体を洗えずにいたのだろう、据えたにおいが鼻をついた。少女は目を閉じ、弱弱しく呼吸をしている。
預言者に言われたとおりに、故郷とは反対の方角の荒れ野の地を歩いていた。しばらくして少女と出会うだろうから、保護するようにと言われていた。預言者はその少女はきみのこれからの仕事の重要なパートナーになるだろうと。
まさか、こんな骨と皮だけで、今にも息絶えそうな弱弱しそうな少女のことだとはにわかに信じられない。
集落の住人たちが、離れたところから、こちらの様子をうかがっている。彼は声を張り上げて、「この少女の両親や保護をしている者はいないかね」と呼びかけるも、遠目から様子を伺いみていた集落の人々はそっぽを向いたり、住居に引っ込んだりした。
「では、わたしが一時この娘を預かろう。もしこの娘を保護するものがいたら、隣町のケラスズ城にきてくれ。そこで数日滞在する予定だ。わたしはエラディン。ケラスズ城に滞在中のエラディンをと訪ねてきてくれ」
エラディンという名をきいて、集落の人々は顔を見合わせ少しザワついた。旅から戻り、帰郷したというニュースはもう広がっているのだろう。そして、期待されていたような成果もなく戻ってきたという不名誉なニュースとともに。
集落の近くの馬屋に預けていた馬を迎えて、抱えていた少女を一緒に載せて、ケラスズ城へ向かって走らせた。
日がしずみ、あたりが暗くなってきたころ、ケラスズ城に到着した。門番に名乗って、門を開けてもらった。門の近くの馬屋に馬を預け、少女を抱きかかえた。少女は目を閉じたままでスース―と眠っている。広大な城の敷地の中には、城主に使える職人たちが住む住居や工房がある。城主が住む中央塔まで歩いている途中にある工房のいくつかからは光が漏れていて、職人たちが夜遅くまで何かを作っているようだった。香ばしい匂いが漂ってきて、数時間馬を走らせてきたエラディンもさすがに空腹を感じ始める。工房の一つの扉があき、ひとりの職人が出てきた。大きなバスケットを抱えていて、その中には金色に輝くピソがたくさん入っていた。あれを食べられるならば食べたいものだと思うが、あれほどまでに輝く金色ピソは、尊い地位にいる方々しか食べられない。おそらく、これから城主に献上されるものだろう。そんなこと考えながら、そのピソ職人を眺めていたら、その視線に気づいたピソ職人がエラディンの存在に気付いた。
「あなたは、もしや……エラディン殿ですか?」
「ああ、そうだが」
「お帰りでしたか!おつとめご苦労さまでした」
誰だろうと戸惑っていると
「お忘れですか? フィリッポですよ」
ニカっと歯を見せて笑うその青年は、たしかに数年前のあの坊やの面影がある。
「ピソ焼き坊のフィリッポか! 大きくなって」
「その呼び名も懐かしいものですね。僕はもう見習いではなくなって、正式にピソ職人になりました」
数年の月日は若者を立派にする。それがまぶしい。まだエラディンが旅をする前、ピソ職人を目指すんだと言っていた小さな少年が、立派な大人になり、ピソ職人になっていた。
フィリッポはエラディンが抱えている少女を見て、どうしたのかと尋ねた。
「旅の最後の成り行きでな、一時的に預かっている。」
「そうですか、帰ってきたばかりなんですね!お腹がすいているでしょう? このピソを陛下にお届けしたら、ごちそうしますよ」
「それは、ありがたい」
フィリッポのすすめで、その少女をフィリッポの工房兼住まいの一室の部屋のベッドに寝かせ、フィリッポと一緒に城主のグランディン王のもとに行くことにした。
食卓についているグランディン王の目の前には立派な食事が並べられていた。席についているグランディン王のそばにフィリッポは行き、金色ピソの入ったバスケットをグランディン王に献上した。
「今宵のピソの出来も上々だな。素晴らしい金の焼き色」
「ありがたきお言葉」
グランディン王は金色ピソをかじり、咀嚼する。
「力が湧いてくるようだ」
グランディン王の食事の様子をしばらく眺めていて、話すタイミングをうかがっていた。グランディン王が金色ピソを含め、食事をしている際の集中力はすさまじく、こちらからおいそれと話しかけられないものであった。
食事に集中することによって、その者の湧き上がる力をどれくらい最大化させるかを左右する。
バスケットにこんもりするほどたくさんあった金色ピソがすべてなくなり、グランディン王の目の前の皿もきれいになった。
「さて、数年のときを経て帰還したか、エラディン」
「期待どおりの成果を出せず、誠に申し訳ございません」
エラディンは膝につくくらいまでに、頭を下げた。
「いやいや、頭をあげよ。帰還したばかりで腹が減っているだろう。お主も食事をしようぞ。フィリッポ、エラディンのためにピソはないか」
「は、ご用意します」
フィリッポは、新しいピソを取りに工房に戻った。
「ワシもデザートを食べようかな、隣国から、たしかパチェイという菓子が送られていたはずだ。出してくれ」
給仕係が「パチェイ」という菓子を準備し、フィリッポは黄色いピソを持ってきた。
今日はここまで、まだまだ粗いけれど物語を進めていきながら、キャラクター構成考えていきたい。
いいなあと思ったらぜひポチっとしていただけると喜びます。更新の励みになります。また今後も読んでいただけるとうれしいです。
