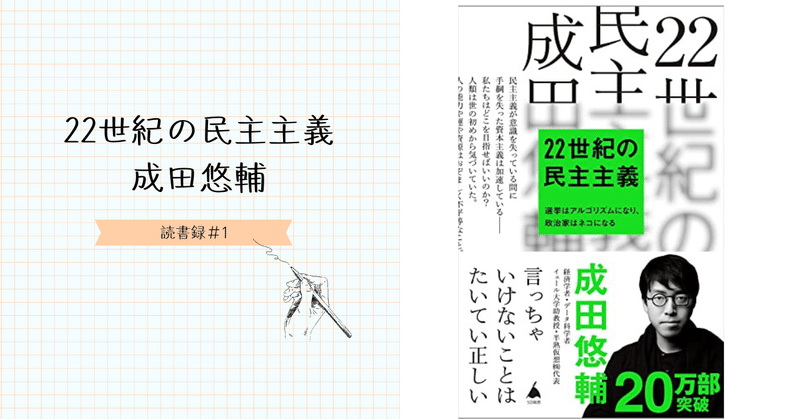
『22世紀の民主主義』成田悠輔 -読書録#1
アメリカの名門、イェール大学助教授の成田悠輔さんの著書『22世紀の民主主義』を読んだ内容をまとめました!成田さんは最近よくメディアでも取り上げられているので、注目しています👀
民主主義の「劣化」には共感することが多く、新たな民主主義のあり方について考えさせられました。ここ最近で読んで良かったと思える本のひとつです。
なぜ民主主義は失敗するのか?
ネットやSNSの浸透とともに進んだ民主主義の「劣化」が原因である。ヘイトスピーチやポピュリズム的政治言動、政治的イデオロギーの分断は今世紀に入り民主主義国家を中心に世界的に進んでいることがわかる。
民主主義の劣化とは?
政治がWebとSNSを通じて人々の声により早く、強く反応しやすくなったことで扇動的で分断を生むような傾向が強まった。仮想敵を仕立て上げて批判する言動や非科学的だが胸躍るような発信で大衆の目を集めると知名度が上がるので選挙に勝ってしまうという構造だ。
政党や政治家によるポピュリスト的言動
政党や政治家によるヘイトスピーチ
政治的思想・イデオロギーの分断
保護主義的政策による貿易の自由の制限
以上の4つの驚異の高まりは2010年以降顕著である。驚くべきなのは、これらの傾向は民主主義国家であるほど強く見られると言うことである。明らかに民主主義は「劣化」しつつある。
そもそも「民主資本主義」という組み合わせは奇妙である。
なぜなら資本主義は強者が閉じていく仕組みで、民主主義は弱者に開かれていく仕組みだからである。
資本主義的な市場競争は、生まれつき不平等な能力や運などの格差をさらなる格差に変換する仕組みである。それを抑制する装置としてあったのが民主主義である。民主主義によって、貧富の格差が広がりすぎたときに貧乏な大衆が金持ちに反乱を企て勝利することができるのである。
しかし現在、資本主義が加速する一方で民主主義は重症に陥っている。
ネットを通じた民衆動員で夢を実現するはずだった「アラブの春」は頓挫。フェイクニュースや陰謀論、ヘイトスピーチが選挙を侵食しトランプに象徴されるポピュリスト政治家の出現。実際今世紀には非民主化・専制化する方向性に政治制度を変える国が増加している。
民主主義国家の経済成長停滞
欧米や南米の民主主義国家の経済停滞に対し、中国を代表とする東南アジア・中東・アフリアなどの非民主国急成長は驚異的である。また、コロナ渦への対応にも、民主国家と非民主国家の対応の結果の差が現れた。非民主国家の方が志望者数を抑えられたのである。
そのように見ると、世論に忖度しなければならない民主主義は限界を迎えているだろうと思われる。
では、民主主義の再生には何が必要か?
答えは3つある。
民主主義との闘争
民主主義からの逃走
まだ見ぬ民主主義の構想
①民主主義との闘争
民主主義との闘争とは民主主義を改良・調整していこうという営みのことである。
具体的には、ソーシャルメディア・選挙・政策の悪循環のどこかに手を加える必要があるだろう。そうすると、以下のような選択肢がある。
有権者内の同調圧力や極論化をつくるソーシャルメディアに介入して除染する
量への制約:公開ウェブでの同期コミュニケーションの速度・規模への制約
質への制約:コミュニケーション・情報の内容に応じた課税
有権者が政治家を選ぶ選挙のルールを未来と外部・他者に向かうように修正する
政治家への定年や年齢制限(世代交代と新陳代謝により注意を未来に向けるため)
有権者への定年や年齢制限(若者の投票インセンティブによる未来志向の強化のため)
世代別選挙区(マイノリティの意見の反映のため)
投票者の平均余命で票の重み付け(未来志向の強化のため)
選ばれた政治家が未来と外部・他者に向かって政策を行うインセンティブを作る
政治家への長期成果報酬年金:政治家が退任した後の未来の成果指標に応じて引退後の成果報酬年金をだすということ
ガバメント・ガバナンス(政府統治):成果に向けたインセンティブを与えるための、企業統治を政府に取り込んだもの。
②民主主義からの逃走
タックス・ヘイブンのように、政治的デモクラシー・ヘイブンはありえるのではないか。独自の政治制度を行う新国家群が企業のように競争し、政治制度を商品やサービスのように資本主義化した世界である。
しかし、民主主義から逃走したところで、民主主義に内在する問題を解決はしない。民主主義の再生を図るならまだ見ぬ民主主義の構想が必要だ。
③まだ見ぬ民主主義の構想
民主主義とはデータの変換である。それはつまり、有権者の民意を表わすデータの入力があり、何らかの社会的意思決定を出力するルール・装置であるということである。そこで新しい民主主義の構想として、入力される民意データ、出力される社会的意思決定、データから意思決定を計算するルール・アルゴリズムをデザインすることが考えられる。
そこで、まだ見ぬ民主主義の構想として挙げるのが「無意識データ民主主義」である。
「無意識データ民主主義」とは
「無意識データ民主主義」
=①エビデンスに基づく目的発見+②エビデンスに基づく政策立案
である。
①エビデンスに基づく目的発見
まず、ネットや監視カメラが捉える人々の言動や表情などの民意データに基づいて、人々が重要視する政策や論点を発見する。
②エビデンスに基づく政策立案
①で発見した目的関数や価値基準に従って最適な政策的意思決定を選択する。これは、過去に様々な意思決定がどのようなせいか指標につながったのか、過去データを基に効果検証されることで実行される。
無意識民主主義は大衆の民意による意思決定、少数のエリート選民による意思決定、そして情報・データによる意思決定の融合である。
おわりに
ここ数十年で、人々の生活は驚くほど変化を遂げてきた。情報コミュニケーション・データ技術は地球の裏側の人々を容易に繋ぐことを可能にした。その一方で、選挙制度や政治の仕組みは変わっていないままであるのは異常なことではないか?民主主義は単なる意思決定のアルゴリズムであるという機能に着目すると、改善の余地は山ほどあるだろう。今こそ現在の民主主義の形を疑い、異常を普通にしていくべきときなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
