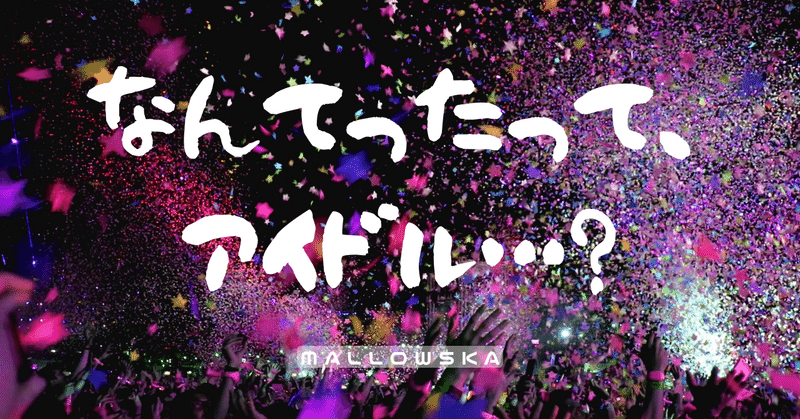
【小説】なんてったって、アイドル…? 前編
「あん? 今、何て言った?」
「K-POPアイドルになろうと思って、と申しました」
二度目はわざと丁寧な言葉で嫌味っぽく言った陽菜だった。稜央はまだ、何を言ってるんだコイツは、という目で妹を見ている。
「えー、ごめん。君は日本人なのにK-POPアイドルになるとは、どういう…」
「お兄ちゃん分かってないね。今はグローバルがスタンダードなんだよ。国籍関係ないの。アイドルになるために韓国に渡る時代だよ。アメリカンドリームならぬ、コリアンドリームなんだから」
それでも稜央は呑み込めない。え、何。そもそもアイドルって、正気なの。
「お前、アイドルになるつもりなの?」
「だからそう言ったでしょ」
「ちょっと待って。アイドルってそんなに簡単になれるんだっけ」
「簡単ではないよ。まだ練習生にもなってないんだからわからないし。で、何でお兄ちゃんに話したかっつーとさ」
快活で身体を動かすことが好きな陽菜は、中学でバスケ部に所属しながらもダンスにもハマり、部活のない日は友人と公園などで踊っている。
その趣味が段々と高じてきた、というわけだ。
ある日、友人のお姉さんの友人が、オーディションに受かって現在韓国に渡り、練習生として活動しているという話を聞いた。
へぇ、行けるもんなんだ…。そう思うと陽菜も行けるんじゃないか、という気が沸き起こってきた。
が、当然ながらタダで行けるわけではない。中学生の陽菜は自分で稼ぐことも出来ないし、兄の稜央だってピアノが好きで才能もありながら、金銭的事情で専門的な教育を受ける事が出来なかった。母は大学を中退して稜央を産み、シングルマザーだったこともあって、お金の余裕なんて当時全くなかったからだ。
だから陽菜もお金のかかる習い事を申し出るのは気が引ける。
陽菜は、そんな稜央の意見が聞きたく、兄の部屋を訪ねたのだった。
案の定、稜央は腕組みをして唸った。
「いつもだったら母さんはやりたい事やんなさいよ、とは言いそうだけど…でもなぁ…韓国だろ? 向こうで暮らすって事だよな」
「うん、寮に入る事になると思う」
「母さん、寂しがるっていうか、心配するっていうか、そりゃダメだって言うと思うな」
「まぁそれを言ったら、どこへも行けないでしょ」
陽菜の感覚は稜央とは逆のようだ。稜央は母と幼い妹が心配で、地元に残り進学し、就職もした。
「まぁ、そうだけど…。高校どうすんの? 韓国で通うつもりなの?」
「そうなるだろうね。日本人学校がないからインターナショナルスクールか韓国の学校に通うみたいなんだけど、そこはもう多くの日本人の先人がいるからさ、そこを参考に出来るでしょ。でもさお兄ちゃん、私が気にしているのは、私だけそんなワガママ言って、なんか変な感じにならないかなとか思って」
「何がよ」
「お兄ちゃんはピアノ…独学で通したでしょ、学生のうちは」
「そのこと? 俺は別に今更…どうとも思わないよ」
「あとやっぱりママの負担が…」
「まぁ、そうだなぁ…」
鼻で大きく息をついて稜央は天井を仰ぎ見た。
いや、でもアイドルって。いやいや。
稜央はまだよく呑み込めていないようだった。
***
「はぁ?」
案の定、母の桜子は素っ頓狂な声を挙げた。稜央はむしろいたたまれない気持ちで、ごもっとも、と言わんばかりに黙って頷く。
「お兄ちゃんと同じリアクションだね。K-POPアイドルになろうと思って」
「待って待って、ちょっと待って」
桜子は自分の頬をペチペチと叩いた。
「K-POPって、韓国だからK-POPっていうんじゃないの? 韓国の子がなるからK-POPなんじゃないの?」
「だからー、今はグローバルなの。国籍関係ないの。確かに本拠地は韓国だけど、どの国の子でもなれるんだよ」
「日本のアイドルじゃダメなの? アイドルってそもそもアレだけど…。近くのダンススタジオに通うんじゃダメなの?」
「うーん、ダメっていうか、所詮片田舎だから」
「いきなり高みを目指すのも大事かもしれないけど、まずはこんな片田舎でもそこから国内でトップを目指すとか、段階踏んでみてもいいんじゃないの?」
桜子の言うことは最もである。
しかし今やK-POPアイドルは、早ければ陽菜と同い年でデビューを果たす者もいる。
そして韓国芸能事務所の練習生は15歳前後で入るのが望ましいとされている。練習生として4~5年はかかると言われているからだ。陽菜は今14歳。瀬戸際だ。焦っている。
陽菜は自分で調べた、練習生になれる可能性の条件を満たしていると思っての懇願だった。
バスケのお陰で身長は14歳にして159cm。体重も太すぎず細すぎず。音痴というわけでもない。見た目は…多分まぁまぁ。しかし意外と見た目はこの時点では左右されない。女性の見た目は年齢とともにどんどん変化するため、今の時点では最重要というわけではない。メンタルもまぁまぁ強いと思う。
イケる…そう思ったから、こうしてお願いに上がっているというわけだ。
とはいえ所詮まだ中学2年生…保護者の同意なくしては何も出来ない。
「もう一度よく考えたら? これはお金があればいいっていう話でもないし」
「お金もそうなんだけど…、そんなに呑気にもしてられないんだよ」
陽菜は悲痛な声を挙げ、桜子はため息をついた。稜央はどうコメントしていいかわからず押し黙ったままだ。
「それに陽菜、来年高校受験だよ? 学校どうするの?」
「韓国で通うことに…なると思う」
「えぇ…あんた韓国語出来たっけ」
「アンニョンハセヨ。カムサハムニダ、なら完璧」
「ダメじゃない」
「挨拶できればなんとかなるよ!」
「楽観すぎでしょ」
呆れる桜子に、ふてくされ顔の陽菜。
「ねぇ陽菜。何度も言うけど、どうしても韓国でないとダメなの? 日本だって似たようなアイドルグループあるじゃない」
「だから! 韓国でやることに意味があるの! 日本のアイドルグループには興味がないの!」
陽菜は大人数グループの一人よりも、歌もダンスも徹底的に鍛えられ、ザ・プロ!という雰囲気を持つ韓国アイドルの方が魅力的に思えていた。
桜子はため息をつく。稜央がようやく口を挟む。
「なぁ陽菜。母さんも言うようにもう一回よく考えてみろ。みんな色々な事情があるはずだろ。道だって1本しかないわけじゃない」
「…」
だから、じっくり考える時間はないっていうの。私はもう14歳なのだ。陽菜は強く思う。
***
陽菜が留守にしている、とある休日の昼下がり。
稜央は実家を訪れ、桜子と1本の動画を観ていた。それは韓国のアイドル登竜門とも言うべきサバイバルオーディション番組、通称 "サバ番" だった。
桜子にとっても、若い稜央にとっても、咄嗟に外見を区別するのが難しいような、言ってみれば似たり寄ったりの色白・長い黒髪・細長い手足を持ったスタイル抜群の女の子たちが歌い、踊り、パフォーマンスを披露する。その容姿、笑顔、ポージングにウインクまで、すでにアイドルそのものだ。これがまだプロデビュー前だというのだから驚きだ。
審査員はプロデューサーやダンスやボイトレの講師であったり、現役のアイドルであったりするようだ。彼らは時に辛辣な言葉を挑戦者らに容赦なく投げつけ、その場で涙ぐむ者もいる。勝者と敗者の落差は、観ているこっちがいたたまれない気持ちになる。
「こんなに大勢の子たちが、同じようにアイドルを目指してるの…」
「これって参加者は事務所の練習生だっていうから、陽菜が目指しているとこの、そのまた先の姿ってことだね」
「こんな幼い子たちに結構辛辣な言葉浴びせるんだねぇ…」
「これくらいのこと乗り越えないと、芸能界ではやっていけないだろうよ。そういう試練の意味もあるんじゃない?」
「そうよね、芸能界は華だけじゃないし」
「むしろ華の裏にある闇の方がはるかに広くて大きいんだろうな」
そうして2人は押し黙った。
「…なんでまた陽菜はK-POPアイドルを目指そうなんて思ったのかしらね」
「さぁ…流行ってるし…ちょっと踊れて、背もまぁ高いし、自分はイケるって思ったんじゃないかな」
「まったくもう…」
「母さんはさ、仮に陽菜が本当にアイドルでデビューすることになったら、どうする?」
「えっ!? え~、そりゃあ…そうなったらまぁ…応援はするだろうけども…」
「デビュー出来たとしてもさ、世の中にはアンチも必ずいるし、こういう審査委員以上に辛辣な言葉とか浴びたりするんじゃない? SNSとかで…」
「えぇ…? ちょっとやめてよ、そんなこと言うの…」
「ま、アイドルになったら、の話だけどさ」
そうして再び2人は押し黙った。
*
その頃。
陽菜は近所の公園で、友人らと集まって曲を流しながら踊っていた。
さすがバスケで鍛えた体幹、ダンスの切れ味は良い。調子に乗る要素は、まぁある。
休憩の時、陽菜は友人に実家でのやり取りを吐露した。
「やっぱりすんなりOKとはいかなかったわ」
「それってもうどこかから選考通知とか来てるってこと?」
「ううんまだ。出してもいない」
友人はわざとらしく大きなため息をつく。
「そこはさ、まず申し込まなきゃ何も始まらないよ。それで通ればオーディションがある。まずそこまで進もうよ。オーディションに受かってから報告すれば、さすがに辞めなさいって言いにくくなるんじゃない?」
中学生はあくまでも楽観的である。陽菜はなるほど、それももっともだ、と思った。
「よーし、こうなったらもう片っ端から事務所にメール送るしか無いね」
そんなわけで陽菜は帰りに友人の家に寄り、友人のパソコンから翻訳ツールを使ってES(エントリーシート)を埋め、顔写真、全身写真、ダンスや歌の動画を添付して8ヶ所ほどに送りつけた。自分のスマホもパソコンも持っていない陽菜に友人は「連絡が来たらすぐに伝える」と言ってくれた。
***
アイドルになりたいと突然の相談を受けてから1ヶ月。ここ最近の陽菜はそれについて触れることもなく、大人しかった。
「あんた、アイドルの夢は諦めたの?」
「…」
1ヶ月経過しても、まだどこからも1通の返事も届いていないのである。世界中から同じような夢を持った若者が応募するわけだから、処理に時間がかかるのはわかるが、比較的規模の小さな事務所にも送っている。まさかESの時点で全滅なのか、と暗い気持ちになっていた。
桜子は桜子で、その話題に触れようとしない娘を少し不憫に思った。あまりにも突飛で賛同してあげられなかった。あれだけ厳しそうな世界なのだ。その現実を知るためにも、応募させて、その上で挫折を知ることも大事か、と思った。
受けるだけ、受けてみたら ー。
そう言ってやろうと思ったが、やはり思いとどまる。
でも、韓国でしょう…。遠いわ。
とはいえ、比較的近くの福岡から飛べば東京へ行くよりは近いのだが…。何しろ、海外だ。
「ダンス教室とか、とりあえずそういう所から行ってみたら…」
「いったん、いいから、その話」
陽菜は触れてほしくないと言わんばかりに話題を避け、部屋に行ってしまった。
やれやれ…。
14歳。難しい歳頃よね…。
*
翌日。
学校で陽菜は友人から朗報を受け取った。
応募したうちの1社から、オーディション案内の連絡が届いたというのだ。同じくスマホを持っていないその友人はメールをプリントアウトして持ってきてくれた。
「陽菜、やったね! チャンスが出来た!」
「あ…通った…本当に書類選考が通った…!!」
その事務所はオンラインオーディションを実施するという。日時と方法について案内が書かれていた。
陽菜は友人とガッツポーズした。
家に帰った陽菜は、
「マm…!」
桜子に報告しようとして留まった。友人からは『オーディションを通過した上で報告すれば、ダメとも言われないだろう』と言っていたからだ。報告は時期尚早だ。
*
その後も合計2社から一次選考のオーディションの案内が届いた。さすがにどこも大手の事務所というわけではなく、この時点で既に門の狭さを感じた。
そのうちの1社が都内でオーディションを開催するという。
東京…遠い。パスポートなしでも行けるが、ここからは直線距離だったら韓国より遠いのだ。
陽菜は稜央に連絡した。
「お兄ちゃんって東京に行っちゃった彼女とまだ続いてるんだっけ?」
『なんだよ急に…いや、もうしばらく会ってないよ…』
「えっ!? 別れちゃったの!?」
『うるさいな、いいだろそんなこと。何でそんなこと訊くんだよ』
「私を東京に連れて行ってほしいと思ってさ、ママに内緒でさ」
『内緒で? 何を企んで…あ、もしかして…例のアイドル話か?』
稜央は日本の芸能事務所に申し込んだのかと思ったらしいが、陽菜が状況を説明するとため息をついた。
『っていうか書類選考通ったって…大したもんなんだな、お前』
ちょっと鼻が高くなった陽菜。
「でさぁ、チャンスなんだから、どうしても行きたいの。ママに内緒で連れて行って! ね? お願い!」
チャンスって言ったって…。福岡とは言わない、せめて大阪でやってくれればまだ近いのに…。と稜央は思う。
それに東京は、遠距離していた彼女のことも含めて、数々の苦い思い出が今もなお生々しく稜央の胸に残っているのだ。複雑な心境だ。
先日桜子と観たサバ番を思うと、あの過酷な世界の初めの扉を開こうとしている陽菜に対し、これまた複雑な心境になる。選ばれし者だけが残る世界。されど厳しい評価を受ける世界…。
「ねー、お兄ちゃんしか頼れる人いないんだからさー!」
『わかったわかった…。ったくしょうがねぇなぁ…』
「連れてってくれるの!? やった!」
ま、どっちに転ぶにしても、行けば気も収まるか。合否を決めるのは俺じゃないんだし。
稜央の気持ちは、そんなところだった。
後編に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
