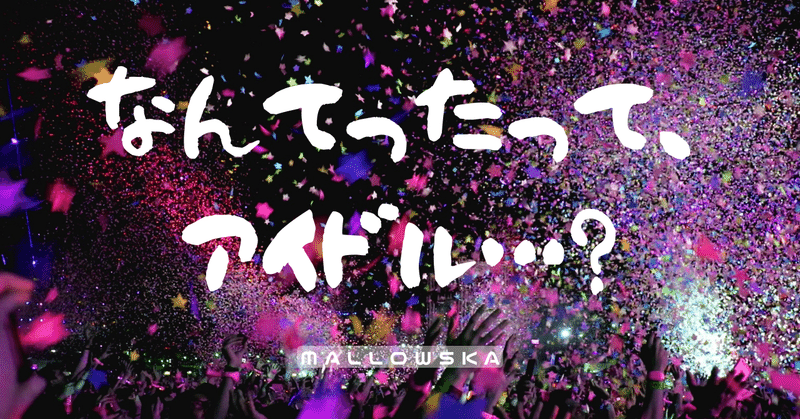
【小説】なんてったって、アイドル…?後編
陽菜と稜央は空路で羽田に降り立った。
なにせ母親に内緒で出てきているのだ。日帰りしなければならない。時間節約のために飛行機を選んだ。費用はもちろん稜央が負担している。痛い出費だ。陽菜には出世払いしてもらわないとな…と思いながら、いや本当にアイドルになって稼ぐようになっちゃったらどうなるんだよ、とまたもや複雑な心境になる。
稜央が学生の頃は夜行バスで東京に出てきた。遠距離の彼女に会うため、そして、会ったことのない父親を探すため…。
ブルブルと頭を振って苦い記憶を追いやる。今日は陽菜のオーディションなんだ。俺は保護者代わり、大事なことだぞこれは、と言い聞かせて。
「お兄ちゃん、東京やば! 空気悪そっ! 本当にビルばっかり! 空がめっちゃ狭いよ」
そうか、初めての東京というのはそういう感想を持つのか、と思う。修学旅行だって来年の話だ。東京へ行くのかは知らないが。
稜央は自分が東京に初めて出て来た時、空が狭いとかどうとか、何とも思わなかった。むしろ、空なんて見上げた記憶がない。
あの時の俺は…針の先のような視野だったなと思う。
スタジオのある原宿まで移動すると、休日も相まってむせかえる程の人でごった返している。陽菜は先ほどから徐々に口数が減っている。
「流石に緊張して来たか。こういうの初めてだもんな」
「オンラインオーディションはこの前1件受けたから初めてってわけじゃないけど、今回は何人か集まってると思うから、ちょっとね」
「へぇ。もう受けたんだ。そっちの結果はどうだった?」
「まだわからない。合格なら連絡が来て二次に進むんだけど」
「二次まであるのか」
「三次まであるよ」
稜央は仰天した。
そして “サバ番” を思い出す。過酷だな…、と。
「そうまでしてみんなアイドルになりたいもんなのか」
「他の人の事情はわからないけど」
「まぁな。でもお前はさ…」
「まぁ別に、何がなんでも絶対アイドルになりたいわけじゃないけど…」
稜央は意外に思った。この間までの勢いはどこ行った。でも今はオーディション前。余計な事を言ってナーバスを増幅させても仕方がないと、黙ることにした。
「じゃ、行ってきます」
会場の建物の入口で陽菜は顔を引き締めた。中までついて行けないため、稜央は近所のカフェで待つこととなっている。大体3時間ちょっと掛かると聞いている。
「おぅ。頑張れよ」
どことなく頼りない背中を見送り、稜央はその建物近くのカフェに移動した。
*
会場には陽菜を含めて13人の挑戦者たちが集まっていた。中学生が8人、高校生が5人。着替えを終えた参加者はスタジオの隅に置かれたパイプ椅子に座って待機する。
当たり前かもしれないが、皆スタイルが抜群に良い。そして垢抜けている、ように見える。陽菜以外にも地方から出てきた人はいただろうが、それでも陽菜は怯んでしまう。
"これが…世界か…"
いや、まだ全然国内なのだが、陽菜にとっては東京に出てきただけでもう十分 "世界" なのである。
オンラインオーディションを受けて以来、陽菜は少々怖気づいていた。“ジャッジを下される” と言う事は極めて冷ややかなのである。
『10』と書かれたゼッケンのような番号札を渡され、胸の中央に付ける。
参加者はスタジの隅に並べられたパイプ椅子に座り、他者のパフォーマンスを目の前で見ながら、自分の番を待つ。
まずはダンス。
他人のをじっくり見るべきか、それとも他人に左右されないように目を閉じて気持ちを集中させるべきか…。
周りを見ると、皆しっかりとライバルの演技を凝視している。仕方無しに陽菜も同様にした。
しかしやはり、落ち着かなくなってくる。みんな自分よりも洗練され、優れているように見えてしまう。
やがて自分の番になる。
陽菜はどちらかというと歌に自信がないので、ダンスに掛ける必要があった。エレクトロスィングな曲でヒップホップダンス。ステップに重きを置いた、ちょっとこれは選ばないだろう、という線を攻めたつもりだ。
↓イメージ曲
踊り終えて、審査員からの質問とフィードバック。他の参加者も隅のパイプ椅子に座り、じっと様子を伺っている。
「体幹はいいですね。ダンス歴は…独学で約1年ですか」
「はい、バスケをやっているので、そのトレーニングなどで鍛えられたと思います」
「リズム感も悪くない。けれど荒いですね。独学ですものね。指先の意識がおろそかです」
「はぁ…」
*
次は問題の歌。
曲はBeak A Yeonの『I Need You』を選んだ。
特段ものすごく思い入れがあるわけではないが、ラッパーを目指すわけでもない限りは、こういう時は皆バラードを選びがちなので、それに倣った。流行りの歌よりも気を引くかも、という思いで選んだ。ダンスでは攻められたのに、歌は守りに入ってしまった。
自分に視線が集中する中でのバラードは思った以上に難しかった。声が思うように伸びず、これはダメだな、と思った。
歌い終えて、審査員からの質問とフィードバック。
「何故この曲を選んだのですか?」
「メロディがすごく良かったので」
「それだけですか?」
「…」
「カラオケとは違いますよ。あなたの歌で、思い入れも無しに、目の前にいる観客が夢中になり、心を揺さぶられると思いますか?」
「…」
そんなこと言われたって、私は未だアイドルじゃない。それをこれから訓練していくためのオーディションじゃないの?
隅にいる参加者たちに目をやると、心なしかみな安堵の表情を浮かべているように見える。
ここでは誰かが悪く言われれば、自分には希望が持てるからだ。
そういう世界だ。
*
全員分が終わった後、一次の結果はその場で発表される。番号を呼ばれたものだけが残り、次のステップの案内をされる。呼ばれなかった者はその場ではい、さようなら。
陽菜の番号は、呼ばれなかった。
合格者は5人。中学生3人に、高校生2人。
仕方がないとはいえ、悔しかった。経験不足? 当たり前じゃない、田舎に住む中学生なんだから!
そう思って気付いた。もう経験を積んでいる子はガンガン積んでいるのだ。歳だけではない。環境、積極性、そういったものも含めて陽菜は未熟だったということだ。
陽菜はようやく、無謀な挑戦であることを悟った。田舎の片隅で調子に乗っていたことが恥ずかしくて、悔しくて、涙が溢れた。他の敗者も泣いている子がいて、便乗したといえばそうかもしれなかった。
『ここに来れただけでもすごいと思わないと』
『でもここ、初回の場合、よっぽどのことがない限り書類では落ちないよ』
そんな会話が陽菜の耳に届いた、他の参加者たちの会話。
そうか。
自分も「とりあえず来い」だっただけなのだ。それで「お遊びの延長」の烙印を押されただけなのだ。
"もしかしたら" という期待が、いつしか "きっとうまくいく" という錯覚に変わっていた。
だからこそ、落選は思った以上にショックだった。
*
待ち始めて3時間半が過ぎ、何度も時計を見ながら段々と稜央も落ち着かなくなってきている。
「もうそろそろだよな? どうだったんだろうな…」
予定している時間を過ぎても陽菜は現れない。オーディション会場はここから見える場所にあるから、裏口から逃げもしない限り、途中で事件事故にあったとは考えにくい。
ヤキモキしていると、ようやく正面玄関から陽菜が姿を現した。
見た瞬間、あ、ダメだったんだな、とわかった。
「よ。どうだった?」
それでも、稜央のテーブルまでやってきた陽菜になるべく明るく尋ねる。訊くまでもなさそうだが、一応。
「不合格」
陽菜ははっきりとそう言った。
「まー、そんなもんだろうな」
「そうだね」
覇気のない声。まぁ、当たり前か。
「でもまだもう1つの方が連絡待ちなんだよな?」
「そっちもダメじゃない?」
もう、投げやりだ。
「…まだ搭乗までちょっとだけ時間あるから、なんか旨いもんでも食って帰るか! な!? せっかく東京まで出てきたことだし」
励ますようにわざと明るく声を掛けたが、陽菜は「お兄ちゃん、都内の美味しいお店、知ってるの?」と鋭いことを訊いてくる。
「ラーメンとか、そういうつまらないのは嫌だからね」
ラーメンのどこがつまらないんだ!と稜央は憤慨しそうになったが、中学生の陽菜が初めての東京で、もっとハイソなイメージを持つのも最もだった。
「じゃあ何がいいんだよ?」
「フレンチ」
「はぁ? お前、それを言うなら韓国料理くらい言っとけよ」
「何でもいいよ」
稜央は鼻でため息をつく。
「まー、その辺歩いたらあるだろ、なにか!」
しかし外に出れば若者・外国人観光客でごった返す原宿・表参道である。稜央はうんざりしてしまう。
「…空港の飯でもいい?」
「だからなんでもいいよ、別に」
冷めた陽菜である。ラーメンは嫌とか言っておきながら、まったく。
結局2人は羽田空港内の回転寿司に行った。陽菜は中トロ・ウニ・イクラと高い皿ばかり重ねた。内心 "この野郎" と思っても、何も言えない稜央だった。
「ねーお兄ちゃん。“HINA” って綴りはさ、アイドル感出てるよね?」
寿司を食べて少しは気力が戻って来た様子で陽菜は言った。
「綴り?」
「アイドル感ある名前でしょ?」
「はぁ…まぁ…そう…なのか…ね…」
「あーあ。もっと早く気付けば良かった。もっと早く準備しておけば良かった!」
そう言いながら5皿目のウニとイクラに手を伸ばす。
おいおい、そんなにプリン体取って、身体に悪いぞ…と言おうとした所でまだ14歳。
大きなため息をつき、ヤリイカに手を伸ばす稜央だった。
*
結局、オンラインオーディションを受けた事務所からもその後の音沙汰は無かった。合格者のみに連絡が行くとのことだったので、たぶん落ちたのだろう。
これが現実。
陽菜は潔く諦めた。『黒歴史』として封印する事になるだろうな、と思った。
成仏してね、私の儚い夢🙏🏻
***
数日後。
「お兄ちゃん、ちょっとうちに来てくれない?」
仕事を終え帰宅し、一息ついていた稜央に陽菜から電話が掛かって来、唐突にそんなことを言う。
『何、どうした?』
「ママが大変なことに」
『えっ!? 何、倒れたのか? 救急車呼んだか!?』
「あ、全然そういうんじゃなくって。元気なんだけど、ちょっと…」
訝しがりながらも稜央はすっ飛んで実家に向かった。
「あ、お兄ちゃん。ママ、リビングにいるから」
「一体何があったんだよ?」
慌てて駆け込んだ稜央が目にしたのは、うちわを手にした桜子だ。そのうちわにはハングル文字が描かれている。
そして桜子が観ているTV画面には…華麗なダンスを披露する男性アイドルグループ。
「もしや…」
桜子は2人に気づくと、喜々として画面を指さした。
「あら、稜央、どうしたのこんな時間に?あ、ちょうどよかった。ちょっとこの子見て!キレイな顔してるでしょう? こんなにキレイな顔した子、この世にいる? いるのよねぇそれが…」
「母さん…」
「ねぇ、この子たち今度日本でドームツアーやるんだって。福岡にも来るかしら。そうしたらあんたたち、チケット取るの手伝ってよ。あ、やっぱりファンクラブ入らないと厳しいかしらねぇ。どっちにしても1人で行くのはちょっと恥ずかしいから、陽菜、あんたもついて来て」
「ママ…」
「っていうか陽菜、高校に入ったらもう1回K-POPアイドル目指してみたら? ママ応援するわよー。あ、何ならママが目指しちゃおうかな~」
「えっ…」
「なーんて! 冗談よ、冗談! でもね、ママだって身長ある方だし、学生時代はスタイルだってそれなりに良かったのよ~」
「そ、そうなんだ…」
稜央は呆気にとられている。「はぁ、なるほど。そういうことね…」
陽菜は稜央に耳打ちした。
「まさかママがハマるなんてさ。それにしてもママって、相当な面食いだったんだね。ママが好きな彼はビジュアル担当なんだよ。私のパパとは似ても似つかない。やっぱ理想と現実は違うんだね」
稜央と陽菜は異父兄妹である。
稜央は陽菜の父親の顔をはっきり覚えていない。そもそも彼に対して稜央は憎々しい思い出しかないため、無意識に記憶から消し去っているようで、思い出そうとすると靄がかかる。
陽菜は自分の父親が稜央に何をしたか、知らない。
一方の稜央の父親の方は、そっくりだと言われた自分が思うのも何だが、なかなかのイケメンだと思う。それは自分にない内面から滲み出るカッコ良さなんだろうと思っていた。
稜央はそのメンバーの顔をじっくりと見た。
言われてみれば…どちらかといえば…親父に似ていなくもない…かもしれない…。
いや、わからない…メイクしているし…髪、紫色だし…手でハートマーク作ってるし…。
何故か稜央の脳内では、父がウインクしながら "きゅんです🫰🏻" ポーズをしている姿が浮かんだ。
いや、ないない、ないないないないない。
あの人、そんなかわいい人じゃない。
なんか、ごめん。
稜央は何故か心で謝った。
「あ~もう、生まれてきてくれてありがとう🥺!! って気持ちになるわぁ」
桜子はもう2人に背を向け、うちわを振りながら画面の中の彼らに夢中になっている。
「ね、お兄ちゃん。大変なことになってるでしょ…」
「う、うん、まぁ…」
「最近の晩ご飯、毎日韓国のりとキムチが出てくるの」
「へぇ…そりゃ、コリアンだ、ね…」
「たまには納豆も食べたくならない?」
「まぁ…良かったんじゃない…夢中になれるものがあるっていうのは…」
アイドルの道を開いたのは、どうやら桜子の方であったようだ。
沼、という名の道ではあるが。
「アイドル、最高〜〜〜🫰🏻💕🫶🏻」 by 桜子
END
※オーディションの様子はフィクションです。どこかの事務所の例を上げたものでもありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
