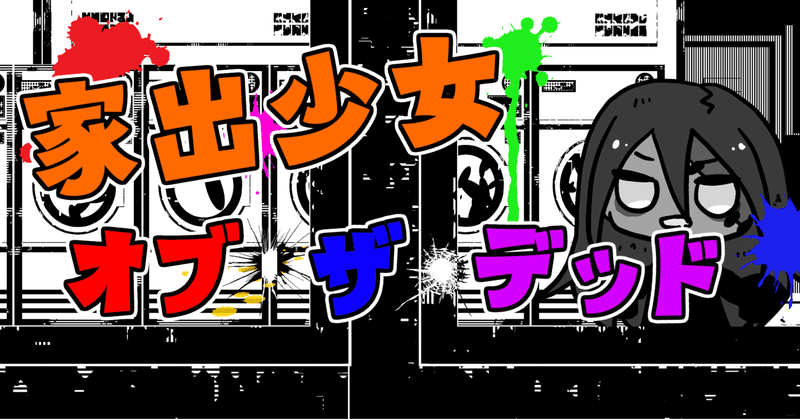
家出少女・オブ・ザ・デッド
夜の町を歩くのは様々だ。
仕事帰りの人、勤務中の人、部活終わりの学生、今から塾に通う学生、いかがわしい店の呼び込み、下心満載の下衆、暇人、酔っ払い、プッシャー、今夜あたり飛んでしまいたい人、実に様々で中には変なのがひとりやふたり混じっていても、多分そんなに気づかれないだろう。
でも変なのは自身の状況が変である自覚があるので、なるべく安全な場所に向かってしまう。
夜の町で最も安全な場所はコインランドリーだ。
コンビニのイートインもいい線いってるけど、飯を食べ終えたら出ないといけない。安全に対するコスパが悪い。
その点、コインランドリーは圧倒的にコスパがよい。洗濯をしている時間はもちろん、空いてさえいれば洗濯をしているふりでもして過ごせば、少なくとも夜の9時くらいまでは平穏に過ごせるし、24時間営業であれば朝まで過ごすことも不可能ではない。
もちろん警察から何をしているのかと問われることもない。答えは問うまでもない、一目瞭然、見ての通り。洗濯をしている、だ。
おまけに防犯カメラ完備で死角も皆無だから、捕まる前に稼ぐだけ稼いで国に帰っちまおうな外国人窃盗団でもない限り、小銭目当てなんかで大胆な無法を働きはしないし、そういう連中はもっと金の臭いのする宝石店やブランド品店を狙うため、結局コインランドリーが安全であることは揺るぎない。
「この世に存在してくれてありがとう・オブ・ザ・イヤーだ」
行く当てのない家出少女が砂糖多めの缶コーヒーを飲みながら一息吐く。
帰る場所もなければ帰るつもりもない、かといって生活を変えるつもりもない少女からすれば、この防御力高めの砦は実家よりも教室よりも安全で安心なのだ。
変な来訪者でもない限りは。
「……あ、人がイる。穴場だと思っテたのに……」
「そりゃいるでしょ、コインランドリーなんだから」
少女は夜9時過ぎの来訪者の、妙に片言な言葉に無作為に返事をしながら、視線をゆっくりと移して目を丸くした。目を丸くしたというのは比喩的表現というやつで、実際は怪訝な表情というか、眉をひそめるというか、どちらかというと目を細めた。
理由は簡単、そこにいたのが明らかに不健康な青白い肌の色をしていて、若干の腐臭を漂わせる小柄な女だったからだ。とにかく尋常ではないのは、裸足の足元からは体液のような生臭い汁が漏れていることだけでも十分わかる。
しかし生臭いものが危険かと問われれば、答えはノーだ。
「こ、怖くないんデすか……?」
「んあ? 別に?」
怖くないといえば嘘にはなるが、怖いといえば過剰になるのも、また一つの真理だ。
ゾンビである。
もちろん決して喜ばしいものではなく、ましてや出会いを祝してハグのひとつもかましたくなるものではないが、それでも非力で後ろ盾のない家出少女からすれば、露出狂や強姦魔の類よりは幾らか健全で安全で平和的なものだ。そのゾンビが女子であれば尚更。
しかもゾンビ女子は、いうほどゾンビという状態ではなく、肌は生気こそ失われているものの腐り零れているわけでもなく、発音はややおかしくなっているものの、片言の外国人程度の発声と考えたら十分に許容範囲だ。おまけに少女よりも頭半分ほど小さく線も細い、いざとなれば腕力でどうにか出来る体格だ。
それにだ、
「でも、ゾンビですヨ!」
「だから怖くねーって言ってんでしょ。ぶっころすよ」
家出処女は鞄から拳銃を取り出して、ゾンビ女子に向けてみせる。
パッと見は偽物、もしくはモデルガンと思われても仕方ない。一介の家出少女が持つには重たすぎる代物だ。
しかしこの銃は紛れもなく本物であり、撃てば鉛の弾丸が発射されるし、弾丸が当たれば人は死ぬ。引き金を引くだけで簡単に仕事を終えてくれる最低最悪の無慈悲な道具だ。
それが証拠に、少女の母親が懇ろになっていた反社の男、本来の拳銃の持ち主である彼は、自分が拳銃を隠させていた愛人の娘、つまりは家出少女に背後から脊髄を寸断されて大量の血を吐き出して絶命したのだ。
今頃、少女の母親は大慌てだろう。夜職を終えて家に戻れば、秘密裏に隠していた拳銃が無くなり、部屋の中には持ち主の死体がひとつ、おまけに娘は何処へと姿をくらましているのだ。どのみち事件に変わりはないが、外部の犯行なのか、内部の、いわゆる反社会的勢力同士の争いなのか、男の所属していた九頭竜組という名前だけは勇ましい田舎町の小さな組織内の揉め事なのか、それとももっと内部の、少女自身に因る環境への反抗ともいうべき犯行なのか、もはやあの流れに流されるだけの母親に判断できるとは思えない。
事実、母親は流れに身を任せて家を飛び出し、数日後に異臭に気付いた隣人の通報で暴力団員の死体が発見され、現在容疑者として報道されているわけだが、スマホの充電が切れたままの犯人はまだ知る由もない。
「なんでソんなもの持ってルの……!?」
「それを言ったらゾンビがいる方がおかしいでしょーが。拳銃とゾンビだったら、ゾンビの方がウルトラレアじゃん」
「なるホど……?」
「拳銃なんかノーマルよ、ノーマル。レアリティは星ゼロだよ」
それが証拠に少女の持っている拳銃は1丁ではない。死んだ持ち主は重度の拳銃愛好家だったため、数ヶ所に分けてコレクションを隠していて、少女の家に在ったのは東南アジアあたりの与太ったコピー品の自動拳銃と、レンコンを思わせる形の回転式拳銃、さらには過去に使われて本来川や海にでも捨てられるはずだったものまで数丁が100を超える実弾と一緒に隠されていた。
そんなものが家の中にあると考えるとぞっとする話だが、少女からすれば幼い頃から身近に、天井裏に当たり前にあるものだったので、いつか盗み出してやろうと考えていたし、それを実行した日に持ち主がやってきたのは誤算中の誤算ではあったが、目論見通りに盗み出して、今は鞄の中で静かに眠っているのだ。
隠すという点でもコインランドリーは都合がいい。大きな旅行に行くようなサイズの鞄を持っていても、洗濯物を入れているだけで無理が通るし、銃の上に数枚のシャツでも乗せておけばそれだけで道理が引っ込む。
温かい布に覆われた銃たちも、さぞ寝心地がいいことだろう。
「で、ゾンビが何の用?」
「実は……!」
ゾンビ女子は堰を切ったように語り始めた。
世の中にはゾンビ病という奇病があるらしく、つい数日前にゾンビ病に感染してしまったことで、家族も全員ゾンビ化を発症してしまった。ゾンビ化の進行はどうやら若いほど遅く、年老いてるほど早いそうで、彼女の両親は今となっては意思の疎通も図れず、うあぁぁと呻き声を上げて人肉を求める化け物と化したのだとか。
「私が母親の彼氏ぶっころしたり、中学校で虐めてきたやつの家に拳銃撃ち込んだりしてる内に、世の中がそんなことになってたなんて……」
「エ? なんか怖いコト言った?」
「んー? だからー、母親の彼氏ぶっころしてー、せっかく拳銃手に入れたから虐めてきたやつの家に鉛玉撃ち込んでやったり、頭吹っ飛ばしてやったりしてー」
少女が指を折りながら使った弾丸の数を数える。
彼女が使った弾丸は10を超えて、奪った命は5に満たない。それでも積年の恨みつらみや憎しみや悔しさを晴らすには十分で、彼女の小さな狭い世界の中には、もう明確な敵対者はいない。
後々、地獄で再会するかもしれないけれど。
「そういうわけで堅気の人生はドブに捨てちゃったから、どうしようかなーてところ」
「人生はちゃんと生きた方がイいよ! 人生は短いンだかラ!」
「ゾンビがいうと説得力大だね。辻説法して来い、本とか出せ」
もちろん少女にだって未来の展望がまったく無いわけではない。いつまでもこんな生活を送るつもりはない、いずれはどこか知らない土地に生活の拠点を築いて、細々とでも平穏無事に暮らしたい。しかし、それには部屋を自分の意思で借りれる18歳になる必要があり、18歳になるまでにはまだ3年以上ある。
今はまだ生き延びるのに必死なのだ。
拳銃という心強い武器はあるけれど、まともに住める場所はなく、金は銃の持ち主や襲撃した家から盗んだ70万円ほど。とても3年も過ごせるような金額ではなく、ゲームでいうと攻撃力は馬鹿高いけど防御力は紙切れ並みといったところ。
必死になっても生き延びれるかどうかも危うい状態だ。
「ヤクザの事務所でも襲うしかないのかなー」
「だったらサあ、私とラーメン屋ヤろーよ!」
「ラーメン屋ぁ?」
少女は少し上ずった声を出しながら、そういえばラーメンとかしばらく食べてないなー、なんて不意に思い浮かべたりしたのだ。
・ ・ ・ ・ ・ ・
ゾンビ女子には夢があった。
地元でそこそこ人気な家系ラーメンを経営する両親の背中を見て育った彼女は、物心つく時には家系ラーメンの虜になり、当たり前のように将来の夢はラーメン屋さんになった。なにせ初めて喋った言葉がアブラオオメニンニクヤサイマシマシだったとか。ラーメン屋を夢見るのは川の水が海に向かうほど自然な流れだ。
「そーいうワケで、私がラーメンを作ルよ! あなたはホールをお願イね!」
「まあ、あんたゾンビだからね」
ゾンビが注文を取るわけにはいかない。かといって元々のラーメン屋は食券制ではない、注文制だ。単に食券機を導入する余裕がなかったのか、直に注文した方が性に合ってたのかはわからないが、ゾンビ女子にとっては大きな壁として立ち塞がっていた。
それを打破したのが、たまたまコインランドリーで出会った家出少女の存在だ。
なんせ家出の経緯はともかく容姿は普通の女子中学生。おまけにゾンビである自分を怖がらない。共に働くにはこれ以上ないくらいの、いわゆるウルトラレアな人材だ。
おかげで諦めかけた夢への道が繋がった。その道は細い糸のような頼りない道かもしれないが、カンダタの掴んだ蜘蛛の糸のように、掴まずにはいられない細い細い糸だ。これを逃してしまってはまさしく、縦の糸はあばば、横の糸はわわわ。この腐りかけた両手でしっかりと掴め、ゾンビ女子は自らの未来に対して固く決意したのだ。
「で、あんた、ラーメン作れるの?」
ゾンビが作っていいのか、という言葉は一旦飲み込んだ。
少女としても金は要る、このラーメン屋で衣食住を凌ぎながら18歳まで生き延びれるのなら、それは少女にとっては願ってもないことだ。この際ゾンビ云々は目を瞑ろう。悪臭とか保健所とかゾンビの隠蔽とか、まだ見ぬ敵は山ほど立ちはだかるだろうけど。
「見てテよー」
彼女の目の前では、ゾンビ女子がぐらぐらと茹だった寸胴の前で、湯切りザルを片手に握り締めている。ちなみに正式名称はテボというらしい。おそらく覚えておく必要はないだろうから、少女は数分後には忘れてしまうだろう。
ザルの中に麺を入れて、沸騰した湯の中で熱を加える。
熱を帯びたゾンビは、なんていうか酷い臭いを発する。酷いという言葉を適切なものに言い換えるなら、保健所が飛んできそう、そういう実にやばい臭いだ。
「天空! 湯切り落とシ!」
必殺技のように叫びながら、ゾンビ女子がテボを勢いよく振り下ろすと、その勢いで肩関節が外れて、もげた腕がくるくると宙を舞って、厨房の床にボトリと転がり落ちた。
どうやらゾンビは加熱すると脆くなるらしい。学会に発表したら専門家に褒めてもらえる発見かもしれないが、少女は別にゾンビ研究家でもないし、むしろ目立つのは得策ではないと考えているタイプだ。出来ればこそこそと日陰に咲いた苔のように生きていきたい、そう思っているくらいだ。
「失敗失敗……!」
「いや、それ大丈夫なの?」
「大丈夫、ゾンビに痛覚ナいから!」
ゾンビに痛覚はないらしい。ついでに腕がもげても割と大雑把にくっついてしまうらしい。世の中でいらない無駄知識のベストスリーが一瞬で埋まってしまった。
家出少女は乗った船がどうしようもない泥舟だと改めて認識して、はぁーっと長く深い溜め息を吐いた。
空気を吐き出すと、鼻から吸い込む臭いが更に酷くなる。適切な言葉を選ぶなら、ヘドロを煮詰めたような激臭だ。激臭と湯気の中で目を凝らすと、なにをとち狂ったのかゾンビが寸胴で自分の腕を煮込んでいるのだ。
「……おいおい、なにやってんの?」
「豚骨や鶏がらノ代わりになッタら経費削減にナるなーと思っテ」
「いや、駄目でしょ絶対」
ゾンビの骨から出汁を取りゾンビが茹で上げる失われし生命の無限ループ【ゾンビラーメン死んどる軒】
いやいや、1発アウトだろう。家出少女は首をぶんぶんと、それこそゾンビだったら飛んでいきそうな程度には力強く振って、頭の中に浮かんだゴミのようなフレーズを消し去った。
その間も煮込まれ続けたゾンビの腕は、死臭をまた別の種類の悪臭へと変化させて、鼻を突き刺し目を潰すような刺激臭へと進化して、少女を本能的に店の外へと飛び出させた。
店内のガスは更に性質を変えて、周辺住民が慌ただしく外へと出てきて、なんだなんだと集まるほどに悪化して、いつしか可燃性のガスへと変質して、辺り一面広範囲をなにもかも道連れにして爆発したのだった。
少女は人が集まり始めた辺りで危険を察して逃げ出して難を逃れたが、集まった近隣住民はことごとく吹き飛ばされて、空気中に霧散したゾンビ女子の体液をまともに浴びてしまい、そのほとんどがゾンビと化してしまった。
ひとりの少女の夢は破れたものの、人類への悪夢と姿を変えて降り注ぎ、夢も希望もないゾンビパンデミックを引き起こしたのだった。
・ ・ ・ ・ ・ ・
この世で最も安全な場所はホームセンターだ。
コインランドリー? 馬鹿を言ってはいけない、世の中で最も大切なものは武力だ。武力とは即ち武器をどれだけ確保できるかで左右される。
その点、ホームセンターにはありとあらゆる武器に代わるものが揃っている。包丁にハンマーに釘打ち機にチェーンソー、他にも知恵と工夫次第で武器に出来るものは無数にある。防御を固めるためのものはもっと豊富で、園芸コーナーと家具と物置を駆使すれば文字通り要塞だって作れるかもしれない。
それにゾンビと戦うならホームセンターは定番中の定番、王道中の王道。つまりはここで迎え撃てということなのだ。
「……もう将来がどうとか言ってる場合じゃなくなったな」
ホームセンターの周りにはゾンビが大挙している。
人間が群れを作りたがる生き物だということを、家出少女は過去の学生生活から重々承知していたが、ゾンビになるとその性質がより強くなるようで、満員電車のように過密に群れている姿は人間ではありえない。中には満員電車やコンサートとか決してありえなくもないけど、それはそういう必要があるからで、意味もなくホームセンターの駐車場にぎっちぎちになっているのは不気味を超えて馬鹿げている。
「絵力えぐっ……」
などと呑気な感想を抱いてる場合ではなく、1階に築いたバリケードの境目では他の逃げ込んだ人間たちが各々武器を手に、ゾンビの頭を殴ったり突き刺したりしている。ゾンビは動きも鈍くて力も弱いけれど、なにせ簡単に死んでくれないので厄介だ。さらに飛び散った体液は普通の人間にゾンビ病を感染させて、瞬く間にバリケードの内も外もゾンビがわぁわぁぎゃぁぎゃぁがっしゃんがっしゃんと金網や壁を叩き合う無法地帯へと姿を変えた。
人間を撃つのは多少の抵抗があるけれど、不思議とゾンビが相手なら躊躇なく引き金を引ける。
家出少女だったヒヨッコは今や一端のゾンビハンターへと生き方を変えて、ガソリン缶や燃料缶をゾンビの群れへと投げ込んで、そこに銃弾を撃ち込んで爆発させる。
爆発オチなんて最低だ。でも爆発でもさせなければ、この混沌とした状況を脱することなどできないのだ。
少女、いや、ゾンビハンターはたまたま駐車場に放置されていたタンクローリーに弾丸を撃ち込んで、ゾンビも夢も希望も平穏な生活も馬鹿げた現実も、なにもかもを駐車場もろとも吹き飛ばしたのだった。
(おしまい、爆発オチなんてサイテー)
腐腐腐腐腐腐腐腐腐腐腐
勢いだけで書きました。
ゾンビものです、皆様ゾンビは好きですか? 私はゾンビ映画大好きです。サメ映画の次くらいに好きです。
嘘です、そこまでではないです。
ちなみに好きなゾンビ映画は、ロンドンゾンビ紀行です。
