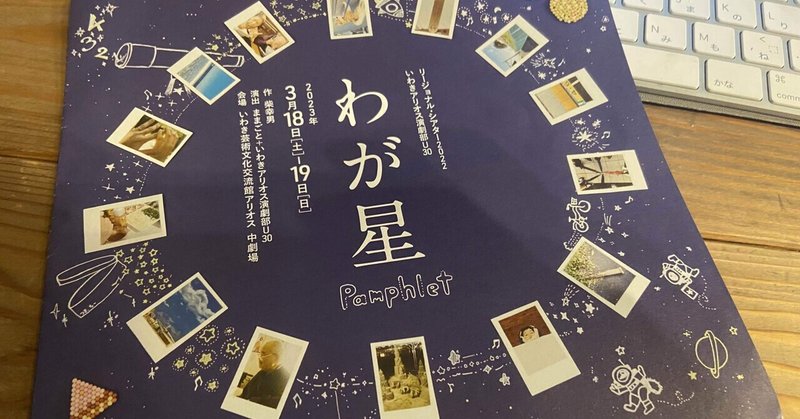
「わが星」いわきアリオス演劇部
23/3/19@いわき芸術文化交流館アリオス
ある少女と星の一生を時報のラップに乗せた物語を
公募で集まった若者らとままごとの柴幸男さん、端田新名さんらでリメイクした今作。
普遍性をもって描かれた一生は、自身の人生と合わせて想像するからこそ面白みがある。
ある種、芸術作品としてでなく、お披露目会のように演じられる形式により
創作の過程と参加者一人一人の人物と人生を想像する大きな余白が生まれる。
それは、ままごとが試みる「ままごと」のような気軽さと豊かさを含んだ演劇の一つの形である。
わが星を観るのは4種類目になる。
自らの公演で、オープニングだけを演出したこともある。(劇中劇として出てくるが、大量の本筋部分の仕事によりほとんど演出はできなかった)
現代演劇を知る人ならば、誰もが通る有名作。多くの人が本家やリメイク(他劇団や学生劇団がリメイクしたもの)、Youtubeなどで1度は観たことがあるのではないだろうか。
初演は2009年というから、14年が経ったことになる。当時を知る人から聞いた話では、普及し始めたSNSで口コミが広がり、劇場には長い列ができたという。劇場へ集まる人たちのワクワク感は相当なものだったろうと想像する度に、演劇の可能性を今もなお感じさせてくれる。ぼくにとってはそんな作品である。
ほぼ全編をラップに乗せたその手法は唯一無二であり、岸田國士戯曲賞を受賞した当時には、相当の衝撃だったのだろう。劇団のホームページで戯曲が公開されており、Youtubeにはオープニング部分の音声が上げられている。そのような試みで多くのリメイクがなされ、再演も多く、今もなお広がりつづける作品と言える。
ぼくが観たのは、本家である「ままごと」の初演版のDVDと再演版のYouTubeの二つ。あと京都の学生演劇でのリメイクが二つ。の計四つになる。
今はもう観劇することが叶わない京都大吉田寮での初観劇は相当な衝撃で、寮の雰囲気と相まって、今もなお空気感が肌に残っている。
このように演劇好きには、それぞれのわが星があるだろう。きっと公募で集まった参加者たちにも、それぞれのわが星がある。
中でも本作は、どのわが星よりも自由で、想像に駆られるものだったと感じた。
現在は(期間限定で?)ままごとの再演2015年VerがYoutubeで無料公開されている。
何度観ても、時報のラップと曲を口ずさんでしまう。
未見のかたは、ぜひ!
公演は、いわき市にあるいわきアリオスの創造事業の一環として行われた。
近年は特に地方劇場で、有名な劇作家や演出家が演出を務め、公募で集まった地元住民が演じるという、地域ならではの公演事業のようなものが多く取り入れられている。知るところだけでも、PLAT(豊橋市)や三重総合文化会館(津市)の例が挙げられる。
ただアリオスが他と異なる点は、市外県外からも多くの役者が集うことだろう。それほどにアリオスの名前が知られていて、講師のネームバリューや事業自体の魅力があるのだろうと感じさせる。
舞台は、向かい合った客席を挟んだ広い空間が用いられる。お決まりの大きな円の白い布が舞台中央を占め、周囲にはハコ馬やお菓子、水の入ったペットボトル、楽器などその他多くの小道具が散りばめられている。客席から見える袖の方には、片方にグランドピアノや楽器類が置かれた演奏スペースと、もう片方に、ちゃぶ台とホワイトボードが置かれた会議場のようなスペース。ホワイトボードには上演に向けた、段取りや準備の様子が書かれている。
役者は開場中から舞台上で自由に過ごしている。ある者は一人で座って、ある者はお菓子を食べる。役者同士で話して、客席を指さしている者もいる。
上演は自然な流れでチェックインのようなものから始まる。ファシリテーション(場作り)の形式で取り入れられるチェックインだが、場に参加する儀式のようなもの。あいさつと名前、上演への今の気持ちを一人ずつ役者が話していく。話し終えると、次の役者を指名して回していく。「今日は友人が来ていて緊張します」「朝からこんなことをしました」「最後のステージなので頑張りたい」など。役ではなく、参加者自身として語っていく。全員が終えてから、ワークショップへと移る。演劇のワークショップとして多く取り入れられる、言葉のキャッチボールのようなものと、全員で手拍子を合わせるもの。お決まりの前節があり、本編へと入る。
その後、柴さんによる短い説明がある。オーディションで集まった参加者が計1ヶ月間、アリオスに通って本作が作られたこと。戯曲をもとに、参加者がそれぞれの「やりたみ」(言いたいセリフ、演じたい場面、演出など)を尊重してシーンごとに参加者たちが創作したこと。すなわち、本作には主役も脇役も演出も、そのいずれもが独立しているのでなく、共存している。全員が主役であり、創作者ということなのだと。
本編が始まると舞台には、シーンを演じる役者と、その周りで見守る人とに分かれる。役者も必ずしも一人一役でなく、二人が一役を合わせて演じることもあれば、三人が替わるがわる演じることも。これが「やりたみ」を尊重した結果なのか否か、その経緯に興味を持った。大きな余白を持ったままシーンは進みその自由な芝居で、次はどんな演出が来るのかと想像して観られる面白さを感じた。
さらには多くのシーンで、読み手と演じ手が異なることも面白かった。一人の役を演じるシーンであっても、二人の演技が重なることで、二人分の人生が感じられる。その二人の関係性さえも想像させる。その輪が広がった時、演劇部として集まった集団としての関係性や物語も感じさせられるのは、ズルイやり口でもある。膨大なラップ量とセリフを挟むタイミング故に相当な技量を求められる戯曲だが、この手法でそのハードルを大きく下げられるのかもしれない。中には台本を持ったまま、演じる参加者も少なくなかった。
加えて周囲で見守る参加者は、それぞれが本当に自由に過ごしている。シーンの効果音やBGMを演奏したり、ガヤを入れたり、アポロなどのお菓子を食べたり。なんなら客よりも自由に過ごしていて、羨ましい。チケットを買って観客席にいる自分の方が窮屈さを感じている状況に「おいちょっと」とツッコミを入れたくもなる笑 時折、袋を開ける音などが気になることはあったが、それも含めて生きることを見ているような気がした。水を飲みお菓子を食べ、他の参加者と交流し、出番が来れば中央の円へ向かう。戯曲も相まって人が生きる上で必要なことが、我慢なく舞台上で行われている。そんな演出にも観て取れる。(観ようと思えば)流石に寝ている者はいなかった。
気がつけば後半の半分くらいは、周りの見守る人たちを見てしまっていた。そこには、それぞれの過ごし方があるように、それぞれの眼差しがあった。声をあげて笑っている人もいれば、そっと微笑む人もいる。愛おしい眼差しもあれば、役者特有の少しの嫉妬を感じさせる眼差しもある。全員が中央の円に目を向け、わが星を見ている。それは役としてでなく、参加者として。その人自身が眼差しに映し出されていた。
印象に残ったシーンは二つ。
終盤に私と姉が話して回顧するシーンだが、小中高と長い時間をともに過ごした二人が演じていた。
「あなたたち本当に仲がいいね」
シーンが始まって途中、見守っていた他の参加者が二人に話しかける。
もちろん戯曲にそのようなセリフはなく、本当に稽古場の休憩時間の一幕のような
そこで二人の関係性が少し語られる。その後の二人のシーンは二人の関係性を持って見られる。
もう一つは、終盤の男が私と出会うシーン。本家では自転車で登場し、一人でラップを重ねるシーンだったように覚えている。ここで用いられたのは、見守る人たちによる効果音。夏、リュックを背負って一人旅に出た男は、円の中で女性二人が演じる。その周囲から、鳥の鳴き声や電車の音、風の音、あらゆる夏の音が重なり、ラップを盛り上げる。音の結晶と勢いのあるラップが美しく見えた。
わが星は、役者個人のパーソナルを全面に押し出せる作品なのだと驚いた。
私、姉、母、父、祖母と戯曲上の表記が示すように、役自体のパーソナル(人物像)といったものは極めて少なく描かれる。わが星を好まないという友人は「人物が描かれていない」と批判した。その指摘は間違いではない。
だが、わが星はその普遍性を意図的に作られている可能性もあるように思えた。
人は物語を、登場人物の心情や状況に共有できる部分を感じて、心動かされるものだと思う。多くの人が、意図的でなくとも無意識にそのように物語を読んで、見て、時に感動する。
特異なパーソナルを削り、一般的な少女とその家族が繰り出す、一般的な日常と会話をラップや曲で歌ったわが星という物語は、ほとんどの人に共感できる部分があるはずだ。言わば、平成の日本家族の原風景があるとも言える。だからこそ、多くのリメイクもされる所以だろう。
これまでに観てきたわが星は、役者自身のパーソナルを削ぎ落として(全てではない)演じられるものが多かった。本家のイメージもあるが芸術として、昇華するためには一定その必要性もあるように感じていた。
だが本作は異なった。ワークショップ的なシーンごとの創作や、複数人での芝居、演じる人と見守る人、さらにはシーン外でパーソナルを強化する会話が取り入れられるなど、役者としてでなく、参加者自身のパーソナルが強く押し出された。さらには演劇部として集まり、創作を重ねてきた個別の関係性も遡上される。
それらの試みは、功をそうしたと言える。歌やラップが好きな参加者がその役を持ち、苦手な者は辿々しく時に台本を持ったままなど、何かしらで補って舞台に立つ。 長い付き合いの二人が、作品中で姉妹の関係を重ねてシーンを演じる。物語の奥に、参加者の物語があって、二重にも三重にも重なって観える。
芸術作品とは言い難いだろう。有名劇団がこの手法を用いた時、観客は物足りなさや疑問を感じるかもしれない。市民演劇部だからこそ許され、魅力を増す手法である。シーンごとにゆるく演じられる形式や、客席と舞台の間に存在する見守る人たちの存在、市民演劇部として培ったであろう時間が、それらを許し、さらに魅力的なものにしていたことは、間違い無い。どうしてもあの空気感は、言葉では表現が仕切れず、もどかしい。ましてや楽ステのエモさ五割り増し。あの時間はそういうものだったのだと振り返る。元来、演劇とは、その時その場所でしか味わえない特別な空気感であるはずなのだから、それで良い。
そこにこそ、わが星の魅力があるのかもしれないと感じた。
最後に少し、書き残しておこうと思う。
上演期間を同じくして、2022年の岸田國士戯曲賞の受賞作が発表された。戯曲も公開されていて、選ばれた2作を読んだ。
率直に、個人的に面白いと思わなかった。
わが星が受賞した2014年から、これほどに全国でリメイクが試みられた作品は他にない。好き嫌いはあれど、それほどの本であることは間違いがない。
今回確認した、それぞれのパーソナルを持ち込んで更なるリメイクができる可能性というのは、再現を目指すのでなく作り直す面白さを発揮できるという、演劇そのものの大きな強みであり魅力なのである。これが意図的に行われたものであるならば、わが星は平成の演劇の教科書ともなる存在だと思い直さなければならないとさえ、思う。いやすでに存在はそのような評価を受けるものだろう。このような再演性を持った、令和のわが星はどのようなものになるのか。果たしてそのような戯曲は書かれるのだろうか。大きな夢を失った、今の日本には難しいのかもしれないとも思える。
ただ、そこに挑みたいという野望を持ったことも、そっと書き記しておこうと思う。
https://iwaki-alios.jp/cd/app/?C=blog&H=default&D=02450
いわきアリオス演劇部の活動は、稽古場日誌としてこちらで紹介されています。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
