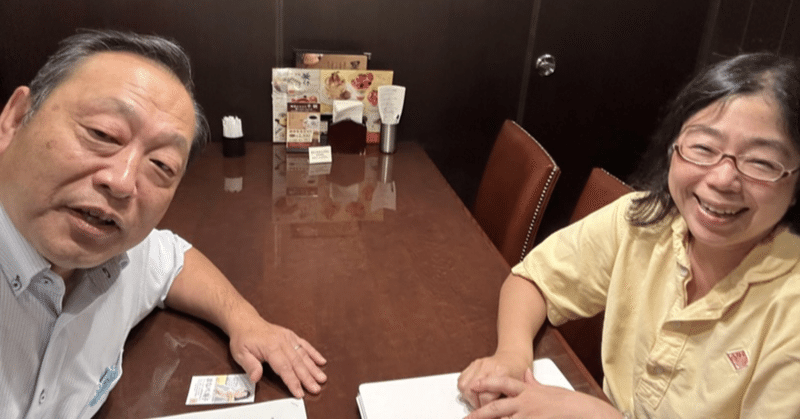
ディスレクシア、読み書き困難、計算障害について
さいとう 武次郎 倉敷市議会議員が、
多層指導モデルMIMについて知りたいと
笠岡まで来てくださいました。
さいとう議員もご存知の、つくば市における最先端の取り組み(※)や、不登校支援や発達障害の子どもたちの現状についてなど、ガチで情報交換した2時間弱。
私もとても学ばせていただきました。
ありがとうございました。
10月に出版される
「発達障害児者の”働く”を支える」
保護者•専門家によるライフ•キャリア支援
監修 松為信雄 編者 宇野京子
出版社 クリエイツかもがわ
についても紹介させていただきました。

まさに今、困っている子どもたちのために何ができるのか。社会全体として問われています。
私は小学生の時、クラスで音読をあてられた子が辿々しくしか読めないのをなんでかな?と、ずっと不思議に思っていました。
おしゃべりも普通にしてるし、休憩時間に接している時は困難さなどみじんも感じないのに、音読であてられた時は、どうして?と。
それが、我が子の読みにくさ、書きにくさ、うまく読めない書けないと頭をぶつけるほどの葛藤に出会い、様々に調べ、学び、行動していく中でディスレクシア、読み書きの困難さ、そして計算障害というものに出会いました。
それから、小学生の時に不思議に思っていたあの子たちは、実はその可能性があったのではないか?と、その時に気づいたんです。
そこで次に不思議に思ったのは
「小学生の私が不思議に思っていたことを、大人である先生方がなぜ気づかなかったの?」
「今、お話していても、先生方にはディスレクシア、読み書きの困難さ、計算障害についてほとんど浸透していない。これはなぜ?」
「私が小学生の時から数えると40年は経っているのだけど、これまで見過ごされてきた子どもたちはその後、どんな人生を送ってきているの?」
「ディスレクシア、読み書き困難さ、計算障害の子どもたちが適切な支援や指導を受けていたら、大人になった時、自分なりに働ける人たちはもっと増えるんじゃないの?」
ずっと放置され続けているこの問題は、本来なら国が真剣に取り組み、国全体でつくば市レベルの取り組みを行うべきだと私は考えています。
ですがそれが全く望めないなら、それぞれの自治体単位で、それぞれの実態の中でできることから取り組み始めていくしかないじゃないですか。
私は、ディスレクシア、読み書き障害、計算障害について知り、そして議員になった今、これ以上この問題について見過ごすことはできないと考え、少しずつでもできることからと取り組んでいます。
※ 内閣府がまとめた「平成25年版障害者白書」の中の「児童生徒の困難の状況」では「知的発達に遅れはないものの学習面で著しい困難を示す児童生徒の割合」は4.5%という調査結果があり、日本におけるディスレクシア(読み書き障害)の発現率の割合として一番近いものと考えられているが、元筑波大教授でNPO法人LDディスクレシアセンター理事長である宇野彰氏の調査によれば、小学生では8%存在すると言われている。
ディスレクシアに対して先進的な支援をされている代表的な自治体、つくば市では、公立の小学1年生と中学3年生全員を対象に読み書きを確認する検査が行われている。まず就学時健康診断において、ひらがな10文字音読検査を行い、その結果では約2割の児童に読み書き困難のリスクがあったとのこと。その内の9割の児童は9月ごろには読み書きの力が追いつくが、1割の児童は読み書きのリスクを抱えたままでいることが確認されており、そのため9月以降、全体の児童にさらに詳細な集団式検査を実施、個別対応が必要な児童を把握、集団式検査で心配がある1年生については、ひらがな及びカタカナの習得状況が確認できる2年生以降に個別検査が行われている。
#ディスレクシア
#読み書き困難
#計算障害
#多層指導モデルMIM
#笠岡市議会議員
#真鍋陽子
#まなべ陽子
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
