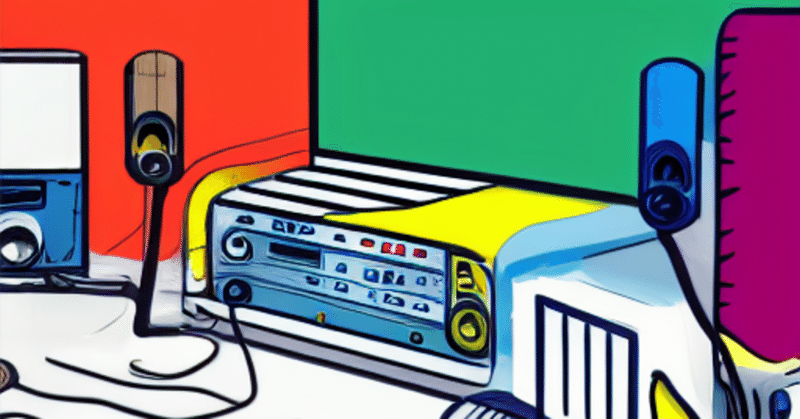
【ソニックブランディング】UI/UX: ジェスチャー機能のサウンドデザイン
僕のキャリアにおいての一つの契機が、GAC Motorのソニックブランディングをしたこと。
EVのAVAS(電気自動車やハイブリッド車の低速走行時、歩行者に車両の接近を知らせるサウンド)を含む、GAC Motorの全車種の49音のサウンドデザインをした。
車のサウンドデザインは、いわばインフラと同じ類で、普通のサウンドデザインとは違ったアプローチをしなければならなかった。
例えば、
高周波数が聞きづらい高齢者の方は聞こえるのか?
ウィンカーサウンドによって、ドライバーを急かせていないか?
EVのアクセルサウンドは、ドライバーのスピードアップの助長をしていないか?
など、人間の生死に関わるサウンドデザインなので、とても慎重かつ理論的に行なった。
その制作の中で著書「音のチカラ by 岩宮眞一郎」はとてもお世話になった。その本の中の一つのトピックを紹介しつつ、僕の経験と照らしわせて、UI/UXのサウンドデザインについて書きたいと思う。
ピッチと空間とエネルギー
「上」「下」と「高」「低」という感覚表現は、ピッチについて表現(上のパート、高い音など)も出来るが、空間の表現(上の階に、低い山)もできる。この両者の感覚表現は聴覚と空間での表現なので、関連性はない。にも関わらず、人間は、ピッチの高低感覚と空間の垂直方向の感覚に関連性を持ってしまう。
同様に、エネルギー可変の感覚表現も関連性を持って知覚している。自動車の加速時のエンジンの回転速度(エネルギー)とエンジン音の上昇(ピッチ上昇)はマッチする。充電チャージする時も同様である。
まとめると、ピッチと空間とエネルギーの感覚表現は、人間は本能的に関連して知覚してしまう。
SMARC (spacial-musical association of response codes)
物体が上昇する映像とピッチが上昇するメロディーパターンの組み合わせは、自然な調和感が得られる。物体が下降する映像とピッチが下降するメロディーパターンの組み合わせは、自然な調和感が得られる。
逆に、物体が上昇する映像にピッチが下降するメロディーパターンを組み合わせると違和感が生じる。
このような視覚と聴覚の結びつきを、「SMARC (spacial-musical association of response codes)」と呼ばれている。
SMARC効果は、UI/UXの人間の反応速度に使われたりする。ピッチの高い音に上側、低い方に下側のキーを割り当てた方が、上下逆転させたキーで回答させた場合より、反応時間が短くなることがわかっている。
当たり前のように思えるかも知れないが、このような研究結果を知った上で、UI/UXサウンドデザインをすると制作の強度がまし、ましてや車などの生死を伴うサービスのサウンドデザインをするときは、この知識は大きな武器となる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
