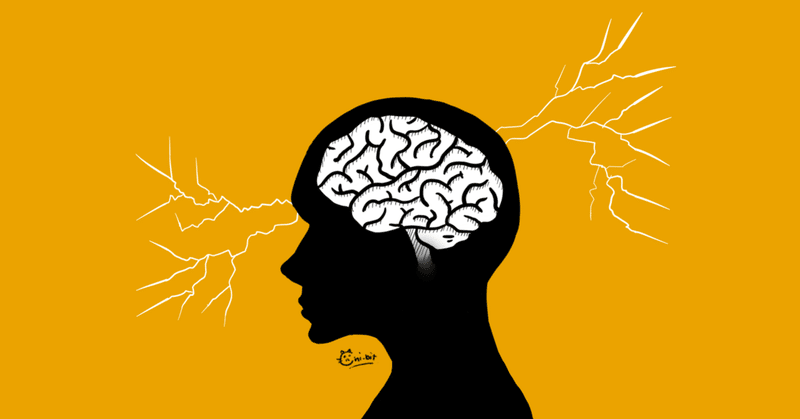
あたりまえを疑ってみた。
当たり前のことは当たり前にやりなさい。
人生で何回かは耳にする言葉だ。母親に言われたか、学校の先生に言われたか、それとも頭の固い会社の上司かもしれない。僕も高校の先生に、当たり前のことを一生懸命にやれと言われたことがある。
僕ら日本人は「当たり前」という言葉をよく使う。そんなのあたりまえじゃないか。ほら、今まさに使った。世間には当たり前体操や当たり前ポエムなどもある。
では「当たり前」とはどんな意味か?
よく使う言葉なのに意味を知らない人はいないだろう。しかし、一応知らない人のために、当たり前には2つの意味がある。
⑴道理上、そうあるべきこと。当然。
⑵特に変わったことがないこと。普通。
すなはち、誰にでも当てはまる、言うに値しない普通のことだ。
遅刻をしない。
日本語で会話する。
学校に行く。
歩く。
食べる。
考える。
いくつか例えを挙げたが、これらは誰もが知っていることであり、そのことについてあれこれ考えるだけ時間の無駄である。
しかし、僕はそれをあえて疑ってみた。本当に誰しもが当てはまることなのだろうか。なぜ当たり前なのだろうか。僕の出した結論から言えば、
当たり前のことなんて一つもない。
まず、当たり前という言葉を他の言語と比較してみる。僕が勉強しているドイツ語で、「そんなの当たり前だよ。」とドイツ人の友達に伝えたいとき、少し悩んでしまう。日本人の当たり前は彼らの当たり前ではないからだ。
ドイツ語には「当たり前」の意味を表す単語がいくつかあるが、その一つにselbstverständlichという単語がある。これはselbst(自分自身)とverständlich(理解できる)が組み合わさった言葉だ。ドイツ語では
自分自身で理解できること=当たり前のことなのである。
しかし、僕ら日本人の多くが当たり前の本質を理解できていない。
例えば、学校に行くのは当たり前だ。しかし、なぜ学校に行くのかを教わった人はいるだろうか。それか学校に行く意味を考えたことはあるか。
今ここでなぜ学校に行くのか考えてみよう。そして自分の考えを他の人と共有してほしい。
僕の答えは、「人生を通してやりたいことを見つけるため」だ。
同じような考えを持った人もいれば、全く違う考えを持った人もいるだろう。当たり前のことでも人それぞれ異なる理解の仕方があるのだ。それなのに当たり前という言葉で一括りにして、その本質について考える機会を失っているのではないか。この事実に気づいたとき、僕は今まで当たり前に思っていたことを疑い始めた。
なぜ右に倣わければならないのか。
なぜ赤信号では渡ってはいけないのか。
なぜ肉を食べるのか。
大小さまざまなことにも疑問を持つことで、その物事について自分なりに考え、理解できるようになった。だからこそ、誰にでも当てはまることなど一つもないと僕は思う。もっと正確に言うのであれば、みんなそれぞれの当たり前を持っているのだ。しかし、日本の教育ではこの当たり前のことを考える習慣がない。僕らはただ右に習い、集団の和を乱さないように教えられてきた。何か新しいことを知るときに、自分で一度考えるという過程が抜け落ちてしまっているのだ。
僕がドイツで出会った一人の日本人サッカーコーチは、子供たちが考える機会を積極的に与えている。例えば、練習の準備をしないでさぼっている子供たちがいると、ただ怒るのではなく質問を投げかける。
「なんで君たちは準備をしないの?それでいいの?」
そうすると子供たちは、
「みんなで練習するから、僕たちも準備するべきです。」
と答え一緒に準備をするのだ。
日本では当たり前のことは当たり前にやりなさいと言われ、しないと怒られる。その結果、子供たちはしなければならないこととして覚え、準備をするようになる。それに比べて彼の指導を受ける子供たちは、準備をする本質を自分で考え理解した上で、練習の準備をする。結果は同じでも、当たり前としてそのまま受けとるのと、なぜそうなのかを自分で考え、行動するのでは思考の過程が大きく違うのだ。
ここまで、当たり前を疑ってきたが、
そもそも当たり前のことなんて考えなくていいじゃんか。
と思う人が大半だろう。なぜ学校に行くかについて考えるより、今日の晩御飯を考える方がよっぽど有意義かもしれない。しかし、この場で当たり前について考えた経験が、人生の大切な決断や、何かを学ぶときに自分で考えるきっかけになってほしい。さて、次はなにを疑おうか。
押していただいたスキは文章を書くモチベーションに寄付させていただきます。 このご縁がきっと良縁となりますように。
