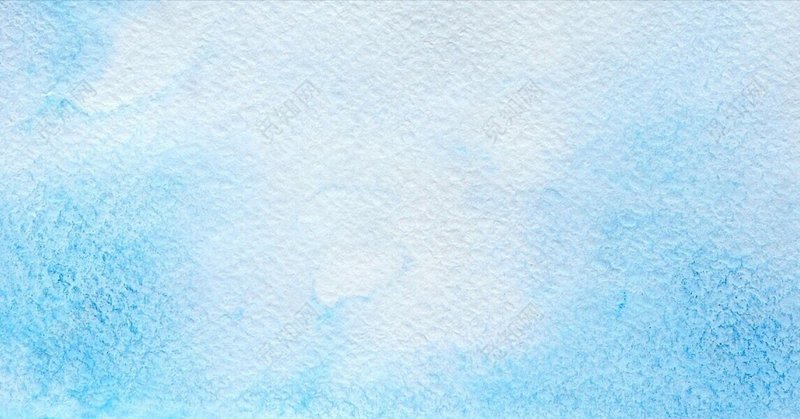
21日間の21の間——「インディゴの気分」視覚テキスト分析(第四の間と第五の間)
作者 Maomono
翻訳 sekiisekii
第四の間 木島宅での最初の夜(1)
「第四の間」も「第五の間」はともに、第一話の最後の5分間の長回しを巡って分析しようとする。「第四の間」はシーンにおける長回しの役割に焦点を当て、「第五の間」は登場人物の心理分析に留める。
インタービューでは、監督も俳優も、第一話にある重要な長回しについて何度も言及している。それは城戸がシャワーを終えて服を着て(第一話15分34秒)から、食卓に座る(20分27秒)まで、約5分間も続く。『カイエ・デュ・シネマ(Les Cahiers du Cinéma)』誌の創刊者アンドレ・バザンは長回しだけが時空の連続性を提供し、リアリティをもっとも現実的に表現できると考える。実際の撮影では、長回しは最も精密な計算を必要とし、制作チームの管理能力が大いに試される。簡単に言えば、長回しはカットを入れず、撮影を途切れさせずにカメラを回し続ける撮影方法で、10秒以上続くカットだ。2019年アカデミー賞最優秀映画候補作品「1917 命をかけた伝令」は長回しで大きな話題になった。近年、映画業界の長回しブームが多少下火になってきたが、長回しを完璧に撮ることは依然として監督と撮影チームの能力の象徴で、成功するためには数回のリハーサルと制作グループの精密な協力が必要だ。最良の効果を得るまで、数々の調整や退屈な待ち時間、何度もの失敗を経験しなければならない。というのは、特定の美学的スタイルを追求しなければ、または映画の品質を大幅に向上させるためではなければ、制作グループは長回しに挑戦する必要がない。こういう理由で、率直に言うと、BL漫画のドラマ化に対して期待がそれほど高くない私は、「インディゴの気分」の5分間もある長回しを非常に嬉しく見て、制作グループの職人技に感心した。配信ドラマや深夜ドラマにして、「インディゴの気分」の制作グループは何度もの視聴に耐える精緻なドラマを作り上げ、よく頑張った。
三木監督はインタビューで、「インディゴの気分」では意図的に多くの長回しを使用したと話した。それに対して、「ポルノグラファー」では長回しが比較的少ない。なぜそうなったのであろうか。それが主人公の関係性による違いのである。「ポルノグラファー」では久住は謎の手がかりを握る人物であり、彼は視聴者が同じ立場にたって木島の交流を通じて、木島を少しずつ理解するようになる。そのため、「ポルノグラファー」では、木島に多くのクローズアップされ、表情、手の動き、さまざまな仕草が見せられる。一方、「インディゴの気分」では、城戸と木島は対等な地位におり、二人のやりとりがドラマを理解する上で重要な要素となる。そのため、二人の状態変化を連続的に表現するための長回しが非常に理想的である。もちろん、それはドラマでよくみられる肩越しショットでも表現できるが、三木監督は感情や情熱を一気に表現することに非常に高い要求を持っている。
俳優から考えてもそうだ。城戸を演じる吉田は舞台出身の俳優で、当時、木島を演じた竹財もちょうど舞台劇「あいあい傘」の出演を終えたばかりだ。長回しには通常のドラマ撮影よりも高い集中力が必要だが、舞台劇の俳優はちょうど、そこに長所がある。準備段階で三木は、役者自身の特徴を考慮して、長回しの回数を増やした可能性もある。複数の登場人物が絡む長回しでは、視点の切り替えを反映させるためにピントの切り替えが多用されるが、ピントに合わせられてない役者は気が緩むことができなく、つまり長回しではピントによって際立たせられなくても、演技は続けなければならない。
一方、視聴者からすると、長回しはある種の見る自由を与えられる。視聴者の見る順番が決まったキャラクターの視点から順番に撮影される肩越しショットという撮り方とは異なり、長回しはピントの位置が変わるが、視聴者はピント外の登場人物の演技をも楽しめる。これによって、視聴者は視点を移動する自由を得る。「インディゴの気分」では、城戸と木島のやりとりは長回しで表現することが多い。観察する役者が自由に選べるため、視聴者はどちらかの立場に立ったり、或いは単に中立的に見たりする選択肢を持ち、二人の関係に対する視聴者の解釈の多様化を促進し、鑑賞する興味がそそられる。ここで指摘したいのは、長回しはBL作品の視聴者としての女性の流動している視点と相性がいい点だ。BLの主人公が両方とも男性で、女性自身に関わりがないからこそ、攻めか受けとして想像して、またどちらも想像しなくてもいいから、女性視聴者は主人公の関係の理解と解釈の自由が与えられる。
技術的な説明はここまでにして、この長回しを詳しく分析しよう。考え方は人それぞれ違うが、私はこのシーンは木島と城戸の立場が逆転したことを提示すると思う。第一話の前半では、二人の主人公の関係は元同級生であったが、城戸が木島宅に来てからは、大家さんと下宿人の関係になった。さらに、今度の長回しで作家と編集者という重要な仕事上の関係が現れてくる。周知のように、いかなる関係にも、主導者がいて、または優位を占める人がいる。では、二人の間、主導者は誰だろうか。
このシーンはまず木島の現状を説明する。「春潮」の編集者との不仲、1年以上の休載、経済的な困難。次に、リビングからやってきた城戸が座って、憧れの木島に仕事の依頼をする。ウイスキーを飲みながらデカダンな生活を送っている木島は、官能小説を書くという提案と聞いて、作家としての傲慢さが一瞬にして爆発し、立ち上がって戸棚にウイスキーを取りに行き、官能小説なんて道具に過ぎないと宣言する。この攻防の第一ラウンドでは、「座」っている城戸に対して、木島は「立」ち上がり、ウイスキーを「取」ってから「座」る。すなわち、優位にいるのは木島である。(立つことと取ることが両方、優位な立場に立つ象徴である。)
城戸は木島についてリビングに入って、攻防は対峙の段階に入る。木島は挑発をするが、城戸は冷静さを失わず、素早く戦略を切り替える。彼は冷蔵庫を開けてビールを「取」り出し(この行為は主導権を握ったと見なすことができる)、攻めをはじめる。
あまりにも長いため、また次の間で。
第五の間 木島宅での最初の夜(2)
前回に続く。
ビールをとってから、城戸は心理上の攻めに突入する。まず、木島をなだめ、そして彼の生活難を鋭く指摘する。木島の心理的防衛は破られ、たちまち敗北する。自己実現から生活難の解決まで、いくら考えても城戸の申し出を受け入れることが唯一の選択肢だ。彼は選択の余地がないことを知り、「座」ってスクリーンを出る。城戸だけが「立」っていて、勝利者の笑みを浮かべる。長回しはここで終わる。
次のシーンで、城戸は木島にウィスキーを「注」いで手渡すが、これは仕事関係における編集者の絶対的優位を象徴している。二人の動作は次のようにまとめる。城戸が正「座」してアドバイスをし、木島が「立」ち上がってウィスキーを取りに行く。二人が対峙する。木島が挑発し、城戸が我慢する。城戸がビールを「取」りに行って説得を始める。木島が「座」り、城戸だけがスクリーンに残る。長回しで映し出される状況の変化の間に、この心理の攻防における二人の地位と主導権の転換を感じ取ることができる。長回しでなければ、視聴者が登場人物の動きの連続的な変化に気づくことは困難である。一連の変化こそ登場人物の関係を素早く定義するのに役立っている。
次に、この長回しにあるいくつの「間」を見てみよう。
木島は才能ある作家の尊厳を守るために「官能小説の道具論」を投げだした後、城戸の顔に向かって空気を吹きかけ、城戸の提案と彼が取り組んでいる分野を軽蔑している気持ちを表す。城戸は17秒をかけて怒りを抑え、素早く感情を整え、編集者としての説得力を発揮する。その説得術とは何であろう。
まず、木島の言うことに筋が通っていることを認める(作家の自尊心を保ってあげる)。次は木島の才能に憧れ、彼の忠実な読者であることをアピールする(木島の信用を得る)。そして、彼がその才能を無駄にせず、本を書き続けることを願う(自分の提案は木島自身のためであることを示す)。ここになると、ピント外にいる木島の表情は生意気から和らいでいるが、まだ抵抗があるため戸惑っているように見える。さらに、木島の致命的な現実状態、つまり金が要ることをはっきり指摘する(この仕事こそ収入をもたらすというある意味での脅し)。城戸はさすが現実的である。彼は知っている。確かに作家はプライドが高いが、お金がなければ生きていけない。最後の一撃は木島に借金返却督促状を見せる(借金だらけで、このままでは命が危ない)ことだ。この部分で特筆すべきは、督促状を握る吉田の手である。非常に演出的で、個人的には、この部分が非常に味わい深い形でドラマを盛り上げていると思う。
城戸の最後の一撃で木島はすぐに現実の世界に引き戻され、とっくに選択肢がないこと、先ほどの高慢な発言は見せかけにすぎないことにすぐに気づく。今になると彼は何も所持してせず、仕事を断れないどころか、引き受ける必要性と緊急性がある。そこで長回しのピントは城戸の説得に伴い、木島の顔に合わせるようになる。8秒間の沈黙の後、木島の心理的防衛は完全に崩壊し、今後どうすればいいかわからないと二度も告げる。ピントの変化で、木島の顔はぼやけたものからはっきりとしたものになる。それは木島の未来が徐々に明瞭になっていき、彼がついに官能小説家になるという自らの運命に向かうことも示唆している。
ここまでの第一話はわずか23分だが、木島と城戸の説明しづらい関係を、元同級生、同居人、創作共同体という三段階に分けて展示している。元同級生の関係においては、木島は10代で有名になった天才作家で、城戸は就職が決まらずバイトの出版社に入った官能小説の編集者だ。同居人の関係では、木島は家の持ち主で、城戸は借り主である。創作共同体の関係では、木島は売れない作家で、城戸は唯一の仕事の提供者である。このうち最初の2つの関係では、木島が絶対的な優位に立つが、3つ目の関係では、城戸が優位に立ち、木島の恩人となる。物語が進むにつれて、二人は友情(第二話)、愛情(第三話)を育んでいくが、のちほど、長回しはこれらの関係を展示するのにも大きな役割を果たす。
木島は城戸に利用されたか、そうだったらいつから利用が始めたか、また、「ぐちゃぐちゃにしてやりたくなった」というセリフは城戸の「悪意」を表すかというような議論を時々耳にしていた。私見だが、提案をする当時の城戸は木島を助けようとすると同時に、ビジネスの面の配慮もある。木島がその提案を受け入れたら、ウィンウィンになるはずだ。しかし、木島が純文学作家としてのプライドを捨てきれず、城戸はその傲慢な態度に腹を立てる。その際のセリフはもちろん、多少悪意を感じさせる。この気持ちがあるこそ、城戸はプロの説得術を駆使して木島に素早く納得させ、勝負を決める。「第二の間」で書いたように、城戸と木島はまさに対等的な関係にあり、大人のゲームの勝負におけるあれやこれやの迫力こそみどころである。この強い関係性を、三木監督は長回しで勝負のすべてを表現したが、これが極めて適切である。地位の移り変わり、感情の流れ、表情の変化が一目瞭然で、視聴者を魅了させる。
では、また次の間で
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
