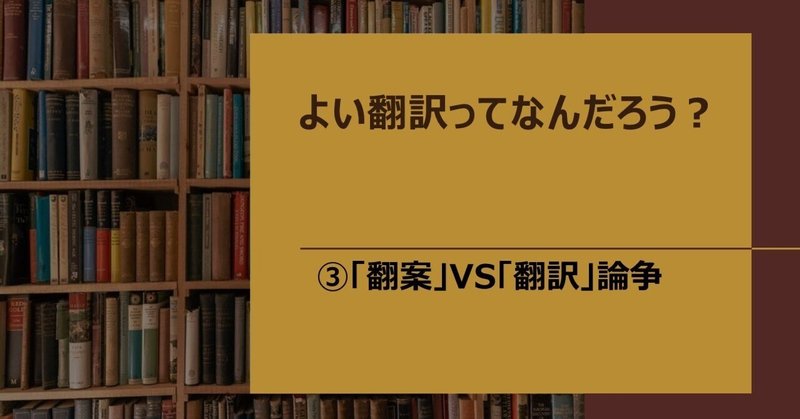
【第三回】「翻案」VS「翻訳」論争
前回、青年誌『新青年』が「シャーロック・ホームズ」シリーズの邦訳史において重要、と前出ししました。
ミステリファンなら、『新青年』を知っている人も多いかもしれません。この雑誌は江戸川乱歩や横溝正史を発掘し、日本の探偵小説ブームを創出した雑誌なんです。
『新青年』が創刊されたのは大正9年(1920年)、第一次世界大戦後のことでした。探偵小説専門誌ではなく、戦後の「新しい青年」たちへ時事情報を提供する啓蒙的な雑誌という立ち位置で、海外の情報なんかも載せていました。
そこで、読者のための娯楽連載として、当時の編集長が海外の探偵小説の翻訳を掲載することを思いつき、創刊号から連載を開始します。もちろん、「シャーロック・ホームズ」シリーズの短編も多く掲載されました。そうしたら本文よりもこの海外探偵小説の連載のほうに人気が出てしまい、日本人のミステリ作家も発掘したらさらに人気が出て、後世では「探偵小説雑誌」として評価されるようになります(最後まで探偵小説専門誌ではなかったんですけどね)。この人気にあやかろうと、競合他社から次々と探偵小説雑誌が出るぐらいの反響でした。
さて、『新青年』には「誌友倶楽部」という、いわゆる読者欄がありました。その読者欄で、掲載されている翻訳に関する熱いバトルがくり広げられたんです。
発端は大正10年(1921年)4月号の「誌友倶楽部」で、こんな読者の投稿が載っています。
小説中の人名が多く西洋の名そのままなので読みにくくて困りますから日本の名に書きかえてくださいませんか、切にお願い申します。
記者:外国の小説を翻訳したのはどうしても外国名ですが、他の諸君も日本名をご希望でしょうか、御意見を聞かしてください。
翌月の5月号には、アンケート結果が載せられました。
賛成者約五十名、反対者は僅かに三、四人でした。記者は無論外国名そのままを宜しいと思っています。
(柳田注:「賛成者」=「外国名のままがいい人」です)
まあ、雑誌1誌の読者アンケートなので、これが当時の全日本人読者の代表的な意見かどうかはわかりませんが、ある程度「翻訳」の市民権が出てきてるのかな、でもまだ「翻案」がいいという人も確実にいるな、という空気は感じます。
そして、さらに次の6月号では、わざわざ読者の意見を以下のとおり載せています。
やはり外国小説は外国小説として人名や地名も外国名そのままを使ってある方がよい。なまじ日本名に直したのではなんだかその小説全体の興味が薄くなってしまう。それから外国小説のかなり原作の形を少しでもこわさない様、原作そのままに訳出いただきたい。
またまた、翌年大正11年(1922年)12月号では、記者の意見も載せています。
今まで本誌に掲載した海外探偵小説の中には既に日本に紹介されたものもありました[…]しかし紹介されたというのは翻案紹介の意味で、翻訳されているという意味ではありません。申し上げるまでもなく、翻訳と翻案とでは、大分ちがって来ます。無論筋の上に似通った話はありましょうが、作そのものの価値に至っては全然味が違って来ます。だから単に筋だけ読まないで、原作の巧味を研究する意味で、御覧下さるようにお願いします。
現代のビジネスマン風に言い換えると、「弊誌では他社と違って翻案ではなく翻訳を載せています!差別化しています!」という宣言ですかね。
だいぶ引っ張った「翻訳」VS「翻案」論争は、これでとりあえず決着したようです。
意図せず「探偵小説雑誌」の草分け的存在となった『新青年』がこの宣言をした影響は、大きかったのではないかと想像します。
これだけ「翻訳」の良さを熱く語るぐらいですから、本誌に掲載された「シャーロック・ホームズ」シリーズは、当然「翻訳」でなければいけませんし、「原作の巧味」が伝わる訳文でないといけません。
いまのように物流が発達しておらず洋書を手に入れるのは難しかったでしょうし、インターネットはもちろんないですし、紙の辞書もまだ数が少なかった時代背景を考えると、けっこうハードル高いです。
そんな『新青年』で翻訳者デビューを果たし、いまも「シャーロック・ホームズ」シリーズの訳者として高く評価されているのが、延原謙さんです。
次回、延原謙さんをご紹介します。
よろしければサポートをお願いします。いただいたサポートは翻訳業の活動費に使わせていただきます。記事のKindle書籍化等を企んでいるので、その費用に使わせてもらえると幸いです。
