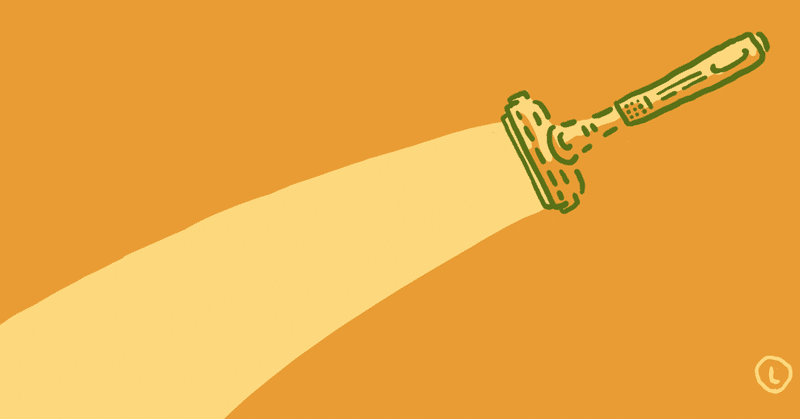
脱毛サロンの女「キッチリした客」
これは、脱毛サロンに勤める女・毛利悠里(26)の日常を切り取った妄想エッセイです。事実とは大きく異なる点があるかもしれません。妄想ですのでご了承下さい。
=1話完結シリーズ=
①「アザのある客」
②「100%の客」
③「減らない客」
B様がうちのサロンに通いだしたのは、およそ2年前だった。「どうしてもキレイに処理したいので」と無制限通い放題コースを選び、通うスパンの目安とされている2ヶ月をキッチリ守り、来店される。
几帳面な性格は予約にも表れる。予約はその月の2週目の土曜日の15時と決まっている。施術日の前日にある程度は自身で毛の処理をしてきてくださいとお願いしているのだが、彼女は背面を除きほぼ完ぺきにしてきてくれる。とてもありがたいお客様だ。だが、キッチリし過ぎるあまり、いつも疲れているように見えた。
2年以上通っていると、日常の脱毛処理はほぼ必要なくなる。B様に関しては元々ムダ毛が多いほうではなかったので、順調に脱毛は進み、ほぼ無くなっていた・・・VIOを除いては。
VIOは所謂デリケートゾーンである(知らない方は調べて)。彼女はVIOもキッチリ処理したい(つまりツルツルに)という希望だった。しかしこの部分はなかなかしぶとく、どう頑張っても時間がかかる。
「完璧になくなるまであと何回通えばいいですか?」
普段はあまり話さない彼女が聞いてきた。
「そうですね・・・あと1年は必要かもしれません」
正直に答えた。無制限通い放題コースとは言え、3年以内という期限がある。3年間キッチリ通い続けても、つるっつるにするのは正直難しい。
「あと1年ですか・・・」
ーガッカリしたーという表現がぴったり当てはまる、魂の抜けたような呟きだった。そんなに通うのが苦痛だったのか。フォローするつもりで言った。
「B様はもうほとんどお手入れが必要ないくらい減っています。あと1年は気が向いた時に通うくらいでも十分キレイになりますよ」
「もう待てないんです」
「待つ?」
「耐えられないんです」
「そんなに苦痛でしたか?」
「・・・」
「たまにいらっしゃるんです。知らない人間に身体を見せることが苦痛で、通うのをやめられる方が。そりゃそうですよね。家族でも恋人でもない赤の他人に全身を委ねるんですから。これまでキッチリ通って下さっていたのでそんなに悩んでいらっしゃるとは気付かずに・・・申し訳ありません」
「いや・・・」
「やめましょう」
「え・・・」
「もう十分だと思うんです。ここまで頑張って通って下さって、申し分ないくらい成果も出ています。自信を持ってください」
なぜか励ましていた。と同時に、お客様の様子に気付かずに施術していた自分を恥じた。施術する約90分もの間、ずっと苦しみを味わわせ、我慢させてしまっていたなんて。
「嫌なら今すぐ止めるべきです。無理することなんてないんですから」
サロンへ来るお客様は、当たり前のように裸になり、恥ずかしげもなくデリケートな部分をさらしてくれる。初めは抵抗があっても慣れていく。だから我々もそれが稀有なことだとは思わず、お互いが作業のようになってしまう。それは決して悪いことではないけれど、そこに苦しさや気持ち悪さを感じたら、無理して続ける必要はない。
「本当に申し訳ございませんでした」
心から詫びて、深く頭を下げた。
顔を上げると、彼女は泣いていた。でも、少し笑っているようにも見えた。鼻をすすりながら、何か思案しているようだった。
そして。
「わたし、やめます」
笑顔で彼女は言った。自分からやめることを進めておいてなんだが、ちょっとだけガッカリした。もう少しコミュニケーションが取れていれば・・・異変を感じられていれば・・・と今更思っても仕方がない。
「かしこまりました。期間を短縮される場合、規定に基づいて返金させて頂きます。お手続きに少しお時間頂きますが、よろしいでしょうか」
「あ、違います」
「はい?」
「やめません、ここ」
言っている意味が分からない。からかわれているだけなのか・・・という表情をしていたと思う。B様は続けてゆっくりと話し始めた。
「死ぬつもりだったんです」
「えぇっ!?」
思わず大きな声が出た。ますます意味が分からない。
「会社が・・・人間関係が・・・つらくて」
話は思いもよらぬ方向へ舵を切っていった。
「でも自殺したら解剖されるじゃないですか。死んだ後に見ず知らずの人に身体見られて、触られて・・・想像しただけでも恥ずかしくて。だから死ぬ前にキレイにしておかないとって思ったんです」
ん?サロンスタッフに見られるのは大丈夫なのか?
「ここは大丈夫ですよ。だってわたしが望んで来てますから。それにスタッフさんは絶対に女性ですし。だけど脱毛って時間かかるの知らなくて、そこは想定外でした。でも全身ツルツルになったら死ねるんだって思ったら、不思議と耐えられました。なのにあと1年って言われて・・・もう無理だったんです、これ以上あの会社に行くのは」
なんと言っていいのか分からない。聞くに徹するしかない。
「でも、毛利さんの言葉で救われました」
頭にハテナが3つ浮かんだ。
「意味わかりませんよね。毛利さんが『嫌なら辞めるべき、無理することはない』って言ってくれたから」
そ、それは、脱毛のことだが。
「わかってます。脱毛のこと言ってたんですよね。でも面白いくらいに全部が刺さっちゃって。そんなこと言ってくれる人いなかったから。あと『自信持ってください』も嬉しかったです、ものすごく。わたし実は・・・とっても几帳面なんです」
そうですよね。
「ふふっ。そう見えますよね。いっつも決まった予約の取り方ですもんね。規則とかも守らないと気が済まなくて。でも、どれだけキッチリしても満足できないっていうか、ちゃんとやらなきゃ、もっと頑張らなきゃって思っちゃって、何やっても達成感ないし、自信も持てないんです。でもここに通ってるだけで自信持っていいって言ってくださって、あぁ~そうかぁ、小さなことでも自信持っていいんだぁって」
キッチリできるあなたはスゴいと思います、心から。
「毛利さんって優しいですね。すごくこのお仕事に誇りを持ってらっしゃるように感じますし、お客さんのことも考えてくれてるなって。話は食い違ってたのかもしれないけど、本質は同じだったんじゃないかと思います」
そう、なのかな・・・
「違うって思ってますよね。でも・・・救われたのは本当です。まぁ、そもそも自殺する勇気なんてなかったのかもしれないですけど。会社を辞める勇気はもらえました」
と、晴れやかな顔で彼女は言うが、これからどうするのだろう。
「とりあえずは貯金で暮らします。けっこうあるので」
怖くなって私は聞いた。
「あの」
「はい?」
「心が読めるんですか?」
「え?」
「聞きたいこととか思ってること、ぜんぶ先に話してくださるので」
「だって、顔に書いてますもん」
「え!ほんとですか?そんなに顔に出てるなら気をつけないと」
「ウソですよ。それはきっと、わたしの話したいことに毛利さんが便乗してくれただけです。要は、毛利さんが聞き上手なんです」
「そうですかねぇ・・・」
「今日は本当にありがとうございました」
「いえ、こちらこそありがとうございました。なんというか・・・」
「またのご来店お待ちしております?」
「はい!」
彼女が帰った後、部屋の清掃に行くと、タオルとガウンがキッチリとたたまれていた。脱毛サロンのいちスタッフのわたしが誰かの命を救うことがあるなんて。心のデリケートゾーンに入ることがあるなんて・・・。そうだ。わたしだってちょっと巧いことだって言えるし、どうやら聞き上手みたいだし、もっと自信を持って生きよう。それが誰かの自信につながるのかもしれないから。
翌日。
2ヶ月後の2週目の土曜日の15時、B様からの予約が入った。
クリエイトすることを続けていくための寄付をお願いします。 投げ銭でも具体的な応援でも、どんな定義でも構いません。 それさえあれば、わたしはクリエイターとして生きていけると思います!
