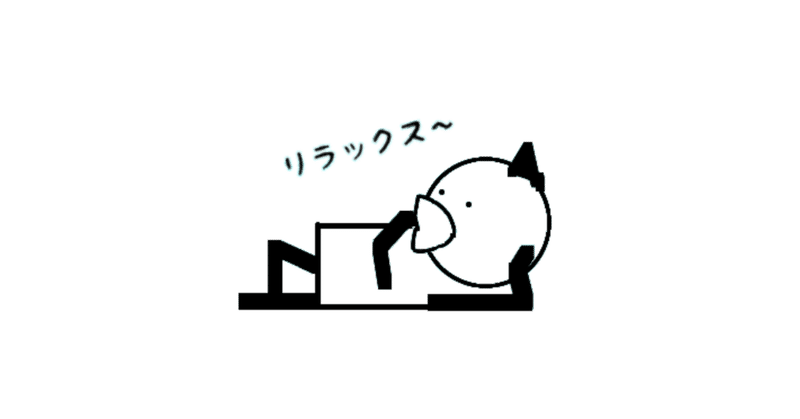
<小説 ユーミン>
*この記事は「脱サラをする前に」というサイトから転載したものです。
ゴールデンウイークもあと1日となりました。毎年のことですが、高速道路の渋滞はすごいことになっています。マスコミがそれを報じるのもいつものことですが、渋滞をわかっていながら高速道路で出かける人を不思議に思っているのが正直なところです。
今から40年くらい前、僕はタクシードライバーをしていました。当時はゴールデンウイークとか夏休みのお盆の季節といった長期休暇のとき、都心の道路はとても空いていました。「ガラガラ」という表現がぴったりなほど車の通行量が少なかったのです。皆さんが遠方に出かけるからですが、近年はそういう光景でもなくなっています。
長期休暇中の渋滞は当時と変わらないにもかかわらず、都心が「ガラガラ」にならない理由が今一つ分かりません。人口にしても昔より減少しているはずですが、それでも「ガラガラ」なってはいません。余計に不思議です。
それはまぁひとまず置いておくとして、僕は遠方には出かけませんが近所のショッピングセンターなどには出かけます。そこそこ混んでいるのは、なんとなく気分を高揚させるものがあります。
ショッピングセンターなどに行きますと、妻が買い物をしている間、僕は本屋さんに行くのが通例です。その本屋さんで数週間前から「へぇー」と思うことがありました。それは「アルジャーノンに花束を」という本が売上げベストテンにランキングしていることです。僕の記憶では、この本は二十数年前に読んだ本ですが、すごく感動したことを憶えています。
記憶があいまいですが、このまま書きすすめていくことにします。記憶違いがありましたらごめんなさい。僕が「アルジャーノン…」を読むきっかけになったのはラジオで見城美恵子さんという方が紹介していたことです。見城さんは当時有名なラジオパーソナリティだった女性ですが、その方が「とても感動した」と内容を簡潔に紹介していて、それを聴いて読みたくなりました。
二十数年前にヒットした本が、今また売れているのがとても不思議でした。そこでネットで調べますと、この「アルジャーノン…」は10年くらいの間隔で定期的に売れているそうで、幾度かテレビドラマ化もされていました。調べた範囲ではテレビ化は2回で、主演は1回目がユースケ・サンタマリアさんで2回目は元ジャニーズの山Pさんでした。これだけの人気者が主演を務めているのですから原作がいかに人気があったかがわかります。
話は逸れますが、僕がテレビドラマを観ていて思うのは作品を制作するプロデューサーの頭の中です。「ああ、このプロデューサーは、青春時代に好きだったテーマを題材にしているな」と想像してしまいます。それは主題歌にも当てはまるのですが、主題歌が昔のヒット曲だった場合など、青春時代に心に刻まれた楽曲を「いつか使いたい」とずっと思っていたんだろうなぁ、などと勝手に思ったりしています。
話を戻して。先週は、なんと「嫌われる勇気」という10年前に大ヒットした本までがベストテンにランキングしていました。名著はロングセラーするといわれますが、ロングセラーになるには名著という要因だけではなり得ません。そこには今ふうの言い方でいいますと、マーケティングが大きな要因となってきます。おそらく今回この2つの本がランキング入りしたのもそれぞれの出版社のマーケティングの賜物だと想像します。
しかし、両者がそろったからといって絶対に売れるということでもありません。このことは本に限らず音楽の世界にもあてはまります。「おニャン子クラブ」や「AKB」を生み出した、あの名プロデューサー・秋元康さんは作詞家としても大ヒットをたくさん作ったいますが、その秋元さんでさえ「ヒットしなかった楽曲が山のようにある」と話していました。
これまでになんども書いていますが、僕の感性は大衆とは少しばかりズれています。僕が「好き!」とか「感動した!」と思ったものはそこそこしかヒットしないのが常です。妻に言わせますと「あなたの感性、おかしい」となりますが、そんな僕がどうしても読みたかった本があります。「すべてのことはメッセージ 小説ユーミン」という本ですが、シンガーソングライター・松任谷由実さんの自伝の本です。
しかし、「自伝」とはいいながらあくまで「小説」という形になっています。著者の山内マリコさんがたくさんの書籍を参考にしながら書いています。もちろん「ユーミン」という名前を使用していますので本人の了承はとっているでしょうが、本人のインタビューから書きあげた作品ではないようです。
それでも、僕はとても面白かったー! 僕は60代後半ですが、僕の年代ではユーミンさんは時代の象徴ともいえる存在です。ユーミンさんの絶頂期はちょうど少年ジャンプの絶頂と重なるのですが、少年ジャンプが600万部の売上げを作った頃、ユーミンさんのCDも300万枚売れていました。その頃に、ある雑誌のインタビューで少年ジャンプを引き合いにして「600万枚を狙う」と話していたのがとても印象に残っています。少年ジャンプが200円、CDは2,000円です。それでも言ってのけるユーミンさんは素敵でした。
これまでにもユーミンさんに関するインタビューや記事などはいろいろと読んでいましたが、どれもヒット曲を出したある時代の出来事について書いたものでした。僕はそうではなくて、ユーミンさんが世に出るまでのいきさつを知りたいとずっと思っていました。ですので、「小説ユーミン」はまさに僕が求めていたものでした。
当時(70年代80年代)の音楽業界には興味があり、ユーミンさんに限らずその時代のアーティストに関する記事はいろいろと読んできましたが、読めば読むほど有名なアーティストの方々のつながりを知ることになりました。「へぇー、あの人とあの人も当時からすでに知り合いだったんだ」と人間関係を知ることは感動的ですらありました。
「小説ユーミン」には名だたるアーティストがたくさん出てきます。例えば、かまやつひろしさん、細野晴臣さん、松本隆さん、村井邦彦さん…、切りがないのでこの辺でやめますが、共通しているのは皆さんがまだ20代前半の若者ということです。僕は音楽業界に詳しくないんでわかりませんが、おそらくそれまでの日本の音楽界とはまったく違った音楽の作り方を始めた若い人たちが勃興していた時期なのでしょう。先ほど70年代80年代の音楽記事を読んできたと書きましたが、そうした記事に頻繁に出てきたのが「キャンティ」というお店です。
この本にも終盤に出てきますが、当時の日本の音楽界の先頭を走っている若者たちが集まっていたレストランのようです。先日お亡くなりになりました坂本龍一さんも、若い頃にべろんべろんに酔っぱらってきれいなモデル風の女性を二人つれてやってきた、となにかの記事で読んだことがあります。
僕がこの本を読みたかった一番の理由は、ユーミンさんがどうやって世に出てきたのかを知りたかったからです。例えば、同時代のシンガーソングライター・中島みゆきさんはコッキーポップという音楽コンテストで優勝したことがきっかけです。ユーミンさんの場合はそうしたきっかけに関する記事を目にすることがありませんでした。
結論を書きますと、ユーミンさんが高校時代に作詞作曲した楽曲がいろいろなアーティストの手を経て音楽業界の人の耳に留まったことでした。この本によりますと、ユーミンさんは中高校時代から作詞作曲をしていて、しかもかなり裕福な家に生まれていたことから、中学時代から都心で若者が集まる場所に出入りしていたことが大きかったようです。つまり、そこで知らず知らずのうちに人脈を構築していたことになります。
そして、僕が一番ユーミンさんの「ラッキー」を感じるのは、ユーミンさんがデビューに際して出会った大人たちです。どんな業界でも新人はベテランの人との出会いがすべてを決めるといっても過言ではありません。ユーミンさんが出あったレコード業界の人たちが素晴らしい人たちだったことがユーミンさんの成功の一番の根源です。
この本ではないのですが、ほかの記事で村井邦彦さんとの出会いが最も大きかったと書いてありました。村井さんは作曲家でありながらアルファレコードの創業者でもあります。この本にも書いてありますが、ユーミンさんは「歌が下手」だったようです。それを作品に仕上げてヒットへと導いたのは村井さんの功績です。おそらく村井さんとの出会いがなかったなら、現在のユーミンさんも生まれなかったのではないでしょうか。そんなことを思わせる「小説 ユーミン」でした。
最後に、「小説 ユーミン」の著者および出版社にお詫び申し上げます。「おもしろかった!」と思ってしまって申し訳ございません。
じゃ、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
