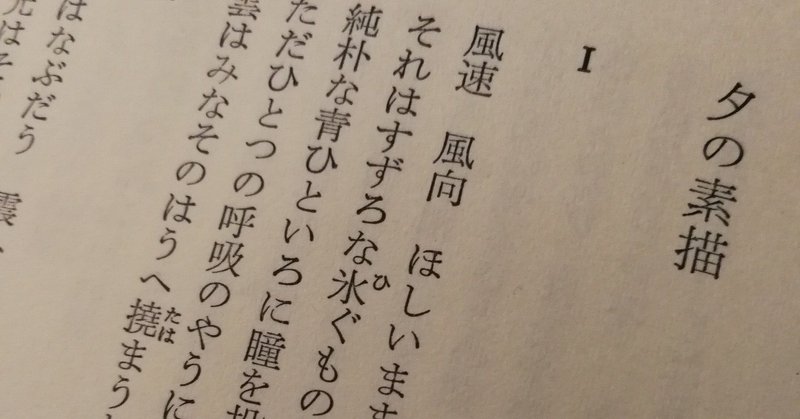
夕の素描
前回の記事では生野幸吉の「書籍返還の要求」を読みました。
今日は、夕の素描を読んでいきましょう。1950年の作品です。
夕の素描
I
風速 風向 ほしいままなそらの攪拌
それはすずろな氷ぐもの脈を結んだ
純朴な青ひといろに瞳を投げよ
ただひとつの呼吸のやうに光の一塊ははるかに沈み
雲はみなそのはうへ撓まうとするけはひをみせる
蛇足かもしれませんがすべての人に味わってほしいので、日常で使わない言葉・読みが難しい言葉について解説します。
ほしいまま:やりたいようにふるまうこと。
攪拌(かくはん):かきまぜること。とくに流体を混ぜること。
すずろ:あてのないさま。漫然。
氷ぐも(ひぐも):氷の粒でできた雲。氷晶雲。

氷晶雲の画像です。
はるか:距離の遠いさま
撓む(たわむ)
圧倒的なスケールと力強さを持つ詩です。この詩に出会ったのは8年ほど前だったと思いますが、今でも完全に記憶しているほど感動した詩でした。自然の美しさと雄大さがこれほどのスピード感を持って眼前に広がるこれ以上の言葉があるでしょうか。太陽の沈む「夕」を「ただひとつの呼吸のやうに光の一塊ははるかに沈」むといっています。
この言葉の壮大さがまずこの詩の一つの魅力ですが、少しだけ踏み込んでアナリーゼしてみましょう。
なぜこれほどまでにスピード感を得るのか。
「風速 風向 ほしいままなそらの攪拌」
ここに畳みかけるように登場するhの子音に由来しているのではないかと思います。そして、読むとき、おそらく自然に6/8拍子で読まれると思うのです。その小節の頭にくるhの音が力強く、また爽やかで、自然界の根源的な力である風を見事に音として表現されています。西欧の詩の研究にあけくれていた生野幸吉ならではの形式美かもしれません。
日本語は非常に韻と相性が悪い言語です。西洋のアレクサンドランのような韻は非常に荘厳で格調高いものですが、日本語で韻を踏むと安っぽく響いてしまいます。生野幸吉はこの詩において、完全に語尾の響きを異なるものにしています。
攪拌n
結んだa
投げよo
沈みi
みせるu
このような行末の母音の豊かさは日本語に力を与え、また色彩をゆたかにするものだと思います。
それでは次の詩を読みます。
II
露はなぶだう 震へるみどりの冷気をごらん
日光はその核にとぢこめられた
そらが酷しくくろずんでゐる
ぼくらははてしない外端に置かれてゐる
円テーブルにすがるやうに… かなしい鉛錘の一塊のやうに
ぼくらの心は離れて沈む……
傾角のおほきいひとひの光から
ぼくらの顔はなにを受けたか?
樹々を? 投げられてとぶ鳥の影を?……
露はな(あらわな):裸である。むき出しである。
ぶだう(ぶどう)
酷しく(きびしく)
鉛錘(えんすい):鉛で作ったおもり

ひとひ:ある日
打って変わって静謐な風景が広がります。太陽はほとんど沈みかけていて、群青が支配してくる空と、その光が神秘的に射してくる背景が浮かびます。
「ぼくら」が誰と誰を表しているのかはわかりようもありませんが、この暗い光の中にいて、静かに別れを予感させます。
今回の詩では、逆に韻を踏んでいます。
くろずんでゐる
置かれてゐる
すがるやうに……
一塊のやうに
樹々を?
影を?……
ある種のリズムを作り、またそれが二人の異なる心象をそれぞれ対置しているような印象を私は受けました。
そして白眉ともいえる三番を紹介します。
III
赤い光が射してくれば
せつなくさんらんする幻…… またふっと
だれか彼岸花を捧げていった
……闇の冷えそめる庭々で
水滴はしたたり打ってゐる しとった泥を
声よさびしい声よ
すこしづつ
すこしづつ
ぼくのからだが侵されてゐる
彼岸花(ひがんばな):群生し、9月ごろに赤い花を咲かせる多年草。その名のとおり、墓に供えられることが多い。全ての部位に強い毒がある。

冷えそめる:冷え始める
二番によって静謐な空気が作られたところ、三番ではさらに静かになります。また言葉の密度も希薄になり、明かりもさらに暗くなっています。死をはっきりと感じさせる空気があり、夜の寂静のなかに響き渡る水滴の音が不気味かつ神秘的で美しさを感じます。
この詩に関して多くのことを語るのはそれこそ野暮というものと思われますが、私がこの詩に初めて古本屋で出会い、
赤い光が射してくれば せつなくさんらんする幻…… またふっと
という言葉に触れ、言葉のみの美しさでこれほど感動した経験が無かったので、この詩のこの言葉のために分厚い名作詩集的な本を購入したのでした。
「せつなくさんらんする幻」という一つの言葉に秘められた美しさは私は一生大切にしていくことだと思います。
IV
白氷を透きとほらしたかのやうな
上からはうつとあかるさが来た
叫びもあしおともひびかない
おまへはゐない
おれはかうして疲れてゐる
――それら玄いしべある花が
しんしんと凝視しているのだ
白氷(はくひょう):急速に冷凍し、空気が入って白くなった氷
玄い(くろい)
そして、無音になります。そして、一人になります。
I、II、IIIと、自然の光の移り変わりをみてその雄大さや神秘さに身を任せていたところから急に私の視点になり、悲しみを通り越した喪失感のみがそこにあります。
私がこの詩を読むと、どうしても無音なのです。そこに言葉があり、声があるにもかかわらず、その声は響かず、感情すら失ってしまうようです。
生野幸吉の詩は「ぼく」を通してその雄大な自然をうたい、その言葉繰りによって自然の美しさを感情に投影し、感情をより生々しく、深刻に、そして美しく見せるというところにあると思います。圧倒的な言葉のセンス、雄大な自然を取り込む感性、生々しい感情の発露、そして形式への審美眼、どれを取っても一級品なのにもかかわらず生野幸吉はそれそのものが魅力の核ではなく、それらが組み合わさって、投影され、多角的に映された概念たちの集合体こそが魅力の本質を為しているのだと思います。
この詩は僕にとって永遠に詩の模範であって究極の姿でいると思います。
--ここから先に有料記事はありません。この記事が面白いと思っていただければ是非サポートと同じように投げ銭していただければ嬉しいです。次のテーマを書く助けとさせて頂きます--
ここから先は
¥ 100
記事のお読みいただきありがとうございます。 即興演奏を通した様々な活動と、これからの執筆活動のために、サポートしていただけたら幸いです。
