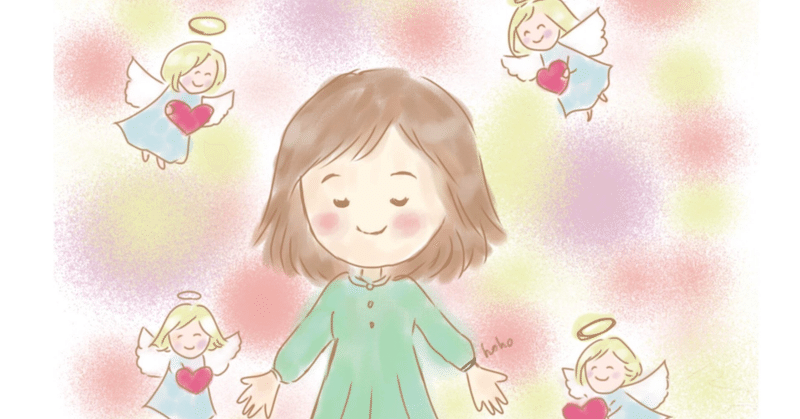
小説『愛子の日常』 本編5.
〜セントの青春 Ⅰ.〜
次の日。
セントは朝起きて母親に挨拶するも、母親は「彼女と結婚する事は許しません」の一点張りだった。
「それは日本人だからかい?」「お母さんは差別しているだけじゃないのかい?」とセントは反発するも母親は聞かなかった。
そんな会話を一時間もした後、セントは会社に間に合わないと思い話を切り上げ職場に向かった。
職場に着くとさやかの姿は無かった。いつもならもうとっくに着いている時間なのだが、彼女の気配すらまったく無かった。
普段いかに彼女が作り出すコミュカルとも思える『さやかワールド』が周りを巻き込んで影響を与えていたかが分かるほどに、彼女がいない空間は静まり返り肝心な物を抜かれてしまった無力感のようなものが漂っていた。
仕事がはじまってもさやかが現れる事はなかった。
セントは「まさか?!」と思った。何か不吉な予感がしたのだ。
上司に聞くと、さやかは熱を出し病院に行っているとの事だった。
セントはその日は仕事も手につかず、何か落ち着かなかった。いつもは彼女のちょっとした言動にイライラしていたセントだったが、いざ彼女がいなくなると人々の会話がどこかぎこちなくなり、セントもその空間にいずらくなってしまった。まるで、会社の中のコミュニケーションの均衡はさやかが保っていたかのようだった。
そしてその日の午後、事態は急変した。
さやかが新型コロナウイルスに罹ったとの連絡があったのだ。セント達も濃厚接触者になり、PCR検査を受けなければならなくなった。
2020年にパンデミックを引き起こした新型コロナウイルスだが、この頃には殆どが終息し、治療薬もワクチンも当たり前のように出回っていた。
しかし、さやかが感染したのは更に新型のコロナウイルスで、ワクチンも治療薬も無いとの事だった。
もともとセントは、新型コロナウイルスというものを信じていない。母親から「あなたが2歳か3歳のころ、世界中でコロナウイルスが流行したのよ」という話は何度も何度も聞かされていた。
しかし、全世界でマスクをした人間が溢れかえるという事はあまりにも信じがたかったし、ロンドンやニューヨークなど世界の主要都市で人の姿が消えるという事も想像が出来なかった。
だから、母親がコロナの話をする度に「それは迷信だ!」と言って一切受け付けなかった。
今回、さやかがコロナに罹ったとの話を聞いた時も、半ば半信半疑でブラックジョークかとすら思ったほどだった。
セントは職場の近くの病院でPCR検査を受けたが陰性だった。他の会社の仲間も皆陰性で、特に問題は無いとの事だった。
やはり、コロナはブラックジョークで、さやかは嘘をついているのではないかとセントは考え込んだ。「昨日の母親の言葉を気にしてるのかな〜?ショックだったのかな〜?」と色々なことを考えた。
上司にも「さやかがコロナというのはジョークですよね?!」と何度も何度も聞き込んだ。
上司もセントが何度も訪ねてくるものだから嫌気がさし、「何で俺の言っている事が信用できないのか?!心配だったら病院に行ってきたらいい。」と病院の名前を教えてくれた。
セントはさやかにスマホからメッセージを送ってみる事にした。
「大丈夫??」とだけ書いて送った。
しかし、それは何時間たっても既読にはならなかった。セントは心配して電話をかけたが、一向に繋がらなかった。
もう日が傾いて来ていた。
(今日はもう諦めようか・・・)セントはさやかが心配だった。しかしどうする事も出来なかった。
さやかに何かあったに違いない事はセントにも分かっていた。ただそれが、コロナなのか何なのかという事はセントには分からなかったのだった。
翌日。
セントは会社を休んでさやかのお見舞いに行く事にした。
もし本当に病気だとしたら、何かさっぱりした物が食べたいだろうからと、途中でプリンとリンゴジュースを買っていった。セントにはさやかの喜ぶ顔が目に浮かんだ。病院までは少し距離があったが、もう直ぐさやかに会えるという喜びから自然と足が弾んだ。
セントは病院に着くと、真っ先に受付に行き、さやかの病室を確認してもらった。セントはやっとさやかに会えるという期待感でいっぱいになっていた。
「大西さやかさんですね。」
「現在、隔離病棟にいるため面会は出来ません。」
セントにはその言葉の意味が理解できなかった。
「あの〜、さやかに会えればいいんですけど。。面会なんてしなくても。これ、渡したいので。」と、セントは鞄からプリンとリンゴジュースを出して説明した。
「ですから、隔離病棟にいるため会うことは出来ません。そちらもお預かり出来ませんので、持ち帰って下さい。」
「隔離病棟って、どういう事ですかっ?!会うことぐらい出来るでしょっ!」セントは反発した。
しかし、「出来ません。」の一言だった。
「どうしてですかっ!!それって、人権の問題ですよねーーーっ!!」セントは凄い勢いで迫った。言葉遣いこそ紳士的ではあったものの、相手を脅迫するかのような勢いだった。
受付の人も一人では対応し切れずに、最後には三人がかりでセントの対応にあたった。
セントには、諦めて帰る事しか選択肢が無くなっていた。
(・・・どうして、さやかに会えないのか?!)セントの心はいきなり重たくなった。心が強く締め付けられ、心の重りが身体へとのしかかり、帰るにしても病院から一歩踏み出す事がやっとだった。
なんとか道端のベンチに辿り着き、そこにドスンと座ると、セントは天を仰いだ。
天を仰いだ頬を涙がつたった。(どうして会えないのか・・・)
セントはさやかを世の中から奪われた気分だった。
セントの心は、まるで泥水に浸かったスポンジのように、溢れ出る悲しみを吸い取って重たくなっていた。
もはやどうする事も出来なかった。
電話も繋がらない。。会うことも出来ない。。さやかがいなくなった世の中でセントは一人取り残されていた。
セントはベンチでずっと泣いていたが、悲しみを吸い取って重たくなった心というスポンジは、身体にのしかかり、身体を動かすこともできないでいた。
腕は肩から下が脱力し、顔は天を見上げ、上半身はベンチに全ての体重を預けてもたれかかっていた。
身体をも動かなくしてしまう重たい心が、セントを潰しかけていた。
(・・・もう、生きられない)セントは一瞬自殺を考えた。
そうして決心した。
悲しみを吸い取って重たくなった心というスポンジを、自らの手で裂いたのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
