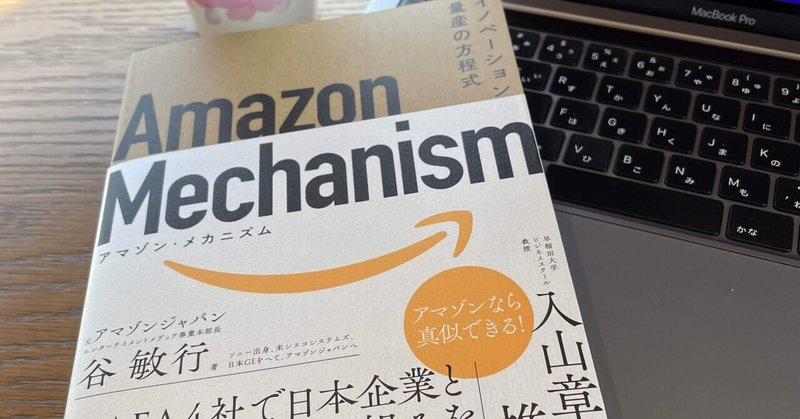
できると思っていなかったけど、できるなら幸せ
金曜の朝、Clubhouseのゲストスピーカーに上がっていた谷敏行さんのお話を聴いてそのまま著書をポチった。
Amazon Mechanism (アマゾン・メカニズム) ― イノベーション量産の方程式 谷 敏行 https://www.amazon.co.jp/dp/B09MCPST4J/ref=cm_sw_r_tw_dp_T7B4Q76SS57QX63YP94V @amazonJP
読み始めてすぐに、ロジカルな価値とエモーショナルな価値というテーマがアタマを掠めたので少し書き出してみた。
モノやサービスを通じてどんな価値を提供するか。
ロジカルに考えれば「不満の最小化」は最もわかりやすく定量的に効果を伝えやすい。
「フライパンひとつで10分以内で料理がつくれます」
「レンチン5分で料理完成」
使う道具がひとつだけ、所用時間が具体的に示されている。解決すべきは時間と労力の最小化で、誰もが歓迎すべきメッセージだろうと納得できる。
商品コンセプトについて、開発や導入の意思決定者にはこれを直接否定する材料があまりない。あるとすれば、そのコンセプトは既存商品で満たされているのではないかということぐらいだろう。
もちろん、商品のコンセプトはひとつではない。複数の切り口のコンセプトを組み合わせて提案を作り上げていく。
「料理が楽しくなる」
そんなコンセプトはどうだろうか。これはロジカルには捉えにくい。どう楽しいのか、どれぐらい楽しいのかを定量的に把握することが困難だからだ。
そもそも楽しいかどうか、すなわち「よろこびの提供」はロジカルな課題ではなくエモーショナルな課題なのだ。
ところで、「不満の最小化」を極限まで突き詰めたらどうなるだろう?
道具を一切使わず料理の時間ゼロ秒、あっ、これじゃ UberEats か 笑
ちょっと論理のすり替えになってしまった。料理の手間がゼロになったとして、利便性は確かにあるが、「料理をする人」の心情はどこへいってしまったのだろう?
時短料理をしたい人の意識をもう少し分解してみたい。
選択肢の中に「料理をしない」があるのだろうか。あるのだとしたら、なぜ「料理をする」を選択するのだろうか。
考えるに、料理をしない選択より、何らかの点で料理をする方がメリットが大きいからに違いない、ということが容易に想像できる。
その理由をいくつかまた想像してみる。
・料理した方が安い
・料理をしないことに罪悪感がある
・実は料理をしたい
大方こんなあたりに大別できるんじゃないだろうか。
料理した方が安い、というのは実際に何と比較するかで変わってくるので一概には言えないが、それなりのクッキング・スキルを持っている人なら、同じクオリティを求めるなら自分で料理した方が安いということはあるかもしれない。あるいは家族が多い場合はやはり料理した方が安くなりそうだ。
料理をしないことに罪悪感、というのは日本人にはとても多いような気がする。昨年あたりの話題だと「めんつゆを使うのは手抜き」みたいな信じられないような時代錯誤発言がSNSを賑わしていたが、それが大きな話題になるぐらいにはそういう意識が世の中に存在しているということだろう。この意識を持っている人たちにとって、料理は本当に苦痛なのかもしれない。
実は料理をしたい。そんな奇特な人いるのだろうかと訝しがる人がかなりいると思っている。特にキッチンに立たない男性陣 笑
ボク自身は、実際には相当数の「料理をしたい人たち」が世の中に存在していると読んでいる。本当はしっかり料理したいんだけど、仕事や育児が忙しくてそこまで手が回らない、という人がかなりの規模でいるはずだ。この場合は「仕方なく」時短料理を選んでいると考えていいだろう。
さて、時短料理のソリューション提案を改めて考えてみる。
料理をした方が安いと考える人にとって、時短料理は魅力だろうか。ここは手間より安さを優先したい人たちなので、あまり大きなメリットにはならなさそうだ。無論手間が少なければ少ない方がありがたいが、そのための手段に大きなコストをかけるのは本末顛倒だから、その課題解決にいくらまでなら許容できるかが選択の採否を決定づける要因になる。
では、料理をしないことに罪悪感を感じる人にとっての時短料理はどうだろう?本当は料理なんかしたくないと思っているのであれば、少しでも時間が短い方が嬉しいに決まっている。
ところがその罪悪感が「手抜き」に対する罪悪感だとかなり厄介なのだ。先ほどの「めんつゆ手抜き騒動」のように、時短料理の利用そのものに罪悪感を感じてしまうと、ここが課題解決にならなくなってしまう。
「レンチン5分で完成」みたいな本当に手間要らずだと、これは料理じゃないと思ってしまう(場合によっては家族に言われてしまう)可能性がある。欧米のようにレンジアップで完成するディナープレートみたいな商品が日本ではまったく普及しないのは、こんな社会意識が背景にあるからだろう。
とはいえ、基本は料理したくない属性と考えれば、ちゃんと料理した感がある仕上がりかどうかがポイントで、どれぐらいの省力化が図れているかが評価を左右しそうだ。
最後に、本当はちゃんと料理したいのに時間が取れない、というケース。この人たちに「レンチン5分」なんて提案はなかなか難しそうだ。料理を大切に考えている人たちに、料理のプロセスを尊重しながらしっかり時短ができる提案になっているかどうかで評価が決まるだろう。
ロジカルに考えた価値提案の「時短料理」だが、実はそのニーズを分解してみると複数の異なる価値基準が存在することが見えてくる。これらを同時に満たすソリューションを「時短料理」という発想から求めようとすると、出口の見えない堂々巡りに陥ってしまいそうだ。
ここで少し発想を変えてみる。冒頭に提示した「料理が楽しくなる」という提案だ。
料理した方が安いという人の場合、食費を切り詰めなければならないほど切実な状況は別として「料理が楽しくなる」ことは誰にでも共通に喜ばしいことだろう。
料理をしないことに罪悪感を持つ人の場合、暗に料理に苦痛を感じているとしたら「料理が楽しくなる」ことは苦痛からの解放につながる。これは大きな評価ポイントになるはずだ。
仕方なく時短料理という人の場合「料理が楽しくなる」のは本当に嬉しいことに違いない。簡単なのにこんなに美味しくできる!となればその感動はみんなに伝えたくなるほど大きくなる可能性もある。
・・・前置きが長いんだよなぁ。
ロジカルに考えて確実に市場取りにいく「不満の解消」は、分析分解型のソリューションアプローチだ。
ターゲットを精緻化しているから獲得市場を明示することができる。
(明示できたからといって獲得できるわけではないが)
しかし、細分化されたセグメントは必然的に規模が小さくなっていく。
一方、エモーショナルに考えて市場に提案する「よろこびの提供」は、統合型のソリューション・アプローチになる。
「よろこびと感動」は万人が希求するものだからだ。
タイトルに挙げた「できると思っていなかったけど、できるなら幸せ」は、最初に紹介した本の中で、著者の谷敏行さんが述べている言葉の引用だ。
「不満の最小化」は、マイナスを減らす漸近線のアプローチ。どこまで追い詰めてもゼロには届かず不満は残り続ける。
不満に直接アプローチするのではなく、不満の感情を別の感情で置き換えようというのが「よろこびの提供」だ。面倒に感じているものが楽しくなれば、その瞬間に面倒な気持ちは霧消している。マイナスの感情をプラスの感情に転じてしまうのだから、まるで魔法のようだ。
「できると思っていなかったけど、できるなら幸せ」
これはまさにその気持ちが生まれる瞬間の言葉なんだろう。
前述したとおり、ロジカルな価値と違ってエモーショナルな価値は定量的に把握することが難しい。定量把握がしにくいが故に「信憑性」が乏しいと思われてしまいやすいという問題がある。
本来は医療製薬関係の用語だったエビデンスという言葉がビジネス用語として使われるようになって久しいが、こうした「根拠」や「確実性」を求める背景に「リスクアバース」が強く働いている。
最初に紹介した本でも紹介されているリスクアバース=成果が低くても確実性の高い選択肢を採用しようとする心理バイアスを解消するために必要なことは何だろうか。
もちろん心理バイアスそのものを解消することは大切だが、社会心理として根深く定着している心理傾向を覆すことは容易ではない。
だとすると高い成果が期待できるが確実性が低かったりリスクが高い選択肢の確実性やリスク評価を改善するアプローチを考えてみるべきだろう。
幸か不幸か、日本企業が抱えるリスクアバースは、大半が知識不足によるものなのだ。既知の知見に基づく情報は確実だと思い、自分が知らない知見に基づく情報は疑わしいと評価する。
そうであれば、知らない知見を知っている知見に切り替えれば確実性やリスクの評価が改善される。
ボク自身、意思決定に関わることも次第に増えてきた。もっといろいろな情報に触れて意識のバイアスによる機会損失を抑えていこうと思う。
社会人よ、もっと貪欲に勉強しようではないか。(自戒を込めて)
