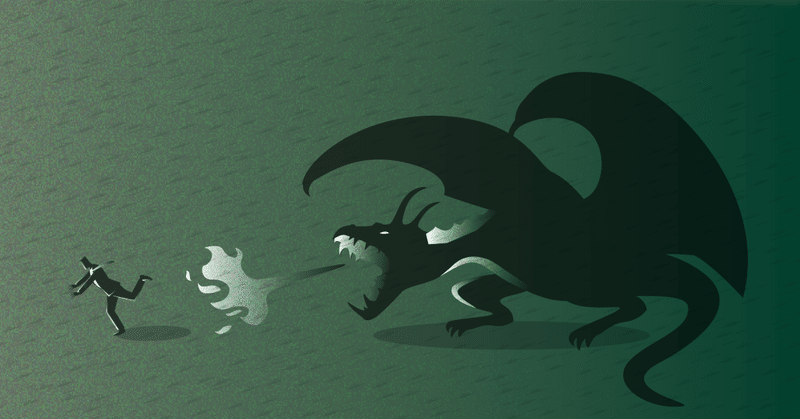
【逆噴射小説大賞2023】波乱の世界に僕はいる
風が戦慄いていた。横たわる彼女の髪に息を吹き込ませてくれるかのように何度も何度も唸っていた。
僕は立ち尽くしていた。悍ましい血で染まり、数分前に触れた彼女の最後の生温かさのなごりの手を見ながら。
死んでいた。彼女は間違いなく死んでいる。僕の大好きな彼女が、シスターが、昨日まであんなに笑ってくれていた人が、今はもう見捨てられた操り人形のように事切れている。
目は充血し乾燥していた。髪の毛がずぶ濡れになるくらい降っている雨が僕の代わりに泣いてくれていた。
ふと視線を感じ辺りを見渡す。そこにはカラスの仮面を被った黒いローブが独り立っている。その傍らには二匹の異形な何かが。血塗れの小さき子供を踏み潰しながら僕に近づいてくる。
一歩一歩、僕の死期が迫ってくる。それでも僕は逃げない。噛み付かれるのを待っているのだろうか。
これが夢だったら——そう思った時、異形な存在が僕に喰らい付いてきた。
気がつけば、僕は木の板を見ていた。
僕は寝ているんだ、と思ったのは頭から足先まで伝う柔らかい温もりの触感。身体の上からかけられた布団が若干重い。でも、心地良い。
視線を上から横へとずらして見る。木目調の壁に付けられた本や皿が並ぶ中、椅子に釘付けになった。誰かが座っていたからだ。
脚と腕を組んで眠りこける人。髪は肩まで切られているから男だと思うが、瞼を閉じた顔立ちは心が揺らぐほど美しい。
男女の垣根を越えた魅力に僕は不可思議な気持ちにされていた。
しばらく何も言わずに見ていると、その人は目を覚ました。
頭を上げて数回瞬きした後、立ち上がって近づいてきた。
衝撃だったのは、予想より背が高かった事と、その顔にどこか懐かしさを覚えた事だった。
でも、それが何故かは分からなかった。
「おはよう。お腹空いた?」
【続く】
↓参加した企画
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
