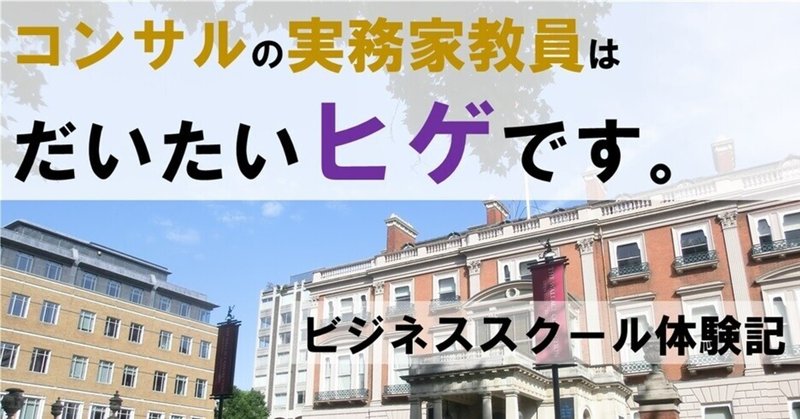
【MBA/体験記】第24話「ゼミの七忍」
こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!
前回の『能ある鳩はMBA』では、
「ビジネススクールのグッドな先生とイマイチな先生」
について見てきました。
今回は、鳩が通っていたビジネススクールのゼミを例に、
「どんな先生たちがいたの?」
「どうやってゼミを選んだの?」
といった内容を紹介していきます。
1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!
「実務家教員」とは
みなさん、大学教員というと、どんな人たちを想像するでしょうか。
アカデミックな世界で研究につぐ研究を重ねてきた人たちが頭に浮かぶかもしれません。

しかしながら、ビジネススクールには「実務家教員」と呼ばれる、大学の外の世界からやってきて教授を務める教授が大勢います。
彼らは大学以外の企業体で実務を積んできた人間であり、
博士号をとっていない教授も大勢います。
「研究なんて考えたこともねえ」
という実務家教授も大勢いるかもしれません。
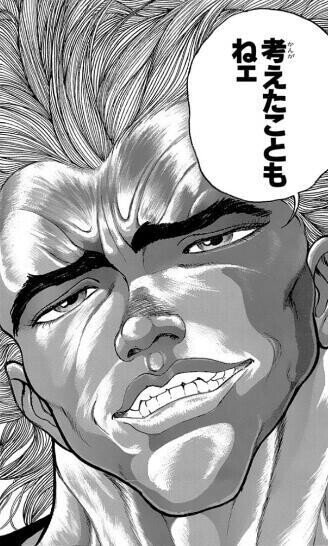
ただし、「AACSB」「EQUIS」「EPAS」「AMBA」といったビジネススクールの価値を認める国際認証の取得には、
「博士号を取得している教授の数」
「教授が研究者として論文を執筆している本数」
も影響するらしく、現在は博士号取得者の確保に動いている、という話も耳にします。
「ウチは博士号取得者の教授がいっぱいいますから!」
という、自慢になるんだかならないんだかよくわからない肩書を持っておけば、国際認証を与える側もアガるみたいです。

先生たちの出身 ①コンサル
というわけで、実務家教員が数多く集まるビジネススクールは背景も多彩です。
さて、鳩が通っていた母校の教師のバックグラウンドを挙げてみると……
まずは、「外資系コンサル」です。
MBA取得者や経済学・工学などの修士が多いイメージです。
教授職と個人事業でのコンサルを務めながら、同時に博士号取得を果たしている方々もときにいらっしゃいます。
コンサル出身の人はクライアントになめられないためか、ヒゲを生やしているパターン多めです。

先生たちの出身 ②起業家
「企業内で新規事業を担当」
「ベンチャーを立ち上げ」
といった起業家気質の先生方もいらっしゃいます。
この手の先生たちは異様な熱気を持っている人たちが多く、
授業やゼミでの生徒指導など忙しい教授生活を送りながらも、何かしらの寄稿などを年に50本もこなす方もいらっしゃいます。

50、60歳を迎えているにも関わらず、理系の実験室の学生かというぐらいにエナジードリンクを接種している様子をよく目にします。
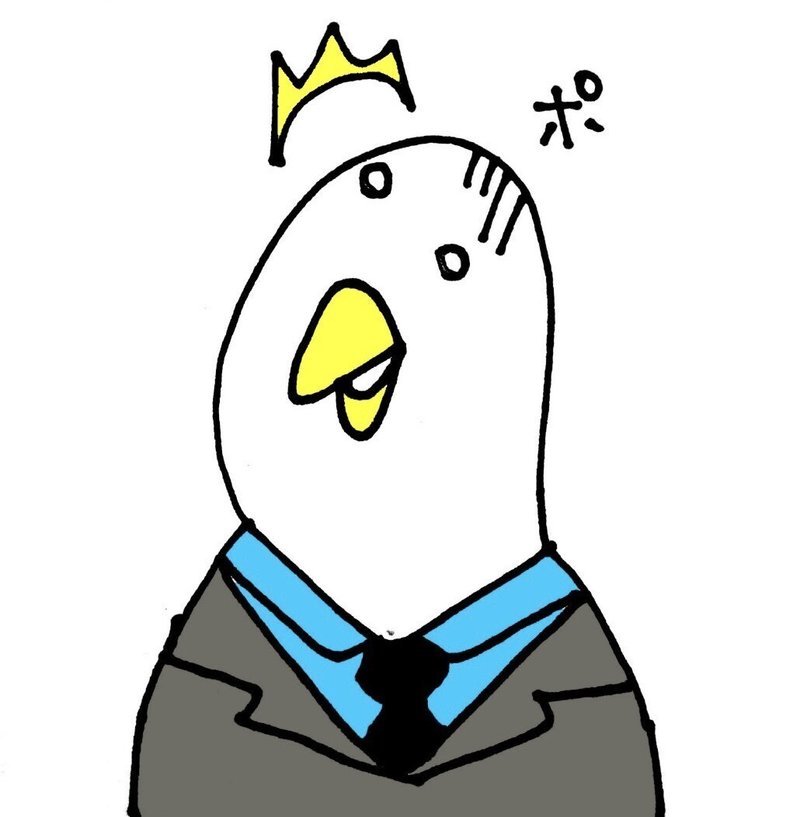
先生たちの出身 ⓷アート思考
MBAというと、
「いかにフレームワークを使いこなすか」
「いかにロジカルシンキングを徹底するか」
のイメージがあるかもしれません。
一方で、そのような左脳一辺倒の姿勢に疑問を投げかける姿勢の先生もいらっしゃいます。
アート思考に代表されるように、
「ロジカルだけでは説明できない領域」からいかに学ぶか、
というような、どこに落ちるかわからない稲妻のような授業を展開するわけですね。

先生たちの出身 ④技術系研究者
工学・情報学を背景にした先生は、統計学やイノベーションを好む傾向にあります。
彼らが「トライ&エラーの新規事業」をテーマに語る場合は、
先に挙げたロジカルというよりアニマルな「起業家」「アート思考」の方々とも似通るように思われるかもしれません。

しかし、技術系研究者畑の先生たちは、冷静に現象を見つめてPDCAを回している印象です。
先生たちの出身 ⑤事業承継
ビジネススクールにやってくる生徒たちは、大きく分けて3つのパターンが多いです。
「大企業の経営」
「起業のための武器」
そして「事業承継」です。
そんな需要に応えるように、事業承継を専門とした先生たちもいるわけですね。
「自分自身が事業承継の実践者だ」という実務家教員の方もいらっしゃれば、
「研究者の立場として、いくつもの企業の事業承継を研究している」という研究者気質の先生もいらっしゃいます。
自分自身が事業承継を経験している先生は、
「親が事業をしてまして……」
と少しでも語る生徒がいようものなら、実践者の血が騒ぐのか、

「親の事業を継ぐんだね! ぜひうちのゼミに来なさい!」
と熱心に勧誘していました。
先生たちの出身 ⑥Ph.D
実務家であるか否かに関わらず、博士号を取得してから教授に赴任される先生も、もちろん多くいらっしゃいます。
ただし、
「アカデミックな世界で経営学の博士号を取得してから教授になった!」
「MBAを取得した後に、働きながら経営学の博士号を取得した!」
というパターンでなく、
「就職する前に工学や情報学などの博士号を取得しており、
なんだかんだあってMBAを取得したのち、大学教授になった!」
の、テヘペロパターンも多いです。

先生たちの出身 ⑦DBA
博士号は博士号でも、「DBA」取得者の先生もいらっしゃいます。
さて、
「『DBA』とはいかなる意味だ?」
と思った方もいらっしゃることでしょう。

青山学院大学では、次のような目的意識でコース分けをしているようです。
Ph.D.コースは、学士取得者を対象とした5年一貫制のフルタイム博士課程です。
これに対し、DBAコースは、MBAなどの修士号を取得したものを対象にしており、働きながら博士を取得することが可能なカリキュラムになっています。
Ph.D.コースとDBAコースでは求められている研究の質も異なります。
Ph.D.取得のためには、自立して研究活動を行なえる理論・実証両面での幅広い分析手法の習得が要求されます。
これに対し、DBA取得のためには、高度な専門性が必要な実践的分野において、独自の着眼点と分析ツールを用いた問題解決能力と洞察力が必要とされます。
青山学院大学 大学院 国際マネジメント研究科
「Ph.D./DBA」より
(2021年4月4日閲覧)
む……
むむむ……
まあ、
「DBAはDBAじゃ!」
「DBAの意味を聞くような者はDBAになれん!」
といったところでしょうか。

鳩の印象としては、
よりアカデミック寄りの、研究者気質が求められるのがPh.Dで、
実務家が知識を深掘りするための資格がDBA、といった感じです。
ゼミの特徴
さて、卒業にあたっては卒業課題(修士論文など)を執筆する必要があります。
というわけで、鳩が通っていたビジネススクールではゼミに配属され、教授から指導を受けることになりました。
ゼミの先生を選ぶときのポイントとして、
「こちらの自意識を粉々に粉砕してくるような恐ろしい先生が好き」なのか……

「優しくも本質を抉るボールをズシっと投げてくる」ような先生がいいか……

その辺は、自身の性質に従って決めることになるでしょう。
また、ゼミの形式ですが、
「月に1、2回、ゼミ生全員が集まって合同ゼミを開く」というパターンと、
「ゼミ生同士の交流は無く、とにかく教授と生徒が1on1を続ける」というパターンがあり、
鳩は前者の合同ゼミの先生を選びました。
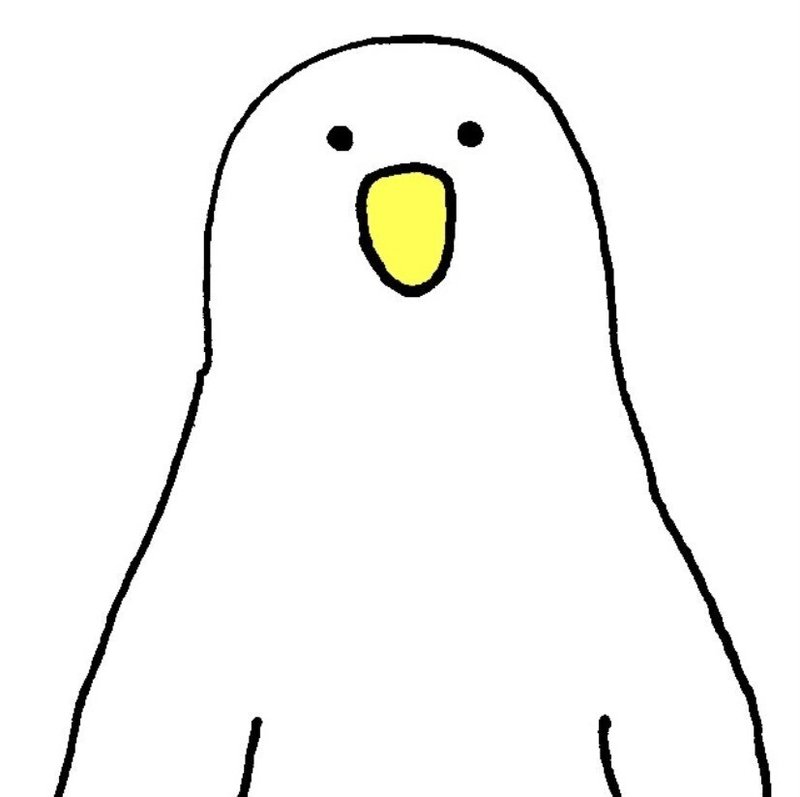
卒業間近にちょうどコロナ禍が広がったこともあり、
どの先生もゼミの進め方はzoomやslackなどを使ってのオンラインでした。
また、合宿を行うゼミもあります。
と言っても、合宿先ではどのゼミもたいてい物見遊山となっています。
費用が「交通費 + 宿泊費 + 現地での実費」の計数万円で済む場合もあれば、
一人あたりうん十万円をかけた一大旅行に連れ出される場合もあるそうです。
一方、1on1の場合、
先生とじっくり話し合えるので、自分の研究したい領域を深掘りするチャンスが多いです。
ただし、教授のテイストで修正が入りすぎた結果、しまいにはほぼ先生が言ったとおりの内容になることもあるそうです。
これを、「自分のオリジナリティが発揮できない……」ととるか、
「なんて楽だ! あざます!」ととるかは、人それぞれでしょう。

また、1on1で指導するゼミではOB/OGとのつながりが持てないため、ビジネススクールを卒業した後は、
「ネットワーキング? 知んねーし」
となることは間違いないです。

一長一短、というところですね。
「自分が一年間付き合うことにある恩師になるわけだから、
『この人でいいや』という惰性ではなく、
『この人がいい」と思える先生は誰なのかをよく考えた方がよい」
ということをおっしゃる教授がいらっしゃいました。
卒業したいまも、恩師とのゆるーいつながりを楽しんでいる鳩としては、納得のいく言葉です。
どの先生を選ぶにしても、自分の人生を豊かにするような選択にしたいものですね!

以上、「どんな先生たちがいたの?」「どうやってゼミを選んだの?」
といった記事でした。
次回、能ある鳩はMBA第25話「合理的経済人に花束を」
お楽しみに。
to be continued...
参考資料
・挿入マンガ①:板垣恵介『グラップラー刃牙 外伝』(秋田書店)
・挿入マンガ②~⑭:山口貴由『衛府の七忍』(秋田書店)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
