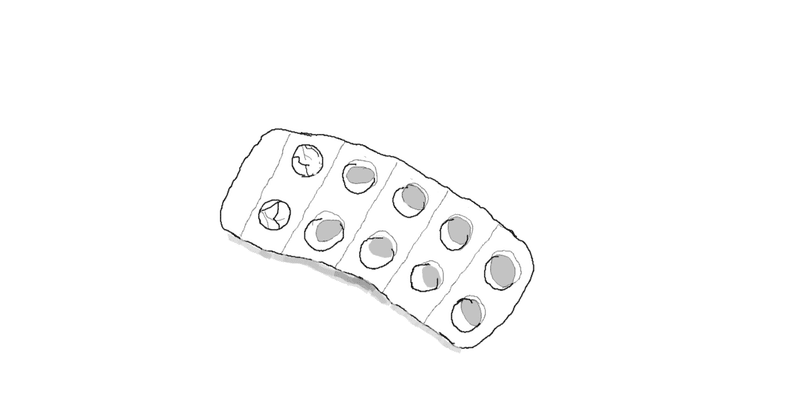
対症療法の難しさ
「薬剤師の処方権」が話題です。超えるべきハードルはいくつもあるように思いますが、基本的な方向性としては賛成です。ただ、SNS等でかなり稚拙な議論が行われていることにはやや辟易しているところです。一部で「対症療法」が軽く扱われているのも気になりました。
対症療法とは
「病気による症状を和らげる、あるいは消す治療」「原因療法、根本治療の対照にあるもの」と定義されることが多いです。
かぜを引いた時に、原因であるウイルスを直接排除できないけれど、咳や鼻汁といった症状を和らげる治療もそうですし、がんに伴う症状や治療に伴う副作用を緩和する治療も対症療法に含まれます。
明確な定義はなく、特にがん領域で用いられる支持療法(surppotive care)や緩和療法(palliative care)との境界線はあいまいです。ここでは主に薬剤を用いた治療を指すことにします。
対症療法の目的は、患者さんの症状を和らげることで患者さんのQOL(クオリティオブライフ、生活の質)を向上させることにあります(これが重要)。
対症療法の難しさ その1 「診断」
適切な対症療法を選択するには、まず「診断」が必要です。可及的に根本的な治療が必要な疾患の可能性を鑑別すべきなのは言うまでもありませんよね。稀だったり非典型なケースもあり、そう一筋縄ではいかないわけですが、医学部教育から研修期間を経て我々は体系的な教育、経験を積んでいきます。少し脱線しますが、可及的に根本的治療が必要な疾患か見分ける一つのポイントとして症状のonsetを確認することがあります。「突然はじまった」というwordが重要なことはその通りですが、何をしている時に始まったのか(症状の始まりが急峻か)、どのくらいで最強点に達したのか、など症状の立ち上がりを事細かに聴取することが重要です。3日前からの症状でも、はじめの症状の立ち上がりが急峻なものには致死的な疾患が隠れていることがあります。
診断名が確定しなければ対症療法ができないわけではありません。実際「風邪」は根本的治療を行わなくても自然に回復することがその定義ですので、風邪だと確定診断する前に対症療法を行なっているわけです。ただ、適切な対症療法を選択するには、その病気の「想定される機序」を診断することが大事です。たとえば痛みの原因がまだ十分に鑑別できていなくても、それが骨や筋由来のものか、神経由来のものか、内臓由来のものか、少なくともある程度あたりをつけて対症療法薬(この場合は鎮痛薬)を選択するわけです。
対症療法の難しさ その2 「エビデンス」
実際のところ、きちんと臨床試験が行われて十分なエビデンスが集積された対症療法は少ないです。たとえば変形性関節症に対してNSAIDsは有効ですが、特に高齢者では長期使用によるリスクがあり、しばしばアセトアミノフェンが用いられていますが、OARSIガイドライン(Osteoarthritis and Cartilage, 2019)ではメタ解析の結果が引用され、その使用が推奨されていません。また成人の風邪における鎮咳薬の使用についても明確なエビデンスはありません(参考:Treatment of the Common Cold. American Academy of Family Physicians)。エビデンスがない、あるいは却下されたにもかかわらず実臨床で処方されている薬は多いです。
対症療法の難しさ その3 「教育」
先に述べたように、我々は医学部教育を通して疾患の病態、鑑別、治療を学習しているわけですが、対症療法について学ぶ機会はほとんどありません。自分で積極的に勉強する以外だと、多くの医師は耳学問や先輩の処方を学ぶ形で経験的に習得するのみです。このため医師によって「好み」の対症療法薬が異なるという事態になっているのです。一方支持療法、緩和ケアに用いられる薬に関しては、少しずつエビデンスが集積されていたり、学習する機会が設けられるので比較的均一な治療が提供されているはずです。
どう選択する? クスリはリスク
エビデンスが乏しいとはいえ、症状をどうにかしてほしいから病院を受診する患者さんが多いわけで、何も処方しないというわけにはいかないことも多いです。
これは個人的な意見ですが、選ぶべき対症療法薬は基本的に「シンプル」であるべきと考えています。たとえば風邪では咽頭痛、鼻汁、咳、倦怠感、発熱、頭痛などなど複数の愁訴が混在していますが、それらすべてに対症療法を行う必要はありません。繰り返しますが対症療法の目的はすべての症状を消すことではなく、患者さんのQOLを改善することにあります。複数の作用の薬を併用することは相加ないしは相乗的に薬の副作用リスクをあげてしまったり、作用を弱めてしまう可能性もあります。風邪のようなself-limited(医自然軽快する)疾患であればなおのこと、その時点で一番強い、QOLを低下させている愁訴に注目し、これを緩和することを目指すべきと考えます。総合感冒薬の使用などもってのほかです。
(逆に1つの方剤で複数の愁訴を改善する(かもしれない)漢方薬に魅力を感じます。これもエビデンスはほとんどないに等しいので、あくまで他の代替治療がない場合に限りますが)
対症療法薬にエビデンスは必要か?
最後に挑戦的なタイトルをぶち上げました。まあもちろんあったほうがよいと思うのですがそういうことではなく。症状というのは患者さん自身の「自覚」に依るところが少なからずあり、たとえば同じような重症度の同じ疾患に罹患しても患者さんによって訴える症状には大きな差があることは想像に難くないでしょう。あるいは明確な原因が存在しない(見つからない)病態もあります。特にこうした場合には薬のもつ「プラセボ(偽薬)効果」が非常に重要です。薬を処方するという行為、薬の形、におい、そのものが治療になりうる場合があるわけです。対症療法薬の効果を高めるために、あえてプラセボ効果を高めるようにお話しすることもあります。毒にも薬にもならないようなものをあえて処方し、「プラセボ100%」で治療している場合もありますので、患者さんに「この薬なんで飲んでるの?」とか「もういらないんじゃない」とか言わないで欲しい場合がありますので、その辺はお察しください。
対症療法に必要なことは
1)診断、見立て
2)できればエビデンスのある薬を選択する
3)なるべくシンプルな処方を
4)プラセボ効果を最大化する
の4つだと考えています
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
