
[書評]ナグ・ハマディ文書抄
新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄 (岩波文庫、2022)
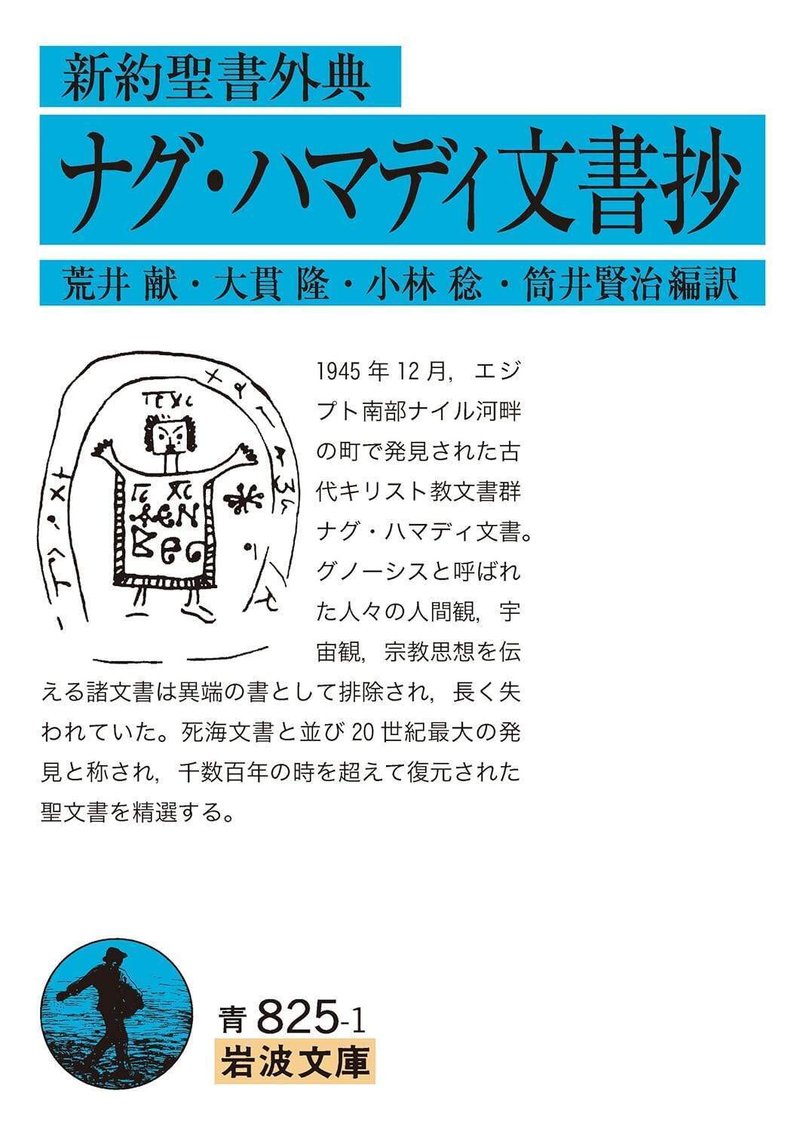
興味の尽きない本——ユダ、AJ、トマスが一冊で読める
充実の一冊
読みごたえがある。興味が尽きないおもしろさがある。
文庫本一冊の手軽さでユダの福音書、ヨハネのアポクリュフォン(AJ)、トマスによる福音書が読めるのはありがたい。
とりあえず、セツ派グノーシスに関心ある人は、これ一冊を熟読すれば足りる。充分のみこめたら、それ以外の文書に赴けばよい。
*
説明のない文献
この一冊でほぼ基本的な理解ができるように編集が工夫されているが、一つだけ何の説明もなくある文献が言及されており、そこだけは苦言を呈したい。その文献は、巻頭の「諸文書略号表」にも記載がなく、参考文献にも含まれない。のみならず、知る限りでは邦訳もないので、読者には手がかりが殆どないと思われる。
ピスティス・ソフィア
それは、トマスによる福音書の注に出てくる『ピスティス・ソフィア』だ(302頁)。ナグ・ハマディ文書の発見(1945年)まではグノーシス主義で最重要の文献の一つと言われた書(『ピスティス・ソフィア』を含む写本[Askew Codex]の発見は1772年だが、出版はコプト語原文が1851年[ラテン語訳付き]、最初の仏訳が1895年、ラテン語からの英訳が1896年)なので、簡便でよいから説明がほしい。
*
トマスによる福音書の10
おそらく、本書の読者はこの注の意味が不明と思われるので、少しだけ書いておこう。
トマスによる福音書の10は本書で次のように訳される。
イエスが言った。「私は火をこの世に投じた。そして、見よ、私はそれ(火)を、それ(この世)が燃えるまで守る」。
これに対する本書の注は次のとおり。
ルカ一二49、『ピスティス・ソフィア』一四一参照。
つまり、この二つの書を参照せよ、の意だ。
ルカによる福音書12章49節
前者は比較的簡単だ。ルカによる福音書12章49節を参照すればよい。
「私が来たのは、地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらと、どんなに願っていることか。」(聖書協会共同訳)
トマスとルカの違い
参照箇所を見つけるのは簡単なのだが、ルカのこの箇所の後半には引っかかる。〈その火がすでに燃えていたら〉とは、その火がまだ燃えていないということだ。だとすると、トマスによる福音書の10とは矛盾する。
その点について、本書でトマスによる福音書の訳を担当した荒井献は自著『トマスによる福音書』(講談社学術文庫、1994)の当該の箇所で次のように記す。
ルカにとって終末におけるキリストの審判は遠い未来の事柄なのである。これに対して、トマス本文ではイエスの「火」はすでにこの世に投じられた。伝承史的には、トマス本文がルカ本文に先行する可能性がある。(138頁、強調は荒井)
これを読むと、この箇所について新たな問題が浮かびあがる。第一に、新約聖書の正典であるルカによる福音書より、トマスによる福音書が先行する可能性があること。これはおおごとである。トマスによる福音書を「外典」と言って閑却する余裕はなくなる。
第二に、イエスの「火」の意味が、トマス本文とルカ本文とで異なること。荒井によれば、ルカのいう「火」は、〈来たるべき終末の時に「地」を焼き尽くす火〉を指し、一方、トマスでいう「火」は〈究極において「御国」=本来的「自己」支配と同義〉であるという。
この荒井の説明はむずかしい。これを理解するためにはグノーシス主義の宇宙観を知る必要がある。ごく簡潔に述べれば、トマスにおける「この世」(kosmos)とは、否定すべき宇宙のことである。したがって、評者の考えでは、ルカは「地」について、トマスの「この世」の意味を理解していなかった可能性がある。
ピスティス・ソフィア四141
さて、もう一つの参照先、後者の『ピスティス・ソフィア』一四一とは、どのようなものか。荒井著『トマスによる福音書』にはここで『ピスティス・ソフィア』の言及はない。本書の元になった『ナグ・ハマディ文書 Ⅱ』(岩波書店、1998)の注は本書と同じであり、そこにも参考文献として『ピスティス・ソフィア』は挙げられておらず、どういう版が念頭にあったのか不明である。
Carl Schmidt版
仕方ないので、手許の版(Carl Schmidt, ed, 'Pistis Sophia', Brill, 1978)の当該箇所(Book 4, Chapter 141)の英訳(Violet MacDermot 訳)を参考までに引く(原文はコプト語)。
Jesus . . . said to his disciples: "Truly, I say to you, when I came I brought nothing to the world except this fire and this water and this wine and this blood."(大意——イエスは弟子たちに言った。「まことに言う。私が来たとき、この世にもたらしたのはこの火とこの水とこのぶどう酒とこの血のみである。」)
トマスによる福音書の114
なお、これ以外に、トマスによる福音書の114の注にも『ピスティス・ソフィア』への言及がある(313頁)。そこも参考までに見ておこう。
トマスによる福音書の114は本書で次のように訳される。
イエスが言った。「見よ、私は彼女(マリハム=マグダラのマリヤ)を(天の王国へ)導くであろう。」
これに対する本書の注は次のとおり。
マリ福17 7—18 15、『ピスティス・ソフィア』一36、二72参照。(313頁)
つまり、『マリヤによる福音書』と『ピスティス・ソフィア』の二書を参照せよ、の意だ。
前者は、『ナグ・ハマディ文書 Ⅱ』(岩波書店、1998)に収められている。
後者は、トマスによる福音書の10の注の場合と同じく、『ピスティス・ソフィア』への言及だが、箇所の指定の仕方が少し違う。ここでは一36、二72というように、『ピスティス・ソフィア』を四書に分けた場合の書番号が前置されている。MacDermot 訳では Book 1, Chapter 36, および Book 2, Chapter 72 に相当する。なお、MacDermot 訳の『ピスティス・ソフィア』第一書、第二書については、Schmidt 編の書とほぼ同じ英訳が Violet MacDermot, 'The Fall of Sophia' (Lindisfarne, 2001) にも収められている。しかし、第三書と第四書、およびコプト語原文については、Schmidt 編の書を見る必要がある。
*
本書が収める6つの書
本書が収めるのは、次の6つの書だ。
①イエスの知恵
②ペテロの黙示録
③ヨハネのアポクリュフォン
④トマスによる福音書
⑤エジプト人の福音書
⑥ユダの福音書
この配列は本書の編集者たちが意図した順序があると思うが、評者は、そもそも、先に普及版を読んだユダの福音書を次に読むなら、本書のような聖書学者の翻訳をと思っていたので、⑥を先に読み、続いてセツ派グノーシス主義の教科書と言われる③を読み、そのあとに、⑤、④、②、①と読んだ。
イエスの知恵の配列に疑問
結論から言えば、ナグ・ハマディ文書の「精選」と銘打つなら、①をここに、しかも巻頭に入れた理由には首をかしげる。読者はこれを最初に読むと、いったいこの本は何だ、とならないだろうか。本書を読み終わった評者には、いまだに①がここにある理由が分らない。それほど、①は、何が書いてあるのか、つかみにくい。①は、『エウグノストス』と比較しながら読まなければ、何が書いてあるかはっきりしないのではないか。
①を除けば、本書は熟読に値する。本書だけで、ナグ・ハマディ文書の何たるかについて(重要な『フィリポによる福音書』が分量の関係で入っていないとはいえ)、読者は思索を深めることができる。
*
ここでは⑥と③について、少し書いてみる。
ユダの福音書
⑥ユダの福音書
結論からいうと、普及版『原典 ユダの福音書』(日経ナショナル・ジオグラフィック社、2006)が、英訳からの日本語訳であることを差引いても、本書(コプト語原文からの日本語訳)とは、翻訳として違う部分が多い。したがって、あらためてユダの福音書の謎が深まった感じがある。
一つだけ例を挙げると、本書ではユダがイエスへの告白として〈あなたはバルベーローの不死なるアイオーンから来たのです〉と語る(408頁)。それが普及版では〈あなたは不死の王国バルベーローからやって来ました〉となっている(27頁)。両者は印象がかなり異なる。普及版のほうはすんなり分った気になるが、本書の表現だとグノーシス主義そのものの表明になっており、その宇宙観と否応なく向き合わざるを得なくなる。評者の旅の元々の出発点『光のラブソング』をより深く理解するには、本書のほうが向いているのかもしれない。
バルベーロー、アイオーン、対
本書はバルベーローについて、巻末の用語解説で〈いくつかのグノーシス主義救済神話において、至高神の最初の自己思惟として生成する神的存在〉と説明する(499頁)。
また、アイオーンについては、〈グノーシス神話では至高の神的「対」から流出し、「プレーローマ」の中に充満する、擬人化された神的存在〉と説明する(474-475頁)。
以上の説明に加え、対についての〈プレーローマの至高神が自己思惟の主体と客体に分化して、さまざまな神的存在(アイオーン)を流出する。それと共に原初的な両性具有(男女=おめ)の在り方も男性性と女性性に分化し、男性的な神的存在と女性的な神的存在が一つずつ組み合わされて「対」を構成する〉という説明をあわせ読むと、イメジがはっきりする(494頁)。
AJ(ヨハネのアポクリュフォン)では、プレーローマの至高神を「万物の父」、バルベーローを「万物の母胎」と呼ぶことが、以上の説明を頭に入れると了解される。
ヨハネのアポクリュフォン
③ヨハネのアポクリュフォン
グノーシス主義の体系をひととおり頭に入れるには最良の書。みごとに構成されており、この基準書との偏差で各グノーシス文書を捉えると分りやすい。
*
「グノーシス主義」の定義
本書には(キリスト教)グノーシス主義文書および新約聖書外典文書が収められているが、「グノーシス主義」とは何かについて、巻末の荒井献「ナグ・ハマディ文書とグノーシス主義」に、興味深い国語辞書の定義が引かれている。
〔ギリシャ gnōsisは「認識」の意〕
一、二世紀頃地中海沿岸諸地域で広まった宗教思想、およびこれに類する考え方。反宇宙的二元論の立場にたち、人間の本質と至高神とが本来は同一であることを認識することにより、救済、すなわち神との合一が得られると説く。マンダ教やマニ教はその代表的宗教形態。(大辞林、第二版)
手許にある大辞林の第三版を見てみたら、同じ内容であった。鋭い定義だが、〈反宇宙的二元論〉がやや分りにくい。この点について、荒井は〈負としての宇宙を形成する原理(宇宙形成者、ギリシア語で「デーミウールゴス」)に相対立する正としての宇宙を救済する原理が前提されていることになる〉と説明する(464頁、強調は荒井)。
実際にグノーシス文書を読まずにこの定義だけ読んでも意味がつかみにくいが、本書に収められた諸文書を手がかりにすれば、具体像がうかんでくるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
