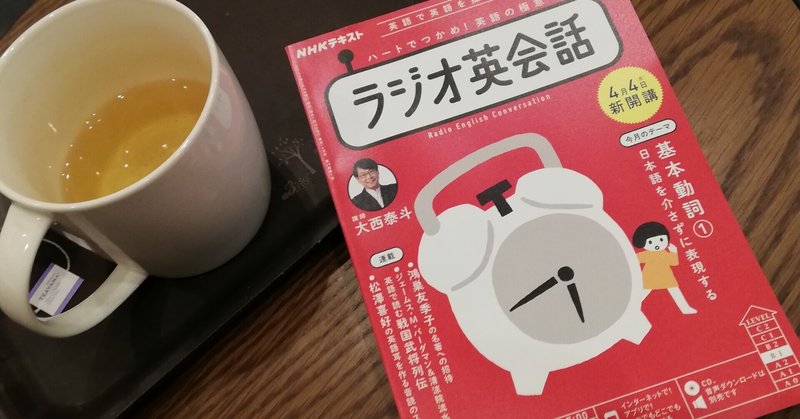
ラジオ英会話
先月から「ラジオ英会話」を、平日毎朝聴いている。
英会話を学ぶのは、観光案内所でバイトしてた時以来だから、7年ぶりくらい……いや、もっとブランクがあるんじゃなかろうか。当時は「業務に必要だったから」学んでいたけれど、今回はちょっと違う。そもそも「学ぶ」という感覚すらない。聴き始めた理由は、日本語を忘れたいから。
御縁あって、今年から編集職に復帰した。毎日、辞書や「記者ハンドブック」とにらめっこしながら仕事をしている。日中は記事のこと、文章のこと、日本語のことばかり考えてしまう。
パソコンに向かっている時はもちろん、外出していても「ああ、あの記事のあの表現、事務所に帰ったらちょっと直そう」と、四六時中文章のことが脳内をぐるぐるしている。それを思考するのも当然日本語。校了日の帰路は「日本語疲れ」でヘトヘトになってしまうこともある。ヘタをすると、帰宅後も、昼間書いた文章のことを思い出してしまい、気持ちだけが草臥れる。
これはいけない。「日本語疲れ」を自宅にまで持ち込むのは、メンタルによろしくない。仕事以外の時間は、仕事の文章のことは忘れたい。何か、思考を切り替える〝スイッチ〟が欲しい。ふと浮かんだのが「英語」だった。日本語に疲れてしまうのなら、言語そのものをスイッチしてしまえばいいのではないかと考えた。
とはいえ、仕事で使うわけでもないし、誰かとのコミュニケーションを目的にしているわけでもない。英会話教室やウェブレッスン、そこまでは必要ない。気分転換(言語転換?)に、大金はかけたくない。
そんな時に放送していたのが、朝ドラ「カムカムエヴリバディ」だった。そうか、ラジオという手があったか。
しかし飽きっぽい私のこと、継続できるだろうか。……いや、別に継続を前提にしなくてもいいんじゃないか? 誰に強制されるわけでもなし、目的は「ただの気分転換」なのだから、聴きたいときに聴けばいいのではないか。むしろ最初から「続けるぞ!」と意気込んでいたから、これまで継続できなかったんじゃないのか。気軽に始めて、楽しければ続ければいい。つまらなければ、必要がなくなれば、やめたっていい。そう考えを改めた。
数あるラジオ英語学習番組の中から選んだのが「ラジオ英会話」だった。
理由は2つ。講師が大西泰斗先生だから。単純に自分が聴きやすい放送時間だから。
その昔英語学習をしていた時、大西先生の一般向け単発英語講座に参加したことがある。先生は講義中、セミナールームを歩いて回り、私が自分の机の上に置いていたペットボトルを手に取り、シャカシャカシャカと振って何事もなかったように戻していった(炭酸飲料でなくてよかった)。印象深い先生だ。お顔も存じ上げない先生よりは、こちらも聴く気が起きる。
そして、放送時間。性格的に「まとめて聴く」とか「聴き逃しを利用する」とか、絶対にできない。その日の放送は、その時間にリアルタイムで聴きたい。朝と夜、家で聴ける時間帯に放送する番組を選んだ。
私の「ラジオ英会話」利用方法は、以下の通り。
▽朝晩リアルタイムで聴く。
▽朝の放送では英文の発音を確認するだけ(時々睡眠学習……)。
▽行き帰りの通勤電車内で、テキストを見ながらボソボソ発音練習。電車内なので、当然声は出さない。マスクの中で口を動かすだけ。「ドラゴン桜」で「ボソボソシャドーイング」という学習法があった。あんなカンジ。これを往復15分間ずつ(計30分)。
▽夜の放送ではシャドーイングをやる。文法事項もさらっと確認。
▽余力があれば、日曜日の再放送を聴いて復習。
▽予習は絶対にしない。
▽買うのは毎月のテキストだけ。それ以外(他の教材や音源CDなど)は買わない(お金をかけてしまうと心理的に余計な負荷がかかる)。
5月に入り、「ラジオ英会話」を聴き始めて1か月が経った。
気分転換が目的なので、英文を憶えることはしていない。テキストを見ながら英文を音読して、そこそこつっかえずに読めたら、それで御の字。ちょっとした成功体験だ。
「日本語を忘れる 」という点で一番効果的なのは、帰りの通勤電車内のボソボソ発声練習だ。職場の最寄り駅に着いたら、電車の待ち時間にテキストを開き、ボソボソ開始。15分間無心に、英文だけを繰り返しボソボソすることで、一時的にでも昼間書いた文章のことは忘れられる。リフレッシュできている、と思う。目的は達成されている。
いつまで続くかわからない。でも、やめたらやめたで「リフレッシュが必要なくなったんだな」と理解したい。もしくは「ラジオすら聴けなくなるほど、仕事に疲弊した」場合か(絶対にいけない。仕事を辞めた方がよろしい)。
誰からも強制されずに、自分で始めたこと。「学習」と思わず、楽しく、ただひたすらに楽しく。こういう英語との付き合い方もある。
いただいたサポートは、旅の軍資金として大切に使わせていただきます。次の旅を支えてくださると嬉しいです。応援よろしくお願いします!
