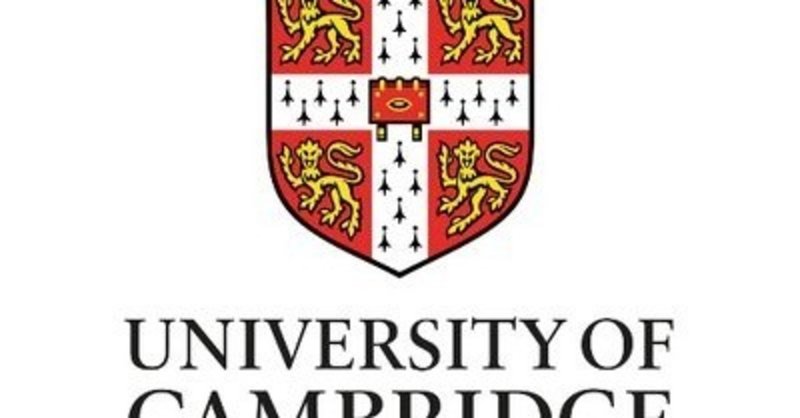
ケンブリッジ大学の裏側 2
Hello, みろろんです。今日は七夕ですね。しかしイギリスは雨。星は期待できそうにありません・・・。
前回に引き続き大学の裏側を振り返りました。
ケンブリッジ大学で働いて見えたこと。それは学生のカリキュラム。
1.留学生の多さ
私は働き始めて気づいたことはまず留学生が3分の1くらいいること。学部1年生の時からそのくらいで、大学院レベルになるともっと多いと思います。きっと優秀なんだろうなと思った通り、地元(イギリス)の学生より優秀な人が多く、勉強熱心でした。
2.学期の短さ
意外だったのは、以上に授業時間(term)が短いです。秋から始まって、春、夏の学期があるのですが、それぞれ8週間しかありません。ちなみに他の大学ではAutunm term、とか季節を表す言葉なのですが、Michaelmas (ミコノス)(running from October to December), Lent (January to March) and Easter (April to June)と言います。これは他のイギリスの大学では類にみない短さです。優秀な人はもう勉強しなくていいのでしょうか? 他と比べて学費を多く払っていることになるのですが、納得しているのでしょうか?私は学生の休暇中も仕事なのであまり関係ありませんが心配してしまうほど短く感じました。
3.ユニークな指導方法
ケンブリッジ大学化学科では、チューター制があり、大学院生や研究に来ている外国人が学部生を教える機会があるのですが、それが私にとってすごく新鮮でした。数学などは4,5人のグループに分かれ、それぞれに先輩(大学院以上)が教えるのです。しかも場所は図書館やデパートメントの公共施設のテーブル。しかもその先輩のほとんどは外国人!奨学金では賄えない小遣い稼ぎなのか、優秀だから外国人なのか。イギリスの最高学府ともいえる大学生を教えているのが外国人、というのが何か滑稽に思えていました。
4.Visiting scholarが世界中から集まってくる素晴らしい環境
これには本当に助けられました。なぜって?日本人の研究者の方々がたくさんいるからです。
学部生にも日本人は少なくもいましたが、みんな若い!(あたりまえ)私は1年や、2,3年で来られるVisiting scholarの方や、ポスドクといわれる方々といろいろ知り合いになり、最先端の研究や、悩みなどを共有できたのはとても貴重な体験でした。日本人が少ないので異種の方(化学科以外)との交流もさかんで、いろいろな分野の第一線で活躍されている人の話はとても楽しく、またたくさん友達になることができました。
日本人だけでなく、世界中の人と知り合えるのも楽しかったです。はやり仲良くなるのは特定の国なのか、私はイタリア人と仲良くなり、彼が帰国した後も遊びにいくほどでした。
また、ノーベル賞を受賞した野依先生にも講演でお会いすることができ、日本にいたら会えない人ともお話しする機会がありました。
しかし私は研究者としている訳ではなく、ただの(というと語弊がありますが)職員。話した後に
「何してるの?」
と聞かれ、technicianです、というと
「あ、そう」
とそれで会話が終了することもたくさんありました。
よろしければサポートをお願いします。サポートしていただければ、現教員、学校に苦手意識のある生徒さんへの支援に使わせていただきたいです。
