
< 時遊人、余暇・趣味の愉しみ>8
8 エッセイの愉しみ
随筆とは、文学における一形式で、筆者の体験や読書などから得た知識を元に、それに対する感想・思索をまとめた散文です。随想、エッセイなどともいう。随筆は、思いつくままに自由な形式で書いた散文のことで、日本では文学の一形式として昔から親しまれてきました。歴史に残る最古の随筆は、十世紀末に書かれた清少納言の「枕草子」だとされています。清少納言は、独特の鋭い観察眼と、女性らしい細やかさで貴族の日常生活を綴っています。またその後も随筆文学は、鴨長明の「方丈記」、吉田兼好の「徒然草」、本居宣長の「玉勝間」、松平定信の「花月双紙」などの傑作が連綿と続いております。その中でも徒然草の冒頭、「つれづれなるままに、日ぐらし、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば~」はあまりに有名で、このままで「随筆」の定義になっています。
エッセイはどうかというと、十六世紀に出版されたモンテーニュの著書「随想録」を起源とするのが定説で、フランス語のエセイユ(試みる)の名詞形「エセー」に由来するそうです。当時、文芸のジャンルにエッセイに類するものはなく、モンテーニュが初めて、「主観的で私的な事物の考察と、内面の探求」を書く試みをしたとされています。
起源だけでみると「エッセイは随筆と同じじゃないか」ということになりますが、ヨーロッパには「エッセイ」という文学ジャンルはありません。本家のフランスではその後、「エッセイ」があまり発達しなかったのです。
随筆とエッセイのもう一つの違いは、エッセイが随筆に比べて論文に近いニュアンスがあることです。そのことは、アメリカに渡って発展した「エッセイ」に如実に表れています。アメリカでは、学校教育で「エッセイ」の書き方をしっかりと学びますが、これは日本でいうエッセイでもなければ、いわゆる作文でもありません。ここではエッセイは、自分の意見を発表するための文章で、日本の小論文に相当するものです。
日本のエッセイでは、自分自身の体験と情趣豊かな表現が大切になりますが、アメリカでは相手を説得し、納得させるものでなくてはなりません。当然ながら、両者はテーマ選びから展開法、表現に至るまで異なってきます。このように同じエッセイという言葉でも、内容はいろいろです。
最後にエッセイの意味を整理しておこう。エッセイは、狭義には「随筆」「散文」「随想」「感想文」などを指しますが、広義では「小論文」「試論」「評論」などを含んだ概念となります。随筆とは、本当にあった出来事の 見聞や感想を自由に描いたもの。エッセイとは、出来事の描写ではなく、書き手の パーソナルな心の様子を描いたもの、告白的なものであるということです。
筆者はどちらかというと、知的な作業で小論文を書くようなエッセイが好きです。最近はエッセイコンテストに応募する愉しみを味わっています。認知症にならないよう、頭脳を働らかせ、パソコンで指を動かして書いています。結果はほとんど駄目ですが、書いている過程が楽しく、その過程を大切にしようという考えです。自己表現を最期までしたいと思います。
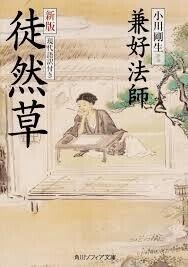

(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
