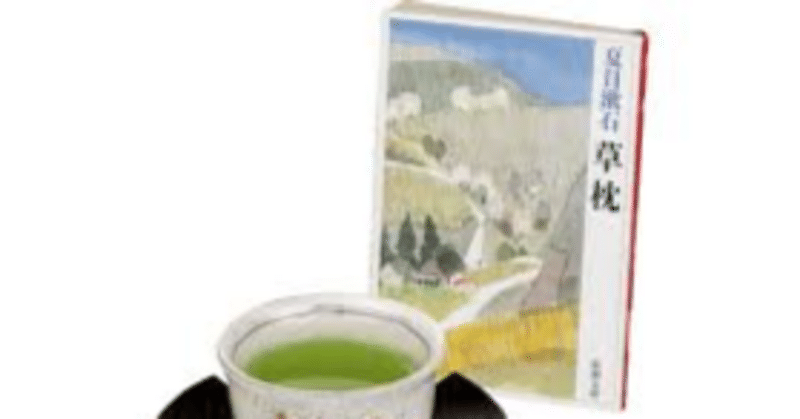
夏目漱石の名作に登場するお茶・紅茶への思い 3
Ⅰ 漱石とお茶 3
❸『琴のそら音』
『琴のそら音』は1905年に雑誌『七人』に掲載された短編。迷信好きのお婆さんと住む主人公が幽霊を研究している友人の津田を訪ねます。婚約者がインフルエンザだというと、津田から最近インフルエンザから肺炎になって死んだ親戚の若い女性の魂が出征中の夫に会いにいったという話を聞きます。その帰り道で出合う葬式や犬の遠吠えの声にだんだん不吉な予感が……という話です。
漱石は若い頃から禅宗に興味を持ち、27歳のときには、鎌倉にある円覚寺で参禅したこともあります。禅といえばお茶。禅院の生活には喫茶の習慣が溶け込んでおり、「喫茶去(まあ、お茶でもおあがり)」という禅語もあるほどです。そして、漱石の小説の中では、お茶を飲むことが、しばしば日常の象徴として描かれています。
『琴のそら音』で、友人の家で怪談話を聞かされた主人公。だんだん怪しげな、非日常な雰囲気が深まっていくなか、友人の「まあ、お茶でも飲もう」という一言が日常を象徴する役目を担っています。
「余はわざと落ちつき払って御茶を一杯と云う。相馬焼の茶碗は安くて俗な者である。もとは貧乏士族が内職に焼いたとさえ伝聞している。津田君が三十匁の出殻(でがら)を浪々(なみなみ)この安茶碗についでくれた時余は何となく厭(いや)な心持がして飲む気がしなくなった。」(『琴のそら音』)
解説
不吉な話を聞き、平常心を取り戻そうとお茶を飲もうとする主人公。しかし、友人の淹れたお茶を彼は飲めません。安い茶碗になみなみとつがれた出がらしのお茶は、学生時代からの気のおけない友人との関係と日常性の象徴を表しています。お茶を飲めないことで、徐々に不安に飲み込まれ、日常の判断力が揺らいでいく、主人公の動揺がうかがえるシーンです。(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
