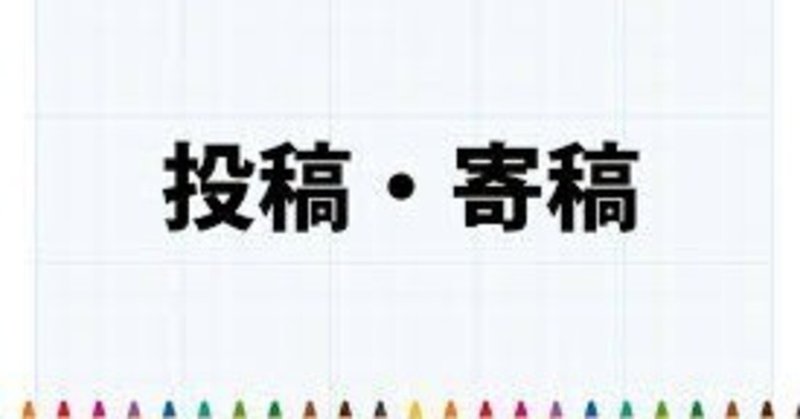
マイ 投稿・寄稿 13
13 「半農半X」、「二刀流」の生き方の理想郷
二〇二三WBCで侍ジャパンが世界一になり、MVPは前例のない「二刀流」で大活躍し、アメリカ・メジャーリーグでア・リーグのホームラン王とMVPを獲得するなど活躍を続ける大谷翔平でした。
二刀流は、「Two-sword style」、「Two-way player」、 「Dual-wielding style」などの英語訳があります。
二刀流の基をたどると宮本武蔵に遡ります。江戸時代初期に大名家に仕えた剣術家・芸術家で、兵法書『五輪書』の著者。「二天一流(二刀一流)」の開祖です。
私の実家は兼業農家(半農半X)で、父は米作農業と旧国鉄の線路保全や除雪組合長を、母は野菜栽培と行商をしていました。半農半Xとは、農業収入に兼業収入を加えて生計をたてる「二刀流」の生活を指す言葉で、塩見直紀が1990年代半ばに提唱し、「持続可能な農ある小さな暮らしをベースに、「天与の才」(X=天職、使命、生きがい、大好きなこと、ライフワークなど)を世に活かす生き方」と定義づけました。
鶴岡には農業と他の仕事を組み合わせた暮らし方が元々あり、夏は米作りで冬は酒造り、山伏、地産地消の農業と民宿や商業などに従事する人や移住者が多くいます。
国では「働き方改革」を2019年に施行し、長時間労働の是正やテレワークなどの施策を講じていますが、新型コロナウィルスの感染拡大で在宅勤務・テレワークの普及が一気に進み、都心から地方への移住や二拠点生活を考える人も増えました。
最近は、企業が副業を認めたり、公務員にも副業として農業を勧める自治体が出てきました。専門性を2つ以上持つ働き方・生き方「二刀流」の時代の到来です。
知の巨人・荻生徂來の「徂徠学」は古文辞学ともいわれ、古い辞句や文章を直接読む(素読する)ことで後世の註釈にとらわれず孔子の教えを研究しようとする学問です。
優れた人材育成を目的に、庄内藩酒井家九代目(藩主として七代目)・酒井忠徳が創設した藩校「致道館」(論語の「君子ハ学ビテ以テソノ道ヲ致ス」が原典)は鶴岡公園近くにあります。その名を冠した中高一貫校「県立致道館中学校・高校」が来年開校です。
庄内藩では徂徠学を教学とし、自主性を重んじた教育方針で、質実剛健な教育文化の風土を育む土壌を作りました。その教育風土と気質は、明治の政治家で漢学者、佐賀県出身の副島種臣に「沈潜の風」と評されました。「沈潜」の語は、儒教の経書の1つである『書経』や『中庸』にあります。副島が庄内を訪れ『詩経』を講じた時、「庄内は既に徂徠学を抜け出て庄内学です」と語り、庄内には藩祖以来「沈潜の風」があると述べました。「沈潜の風とは強情っ張りが芯になり、華やかなことはせずじっと底に潜み、自分の教養を高めることで、そこには反骨精神が生まれること」(犬塚又太郎の「庄内人の風格について」)だといいます。「花よりも根を養う」が庄内人の生き方だそうです。こうした教育風土の中で、「文の達人」など多くの優れた文人が輩出しています。
港町で商業都市・酒田は近代的な「進取の風」といわれます。鶴岡の「沈潜の風」を融合し、根も花も養う「二刀流」を今後目指したい。
米どころ庄内平野は豊かな自然や食に恵まれ、歴史・文化遺産を持ち、さらに慶應義塾大学先端生命科学研究所や山形大学農学部など、産官学連携のバイオテクノロジー(生物工学)研究施設と企業が鶴岡サイエンスパークを形成。宿泊施設や子育て施設も集まる次世代の知的産業振興の街づくりが進行しています。
かつて世界経済の中心が農業から工業へと変革した産業革命がありました。18世紀末以降、石炭や水力を利用した蒸気機関による軽工業の機械化である第一次産業革命が起こり、20世紀初頭に石油や電力を用いて大量生産する第二次産業革命、1970年代初頭に電子工学や情報技術で自動化する第三次産業革命が続きました。
そして現代、IoT(Internet of Thingsモノのインターネット)やAI(人工知能)が高度な知的活動を担う第四次産業革命が起き、世界共通のインターネットが生活基盤の在り方を変えています。
近未来に起こるであろう第五次産業革命は、情報通信技術とバイオテクノロジーの融合「二刀流」です。世界に発信し、相互に交流できる「デジタル田園都市」を目指す鶴岡は定住・移住の未来都市、理想郷といえましょう。
(『鶴岡タイムス』2023年12月15日号掲載) (つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
