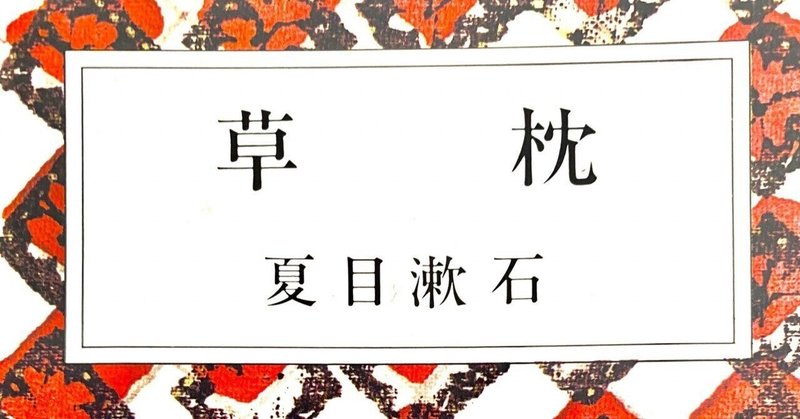
『草枕』、著作の裏側など 13
13 羊羹 3
もともと羊羹は、「羊の肉を具にしたとろみのある汁物」の意味でした。日本に汁物の羊羹が伝わったのは、鎌倉時代以降だといわれていて、禅僧が点心の際に出した料理でした。しかし、禅の影響を受けて肉類を使わず、小豆やその他の豆を使ったものになりました。饅頭も同様に、中身に肉などを使う中国とは異なり、植物性の餡が使われました。これが、羊羹や饅頭などが和菓子として発展していくもととなりました。
室町時代の儀礼書『小笠原礼書』には、汁物(羹)として、汁に粉を入れて蒸し固めたものが登場しています。点心であった羊羹は、饗宴の料理として使われるとともに、茶会の菓子としても使われるようになります。この辺りから、羊羹がお菓子の世界に入り込み、寒天が発見されて、甘みの強い練羊羹へと進化したのではないかと考えられています。
蒸し羊羹が主流だったお茶受けの菓子は、寒天を使った練り羊羹だと日持ちがする上に美味しくなり、食感が良くなるために、練り羊羹が好まれるようになりました。『嬉遊笑覧』には、「寛政(1789〜1801)の頃、紅粉や志津磨(どちらも地名・江戸日本橋の近く)が初めて製す」と書かれています。
『東京百事便』には「藤村 本郷4丁目」として「練り羊羹をもって有名なり。そのほか大徳寺は茶人の好むものにて田舎饅頭は一般下戸の喜ぶ菓子なり」とあります。
「藤むら」は、もともと加賀の菓子舗でした。加賀百万石の前田利家は、豊臣秀吉が催した茶会で供された羊羹に括目し、金沢の地で羊羹を創るよう、金戸屋の忠左衛門に命令しました。忠左衛門は、40年にわたる苦心の末、三代藩主・利常の時代にようやく独自の羊羹を完成させます。
利常から「濃紫の藤にたとえんか、菖蒲の紫にいわんか、この色のこの香、味あわくして格調高く、藤むらさきの色またみやびなり」との絶賛を受け、金戸屋は藩の御用菓子司になります。
宝暦4年(1754年)、加賀十代藩主・重教の江戸出府に従い、金戸屋は江戸の加賀藩邸前に店を移転しました。その際に、羊羹の色に因んで「藤村」と名乗り、店の屋号を「藤むら」としています。しかし、現在、本郷の「藤むら」は、店を閉めてしまいました。 (つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
