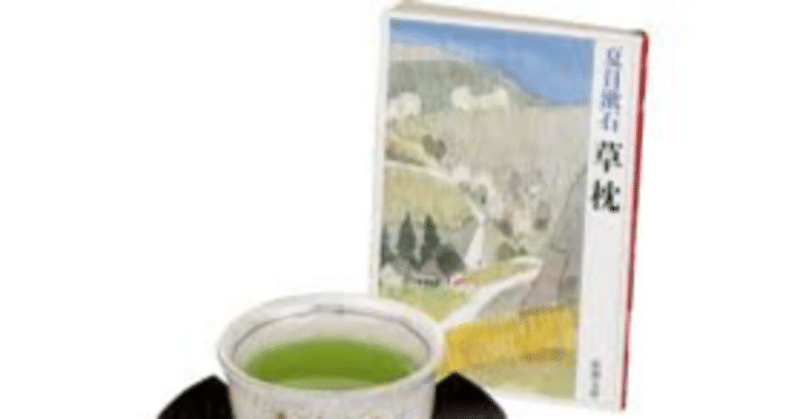
夏目漱石の名作に登場するお茶・紅茶への思い 2
Ⅰ 漱石とお茶 2
❷『虞美人草(ぐびじんそう)』
1907年に東京帝大講師をやめて朝日新聞社に入社し、職業作家になる道を選んでからの夏目漱石の最初の小説『虞美人草』。
主人公の小野が、自我の強い女性・藤尾と、古風でもの静かな恩師の娘・小夜子との間で揺れ動く物語です。
美文を味わえる『虞美人草』(八)では、母娘がお茶を飲む場面でさえも、美しく魅せてくれます。冷めきった出がらしのお茶なんて、あまりおいしくないだろうに、それを表現する言葉の心地よい響きといったら! 文豪、夏目漱石のテクニックに脱帽するばかりです。
「母は鳴る鉄瓶(てつびん)を卸(おろ)して、炭取を取り上げた。隙間(すきま)なく渋(しぶ)の洩(も)れた劈痕焼(ひびやき)に、二筋三筋藍(あい)を流す波を描(えが)いて、真白(ましろ)な桜を気ままに散らした、薩摩(さつま)の急須(きゅうす)の中には、緑りを細く綯(よ)り込んだ宇治(うじ)の葉が、午(ひる)の湯に腐(ふ)やけたまま、ひたひたに重なり合うて冷えている。
「御茶でも入れようかね」
「いいえ」と藤尾は疾(と)く抜け出した香(かおり)のなお余りあるを、急須と同じ色の茶碗のなかに畳み込む。黄な流れの底を敲(たた)くほどは、さほどとも思えぬが、縁(ふち)に近くようやく色を増して、濃き水は泡(あわ)を面(おもて)に片寄せて動かずなる。」(『虞美人草』八)
解説
華麗な語句で飾った美文が特長で、ヒロインの藤尾と彼女の母が茶の間でお茶を飲むシーンも、美しい文章が流れています。急須の中には、以前飲んだときの茶が残り、母が入れ直そうかと言ったが藤尾は断り、そのまま冷たい茶を茶碗に入れて飲み干した、という場面です。さらさらと並ぶ美しい言葉に潜む、お茶の冷たさと、藤尾の母に対する冷たい態度が重なり合い、うまくいっていない親子関係を象徴しています。 (つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
