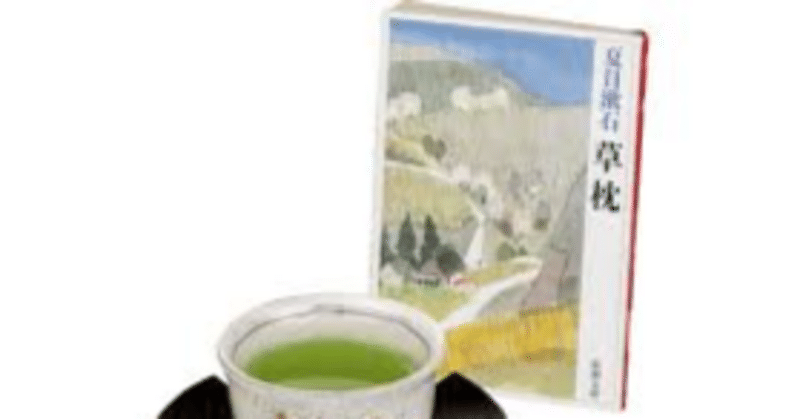
夏目漱石の名作に登場するお茶・紅茶への思い 11
Ⅱ 漱石と紅茶 6
❻『永日小品』
漱石のエッセイ『永日小品』には、紅茶茶碗を持って書斎に入る場面が出てきます。
「眼が覚さめたら、昨夜抱いて寝た懐炉(かいろ)が腹の上で冷たくなっていた。硝子戸越しに、廂の外を眺めると、重い空が幅三尺ほど鉛のように見えた。胃の痛みはだいぶ除れたらしい。思い切って、床の上に起き上がると、予想よりも寒い。窓の下には昨日の雪がそのままである。
「風呂場は氷でかちかち光っている。水道は凍り着ついて、栓が利かない。ようやくのことで温水摩擦を済まして、茶の間で紅茶を茶碗に移していると、二つになる男の子が例の通り泣き出した。この子は一昨日も一日泣いていた。昨日も泣き続けに泣いた。妻にどうかしたのかと聞くと、どうもしたのじゃない、寒いからだという。仕方がない。なるほど泣き方がぐずぐずで痛くも苦しくもないようである。けれども泣くくらいだから、どこか不安な所があるのだろう。聞いていると、しまいにはこっちが不安になって来る。時によると小悪らしくなる。大きな声で叱しかりつけたいこともあるが、何しろ、叱るにはあまり小さ過ぎると思って、つい我慢をする。一昨日も昨日もそうであったが、今日もまた一日そうなのかと思うと、朝から心持が好くない。胃が悪いのでこの頃は朝飯を食わぬ掟にしてあるから、紅茶茶碗を持ったまま、書斎へ退いた。」(『永日小品』 火鉢) (つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
