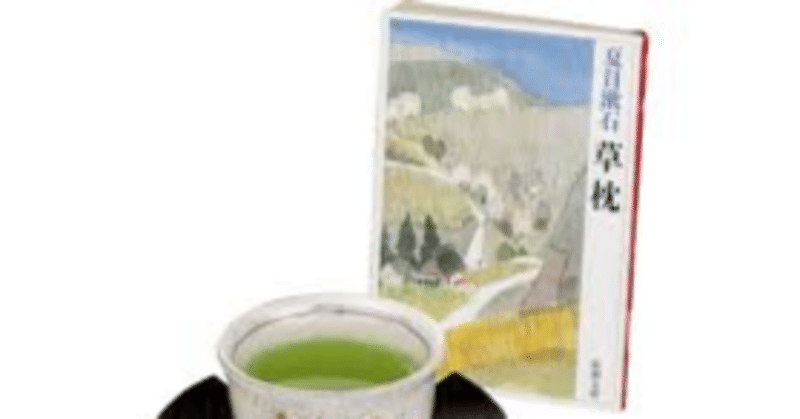
夏目漱石の名作に登場するお茶・紅茶への思い 12
Ⅲ 漱石と茶の俳句
漱石は明治二十八年、松山で子規と同居中句作に熱中。茶に関係した句として次のようなものがあります。
茶の花や白きが故に翁の像 (明二十八)
芭蕉忌や茶の花折って奉る (〃)
炉開きに道也の釜を贈りけり (〃)
炉開きや仏間に隣る四畳半 (〃)
口切や南天の実の赤き頃 (〃)
口切にこはけしからぬ放屁哉 (〃)
堆き茶殻わびしや春の宵 (明二十九)
茶煙禅榻外は師走の日影哉 (〃)
郭公茶の間へまかる通夜の人 (明三十)
寒菊や京の茶を売る夫婦もの (明三十二)
茶の会に客の揃はぬ時雨哉 (明三十二)
茶の花や長屋も持ちて浄土寺 (〃)
小春日や茶室を開き南向 (〃)
水仙や髯たくはへて賣茶翁 (〃)
梅の香や茶畠つづき瓜上り (〃)
梅林や角巾黄なる賣茶翁 (〃)
茶の花や黄檗山を出でて里余 (明四十)
茶の花や智職と見えて眉深し (明三十四)
茶の花や読みさしてある楞伽経(〃)
茶の木二三本閑庭にちよと春日哉(大三)
賣茶翁花に隠るる身なりけり (〃)
四つ目垣茶室も見えて辛夷哉 (〃)
春惜しむ茶に正客の和尚哉 (〃)
*ご購読ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
