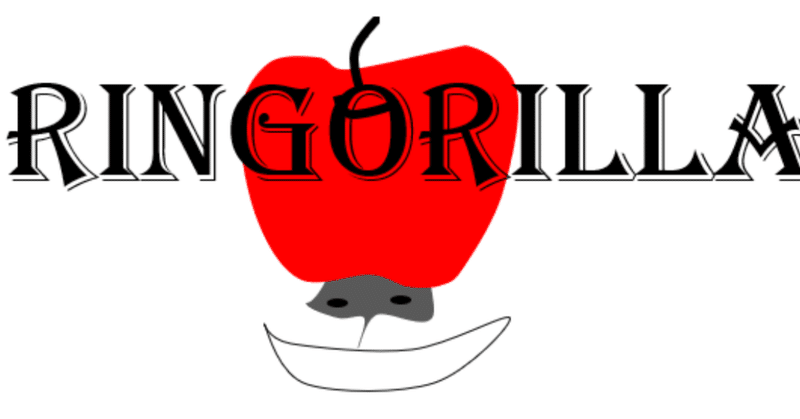
リンゴリラ #3
また、月島アークホテル
「参ったな、こんな惨状を見るのは初めてだよ」
小暮は笑った。ふだんはカエルのような様相でキャバ嬢に気味悪がられている小暮だが、笑えば実はニコちゃんマークのような愛嬌のあるシンボリックな表情になるのだ。
小暮は月島アークホテルのロビーのソファに横になっている。遺体は全部で十二体。すべて一発で脳天を撃ち抜かれている。ルーベンスの伝では、二人の殺し屋によるものだという話だった。一体なぜルーベンスがその事実を掴んだのかについては、小暮は尋ねなかった。それが二人の間の取り決めだったからだ。
「オレはお前さんの出世のためのネタをくれてやる。だがお前さんから根掘り葉掘り聞かれるのは好まない」
その取り決めに従って、小暮はこれまでにおいしい思いもしてきた。だが、今回のヤマは、さすがにルーベンスの情報を鵜呑みにするにはデカすぎた。というか死体がいささか多すぎたのだ。せめて犯人の自白があればいいのだが、と小暮は思った。
「やったのはパンツとウォンという二名の殺し屋。いずれも第一級の殺し屋だ。手こずるようなら撃ってもかまわん」
ルーベンスに電話でそう言われ、小暮はその場でPCのデスクトップにある殺し屋のフォルダを開いた。だが、二名ともそのリストには存在しなかった。
「仕事の速い連中だ。のろまなおたくらのリストにはないはずだ」
「でも、その仕事の速い殺し屋を売り飛ばすわけですね?」
「それは質問か? カエルくん」
「いやいや、違いますよ、旦那、参ったなぁ」
小暮はへらへらと笑った。内心で舌打ちをしながら。
恐らくルーベンスは二名の殺し屋を抹消し、死体でもって自白の代理とするに違いない。だが、それで丸く収まるかどうかは、ルーベンスの事後処理の手際にかかっている。
「二人はいま豊洲にいます。住宅街をうろついているようです」
部下の磯田が教えてくれた。GPSという機能は本当に便利だ。ルーベンスが教えてくれた二人の携帯電話番号を元に居場所を探り当てられるというのだから。
「なぜ豊洲?」
二人の殺し屋の住所はさっき割り出したばかりだ。二人は渋谷方面に住んでいる。
「仕事帰りの夜遊びにしちゃあ、場所が豊洲ってのも妙だ」
「あのへんは大規模開発が進んで、最近では昔と違ってずっと栄えてるみたいですよ」
「バカ、それと夜遊びは別だろうが」
そのとき、小暮の携帯電話が鳴った。
「もしもし?」
「白菜とニンジンが切れてるよ」
不機嫌なくぐもった女の声。小暮の妻だ。
「白菜とニンジンが切れてることがオレにどんな関係があるんだい、ハニー」
「帰りに買ってきて」
所帯持ちの刑事の何割が仕事帰りに買物を頼まれているのか、一度調査してみたいと小暮は思う。
「なあ、ハニー。白菜とニンジンはキレたりしない。キレるのはオレの頭だよ、ハニー」
電話の向こうでため息。早く切りたいのだろう。何しろ、彼女にしてみればもう用件は伝え終えたのだから。
「あなたのヘンな絡みに付き合うほどヒマじゃないのよ。海外ドラマが始まっちゃうんだから」
海外ドラマ、と小暮は頭のなかで反芻する。アメリカのドラマは山場が分かりにくいし、韓国のドラマはチョコレートに砂糖をまぶしたみたいで食えたものじゃない。だが、それが嫁にとっては小暮の愚痴を聞くより遥かに楽しいものらしい。
「オレの頭がキレちゃったら、ハニーの体が真っ二つだよ、分かってるのかい、ハニー」
「もう切るわよ、ガマガエル」
宣言どおり電話は切れた。
「あぁあ、キレちゃった」
小暮は今年で結婚二十周年を迎える。この世のものと思えないほどの醜女となぜ自分が二十年も結婚生活を続けているのか。小暮はそのわけをよく分かっている。彼女は小暮が宇宙のなかの小石であることを教える。誰にも相手にされることのない孤独で無意味な存在であることを。そのことに、奇妙な安堵感を覚えるのだ。
小暮のやりとりを見ていた磯田に向って、小暮は顔をくしゃくしゃにして威嚇した。くしゃくしゃにすると、小暮の顔はブルドッグに似ている。磯田はその顔に腰を抜かし、後ずさりしようとして倒れた。この世のものと思えぬ形相は、ときに銃よりも強力なダメージ力を誇る。
「よし、それじゃあ豊洲、行ってみようか」
小暮はニコちゃんマークのような笑顔で磯田に言うと、すぐにカエルの顔に戻ってノートパソコンで現場確認のディスプレイを表示させた。一点だけ奇妙な点があった。一九〇四号室には男の死体が一体。だが、男の死体からだいぶ離れたドア付近のカーペットに大量の血がこびりついていた。恐らくそこにはもう一体の死体があったのだ。その死体はどこへ消えてしまったのだ?
まさか、一体だけ殺し屋が持って帰ったとも思えない。
小暮は、過去にこのような死体消失の現場を三度見たことがあった。いずれもこの一年以内の話だ。いずれも中国人のマフィアが絡んでいた。小暮は中国マフィアの中から一人の人物をピックアップする。
爪楊枝。
今回の事件はルーベンス以外に爪楊枝も絡んでいるということか。だが、二人は本来縄張りも違うし、過去に抗争になったこともない。二人は別種の生き物だ。しかも、ルーベンスは十二人惨殺の犯人を自分の息のかかった殺し屋のなかから推挙している。もし爪楊枝と争っていたのなら、爪楊枝サイドに責任をなすりつければいい。だが、ルーベンスは今回そうしていない。
考えられるのは、爪楊枝の関与をルーベンスが知らない可能性だ。
「たとえば、爪楊枝がここを訪れたのは、事件の後だった」
何のために?
死体を一つ消すためだ。恐らくは自分の商売が絡んだ人物の死体を回収する必要が生じた。
「すると、今頃爪楊枝はルーベンスの寝首をかこうとやっきになっているかもしれんな」
もしそうなら、手間が省けて助かる、と小暮は思った。いっそ二人で殺しあってくれれば、好都合だ。部長昇進は間近に迫っている。ここから先は、闇の人物とのコネは整理していったほうがいい。
「悪いが、警察はあんたが思ってるほど無能じゃないよ、ルーベンスちゃん」
そのとき、別の刑事がやってきた。この刑事は、前日の小説家殺害事件を追っていた。プラトニ・カルキという奇天烈なペンネームは本を読まない小暮でさえ耳にしたことがあった。噂では、ノーベル文学賞の有力候補と見られていたという。
「どうしたの? 田村ちゃん」
「プラトニ・カルキ殺害現場に残された指紋と髪の毛から犯人の正体が、分かりました」
「お、仕事が速いね。このホテルの事件が表沙汰になる前にそっちを発表しちゃおっか」
「容疑者は、庵月ユウジ。職業、寝かせ屋」
「寝かせ屋? 何それ? そんなのあんの?」
「さあ……それともう一人、隅島尚惟。隅島グループの社長です」
「あ、そっちはね、上で死んでた」
言ってから小暮は黙った。どういうことだ? なぜプラトニ・カルキ殺しの容疑者がこのホテルで殺されているんだ? これはまずい、いやがうえにも世間の注目がこの事件に集まってしまうではないか。この事件はそんなごたいそうなヤマじゃないんだ。ただの殺し屋たちのララバイに過ぎないんだから。
「田村ちゃん、後ろに本部長」
田村は言われて慌てて振り向いた。その後頭部を小暮は消音銃で撃った。それから背後にいた磯田の額に一発。
「『殺戮現場に興奮し、刑事同士が撃ち合い?』 こりゃいい見出しになるね」
また小暮のポケットで携帯電話が鳴り始めた。
「もう分かったって、ハニー。白菜とニンジンだろ? え? 牛乳も? その牛乳をお前の頭からかければいいのかい? ハニー」
電話は、すでに切れていた。
あじさいコーポ中野
「つまらない部屋だ」
爪楊枝は狭い4LDKのなかをぐるぐると見回してそう結論付けた。もっとも、面白い部屋を求めていたわけでもないのだが。
壁には本とCDが共存を余儀なくされている。服は箪笥にしまってあるのだろう。箪笥の大きさから察するにさほど服を持っているタイプではない。アイロンもかけない。食器の数は最小限。自炊はほとんどしていない。旧型の電気コンロでまともな炊事ができるわけがない。少なくとも、中華料理は無理だ。
「こんなところに住んでいる男、ワタシになぜ電話かけるか?」
独り言はむなしく室内の静寂に飲み込まれる。爪楊枝はショッキングピンクの携帯電話に付着していた指紋からこの部屋までたどり着いた。指紋は、通常警察が前科者にかぎり管理している。だが、それだけではない。「SC(指紋管理センター)」では違法に搾取された指紋データが大量に保存されている。そのデータを使えば、夜逃げをした人間を捕まえるのも容易だ。五年前、東京を活動拠点とする十二組織の共同出資によって「SC」は創設された。爪楊枝も、「SC」創設の功労者の一人だった。そして、ようやくデータが充実し、機能しはじめたのは2年前。
「目的は何だ?」
そのとき、爪楊枝はよく見知った匂いを嗅ぎ取った。
「この匂いは……」
爪楊枝のよく知っている匂いだった。爪楊枝はすぐさま白のアウディに戻ると、車内で寝そべっている風船男の頬を叩いた。
「ジンジャエールがここに来ている。やはりアイツの仕業だ」
風船男は顔をしゅぱしゅぱと瞬間的にストレッチして、自分がどこにいるのかを思い出そうとしているようだった。
その間に爪楊枝は、空気男の反対側の頬をさらに強く叩いた。
ようやく目の焦点が合った。
「するってえと、ここはジンジャエールの男の家ですか?」
「知るか」
風船男は、いま一度二階建の安普請のアパートを眺めた。
「あのブルジョワのメス猫がこんなとこの住民と駆け落ちするとは思えないんですがね」
「捕まえて確かめる。もっとも、しゃべらせるまで、お前が食事を待てるなら、だが」
「困ったな」
風船男はポリポリと頭をかき、アフリカ大陸を丸呑みにしそうな大あくびを一つした。
「よく眠ったんで、また腹が減っちゃったんですよ」
爪楊枝はむっつりとしたままでキーを差し込んだ。
「じゃあ真相は分からないまま。それで構わない」
アウディは、アクセルをふかして闇のなかに猛スピードで駆け出した。風船男の乗った左後輪だけが、少しばかり沈んでいたが。
第二豊洲アパートメントまで
ラッパが吹けない。庵月はそう言って、十七の夏、演奏会をキャンセルした。当時、庵月はトランペット奏者として俄かに注目を集め始めており、玄人の目にも留まる存在だった。
「お前は必ずいつか世界を揺るがすラッパ吹きになるだろう」
十五の夏、来日していた世界的なトランペッター、スライ・シュガーが、高校に最寄りの駅前で行われたチャリティ演奏会をたまたま目撃して絶賛した。彼は庵月に独特のスラングを混ぜた英語で話しかけた。
「でもな、坊主。まだ何か足りない。お前の音は、クソすばらしいにも関わらず、お前がクソ何者なのかが記されてないんだ。ノーネイム、そう、それが今のお前の音だ。それはクソいいことでもあり、クソ悪いことでもある」
スライ・シュガーは、気まぐれに若者に声をかけただけなのかもしれなかった。だが、吹奏楽部の教師は舞い上がったし、母親も喜んだ。スライの警告に苦しめられていたのは、庵月ひとりだった。スライ・シュガーの指摘したことは、何よりも庵月自身が気にしていることだった。たとえば、庵月はスライ・シュガーのナンバー、「うずくまる女」をスライ以上にスライらしくファンキーに吹く。だが、それはあくまで「スライ以上にスライらしく」でしかない。
自分に何が足りないかは分かっている。「名前」だ。それは、分かっていても簡単に得られるものではなかった。これが自分の音だと思っても、結局先行するトランペッターたちからの影響の累積でしかなく、そのために幾度も壁にぶち当たった。
そのうち、悩みは次のレヴェルに移った。今度は、どの曲を吹いても、スライ・シュガー的になるようになった。スライを意識しすぎるあまり、自分をスライに近づけようと無意識が働いてしまうのだ。これは自分でもどう制御したらよいものか分からなかった。
その悩みのさなか、母が脳梗塞で倒れた。母親はスライの吹く「うずくまる女」を愛していた。だから、庵月はいつか自分なりの名前のある吹き方で、「うずくまる女」を演奏しようと思っていた。そしてその演奏を、母に聴かせようと。庵月は、不思議なことに植物人間になってからの母とのほうが気楽によくしゃべることができた。
庵月にとってはきわめて充足した日々だった。庵月は、意識のない母に聴かせるために「うずくまる女」の練習に励んだ。自分の名前を刻んだ演奏をするために。
だが、十七の夏に夢は潰えた。
母親に完全なる死が訪れたのだ。
庵月ユウジ、十七歳。ラッパを置くには早すぎる歳だが、庵月のなかでは、もう何かが終わってしまっていた。
GPS探査機に携帯ナンバーを入力すると、場所は豊洲駅周辺にあるアパートを指していた。
庵月は手を挙げ、タクシーをつかまえる。運転免許をもったほうがいいのかもしれない。いや、都内の移動なら自転車があればいいのか。何であれ、わざわざ手をあげてタクシーを停めるという古いしきたりは何とかならないものか。庵月はそんなことを考える。
「第二豊洲アパートメントまで」
しばらく沈黙があった。
「知らない」
静かな、そして短い返事。東京の人口密度を考えれば、少しくらい奇妙なタクシー運転手と鉢合わせることは覚悟しなくてはならない。
「ここだ」
庵月はGPS探査画面を運転手に突き出す。運転手はしばらくじっと食い入るように見つめている。まるで、庵月には見えない地獄絵がそこに描かれているみたいに。そして、ゆっくりと発車しはじめる。
「ハイテクノロジーは好きになれない」
「オレもだ。殺し屋と同じくらいに」
五分後、豊洲駅付近に着いた。だが、困ったことが起きた。庵月の追っていた赤いマークが忽然と画面上から消えてしまったのだ。
そして、庵月の目は、住宅街の夜空をオレンジに染め上げる炎をとらえていた。それが第二豊洲アパートメントなのはほぼ間違いなかった。庵月はそこでお金を払って降りようとした。
だが、すでにそこには運転手は乗っていなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
