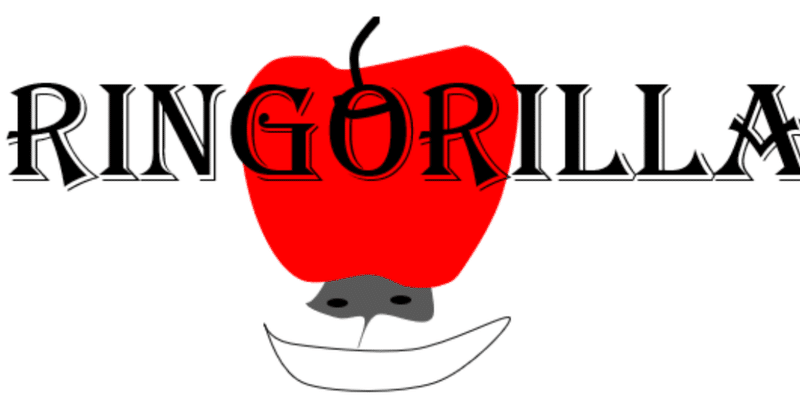
リンゴリラ #6
トヨス・パーク付近
埃でも払い落とすように頭を叩かれて、爪楊枝は覚醒した。
叩いているのは警官だった。
「おい、生きてるか」
爪楊枝はしばらくの間目を開かなかった。
「参りましたよ」
べつの警官の声だ。
「あっちのデブは4人がかりでも運べそうにないですって」
「馬鹿野郎、泣き言いってんじゃねえよ」
爪楊枝は考える。俺の頭を叩いた警官は、上司に当たるらしい。
「おい、お前らコイツしょっ引け」
「でも意識が戻らないと」
「寝てるだけだ。そのうち目覚めるさ」
愚か者の命は長くない。爪楊枝の手は、男の腰にある拳銃を簡単に奪い取れる位置にあったのだ。○・三秒後に眉間に銃弾をお見舞いするのは造作のないことだった。
他の警官が警戒態勢に入ったときには、爪楊枝は起き上がりながら銃を連射し、それぞれの脳天を撃ち抜いていた。
「小国の臓器は、大国に」
これが爪楊枝のルールだ。だからできる限り脳天を狙う。
死体を完全に消したい場合は風船男が便利だが、風船男の登場は死の実数から言えば、稀だ。臓器は重要な財産だ。何も残せない貧乏人でも臓器だけは残すことができる。移植医療がいくら発達したところで、需要に追いつける速度ではない。結果、相変わらず高値で売買される。むしろ、一部は合法的に処理できるようになったぶん、この国の法改正はありがたいというべきかもしれない。
そして商売で儲けた余剰分は大国に。これは爪楊枝が中国外務省との間にとり交わした約束だ。年間で百の臓器を提出することを条件に、爪楊枝は日本の領土を譲り受けた。
「もうここはお前のシマだ。好きにやれ」
外務省の官僚はそう言って爪楊枝を放った。
爪楊枝は東京の街を暗躍し、あらゆる手管で臓器を回収する。自己の利益のために。そして祖国との密約のために。
爪楊枝は電話をかけ、臓器屋を呼ぶ。
十分後に大型のトレーラーが現場に現れる。
「どれですか?」
「全部だ」
青い帽子を被った無表情な男たちが死体をかき集めている間、爪楊枝はここ数時間で起こったことを思い出そうとした。風船男を殺したことまでは思い出せる。だが、その先がうまく思い出せない。なぜ自分はあの間抜けなノッポに逃げられなくてはならなかったのか。
──寝かせ屋。
そうだ、奴は自分のことを寝かせ屋だと言った。だが、それが何だ? 逃げられたこととどう関係がある? 脳の芯がまだぼんやりしていて頭の中で何かが結びつきそうになると、それが無理やり引き離される。
だが、爪楊枝はやがて会話の一部を思い出す。
──あんたの大事な商品を殺したのはルーベンスという男の組織だ。俺じゃない。
──ルーベンス……。
──知ってるか?
──画家だ。
爪楊枝は東京で活躍する中国マフィアや日本のヤクザ組織なら大体把握していた。だが、ルーベンスの名はそこになかった。爪楊枝の知っているルーベンスと言えば十七世紀の宮廷画家だ。ピーテル・パウル・ルーベンス。爪楊枝は十年ほど前まで贋作師をしていた。爪楊枝の描いた絵のいくつかはいまだにルーヴルに置かれているほどだ。
生まれ故郷では西洋の油絵の複製画が家内工業的に行われていた。爪楊枝は物心つく前からその技術を学ぶことを強制されたし、そのことを不思議に思ったこともなかった。そのうち、工場制が導入され、流れ作業で贋作の大量生産が行われるようになると、爪楊枝は周囲から浮くようになった。
爪楊枝の担当する部分だけが際立ってレベルが高かったのだ。村にいる絵師の一人が爪楊枝の高い能力に目をつけ、大量生産用のコピーではなく、より高度な《模倣》を習得するように求めた。そのほうが給料も高かったから、爪楊枝は男に従った。だが、やがて爪楊枝はそれが理由でやっかみを買うようになり、徐々に村八分にされていった。
コピーを信条とする村のベクトルと、爪楊枝のベクトルは違っていた。皮肉にもそれは村が爪楊枝に課したことでもあった。そんな折、爪楊枝は村の金持ちの家に盗みに入った罪に問われた。明らかに濡れ衣だったが、中国の司法はそんなことは気にしない。
爪楊枝はいくつかの贋作の試作品を無理やり競売にかけられ、その代金をすべて奪われた。家を奪われ、母は首を吊って死んだ。
文化大革命のさなかに生まれた爪楊枝にとって、この記憶は個人的文化大革命ともいうべき瑕を残した。爪楊枝は保釈後、贋作師をやめ、裁判官の下で「罪人作り」の任に就いた。やがて、その裁判官自体を罪人に仕立て上げて辞職に追い込むと、その手柄をもってマフィアの門を叩いた。そのままマフィアの中で爪楊枝は地位を確固たるものにしていき、「まずは一財を成す」を目標に、他のマフィアとは違って臓器売買に特化したビジネスを成功に導く。この成功で金庫番となった爪楊枝は、トップ争いをする3人の男たちからそれぞれに暑苦しいまでの信頼を勝ち取ることになった。
あとは三人が殺し合うのを静観し、生き残った最後の男を始末すれば自然と爪楊枝の天下になった。爪楊枝は「黒社会」と総括される中国マフィアの中では特殊な存在だった。黒社会の組織は地域によっては警察さえも手出しできない脅威となっている。警官たちの目の前でマシンガンをぶっ放そうと、彼らはそれを止めようとはしない。そもそも、あんな膨大な領土を一つの国家が掌握し切れるはずがないのだ。そのことは国家も理解している。ただ、大国を維持するがために、すべては見て見ぬふりをされる。
結局、諸外国に対して面子が保たれればそれでいいのだ。国民が国家に反逆するのは駄目でも、国家以外のものに噛み付くことは気にしない。中国という国家は、実際にはいくつもの無法組織と国家との連携組織によってどうにか保たれているツギハギ国家に過ぎないのだ。それをを早々に見抜き、国力のレベルアップを打ちたてた点で、爪楊枝は他の黒社会の面々と違っていた。直接的に組織の利益の一部を国家につなぐことで、組織と国家の双方を補強していく。それが爪楊枝の狙いだった。爪楊枝は、日本をそのための重要な資材とみなしていた。
臓器移植医療が大幅に遅れている日本には、大量に余った臓器がある。爪楊枝はそこに目をつけた。眼球から心臓、腎臓、肝臓など8箇所を現金化すれば死体一体で得られる金額は宝石を売るよりよほど率がいい。そうしてこの五年の間に、爪楊枝は黒社会の世界のみならず、国家とのパイプにおいても重要なポジションに就くに至った。
いまでも爪楊枝は贋作を作製していた頃のことを思い出すのだが、制作時間2週間をかけて得ていた賃金は、今の十分で得られるお金にも満たない。絵筆をとれば、今もそれなりの贋作を作ることはできるだろう。いや、もしかしたらオリジナルだって描けるかもしれない。だが、芸術というものを労苦の指数としてしか見ることができない以上、爪楊枝が再び筆をとる可能性はゼロに近かった。
──中国の無意識。
そんなものがあるのだろうか?
もしも中国に無意識があるなら、自分もいつか筆をとることになるだろう。だが、それはきわめて希望的観測に過ぎない。ギザギザの意識のせめぎ合う大国に、少しでも無意識が生じるなら、そのキャンパスに自分は何を描くのか? その答えは、ルーベンスにでも尋ねてみるしかない。
青い帽子の男たちがトレーラーに乗り込み、頭を下げて走り去るのを見送りながら、もう一度ルーベンスという名前に聞き覚えがないか考えた。ルーベンスという男の組織がリャンリャンを銃殺し、ジンジャエールを爆殺した。
第二豊洲アパートメント。
あのアパートは誰のアパートだったのだ?
少なくとも爪楊枝がジンジャエールに分け与えたものではない。
爪楊枝は思考を停止する。
推理に意味はない。事実はこうだ。爪楊枝の傘下の人間が二名消され、爪楊枝が所有するべきものが奪われた。
ルーベンス。それがその危険な略奪者に与えられた記号だ。記号には二通りの用途がある。最終的に記号に具体的数字を与える場合と、記号は記号のまま使用して別の目的を達成する場合。
リンゴが手に入るためなら、ルーベンスの正体が分かる必要はなかった。
「我々はリンゴが手に入りさえすれば、何ら問題がない」
たとえば、「ルーベンス」を「日本国」という風に置き換えても構わない。とにかく何であれ、リンゴを手にしなくてはならない。それは幾百の臓器を手に入れるよりも、重要かつ緊急を要する使命だった。リンゴが手に入れば、臓器売買など必要ないと言っても過言ではない。
爪楊枝は晴海通りに面したトヨス・パークに入った。
音のしない公園の、無機質な光景を見つめる。爪楊枝が生まれた村にも公園と呼ばれるものは存在した。そこでは早朝から気孔に励む年寄りの集会場となっていた。爪楊枝は筆の動きが悪くなるとその公園を訪れ、自分の中から不規則で無用なものを追い払うために公園内を歩いて回った。
しかし、改めて公園に立つと、その頃とは真逆の感覚が爪楊枝を襲った。論理的でクリアな思考の隙間から、奇妙な無意識が顔を覗かせる。
そうだ、寝かせ屋だ。あいつのせいで、わずかな時間だが、死にも似た深い眠りの底に落ちた。その体験が、精神に何らかの作用を与えているのだ。
胸ポケットで携帯電話が鳴る。
「……」
爪楊枝は通話ボタンを押し、黙って電話を耳に当てた。
「助けて」
それはジンジャエールの声だった。
「ワタシはお前を信用していない」
「それでもいいわ。でもリンゴは欲しいでしょ?」
爪楊枝はジンジャエールの声の調子を吟味する。女だろうと男だろうと、大体の嘘は見破れる。だが、ジンジャエールの嘘は分かりにくい。ジンジャエール自身が嘘を嘘だと自覚していないせいなのかもしれない。爪楊枝は過去に何度も彼女に嘘をつかれた。そのたびに背中に熱した鉄を捺し当て、彼女も泣きながら謝罪するのだった。だが、舌の乾かぬうちに再び盗みや浮気を繰り返す。そのうち爪楊枝はこの女が自分に殺されたいのだということがはっきりと分かるようになった。どういう理由でかは知らないが、この女は殺されたがっている。
爪楊枝はそれゆえにジンジャエールを生かした。そして、元来の盗みの才能に磨きをかけ、それを彼女の仕事にさせた。
「まだ私を愛してる?」
「ナメた口をきくんじゃないよ」
「あなたは私を信用できない。でもまだ私を愛してる」
爪楊枝は外灯と高い木々の間で夜明け前の月を見つけた。
その月が滲んで見えるのは闇が朝日に溶かされるためではなかった。爪楊枝の瞳には、涙がたまっていた。
何だ、コレは。
爪楊枝は自分の内奥から沸き出でる感情の泉を押さえることができなかった。それは、さっきの眠りによって、覚醒した何かだ。
「どこにいるんだ…マーマ、寂しくて死んじゃうよ」
彼女は黙っている。黙らないでくれ、と爪楊枝は考える。すべてを受け止めてくれ。でないとワタシは次に進むことができない。
「もう知らない間にいなくなっちゃうのはイヤだよ」
鼻水が滴り、何十年ぶりかにしゃくりあげて泣いている。『タイタニック』を見たって泣かなかったというのに。
頼む、沈黙しないでくれ。
それはもはや願いと化している。その願いは、これまでの人生で積み上げた地位を投げ打つ価値のある崇高な願いだ。
やがて、女神が爪楊枝に微笑みかけた。
「大丈夫よ、坊や、私は元気。でも助けに来てくれなくっちゃ」
「うん、行くよ、マーマ」
爪楊枝の目には、月が珊瑚の海のようにきらめいて見えた。
オテル・ド・パシフィック台場
三十二階のバルコニーからは「船の科学館」や日本テレフォンサポートセンターの建物等の大型の建物が要塞のようにいびつな光を放っている。そして、SFに登場する誰も人の住んでいない人工タウンを思わせる大型パークがその手前に広がっている。そして海。
ここから先は海だ。
「私たちにはいくつかの選択肢がある」
いかつい看護師は似合わないピンクのバスローブに身を包んでそう言った。
「一、飛行機に乗って長崎に渡る。長崎から週に一度だけ外国へ出る船が出ている。その船で中国に渡る」
パンツは何も答えなかった。
「二、東京に戻り、三人バラバラで逃げる」
看護師はここでしばらく黙る。
「三はないのか?」
パンツは聞き返した。
「なんだ、ちゃんと聞いてたのね」
「人の話はちゃんと聞くほうだ」
「らしいわね」
「ばお、ばお、くーば」
「ねえ、静かにしてなさいよ」
犬の顔をした少年はウーと唸った。そろそろ犬であることに順応しはじめているのかもしれない。犬であることを受け入れられなかったのは、あのいかさま医師への反抗心があったからか。今の少年は、のびのびと犬になっていた。
パンツは少年の前にカップを置き、ミルクを注いだ。少年はそれをうまそうにぴちゃぴちゃと飲み始めた。
「三、とりあえず私とセックスをする」
「……面白い冗談だ」
パンツは真顔で答える。
「だが、俺の左足にくっついた中国人はお堅い奴でね。コイツの前で女を抱く気にはなれない」
「案外紳士なのね。私みたいなナリの女からの誘惑にも優しい断り方ができるなんて」
「今は何も考えたくないだけだ」
神経がへとへとに疲れきっていた。
だが、それでもパンツの中から、復讐の炎が消えたわけではなかった。そのベクトルはまっすぐルーベンスに向いていた。脚を切り落とした男も、部屋に自分たちをおびき寄せた女も、結局すべてルーベンスの指示で動いているはずだった。
ルーベンスは十代から彼のためにつき従ってきた部下を呆気なく切り捨てることができる男だったのだ。ルーベンスの冷酷さは知り抜いていた。だが、心のどこかで、自分にだけはその矛先は向くことがないと信じきっていた。この十数年の忠誠心は返ってこない。ならば、ルーベンスの存在をせめてこの世から消し去る。そのためには、今看護婦が言った三つの選択肢はどれもパンツには無用だった。
「俺はこれからやることがある」
「これから? こんな時間に?」
「ああ。その後は死ぬだけだ」
「なぜ? なぜ死ぬ?」
「脚に顔のある奴が生きていける場所なんかこの世にはない」
「それは、あんたの決めることじゃない。決めようとするのは、あんたが弱虫だからさ」
別段腹は立たなかった。女は正しいことを言うのが仕事だ。だから正しいことを言えばいい、そしてそれを無視するのが男の仕事だ。
「分かった、お前とセックスをする。ただし十分だ」
「後悔はさせないよ」
パンツはウォンの頭を撫でた。
「この世の終わりの風景を見せてあげる」
それから、ゆっくりとウォンのまぶたを持ち上げ、開かせた。
まぶたは、すぐに落ちた。
視界がふさがった。看護婦がパンツに覆いかぶさってきたのだ。
パンツはキスをしながら、看護婦が口髭をきれいに剃ったらしいことを舌で確認していた。不思議なほど濃密な時間だった。そのわずかな時間、パンツの意識は浮遊した。
無意識のなかで、パンツは月島アークホテルで見た中国人の女の死体とまぐわっていた。そこはホテルですらなかった。どこかの農家。
ああ、そうだ、ここは中国の……。
と、そこまで考えてパンツは、これは自分が見るべき幻想ではないのではないか、と思った。だが、それ以上は考えられなかった。
暖かい手のひらがパンツの生殖器を包み込み、リズミカルな動きを始めたからだ。パンツは目を閉じた。そして呟いた。
「リャンリャン……」
東京湾景
動物園の外からでも唯一見える動物がキリンだ。かつて、庵月はキリンが舌を掃除するために奇妙にそれを動かすのを眺めるために、近所の動物園まで出かけ、入館することなくキリンを眺めたものだった。
東京湾に佇む船の窓から首を突き出したキリンの姿を見つけたとき、庵月は親戚に出会ったような気持ちでそれを眺めていた。キリンは、庵月のライフにとってきわめて重要かつ自然なモチーフだった。
最初に動物園へ行ったのは母とだった。
彼女は単に子どもを楽しませたくて来たわけではなかった。彼女はそこで見知らぬ男と逢った。偶然出会ったようには、庵月の目には見えなかった。恐らく二人は申し合わせていたのだろう。
そして、母親は庵月にソフトクリームを買い与え、キリンを見ているように言ったのだ。母親がその間たしかに後方にいたのかどうか、今となっては分からない。ましてやその隣にいた男の存在など、分かるはずもない。
だが、それから母親は一週間ほど部屋から出ることはなかった。彼女は部屋にこもってスライ・シュガーの「うずくまる女」を聞き続けた。サックスブルーのソファに身を横たえ、川の中から拾われて乾くのを待つ石ころのようにじっとしていた。彼女は、水が消えるのを待っていた。
ソファの脇にあった小さな円卓の上には、読みかけの小説がバナナの皮のように置き去られていた。『風のトポロジー』。プラトニ・カルキの処女作だ。庵月がありし日の母親を思い出そうとすると、決まってこの光景が浮かぶ。それは、その数年後に彼女が辿った運命の片鱗のようなものが、そこに凝縮されているからだ。
庵月は、東京湾景に向って長い舌をゴロンゴロンと自由に回転させて遊ぶキリンの様子を眺めた。その一瞬の間に庵月は母に出会い、いくつもの動物園を駆け巡った。最後の動物園の記憶は、不思議なことに行ったことのない動物園のイメージで終わっている。
「あなたはキリンに似てるわ。言われたことない?」
あの夏、少女は音楽室のグランドピアノの上に寝そべり、顔にハンカチをかけたまましゃべっていた。庵月は彼女の短すぎるスカート丈と白く長い脚をじっと見ていた。その手前には、ジンジャエールの缶。何か飲みたい、という少女のために、庵月が購入した。だが、少女は「私、炭酸ダメなの」と言って口をつけてくれない。
庵月の左手には、握り締めたトランペットが夏の暑さに汗をかいていた。
「キリンに? 言われたことないな」
「のんびりしていて、何考えてるのか分からないけど、あれで喧嘩になるとかなり凶暴らしいわ」
「僕は喧嘩はしない」
「一般的な喧嘩はね。でも、キリンにはキリンの戦い方がある」
庵月は答えなかった。白い脚は時折組み替えられ、そのたびに浮いた片脚はまるで指揮棒でも振るみたいにリズミカルに揺れた。
その日、庵月は彼女と上野動物園へ約束をした。
行ったことのない動物園とは、上野動物園のことだ。庵月は、東京に生まれながら、一度として上野動物園を訪れたことがなかった。
「来週の日曜日、私の日課に付き合ってよ」
彼女の日課とは、毎週日曜日に上野動物園に行き、あらゆる動物たちのそれぞれの動きを観察して回ることだった。
「何故そんなことをする?」
「生きることから少しでも自由になるためよ」
「生きることから少しでも自由になりたければ、眠るのが一番だ」
「あなたならそうするんでしょうね」
彼女が何を思ってそう言ったかは分からないが、事実庵月は当時、夜十一時きっかりに就寝するように心がけていた。それが庵月の唯一の日課であると言ってもよかった。
「眠りに恵まれない人生だってあるの」
「君の人生のことか?」
「誰でもある日そんな人生に迷い込むのよ。私の夜はあなたの夜じゃないし、あなたの夜は私の夜じゃない」
「僕が眠れない夜を過ごす頃、君は眠っているかもしれない」
「そういうことね」
「そして君は、よい眠りを手にする代わりに、動物園を訪れる。僕がその日課に付き合うことに何の意味がある?」
「人間以外の生き物を凝視する時間は大事よ」
彼女はまた脚を組み替えた。スカートがめくれあがり、太ももから尻に向かうなだらかな曲線が露になった。
「ウィー・マスト・ゴー・トゥー・ザ・ズー・ネクスト・サンデー」
ジャパニーズ・イングリッシュが、彼女の曲線を滑っていく。
庵月は、明け方の港で出航を待つキリンに、結局行くことのなかった上野動物園と少女の白い曲線を見る。
なぜズーに行かなかったのか。
庵月は考える。そこの部分の記憶が曖昧だ。あるいはすっぽりと抜け落ちていると言ってもいい。なぜだろう?
十七歳。自分はその少女に恋をしていたはずではなかったか。
なのに、なぜ行かなかったのか。
日曜日。十七歳。夏。
庵月は思い出しかける。何かを。砂をすくって捨てる。その下にあるはずのものを、傷つけぬように掘り起こすのだ。
しかし、目の前の現実も無視するわけにはいかない。まずダチョウだ。ダチョウがデッキを走っている。そして次に奇声を発しながらタラップを降りてくるのは、サルたちだ。手摺を滑るもの、二足歩行で一段一段下ってるもの、それらが自由な前衛的音符を為す。
開いたままの窓からはいっせいにフラミンゴが飛び立ち、船内からはライオンの唸り声が響く。
何かが起ころうとしている。
あるいは、それはもうすでに起こってしまったのかもしれない。
とりあえず、ここに長居している時間はなさそうだ。
庵月は、GPS探査装置をポケットから取り出す。
そこにはルーベンスの居場所が表示されている。
追跡を開始するのは、位置が固定されて十分経過してから。
ルーベンスの位置を示す赤いマークは、十分前と同じ位置で留まっている。位置の詳細ボタンをクリックすると、その細かい場所が表示される。
「月島……」
ルーベンスは月島にいる。月島アークホテルに戻ったわけではない。その裏手にいるのだ。今頃は警察がうじゃうじゃいるはずなのに、彼はそこへ舞い戻った。月島アークホテル裏手にあるのは、月島神社だ。もう十分以上彼はそこに留まっていることになる。
庵月はルーベンスに催眠をかけ、上野動物園に向かうようタクシー運転手に告げたのだが、どうやらルーベンスは上野動物園には行かなかったらしい。代わりにホテルの裏手に戻ってきた。
理由は定かではないが、催眠が解けたようだ。庵月はそこへ行かなくてはならない。もはや手がかりが彼以外にない。そして夜は間もなく明ける。
明日の夜には別件の仕事が入っている。
これ以上この問題に関わり続けるわけにはいかない。
庵月にとって、今はなき依頼人のために費やせるのはあと数時間が限度なのだ。
庵月が、もしもプロの私立探偵であったなら、こんな無軌道な調査はしなかっただろう。だが、庵月はプロの私立探偵ではないし、道筋を立てて誰かに自分の行動を説明する義務からも彼は解放されている。庵月は、結局のところ自分ひとりのために動いている。
庵月は走り出す。
一度だけ振り返る。キリンはまだ船から逃げる気がないらしい。
庵月の走っている道の反対側をガゼルたちがプロムナード公園へ向かって駆けていく。その背後から優雅なスピードでトラがジャンプする。一匹のガゼルが逃げ遅れる。ガゼルの尻にかじりつく。
庵月は走る。
カフェ・ムーンリヴァー
カフェ・ムーンリヴァーの店内はがらんとしている。店の主人はさっきからカウンターの奥でうたた寝を開始している。頭髪に恵まれなかった代償のように、豊かに蓄えられた髭が、黒い炎のように上下に揺れる。店内にわずかなボリュームで流れているのはエルビス・コステロの古いヒットナンバーだ。
カウンター越しに見えるのは、暗い隅田川だ。隅田川が光を吸い込むせいで、朝が来ない。その向こう側に勝鬨橋が、さらにその奥に光るビル群が見える。銀座の夜景だ。月島にありながら、カフェ・ムーンリヴァーは完全に月島に背を向けている。
あたかも、ここまでは此岸だとでも言うように。
ドアが開く。
川の匂い。
それから、血の匂い。
店の主人が目を開くと、カウンターに男が立っている。大きな目をした男だ。左手には長い棒状のものを握っている。
「コーヒーを飲む」
主人は時計を見る。4時44分。あまりいい時間ではない。
「残業ですか」
「コーヒーを飲む」
男は繰り返す。男は瞬きもせず主人を見ている。その視線に、主人は酔いが冷める。
男は黒いスーツを着ているが、そのスーツはだいぶ色落ちしてくすんでいる。問題は、それを気にしている風がまったくないことだ。
主人は男に背を向け、コーヒーメーカーに豆を流し込む。
「客は一日にどれくらい来る」
「ざっと、四十組ってとこじゃないですかね」
主人の言葉は、闇に放たれた閃光のように一瞬で沈黙の海に吸い込まれる。コーヒーを沸かす音がふつふつと沈黙を埋める。
「一日、四十回。一日、四十回」
男は誰にともなく呪文のように繰り返す。主人はだんだん気味が悪くなってくる。
「それが、どうかしましたか?」
「一日に四十回も死にかけて、今日まで生き延びた」
主人は返答に困って愛想笑いを浮かべる。
「だから今日も生き延びる。寝起きで対応しようが、どうにかまた夜が明ける」
厄介な客だが、酔っ払っている風はない。こんな時間に、酔っ払いもせずこんな珍妙なことを言う奴は相当頭がイカれてるとしか思えない。
「あんたはそう確信している」
「いや、確信しているわけでは……」
主人は、いまの自分の言葉が投げやりに聞こえないか、言い訳じみていないか考えた。そうしてなぜ自分がそんなことを心配しなくてはならないのかとも一方で思った。
「確信は大事だ。確信によってある程度は進むことができる」
主人は曖昧に笑った。男の話している内容が分からなかった。だが、分からないことを言う客は、初めてじゃない。
「だが、最後まで信じられる人間はいない」
店主は恐る恐る振り返る。
「ひぃ…!!」
男の左手から主人の首元にまで長い棒が延びている。その先がハサミになっていて、しっかりと主人の首を捉えている。
「確信が揺らぐと、人は祈る。目をつぶって祈れ」
主人は祈り方を知らない。主人はこれまでの人生でおよそ祈りというものを生活のなかに持ち込んだ経験がないのだ。だから祈るふりをする。実際には何をどう祈ったらいいのか分からない。
「神様、どうか朝を迎えられますように。再び目を開くことができますように。……祈ったか?」
主人はうなずく。何度も何度も、力強く。
「願いは叶った」
ジョッッッッ
シャンパンのコルクが天井に向かって抜けるときに似ている。
《庭師》はいつもそう思う。
顔のなくなった首から鮮血が噴出する。
まるでパーティー騒ぎだ。
放物線を描いた主人の生首は、カウンターに着地する。
「もう一度目を開けた」
主人は、何も答えず《庭師》を見返している。
《庭師》はカウンターの中に入ってコーヒーメーカーの抽出口にカップを置き、コーヒーを淹れる。芳醇な香りが鼻孔をくすぐる。
《庭師》は、コーヒーに舌だけをうずめる。
百度の熱湯のなかに舌をつけていると、人間は痛みと精神を分離せざるをえない。《庭師》はしばらくの間、そうして舌をじっとコーヒーのなかに入れたままにしている。
「これがお前の一生の味か」
《庭師》は舌を引き上げる。
主人は頭から暢気にコーヒーを被る。乱れるような髪はない。
《庭師》は窓から隅田川を見る。
川の表皮はぬめらぬめらと光っている。
《庭師》は時計を確認する。
間もなく五時になる。
五時にルーベンスがどこに向かうか、《庭師》は知っている。
ずっと前から決まっていたことなのだ。
ルーベンスは必ずそこへ向かう。だが、そこで何が起こるかはルーベンスの予測の域をとうに超えている。《庭師》にも分からない。ただ、《庭師》は、破壊を一つの生き様としてきた男の最後を見届けたいと思う。単純な好奇心。
《庭師》は、店内の古いレコード棚を眺める。それから流れている音楽に耳を済ませる。《庭師》は音楽から何かを感じたことがこれまで一度もない。レコードを収集したがる人間の感情も、理解しがたい。だが、レコードを収集する奴はどこにでもいる。
その事実に、《庭師》は、首を傾げる。何の意味があるのだ?
記憶。写真。それらもまた、《庭師》には無縁の産物だ。それらをとどめたいという気持ちが分からない。
あまりにも死に浸かり過ぎた。
十五年。長すぎる年月だ。長い年月をかけ、《庭師》はここまでたどり着いた。それは間違った選択だったかもしれない。
十五年の間に、生の一切を失ってしまったのだから。
彼はいまや瞬きすら殆どすることがない。すべてはがらんとしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
