
紅色の宝石 ~フジ子さんの話8~
ピンポーン。
扉を開けるといつもの宅配のお兄さんが笑顔で立っていた。
「こんにちは。ちょっと時間より早いんですけど…すいませんっ」
いえいえ。
微笑みながら手元の黒い箱に貼り付けられた送り状に視線を落とす。
山形からか…なんだろう。
ちょっと首をかしげながら、リビングのテーブルへ箱を乗せる。
「あっ、ママ!なに?お荷物?」
娘が目ざとく見つけて飛んできた。
「おお、なにこの黒い箱?あっ!さくらんぼの絵が描いてある!しかも黒い箱ってことは…こっ、高級なやつやん!!もしかしてふるさと納税の??」
果物に目がない娘は、高級そうな箱で届くフルーツは全部ふるさと納税の返礼品だと思い込んでいるし、たくさん届く荷物の中でも、なぜだかそういうものだけはすぐに嗅ぎ分ける。
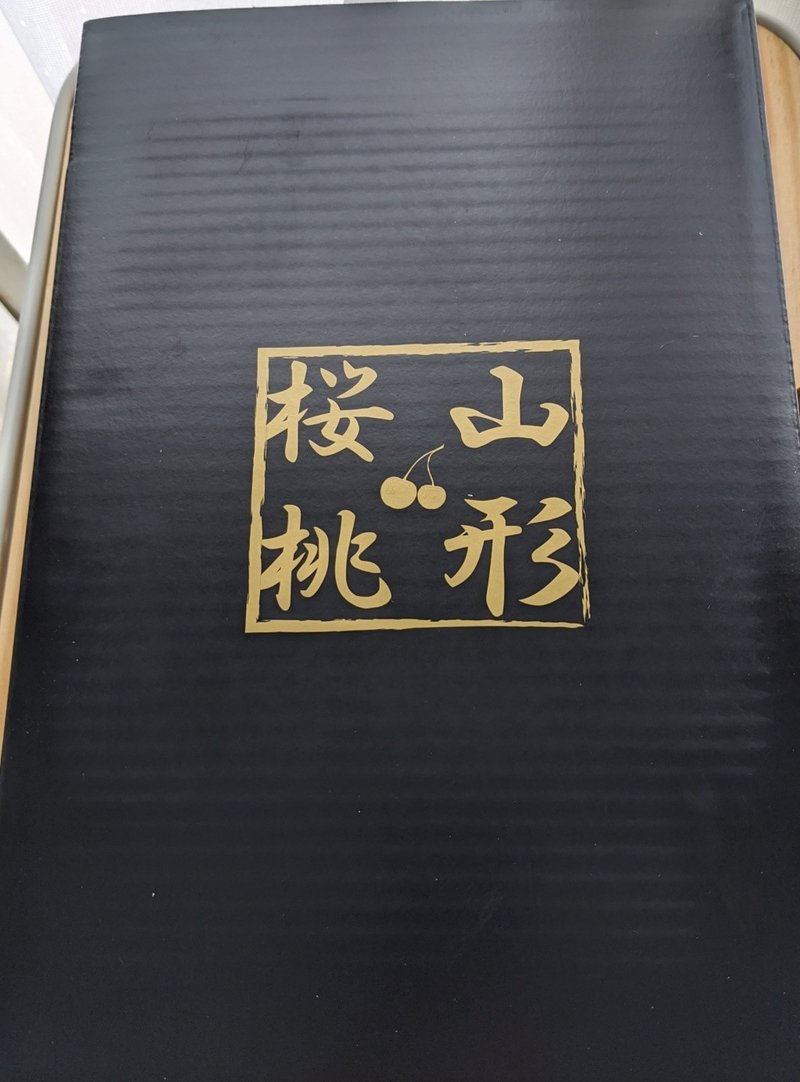
それは娘が言うふるさと納税のものではなく、差出人の名前を見て、ああ、あのひとからだとわかった。
ーーーーー
わたしは毎年、スーパーのフルーツコーナーで季節を知る。
春には春の、初夏には初夏の、果物があるのだ。
これまでなんとなく通り過ぎていたそれを、こんなにも色濃く感じるようになったのは、あのフジ子さんとの日々があったからだ。
6月に入ってから、あちこちのスーパーで店頭に並ぶさくらんぼを見て、わたしは例によってフジ子さんのことを想い出していた。
山形の、佐藤錦。
言わずと知れた、さくらんぼの女王。
つつましやかな生活を営んでいたフジ子さんにとって、それはとても高級品で簡単に手が出せるものでは、なかった。
ましてや、もう食欲がほとんどなく、食べられてもほんの数粒ほどだとわかっているからなおさらだ。
スーパーのフルーツ売場の上段の方で、立派な箱に入って並んでいるそれを、フジ子さんはなんとなく遠目に見ながら「ああ、もうそんな季節なんやなぁ。」とつぶやく。
その視線を追いながら、わたしは胸が痛かった。
ああ、さくらんぼが出てきたんだ。
もうすぐ梅雨が明ける。
ーーーーー
わたしとフジ子さんがいつも行くスーパーは、単身で高齢の利用者が多い。そういうひと向けに、果物を少量だけパック詰めされたものがたまに出ていた。佐藤錦のパックに運よく巡り逢えた時、フジ子さんはふと手を伸ばしてそれをカゴへ入れた。
家に着いたらさっそくパックを開けて綺麗に洗って、小皿へ移す。
「すぐ出してな。今、食べたい気分の時に食べなんだら、また食べる気になれんかもしれへんからな。すぐやで。」
トイレへ入ろうと台所を横切ったフジ子さんが、冷蔵庫に買ってきたものをしまうわたしに大きな声で呼びかける。
うん、わかっとうで。すぐ出すわな。
心の中で返事をして、まだ十分に冷えていないそれを、お茶と一緒に食卓へ並べる。
フジ子さんのお気に入りである藍の菊割の小皿には、パックに入った粒の中から特に紅いものを選んで7粒ほど乗せてある。
トイレから戻ってきたフジ子さんは、ゆっくり愛おしそうに軸をつまんで、さくらんぼを丁寧にひとつずつ口へ運んだ。
そうだな、4つも食べられたら、調子は上々だ。
「どう?甘い?」
「遠慮しとらんと、あんたも食べぇよ。」
フジ子さんが小皿をすっとこちらへ押しやる。
「ありがとう。ほんなら遠慮なく、いただきます。」
口に含んだそれは、甘酸っぱくてまだちょっと早めの夏の香りがした。
「まあ、もうちょいやなぁ。」
「ほんまやね。もうちょいやね。」
ふたりで顔を見合わせて、笑った。
もうちょっと甘くなるまで待ってみよう…
わたしたちには何気なくそんな風に言えるその時間が、フジ子さんにはあるかないか分からなくて。わたしにできることなんて、本当になにもない。
だから、今日食べられてよかったんだ。
小皿に残った紅いルビーと言われる佐藤錦を見ながらわたしは、本物のルビーみたいに輝いていた頃のフジ子さんを、想った。
何度も何度も見せてもらった写真には、豪華なインテリアの店内で、きらびやかなアクセサリーをまとって、お客さんと笑顔でいつだってフレームの中心におさまるフジ子さんがいた。
きっと、あの頃のフジ子さんは、フルーツコーナーの上段で澄ましている佐藤錦の箱みたいに、それはもう当然のようにキラキラ輝く存在で。
そうしてお客さんから贈られた高級な箱に入ったフルーツを、なんの気無しに味わえていたはずなんだ。
今、ほんの数粒のさくらんぼを味わうことが、フジ子さんにとってこれほど深い意味を持つようになるなんて、思いもしなかっただろう。
わたしが、フジ子さんと一緒にこうして季節を感じていられるのは、いったいいつまでなんだろう。
考えてはいけないようで、でもそれを考えなくてはいけないという、矛盾。
わたしはいつも、スーパーのフルーツ売り場に来るとぐるぐると考えてしまう。
ひとりぼっちでここに立っている、今でも。
ーーーーー
「ねえ、ママー!すぐ洗って食べよう?ね?いいでしょ!?」
娘の声に、はっと引き戻される。
「ええー、これからお習字に行くんだから、帰って来てからにしたら?」
「やだ!!絶対いま、食べる!!こんなにいっぱいあるんだよ?いま半分食べて、帰ってきてからまた半分食べるから!自分で洗ってくるからっ!ねっ、いいでしょ!?」
そう言いながら箱をうやうやしく掲げて、娘はさっさとキッチンへ行ってしまった。
もう、しょうがないんだから。
苦笑いしながら、わたしはしぶしぶキッチンへと向かった。
包みをそっとほどいてみる。
蓋を開けると、そこにはまさに輝く紅色の宝石たちが、いた。

大切な友人が贈ってくれたそれは、わたしの知る佐藤錦、ではなかった。
紅秀峰。
はじめて聞く名前だ。
なんでも佐藤錦よりもさらに新しい品種らしく、ひと粒が大きくて紅色の輝きが濃いのだ。
そうか、わたしの知らない間に、さくらんぼの世界はまた新たな世代へと変化を遂げていたんだ。
わたしやフジ子さんがよく知るそれより、さらに大きく紅く輝く宝石たちは、これから先の、もっともっと新しい時代を生きていくんだな。娘たちの世代とともに。
ーーーーー
「見て!夢の贅沢食いーー!!」
振り返ると娘が両手にさくらんぼをぶら下げて、にまにま笑っていた。
そのまま一気に同時にどちらも口に放り込む。
「もうっ!一個ずつゆっくり食べなさいよ。」
「やだねー!だってゆっくり食べてたらおいしくなくなっちゃうもん。いたみやすいから早く食べてねって言われたんでしょ?」
そうだけどさ。
貧乏育ちのわたしには、娘のその無邪気さがとてつもなく、まぶしく見えた。
本当は、お行儀よく食べなさいってきちんと躾けるものなのかもしれない。
けれど、まあ、いいじゃないか。
別に良家の子女でもなんでもない。うちはこどもはひとりだけだし、パパもいまは不在だし、わたしはそんなにたくさん食べられないもの。
そうやって甘やかすから…
どこからか風に乗って誰かの声が聞こえたような気もしたけれど、わたしは伸びすぎた髪をさらりと振って、ベランダの窓を開け放った。
フジ子さん、紅秀峰やって。知ってる?
こんな新しいのん、出てんで。
「ママー!さあ、行こっか。」
娘は習字道具の入った鞄を提げて、もう出かける準備をしている。
冷蔵庫をのぞくと、無造作にガラス鉢に山と盛られたさくらんぼが入っていた。
「もう…カピカピになるでしょ。ラップくらいしなさいよ。」
「あら?そうやったん?ごめんごめん、あ、自分でする!」
にこにこしながら、娘がラップを取ろうと棚に向かって背伸びしている。
あれ?こないだまで椅子に登っていたのに?
ふーん、届くようになったんだ。
たった、それだけ。
だけれど。
そのことがなんだか、とても明るく希望に満ちたものに見えた。
そう、それはまるで、紅秀峰の、弾けるように艶やかに実った粒粒みたいに。
輝け、宝石たち。紅く、大きく。

ーーーーー
今夜は、想いをこの曲にのせて。
明日へ/MISIA
声がかれても なお 歌い続けよう
同じこの空の下 共に向かってゆこう 明日へ
☆はじまりはこちら☆
サポートというかたちの愛が嬉しいです。素直に受け取って、大切なひとや届けたい気持ちのために、循環させてもらいますね。読んでくださったあなたに、幸ありますよう。
