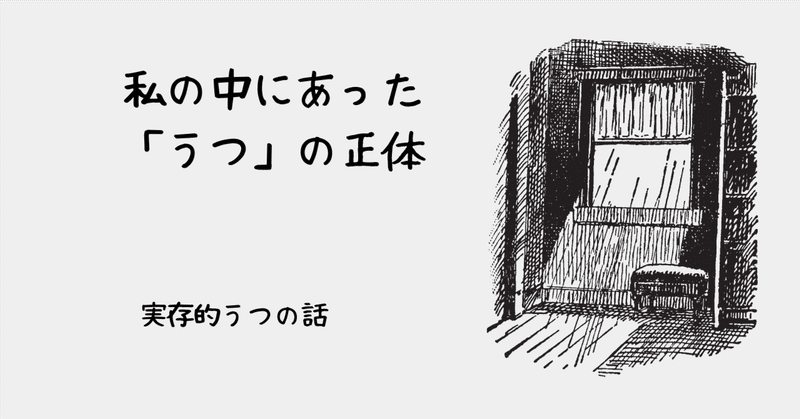
つぶやき:「実存的うつ」の話
今書きたいトピックが複数ありどれも下書き状態だけれど、今日はその合間を縫って少しのつぶやきを(少しといっても5,000文字超えてる)。
今はメンタルが安定している。周期的にいってそうなのと、人生のフェーズとしても、色々なことに挑戦してきたせいで自己肯定感が上がり、過度の承認欲求なんかもないし、誰かと共感話をしたいわけでもない。メタ認知を使うとほぼどんなことも解決できるから、その手法を最大限に活用して性格の歪みや感情の澱みを補正してきたという達成感が強い。苦しみを幸せに換える力を高めてきた、その充実感を自分史上もっとも感じている。
だけど……私の中には常に『うつ』がある。これは、何かをきっかけに起きてしまう外的要因によるものではなく、いわゆる脳機能(セロトニンの欠如による)的に引き起こされる病のそれでもない。
そういう意味とはまた違った『うつ』のこと。
これを何と呼べばいいのか、これまでわからなかった。だから誰かに上手く説明できなかった。おおむね気分循環性障害や双極性障害Ⅱ型に相当するような「見た目」をしている。だからそれだと思い、ドーパミンが関わる脳内報酬系に問題があるのかと何度も疑って調べたこともある。実際クリニックでそれ系の薬を処方され飲んでいたこともある。でも違う。違っていた。とある本にこれの正体が書かれていた。
「実存的うつ」
……これだった。まさにこれ。本からの引用。
実存的うつとは、その悩みの根本が、人間は所詮は孤独であるという感覚とともに、自らの力の及ばないこと、一人の人間としてできることが非常に微々たるものであるという、人間の存在の意味を問うものです。
この文章を読んだとき(実際はここにくるまでのページにとりあげられた様々な部分が重なって)、子供の頃から抱えている何かを言葉に換えられたような気がして涙があふれた。気づけば大泣きしていた。もう長い間忘れていた深く敏感な場所にそっと手が添えられたような感触がして、何十年分の涙が込み上げてしまった。(※自分とこの本のテーマとの関係についてはまた別に書く。)
私は自覚として、自意識(自我)というものが生まれながらにとても強い。周りの世界から受ける刺激だけでなく、意識の奥から込み上げてくる思いや想像や情動というものにも敏感すぎてどうにもならなかった。これの中身について、ここで何かを書いたところでわかってくれる人がいるとは思えない。これまで色々な人と関わってきて同じ感覚を持っていそうだな、と思った人は一人もいない。
私の中にある三つの実存的うつ
1・美との別れがあるという事実
ごく幼い頃から、この世の中に存在する『美しいもの』に魅了されものすごく感動して叫びたくなることが度々あった。あったというか、学校に上がる前から毎日そんな深い感動を味わっていたのを覚えている。特に小学校低学年の頃、その感動の瞬間がくっきり出るようになった。
それは美しい旋律だったり、美しい風景だったり、美しい言葉だったり。特に私は、季節の変わり目に吹く風の、あの何とも言えない郷愁感にも似た懐かしさと清々しさと安らぎがないまぜになった感触がたまらなく好きだ。その「好き」という気持ちは大声で叫んで跳び上がりながら、そこら中を走り回りたいほどの衝動に駆られるようなもので、激情といってもいいくらいのもの。叫んでも叫んでも叫び足りないほどの喜びと感動。しかし同時に気づいた。──これを味わう回数には限度があるのだよな、と。
人生の時間は限られているから、私はあと何回この喜びを経験できるのか。……そう考えるととてつもない絶望感に襲われた。焦りも感じた。確か小学三年生の頃のこと。
これは一例に過ぎず、あらゆる「好き」への感動には「限界」という絶望感がもれなく付いてくる。心から愛してやまないものとの別れに向かって時間は刻一刻と確実に進んでいる……。生きるとはこういうことなのだ、と幼い心でこの事実を受け止めることが苦しかった。強烈な悦びと表裏一体の強烈な虚しさと哀しみ。
例えば、あなたが『あと半年の命ですよ』とガンの告知をされたら何を感じるだろう。これまで普通に思っていたものへの意識が変わるんじゃないだろうか。道端に咲いている花や風の匂いなんかが昨日までとは違った意味と重みを持ってくるはず。当たり前に感じてきた世の中の美しさが特別なものに思えるかもしれない。同時に、この貴重なものを手離す時が近いことに対し言葉にならない絶望を抱くだろう。……私が幼い頃感じた、今も心に張り付いている強烈な思いとはこの感覚のことだ。
イギリスの古い詩に『'Beauty is truth,truth is beauty.'──that is all Ye know on earth,and Ye need to know.(美こそが真実であり、真実は美である。──これこそ世の人が地上で知るすべてであり、また知るべきすべてである)』という言葉がある。詩人キーツの有名な一句だ。烏滸がましいことながら、これが誰しもが感じ得る感覚なのだとすれば、私の『うつ』はこの言葉に込められた心情や観念あるいは強い直感みたいなものに端を発しているような気がしてならない。
また、別のもっと強い絶望がある。
2・人の尊厳と幸福を守りきれない己の非力さへの絶望
子どもの頃悟った歴史上の事実。これまでどれほど多くの人が人としての尊厳を剥ぎ取られて命を全うできずに亡くなっていったか。「死」ですら受け入れ難いのに、「早死に」ですら恐ろしいのに、この世でもっとも侵されてはならないもの「人としての尊厳」を踏みにじられるという恐怖と苦悩を受けて亡くなった人の心がいかほどのものか。それを想像しただけで、自分には背負いきれない苦しみという重圧を感じた。なんとかなるならなんとかしたい。よく、二度と起きないように、というスローガン的なものは世界中で叫ばれる。綺麗事ならいくらでも言えるし、大抵は過去から学んで未来へ活かそうという考えでまとめられる。でも、すでに亡くなった人の存在価値はどうなるのか。
こんな、自分の力ではどうにもならない世の中の不公正や不条理な現実に対して感じてしまう自らの非力さ、無力感、そういったものが心の根底にへばりついたままになっている。屈辱、苦悶、恐怖、無念、義憤……そういった情念で濡れに濡れた重い絨毯が心という部屋の底にべったりと敷かれていて、それは重すぎて容易に剥ぎとることができない。かといって生きていくためにはいちいちそれを眺めているわけにもいかない。だから、その濡れて重たい絨毯の上に防水布を敷き、さらにその上になんとか乾いた絨毯を敷いて、家具を置いて隠して快適な部屋を装って毎日を過ごしている。
だけどふとした時に、部屋の端っこから水の匂いが漂ってくる。無意識にふらふらと近づいてしまい迂闊にもチラッとめくってしまう。もう無いのでは? という予想もしてみる。だけどそれは変わらない重さと水分量をもってやっぱりそこに在る。
おおかた日々というものは、部屋の中に満たした柔かい空気やきれいな家具や窓から入る光や訪ねてくるお客や灯した灯りや、そんなもののおかげで楽しく過ぎていく。歳を重ね思考を鍛えることで意識をコントロールする能力を高めてこられた。でも私の心の部屋にはいつもこの濡れた絨毯の匂いがそこはかとなく漂っているのだ。相変わらず鋭い私の嗅覚がいつもその匂いをどこかしらで嗅ぎつけてしまうのだ。……他の人はこれをどう処理して生きているのか、私にはわからない。この話題を出せそうだと思える場面は日常にはほぼない。
そして最後に、本質的な孤独によるうつ。
3・『理解されない』ことがよく『理解できる』ゆえの孤独感
私がこれほど孤独を感じる理由には、様々なことが関係している。子供時代からおよそ人と違った家庭環境に置かれ人と違った子供としての試練(家庭内暴力と親からの精神的ネグレスト)を乗り越えてきたこと。純粋に、繊細気質ゆえにある生きづらさもある。その他抱えた多くの精神問題の克服の仕方も人と違っている。先回書いたように思考の仕方や興味関心も人と違っている。そもそも、よく人々が求めあう「共感」なんて、私にとっては元々あり得ない、起き得ないことだと子供の頃から悟っている。諦めている。それはもうずっとずっと昔、幼い頃に抱えた感覚だ。
私の中にある精神力、忍耐力、美への感受性、空想力、創造力、それらの度合いについて。何重にも重なった過酷な条件や環境をどのように頭を働かせ、意思を働かせ、強い覚悟で乗り越えてきたか。何があったゆえに乗り越えてこられたのか。……そんなの話したところで誰にもわからないと思う。わかる存在がもしいるとしたらそれは神と呼ばれている高次元の絶対的存在だけ。(実際、神だけが私の人間としての底力を知って認めてくれている、と想像してみることで若い頃はなんとかやってこられた。)
たいてい人は具体の世界でものを見るから、というかメタ思考でものを見る人がとても少ないから「深さ」や「幅」や「質」みたいなものを感じとってくれない。だから、私が自分のことをメタで見た上で「私はこういうものを持っている。それはこれくらいのものなのだ」と話したところで、世間でよくある「自慢話」や「上から目線」や「かまってちゃん」の話のように見えてしまうことだろう。そのことをよく知っているので誰にでも話せるものではない。この人はメタ認知を鍛えた人だ、経験値も高く見識豊かな人だ、読書で広く深い知識と理解を得ている人だ、と思える人がいたとしてもよほどの人にしか語れない。(だから先生やカウンセラーや専門家に聞いてもらおうとこれまで一度も思えなかった。)
また逆に、物事の詳細を理解できない人は、「そんなの私にだってあるし、昔からよく知っている」などと簡単にいう。ディテールを感じ取れないがゆえに出てくる言葉だ。言葉の裏にある本質を掴めない人ほど「なんだ、それ知ってる」としてしまう。頭の中で間違った類推をされてしまうわけだ。この「わかっている」に関わる矛盾が往々にして世にあることを承知している。(ちなみにこれは、二十世紀日本でもっとも売れた自己啓発本と言われている『バカの壁(養老孟司 著)』の第一章に書かれてあった『わかりあえない』と同じ理屈。)
孤独感なんて、もうあまりに親しみすぎて今さら他人事のようにその言葉を扱っている自分がいる。でもこの孤独感をうまく丸め込んで生きてきたはずなのに、やっぱり時々顔を出してくる。
特に、私の年齢的にいえば誰もがこの実存的うつを経験する時期だと思う。(歳を重ねることで段々と死や孤独というものが現実味を帯びて捉えられるようになってくる、ということ。)それもあり、私も他の人のように自然な流れでその「孤独」を眺めてみることがある。こんにちは、そこにいたのね。初めてじゃないけど、本当に久しぶりだね。……って懐かしい友のように、時々それと挨拶したり付き合ったりしてしまう。こんなとき具体的にはどういうことが起きてしまうかというと。夜中に「誰にも理解してもらえない私の過去の苦しみや私の内面的な特徴」が浮かび上がってきてベッドから起き上がり泣き叫んでしまったりする。夜中にふらりと川っぺりまで歩いていきひたすら泣いてしまう。家族を困らせるような行動として現れる。
……こうしてざっとまとめただけで、幼い頃から持っている実存的うつが三つあることがわかった。
もちろん人間なのだから、中にはこの私が言っている「実存的うつ」について、なんとなくわかるよ、と感じとってくれる人や、すごくよくわかる、と理解してくれる人もいるだろうと思う。そうであっても、そういう人と語らい何かを共有し合える機会というものが自分にはない。そんなチャンスはこれまでもこれからもずっと訪れないのかもしれない。
子供時代を経て進学して就職して社会的立場の土台を作る時点で、私も世間の人並みに選択の機会を持てていたなら。学歴やキャリアなど何らかの知性のラベルを貼ってもらえる道を私も進めていたならば、あるいはそんな場面もあったのだろうか。取り返しがつかなくなる前に、もしあともう少しだけ同じような人と交流を楽しめる環境を持てる機会があったなら……。いま社会の底辺で肉体労働をして生きている身に、そんなものは望むべくもない、ひどく縁遠い世界だ。
これからnoteに、自分の過去のことも色々書いてみることにした。どうせ誰にもわかってもらえない話であるのなら、ここで独り言として吐き出してみても悪くないだろうと思う。
性格分析を絡めながら心理面の構造を掘り下げていく内容と並行して、ただの自分語りもやってみよう。少しこのように語尾を変えたり違った文体で区別をつけるのもよいかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
