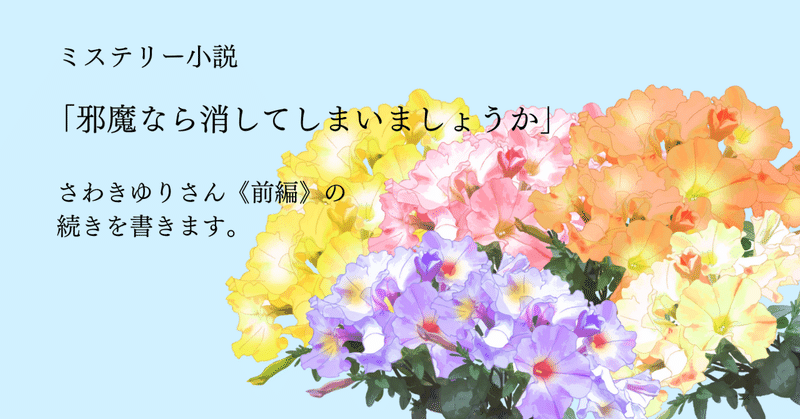
【ミステリー小説】邪魔なら消してしまいましょうか《後編》(さわきゆりさんの続きを書きます。)
さわきゆりさんの書かれたミステリー小説「邪魔なら消してしまいましょうか」(前編)のつづきを書かせていただいています。
物語のはじまりは、こちらから↓
《中編》はこちら。→《中編》本文へ
《後編》
「まだ帰って来ないの?」
夜十時を回り、さすがにおかしいと思い始めたのか、亜美と樹も一階のリビングに下りてきた。
夕食を食べ終えた後、瑛介は煙草を吸うために一度自室へと戻ったが、十分後にはリビングに戻り、それからは私とずっとここで桜花の帰りを待ち続けた。辺りの森は暗闇に包まれ、時々不気味な葉擦れの音が聞こえるが、それ以外に何の音沙汰もない。
「ねえ、こんな時間まで帰らないのは、やっぱり変だよ。もう遅い時間で私たちだけで探すにも限界がある。警察に相談しよう。ね、瑛介くん」
憔悴しきった顔でソファに腰かけている瑛介の肩に手を添える。瑛介は俯いたままだ。
「そうね。さすがに、こんな場所から夜遊びに出たまま、ということは考えにくいわね。まったく、大人になってもあの子は……」
「はあ、警察かよ。ちっ、面倒だな。携帯も通じないし、誰かが直接行かなくちゃなんねぇじゃねぇか」
亜美の溜息と樹の舌打ちが瑛介に向かう。
「ごめん、亜美姉さんと樹兄さん。警察に行ってくれる?」
「ったく、しょうがねえな」
「まあ、瑛介がそんな状態じゃね……」
亜美も樹も煩わしいと態度で示してはいるが、まだ洋服を身に着けており、いつでも出掛けられる支度だけはしていたようだ。亜美は自室から持参したストールを肩に掛け、樹は車のキーケースをポケットから取り出した。
桜花が消えたことにきょうだい誰かの関与を疑っていたが、メモ帳を眺めていてもこれといった決め手もなく、彼らに不審な動きも見られなかった。姉があんなに多くの化粧品を使っていることも、兄が冷蔵庫のように冷え切った部屋で過ごしていることも、母の違う弟が煙草を吸っていたことも、全て初めて知ったことだった。亜美と樹が一緒に行動してもきっと大丈夫だろう。私が気になるのは、どちらかといえば……。
「……そういや、姉貴。さっき二階の廊下に薬品みたいな変な臭いがしてたぜ。あれ、姉貴だろ。もしかして、桜花に何かしてたりして。桜花の心配するなんて、らしくねぇし」
「は? 樹、何を言い出すのよ」
「いやあ、警察行くのはいいけど、姉貴がもし犯人だったら困るだろ? はは」
樹はこの部屋に漂う不穏な空気に耐え切れず、亜美を揶揄ったつもりだったが、タイミングが悪すぎる。亜美はいきなり樹のポロシャツの胸ぐらに掴みかかった。
「もう一度、言ってみなさいよ! 私が桜花に何かしたですって? 何かって、何よ。あんたこそ、部屋から冷たい空気が漏れ出てたわよ? 死体を隠すんなら、温度を下げなくちゃいけないものね!」
「姉貴、そんなに怒るなよ。ただの冗談だろ?」
「私が持ってきたのは、ただの化粧品よ。あんたの言ってる臭いは、きっと除光液だわ。マニキュアを落としてからお風呂に入ったの。それを何? あなたは医者なのに、除光液と薬品の臭いの違いも分からないの? 大学も裏口入学のこんな馬鹿が、どうして父の病院を継ごうなんて思えるのかしら。ちゃんちゃらおかしいわ!」
「馬鹿って……! それは姉貴の方だろ。金目当てで結婚した社長の会社が、今や経営危機なんだから。桜花がいなくなれば、姉貴は助かるだろ。財産の取り分が増えるもんな」
「何ですって!? 私は知っているのよ。あんたが病院の若い看護師に手を出してるってこと。もしかして、桜花もあんたの趣味に合って、どこかに閉じ込めでもしてるんじゃないの!?」
「ひでぇ! 姉貴だからって言っていいことと悪いことがあるだろ!」
「それは、こっちの台詞よ!」
まさに、骨肉相食む。血で血を洗う争い。亜美は樹の髪を引き抜かんとばかりに鷲掴みにし、樹も亜美のストールを奪い、首を絞めようと必死に抵抗している。
「やめてよ、二人とも! 今は、喧嘩してる場合じゃないでしょ‼」
二人の間に身体を挟み込んで、何とか引き離す。
「二人とも早く警察に行ってよ! 一刻も早く桜花ちゃんを探さなきゃ!」
こう言うと、二人はやっとお互いの手を離し、鼻息の荒いまま「ふんっ」と言って玄関で靴を履いた。
「もう、仲いいんだか、悪いんだか、ほんとわかんないんだから。ね」
溜息を吐きながら振り返ると、そこに立っていたはずの瑛介が突然走り出していた。
「どうしたの!? 瑛介くん!」
すでに玄関を出た亜美と樹を追いかけて、瑛介は靴も履かずに外に飛び出していく。
「だ、だめだ! 姉さん、兄さん、車に乗ってはだめだ!」
瑛介が二人に向かって大声で叫んだ。
「はあ?」
「何なのよ」
樹と亜美は、車の扉に手を掛けようとしたところで手を止めた。
「だめだ! 今すぐ離れてくれ! 触ってはだめだ! その車の中には……、ガソリンが充満しているかもしれない……!」
「「え!?」」
二人は同時に後ずさる。
「……瑛介くん、どういうこと? ちゃんと話してくれる?」
瑛介は玄関先で膝から崩れ落ち、こうべを垂れたまま震えていた。
「様子がおかしいと思っていたの。最初は桜花ちゃんを心配していただけだと思っていたけど、自分一人では彼女を探しに行こうともせず、一緒にずっとリビングにいたのも私が部屋からでないように見張っているみたいだった。煙草をあんなに吸っていたのも、何か別の心配事があったからじゃない? 部屋の灰皿に残っていた煙草の吸い口も、ストレスで激しく噛んだような跡が残ってた。お願いだから、瑛介くんが知っていることを全て話して」
「ああ……。ごめんね、海香ちゃん……。ごめん、姉さん、兄さん……」
*
一度リビングに全員で戻ることにした。
憔悴しきった瑛介、そして、怒りとも恐怖ともとれるような複雑な顔をした亜美と樹をそれぞれソファに座らせ、私は温かい紅茶を淹れた。
十分ほど経った頃、瑛介が話し始める。
「今朝……、表参道で桜花を車に乗せた後、長野に向かう途中でガソリンスタンドに寄ったんだ。車の給油と、それから少し休憩するために僕は一旦車から離れて外で缶コーヒーを飲んでいた。その時、なぜか桜花が二・五リットル位のガソリン缶を車のトランクから取り出すのを見たんだ。その後、車の中で『何でそんなのものを持ってきてるんだ』と聞いたら、『向こうは朝晩が寒いからストーブが必要かもしれない。だから、灯油を買っておいた』と、そう答えた。だから、僕はそれを信じたんだ。だけど、桜花が突然いなくなって……、まさかと思って、夕食後に桜花の部屋と空き部屋を見に行った。そうしたら、空き部屋にあるストーブは誰も使っていないのに、桜花の買ったはずの『灯油』がどこにもなかった。桜花を探すために姉さんと一階を探索した時も、あのガソリン缶はなかったんだ。考えたくはないけど、もしかしたら桜花があの時購入したのは『ガソリン』で、それを使って何かしようとしていたんじゃないかって、そう思って……」
瑛介は膝の上で祈るように手を組み、目の前にあるティーカップの縁辺りを眺めているようだった。
「それで、樹兄さんの車の中にガソリンを放置しているか、撒いているんじゃないかって思ったのね」
私がそう言うと、瑛介は頷く。
「ああ。僕の想像でしかないけど、兄さんがここに来ると車に鍵を掛けないことを桜花も知っているし、みんながそれぞれの部屋に入った後、桜花がガソリン缶を僕の車から降ろしているところを部屋から見たんだ。だから……、それしか思いつかなかった……」
「それなら、一刻も早くあの子を見つけて確かめないと、どこにも行けないじゃない! あなたは実兄なのに、なんで何もしないのよ!」
それまで黙っていた亜美がようやく口を開いた。
「……」
「嫌だ……、もしかして、あなた、私たちをそのまま見殺しにするつもしだったの!?」
「……そうか。俺たち二人がいなくなれば、うるさく言うのもいなくなるし、病院も財産も思いのままだもんな。大人しそうな顔して、最低な奴だぜ」
「亜美姉さん、樹兄さん、ちょっと待って。まだ桜花ちゃんが何かしたって決まったわけじゃないわ。それに、どのタイミングで誰が車に乗るかなんて分からなかったはずよ。買い物で私が乗る可能性だって……」
いつものように瑛介を責め始めた二人を落ち着かせるつもりで話に入ったが、それを中断したのは瑛介だった。
「誰でも良かったんだ。きっと」
瑛介の冷たい声に、私たちは固まる。
「姉さんでも、兄さんでも、……海香ちゃんでも。桜花は僕たちの母が、君たちきょうだいに殺されたと思っている。母が亡くなったのは事故で、君たちが何かしたという証拠もないけど、それでも、君たちに殺されたと思ってる。……僕もそうだから」
「瑛介くん……」
「だって、そうだろう? この家に来て、母が幸せな時はあったのか? 父は家庭のことには目を向けない。先妻の子ども達に冷たくされて、最初の頃は母屋にも住まわせてもらえなかったじゃないか。子どもたちがみんな家を出た後も、母は精神安定剤や睡眠薬が手放せなかった。薬を飲んでいたのに、翌日、急に実家に帰ってくると言い出した君たちのために、母は夜遅くに車で買い出しに行ったんだ。そこで事故に遭ったんだ。それなのに、どうして、君たちを恨まずにいられるんだ……!」
《完結編①につづく》
(3,709文字)
※11/5㈰1:06 に《後編》本文を大幅に修正しました。
いつも応援ありがとうございます🌸 いただいたサポートは、今後の活動に役立てていきます。 現在の目標は、「小説を冊子にしてネット上で小説を読む機会の少ない方々に知ってもらう機会を作る!」ということです。 ☆アイコンイラストは、秋月林檎さんの作品です。
